***
「例の先生の授業はどうだった?」
「幼女がヒロインのライトノベルを薦められたよ」
「……へえ」
半笑いの返事を聞きながら、テーブルに広げられている駄菓子をつまむ。
一日の授業を終えた零次は、一直線に帰宅した。午後の授業はほとんど頭に入っていなかった。はっきり記憶に残っているのが、メルティの現国だけというのは皮肉な話だ。忘れられない授業をするという点では、メルティは非常に優秀なのかもしれない。
「どんな小説なわけ?」
零次は鞄から『チヌことと見つけたり!』を抜き出して渡す。
「ああ、このレーベルなら何冊か持ってるけど」
「人気あるの?」
「エロをかなり押し出してるのが特徴ね」
「姉さんの本棚に入れといてよ。ロリコンになりそうで怖い」
「愉快な先生で楽しそうじゃない」
この気楽さがうらやましかった。
「それより今夜はチャーハンがいいな。肉がたっぷりでトロトロのソースがかかってるやつ」
「そういや最近、チャーハン食べてなかったっけ……」
要望どおりにするべく準備に取りかかろうとするが、冷蔵庫に材料がなかったので、沙羅に費用をもらって買い出しに出かけた。
ろくに遠出しない姉が借りたマンションなので、立地という点に関しては相当にいい物件である。スーパーマーケットもコンビニも半径二百メートル以内には営業していて、台所を預かる零次としてはとてもありがたい。おまけに学校からも近いのだから、電車やバス通学の生徒と比べて、はるかに恵まれていると言える。両親の新居は、利便性でここより若干劣る。当初、炊事洗濯係を押しつけられて面倒だと思ったが、それを差し引いても、まあよかったのかなというのが正直なところだった。
スーパーマーケットは奥様方を中心に繁盛している。目当てのものをさっさと買って帰ろうとかごを掴み……前方に思わぬ人物を目にした。
「崇城さん?」
声をかけると、ゆるやかに振り向く。
崇城朱美は無表情で、ほんのかすかな会釈をする。零次と同じように来たばかりなのだろう、かごには何も入れていない。
白いワイシャツにズボンという、女の子にしてはシンプルすぎる私服姿だが、それが逆に魅力的だった。特に胸部を押し上げる大きな膨らみが、制服のとき以上に強調されているようで。
そういえば家が近いんだよな、と思い出す。こうしたサプライズが今後何度もあるとしたら……姉のマンションに住んでいる一番のメリットはこれかもしれない。
そうだ、この子がいれば、先生の誘惑なんかに決して負けない。ノーマルな自分を保っていられる。だからもっと交流を深めよう! そう決意した。
「崇城さんも夕食の買い物?」
「ええ……」
素っ気ない態度だった。もっとも、出会ってまだ二日。クラスメイトとはいえ友達になったとは言いがたい。
そもそもこの崇城という人は、あまり社交的ではない感じだった。休み時間でもあまりクラスメイトと関わりを持とうとしないし、他の生徒も孤高の美しさに遠慮するかのように、少し距離を置いている風だった。
零次は昔から、そういう人とは余計に親しくなりたい性格だった。
まずはコミュニケーションを取る。それが彼の持論だ。誰も友達がいない、内気な小太りの男子に話しかけ、家に誘ってみたら、テレビゲームで瞬く間に意気投合できたこともある。その彼は転校の際、泣いて悲しみ、最後には笑って送り出してくれたものだ。
崇城は野菜コーナーに向かう。零次も食材を吟味するふりをして、さりげなく彼女の側に寄っていった。
「うちさ、両親はいるんだけど事情があって姉さんとふたり暮らしでさ。料理は全部僕にやらせてんだ。まあ料理は好きだし、いいんだけどね」
「……ふうん」
「崇城さんも自分で料理するのかな」
「ひとり暮らしだから。マンションで」
「へえ……!」
軽く驚いた。姉とふたり暮らしというのもレアケースだが、高校生がひとりきりでマンション住まいというのは、そうそうあることではない。
あまり込み入ったことは聞かないほうがいいだろうと直感し、それ以上は彼女の暮らしには触れないことにする。
崇城は魚介類や肉類のコーナーへと次々に移っていき、彼女と会話を続けるために零次もついていく。不自然に思われないため、仕方なく予定していない食材もかごに突っ込んでいく。
しかし、話は上手く続かなかった。好きな芸能人やスポーツ、本といった定番の話題を振ったが、崇城はテレビを見ないしスポーツは興味ないし本もまったく読まないという。そして崇城からは決して話題を提供してくれなかった。
結局すぐに無言になって、互いに買い物を済ませた。最初なんだからこの程度でいいかと、零次は自分を納得させた。
店を出ると、柔らかい西日が建造物群の向こうへ沈んでいこうとしている。
見とれる。何でもないような夕方の景色に、美少女は絵画のように溶け込んでいた。
崇城はジッと立ち止まって、一点を見ていた。
その先に、茶色い毛並みをした猫がたたずんでいた。鈴のついた首輪をつけている。
「どこかの……飼い猫かな?」
「そのようね」
崇城はビニール袋を置いて、猫に近づいていく。人に慣れているのだろう、猫は逃げ出すことなく彼女の接近を許し、顎の下を撫でさせた。
崇城の頬が、わずかに緩んでいた。
「……っ」
零次は銃撃を受けたように胸が熱くなった。
「ね、猫……好きなの?」
「好きじゃない人っているの?」
振り向いた崇城は、クールな顔に戻っていた。
「いや、いないよね! 僕も好きだし!」
猫は鈴を軽やかに鳴らして、気ままに去っていく。崇城は立ち上がってビニール袋を持ち直す。
そろそろお別れの時間か。明日以降もグッドタイミングで鉢合わせますようにと、普段信じてもいない神様に願掛けをしたくなった。
「じゃあ、また明日!」
「ええ」
崇城の後ろ姿が見えなくなるまで、零次はその場に突っ立っていた。
恋を、完全に自覚した。
垣間見たあの穏やかな表情が、零次の心の奥に激しく焼き付いた。女性の微笑みがあれほど美しいとは思わなかった。
魔法。世に秘められた神秘の力。そして魔法使い。メルティが明らかにしたそれらの存在には、確かに驚かされた。零次から退屈というものを根こそぎ奪った。
だが、恋。その甘くて優しい感情こそ、零次の心にもっとも化学反応を起こさせていた。この先どれほど長く生きても、これに勝るものはないと思えるほどの、最高の刺激。
帰宅し、事の顛末を姉に報告する。半分は嫌がらせで。
「それ、確実に死亡フラグだから」
「悔しいからって適当なこと言わないでくれ。フラグはフラグでも、恋愛フラグだと思うね!」
「あ、な~にマジで期待しちゃってんのよ。取り柄のないあんたがそうそう……」
「料理ができるぞ! 今時は家事スキルを持つ男ってポイント高いと思うし」
「ふんだ、舞い上がっちゃって。本気でその子といい関係になりたいんだったら、さらにフラグを重ねに重ねないとねえ。うっかりパンチラを見るとか、すっ転んで抱きついちゃうとか」
「現実にそれやったら、確実にバッドエンドだろ」
「バッドエンドになれ」
与太話はその辺にして、零次は夕食を作り始める。沙羅はのんびりとテレビを見ている。交通事故で三人が亡くなったというニュースだった。
世間では毎日毎日、悲惨な事件や事故が起きているが、零次はごく普通でありきたりで尊い幸せを享受できていることが、何より嬉しかった。
ロリコンに調教してやろうと企むメルティをどうやってかわしていくか……やっかいな問題が降って湧きもしたが、崇城さんがいれば僕は大丈夫! 本気でそう思っていた。

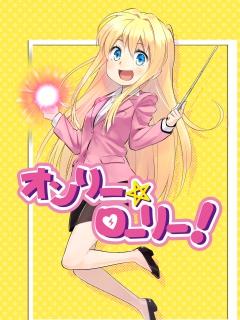



コメント
コメントを書く