何故、宇名月典善(うなづきてんぜん)がここにいるのか。
龍王院弘(りゅおういんひろし)はそう思った。
自分の方が、かつての師、典善にそう問いたかった。
自分が、典善のもとから去ったのは、このままでは、いつか自分はこの師と闘うことになると考えたからだ。
言い出したのは、典善からだ。
出てゆけと言われたのだ。
このままじゃあ、おめえを殺しちまうかもしれないと、そういうことを言われたのではなかったか。
ちょうどよかった。
龍王院弘自身も、似たようなことを考えていたのだ。
闘ったら、どうなるか。
負けるとは思っていなかった。
しかし、勝てるとも思ってはいなかった。
だが、このまま一緒にいれば、ある時、ふいにその瞬間が来てしまうような気がした。
その結果、自分は典善を殺してしまうかもしれない。
逆に、自分が典善に殺されてしまうかもしれない。
そういう闘いになるであろうということはよくわかっていた。
典善も、そう思っていたはずだ。
しかし、それは思いあがりであったかと、今はそう思っている。もしかしたら、心のどこかで自分はそう思っていて、典善のもとを去ったのかもしれない。
いつか、典善を倒すためにそのもとを去ったのだと。
自分は、この典善に対して、屈折した愛情を抱いていると、龍王院弘はよくわかっていた。
恨みなどはないのだ。
ただ、一緒にいるどの時も、典善は、一度たりともこの自分に心を許したことなどなかったと、龍王院弘はわかっている。
典善に認められたい――常にその想いはあった。
自分が、典善と闘うということは、そういうことであった。
弟子であるから、師を超える。
その時、典善は、悦んでくれるのではないか。
この自分に負け、たとえその結果が死であろうとも、この典善はそれを悦んでくれるのではないか。
典善に悦ばれたい。
だから、典善を殺したい――そういう矛盾する想い。
そんな、夢のようなことまで考えていたのだ。
しかし、今、典善は、ひとりの男を連れている。
菊地良二(きくちりょうじ)。
足の短い、ずんぐりした小男。
まだ若い。
見ただけで、高校生とわかる。
どうして、こんな男が、宇名月典善とくっついているのか。
昏(くら)い眸(め)をしていた。
陰気で、粘液質な性格。
そうか。
わかった。
典善は今、この男を弟子にしているのか。
典善好みの何かが、この男にはあるのだろう。
かつて、自分が、そうであったように。
ちろり、
と、暗い、青い炎が、龍王院弘の心の底に点った。
嫉妬と呼ばれる炎だが、そこまでは、まだ龍王院弘自身も気づいてはいない。
「なんでえ、その面(つら)は?」
典善が言った。
「面?」
「ひろしよ、てめえ、ボックとかいう外人にやられたってえ話じゃねえか」
典善は、唇の片端を吊りあげて嗤(わら)った。
どうして、典善はそのようなことを知っているのか。
「よかったな、ひろし」
典善は言った。
「よかった?」
苦いものが、こみあげる。
「これで、てめえはもっと強くなるぜえ」
いつもの典善だ。
龍王院弘の知っている、宇名月典善のもの言いだ。
「気をつけろよ、ひろし」
ふいに、典善はそう言った。
「今、おれが連れているこの男、菊地良二と言うのだがな、こいつ、強くなるぜえ。才能は、おめえの十分の一だが、外道の素質はてめえの十倍よ――」
けく、
けく、
けく、
と、宇名月典善は嗤った。
「まあ、いい。今日は、そういう話をしたくて、こんなところまでやってきたわけじゃねえからな――」
「何故、こんなところに?」
龍王院弘は訊ねた。
「あるものを、追ってきた……」
典善は言った。
あるもの――
という言葉の響きを、耳で聴いた途端、ぞくりと、戦慄が龍王院弘の背を疾(はし)り抜けた。
あるもの、それは、あれではないか。
ついさっき、龍王院弘自身が遭遇したもの。
他に、何が考えられるのか。
微かに、身体が震えた。
「ひろし、てめえ、見たな……」
宇名月典善がつぶやいた。
龍王院弘は、唇を噛んだ。
見た――
そう言うつもりだった。
しかし、その言葉が出てこなかった。
典善の口調からすると、典善は、あれを追ってきたことになる。典善は、すでにあれと出会っているということか。あれを見ていながら、なお、典善はあれを追ってきたというのか。
「震えてるのか、ひろし……」
典善は言った。
典善に、怯(おび)えている様子はない。
むしろ、興奮しているような様子さえある。
追っているということは、あれは逃げているということだ。典善と友好的な関係にあるわけではないだろう。
ということは、つまり、追いついたら、そこで、典善は、あれと闘うことになるのではないか。
無理だ。
龍王院弘は思う。
あれと対峙したら、いかに典善と言えど、闘いようがない。あれは、人間ではないのだ。
あれが迫ってくると、不思議なことに、喰われてもいい、そういう気持ちになってしまう。
こいつになら、喰われてもいい。
そう思ってしまうのである。
だが、この典善なら――
龍王院弘は思う。
この典善なら、平気であれと闘うことができるのではないか。
龍王院弘がそこまで考えた時、
ぽっ、
と、明りが点ったような気がした。
ここではない。
別の場所だ。
ほんの一瞬のことだ。
本物の明りではない。
別のもの。
一瞬の光。
どういう時に、そういう光を見るのか、龍王院弘は、わかっていた。
気を、顔に当てられた時だ。
実際に、気は光を発するわけではないのだが、その光を浴びせられたと、受けた方は感じてしまうことがあるのである。
時にそれは、熱であったり、風圧であったり、打たれるようなものであったり、様々なものであったりする。
その時、気を放つ者と受ける者の心のあり方で、それは様々に変化をする。もちろん、物質的な力はともなわないが、生体は、それを感じとることができる。
当然様々な鍛錬や修行の度合に応じて、それを感じとることのできる者やできぬ者がいるが、龍王院弘も、そして、宇名月典善も、それを感じとることができた。
「む」
と、典善は、視線を、右手の森の中へ向けた。
誰かが、典善が視線を向けた方角で、気を放ったのだ。
それも、相当に大きな、強い気を。
「弘、話はここまでじゃ。ゆかねばならぬでな――」
宇名月典善は、背を向けた。
「ゆくぞ」
そう言って、宇名月典善は、疾り出していた。

画/晴十ナツメグ
■電子書籍を配信中
・ニコニコ静画(書籍)/「キマイラ」
・Amazon
・Kobo
・iTunes Store
■キマイラ1~9巻(ソノラマノベルス版)も好評発売中
http://www.amazon.co.jp/dp/4022738308/
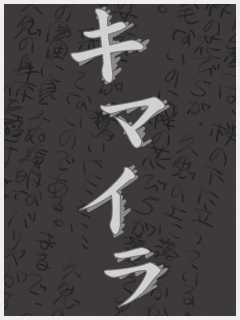
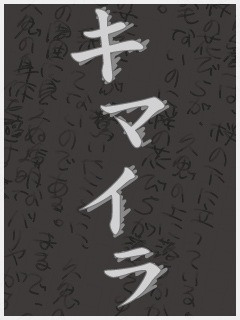
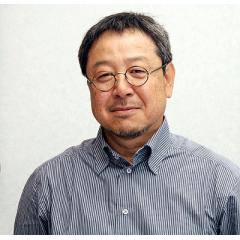
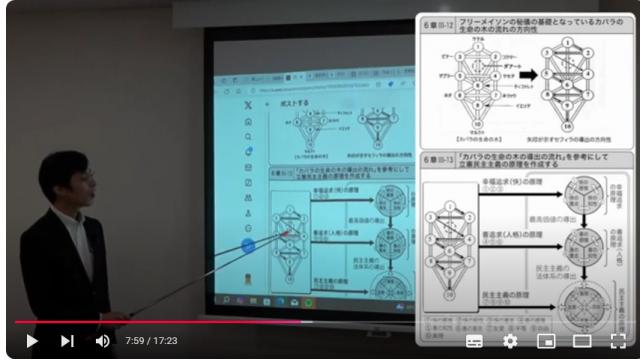
コメント
コメントを書く(ID:7439748)
>たしか典善はわりと平気で戦ってたよな。
巫炎と最初に戦ったときは、キマイラ化で精神的にギリギリだったはず。
(ID:36011524)
これヤバイなww
(ID:30611260)
この気、何の気、気になる気。
なるほどー、この気だったかあ。