久鬼玄造(くきげんぞう)が、巫炎を保冷車の中に閉じ込め、九十九も吐月も、その久鬼玄造と一緒にこの現場に駆けつけているのである。
それにしても、どうして、巫炎はあの保冷車の中から抜け出すことができたのか。
それが、九十九には不思議であった。
おそらく、今、キマイラ化した久鬼の前に立っている僧衣の男が、巫炎を助けたのではないかと、九十九は思う。
しかし、それを訊ねている時間は、むろん、ない。
ツオギェルは、久鬼の前に立って、しきりと身振り手振りで、何やら話しかけているようであった。
ツオギェルの口が開く。
声は聴こえない。
久鬼の口が開く。
声は聴こえない。
久鬼は、もどかしそうに、身をよじる。
そして、久鬼は、時おり、九十九にも聴こえる高い声で叫ぶ。
それに対して、ツオギェルは、たびたび、自分の両手を合わせ、それを自分の頭上へ持ってゆくという動作をしてみせた。
どうやら、ツオギェルは、自分と同じその動作を、久鬼にやってみろと言っているらしかった。
それを、久鬼が理解していないのか、そうではなく拒否しているのか――その動作をいやがっているようでもあった。
話をしている間に、だんだん、久鬼の感情が、昂ぶってきているようにも、九十九には思えた。
「巫炎さん――」
九十九は、巫炎に言った。
「今、久鬼玄造と宇名月典善(うなづきてんぜん)、それから銃を持った人間たちが、この森の中へ散って、久鬼を捜しています」
一瞬、久鬼玄造の顔が、脳裏に浮かんだ。
これは、久鬼玄造を裏切ることになるのだろうか。
そういう思いが、よぎったのだ。
その思いを、九十九は打ち消した。
冷静に考えてみれば――いや、直感的なところで言えば、今の状態の久鬼は、この僧衣の男と、巫炎の手にゆだねる方がよいのではないか。
それが、この場に居合わせた自分の務めであるような気がした。
「それは、おれも気になっていた……」
巫炎は、九十九にそう言ってから、ツオギェルの背へ向かって、
「おれがやろう」
声をかけた。
ツオギェルが振り返る。
「だいじょうぶですか?」
「やるしかない。台湾では、コントロールが利かず、たいへんなことになったが、今は違う。もしも、おれがまた、暴走しはじめるようなことがあったら、なんとか、おれを殺してくれ――」
言いながら、巫炎は、着ていた上着とTシャツを脱ぎ捨て、上半身裸になっていた。
「このおれでなければ、あれは止められない――」
言い終えぬうちに、
めりっ、
と、額から、角が短く突き出ていた。
二本。
めりっ、
めりっ、
と、その角が、伸びてゆく。
バットで、背をおもいきり叩かれたように、
ごつん、
という音と共に、巫炎はのけぞっていた。
背骨が、ごつん、ごつりと、音をたてて変形してゆき、曲がってゆくのである。
肩胛骨もまた、変形が始まっていた。
肩胛骨が、膨らんでいるのである。
肉と皮を突き破って、肩胛骨が外へ飛び出してきたのである。
その、突き破ってきたものが、成長し、伸びてゆくのである。
それは、翼であった。
しかも、その翼は、黄金色をしていた。
身体が、膨らむ。
背骨が、曲がる。
ぞろり、
ぞろり、
と、これもまた黄金色の体毛が上半身に伸びてくる。
そこで、獣化は止まった。
半神半獣――
身体が膨らんだとはいえ、新しい食物を体内に取り込んでいないため、まだ、久鬼よりは、ふたまわりほど小さい。
しばらく前、血と肉を大量に吐き出したとはいえ、まだ、久鬼の方が、その身体が大きかった。
巫炎が、黄金の翼を振った。
ふわり、
と、その身体が、月光の中に浮きあがっていた。

画/卜部ミチル
■電子書籍を配信中
・ニコニコ静画(書籍)/「キマイラ」
・Amazon
・Kobo
・iTunes Store
■キマイラ1~9巻(ソノラマノベルス版)も好評発売中
http://www.amazon.co.jp/dp/4022738308/
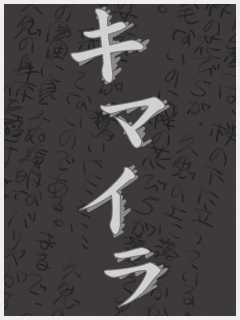


コメント
コメントを書く