
ウェブ2.0カルチャーの爛熟期にあった2010年代初頭、インターネットにはどんな可能性があり、何を失ったのか。メディアアートは、その変化にどのように介入しうるのか。コミュニケーション過剰な巨大な“世間”となった「速すぎるインターネット」の失敗を乗り越え、ありえたはずの可能性を取り戻すためのアプローチを、日本の土着性とテクノロジーを組み合わせた作品を発表し続けるメディアアーティスト・市原えつこ氏の創作活動から探る。(聞き手:中川大地・宇野常寛 構成:大内孝子)
本記事の画像・キャプションに一部誤りがありましたので訂正して再配信いたします。著者・読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。【3月3日13時00分追記】
メイカーズムーブメントと荒廃する地方都市の原風景
──市原さんがアーティストとして活動を始められたのは、まさにインターネットの新しい可能性が信じられていた震災前の2010年前後くらいのメイカーズムーブメントの脈絡からですよね。そこから現在のような民俗学的なモチーフを取り入れた作品作りを始めていった経緯について、まずはお伺いしたいのですが。
市原えつこ(以下、市原) メイカーズムーブメントから出てきた自覚はなかったので、そういえばそうだったなと自分でもビックリしました。もともとアーティストになろうとか、作品を作ろうと思っていたわけではなくて、要はプロパーな美術教育を受けてきた人間ではなく、独学で作品を作ってきました。大学生の頃[1] 、理由は今でもよくわからないんですが、日本の土着的な文化みたいなものにものすごく興味を持って、ひとりでフィールドワークをしまくっていた時期があります。
そのとき、秘宝館とか性器崇拝の神社の異様さに衝撃を受けたんです。性的なオブジェクトが神聖な空間にドカンと飾られている、あの空間はいったい何なんだ、と。もちろん、嫌悪感もありましたが。いわゆるゆとり教育で過ごして、基本的に性的なものや危ないものからは隔離されて育ってきた世代だったので。でも、すごく自分の血に馴染むというか、懐かしいなとしっくりくる感じがあった。当時、安斎利洋[2]さんのデジタルメディア論ゼミにいたんですが、デジタルテクノロジーを使って好きなものを作っていいという授業があったので、日本の土着的な性文化を表象したデバイスを作りたいとプレゼンし、大学時代の先輩の技術協力とともに生まれたのが「セクハラ・インターフェース」[3]です。触ると喘ぐ大根という、言葉で説明すると一発ネタみたいですが。メイカーズムーブメントにまず乗り込んだのは、どこに作品を出していいのかはじめは見当がつかなかったので、親和性が高そうな、というか、意味がわからないガジェットの受け皿になりそうなところに出してみたというところから始まりました。それが2012年。

▲セクハラ・インターフェース
──市原さんとしては、2010年代初頭のメイカーズムーブメントやインターネットカルチャーをどのように感じられていたのでしょうか?
市原 Make Faireはいま、お子さまやご家族連れも安心して参加できるようなクリーンなイベントになっていますが、当時はまだ「Make:Tokyo Meeting」という名称の本当にギークな人たちが集まる危ないものも含んだイベントで、全然「セクハラ・インターフェース」を出しても、運営の方は若干苦い顔をしながらもギリギリオッケーだったんです。カオス感があったし、くだらないアイデアでもそれを媒介につながりがワッと繋がりが広がっていった。こういう場でみたものに対して、純粋に面白い、こういうものを私も作りたい!と憧れて、そこから表現の現場に入った記憶があります。当時、シーンにはあまり序列はなく、インフルエンサーみたいな概念もまだなかったと思います。

 ■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…

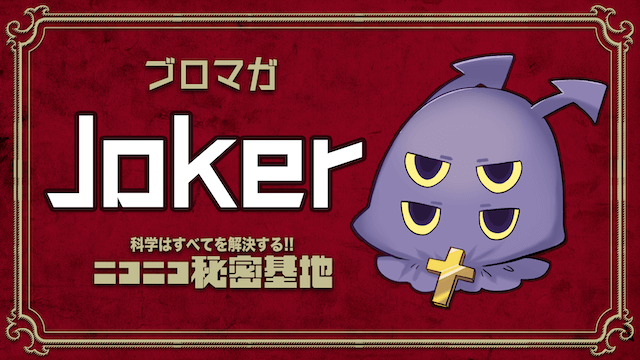


コメント
コメントを書く