(この文章は、とつげき東北が2006年に書いたものです)
映画「博士の愛した数式」
(原作未読)
~「説明責任」を負わされる同世代的感動の文脈における浅薄さの象徴として~
映画、本、音楽等が、決して自分宛てに作られてなどいないことには敏感であるつもりである。博士-愛-数式というリーズナブルな組み合わせで題される本作は、いったい誰宛てに作られたものだろう。数学を愛する学者へ? 癒しを求める若いカップルへ? それとも、原作者へのオマージュとしてだろうか?
交通事故によって80分間しか記憶が保てなくなった不幸な初老の博士と、彼を世話する若い雇われ家政婦、博士から「ルート君」という愛称を与えられることになる家政婦の子供との、数式(数字)を通じた不思議な交流を題材にした本作は、かといって数式がなければ成立しなかった映画というわけではない。舞台である「過去」と、後日、「ルート君」が教師になった際の授業風景である「今」とをリンクさせてみせたのは、「階乗とは」「eとは」といったいささか退屈な観客への「説明責任」をあたかも「自然に」果たすため、という以上には機能しておらず、その中で「数学的に」誤った表現(eのπi乗が-1になる事実を「矛盾した数字の組み合わせが…(略)…ひとつになる」といったように形容したり、無限小数の桁数が「星のように無限に」あると説明するなど)を織り交ぜる手法から見ても、本作はどうしても数学者向けとは呼べまい。
当然、専門的な世界の描写をしようとすればするほど、フィクション性を施さざるを得なくなるという真実は、映画が興行収入を目的として製作される娯楽であることから、避けて通れない問題だろう。例えば映画の世界において描かれるハッカーとは、真のハッカーでは決してあってはならず、敵のハッカーからネットワークに進入されそうになった場合には、(オフラインに切り替えるといった適切な処置を講ずる代わりに)犯人とネットワーク上で「追いかけっこ」しなければならないものだからだ。ストーリー上成立してさえいれば、そうした大真面目な茶番も笑って許せるものである。真実の世界は、2時間という枠の中に愛や感動を放り込むことが必要不可欠な映画の世界に比べれば、驚異的なまでに退屈なものだ――いたずらなリアリティの追求は映画の価値を殺ぐ。
しかし、である。数学の解説をむざむざ嘘で塗り固める必然性はどこにあったのだろうか――。本作「博士の愛した数式」には、この種の「不自然」を越えた何かが描かれていないのだ。
家政婦が毎日家に訪れるたびに、彼女の靴のサイズが4の階乗であることに思い当たって「潔い数字だ」と笑顔を浮かべる博士は何ら愛らしくないし、それにとどまらずルート君が生徒に向かって「博士は人と接するときにどうして良いかわからず、そうして数式でコミュニケーションを取っているんだ」などと「説明」してしまうのを目撃するとき、私たちは浅薄さ以上のものを感じることができない。
数式や証明は美しい、ということを知らない者たちは確かにこの世に存在しはしよう。数学が芸術の一つに他ならないことを信じない野蛮な連中もいよう。だからと言って、数学の論文誌で過去最高の懸賞金を獲得した博士が、「数式の美しさ」について「星はなぜ美しいかを説明するのが難しいように、(数式の美しさを説明することは)難しい」→「だが、数式は美しい」といった流れの中で「解説」し、「直感が大切」であるとしきりに促すのは、受けなかったギャグの面白さを解説している無価値な人間との会話のように、目を逸らしたくなる。
家政婦とルート君の異様なまでの「人間性の高い」設定も、本作とは本質的に無関係の冗長な道徳的名言を撒き散らす際に有効であったということの他に、役割を付与されない。「数式を愛する」深遠さを持つはずの博士が、自分は(世の中の)何の役にも立たない、という理由で臆面もなく頭を抱えてしまい、家政婦はそれに対する「道徳的なフォロー」を実演してしまうのだから。
時代設定にあわない流行の道徳的名言を過剰に織り交ぜながら、本作においては、すべての「感動のタネあかし」が、手垢にまみれた鬱陶しい言辞によってなされてしまう。
ようするに、饒舌に過ぎるのである。
当初は心を閉ざしていた博士の義姉が、博士らの「心の交流」に触れて、あっけないほど唐突に、母屋と離れとを隔離する「象徴」であったらしい木戸を開いたまま母屋に戻る――赤面すべきことに、その行為の意味についても義姉は口で説明してしまう――という残念な描写は、とりわけ圧巻であった。映画という表現手法における経済的限界――一般受けすることが必要である故に、知識を前提とする表現が不可能であり、流行を追わなければならないという芸術的な意味における絶望的限界の存在――に抗う術を模索するどころか、本作はその現状に嬉々として身を売ってしまっているのだ。
教師になった「ルート君」が、詐欺まがいの「感動的授業」を生徒に対して行ったのと同じことを、この作品は観客に対して強いる。ルート君同様、この映画は数式の美しさや数学の深さを決して伝えようとはしない。「数式は美しい」「数学は深い」という呪文を繰り返しながら、「生徒」にその理由を、嫌になるほど単調に、おずおずと説明することを反復するのだ。その結果皮肉なことに、真の意味での「数式の美しさ」や「数学の深さ」は、完全に生徒=観客の視点から計り知れないほど隠蔽されてしまう。
「数式への愛」「数式の美しさ」を、「描く」ことをせずに性急かつ稚拙に「論じ」すぎた本作は、どれかが偶然当たれば良いといった程度の、投げやりな、脈絡のない感動的表現を繰り返しながら、一応のハッピーエンドを迎えてしまう。
本作は数式に対する愛を「説明」して矮小化するための映画であり、名言の現代的ツギハギとしての駄作である。数学の問題に取り組んで悩み、時間をかけて正解に達したが、模範解答ではより美しいやり方が提示されていた瞬間の、胸の高鳴りや、全身が震えたあの感覚を、本作は一つとして伝えないし伝えようとしない。
おかげでデートがイマイチだったかどうかはともかく、一般受けはかなり良い映画らしいから、感動ドラマ等が好きな人には大変お勧めである。



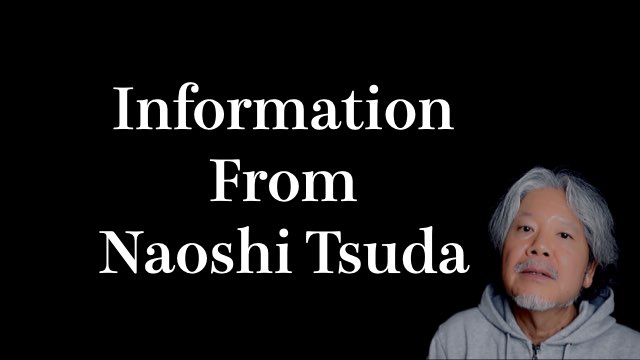
コメント
コメントを書く