

その6 古流武術の身体常識は?(後半)
僕は古流の時代のような武術との向き合い方で引退してからの日々を過ごしていた。島津先生から教えてもらった筋の取り方を毎日やった1年後、僕の指先に変化が訪れた。車を運転してると知らないうちに指先がハンドルに引っかかってたのだ。ハンドルを持たないでもハンドルを動かせる。
スパーリングでもいつの間にか相手に指先や掌が張り付く感じが出てきた。変化が訪れればそれが当たり前になる。当たり前のことを毎日続ければ、当たり前の精度が増してくる。その頃から僕は活法を学ぶようになった。最初は武術の身体の使い方を先生から教わる。ただ形を教わって毎日それを繰り返す。毎日繰り返すと身体が段々変わってくる。身体を動かす時の感覚が変わり、特に身体の内側の感覚が覚醒して出て来るようになった。それまで学んだ操体法と太氣拳で理解して引き出した身体の内側の感覚が学びを助けてくれた。身体の内側の感覚がどんどん大きくなっていったのだ。
古流の柔術は活法と殺法を同時に学ぶ。どちらかに偏ることはない。どちらか一方だけを学び手にすることは無理なのだ。活法で人を治せるくらいの精妙な感覚を身体に持ち、暴れまわる相手を一手に倒すほどの強さも併せ持つ。これが古流武術家の身体。精妙な感覚は闘う時に遅れを取らないもうひとつのコツであり、暴れまわる相手を一手に倒す力強さは活法のもう一つのコツなのだ。どちらか一方では足りない。力強さと精妙さのどちらも併せ持ち、活殺の両面でお互いに行き来しつつ使うことが古流武術には欠かせないのだ。
学びが進み自分で考え、感じる能力を使えるようになると、色々な気付きが生まれる。先生から教えてもらったら、それを持ち帰り毎日続ける。そのうちにやってくる身体の変化。それを次に会った時に先生へ伝える。その変化や気付きが正しければ、次に進むヒントとなるやり方を教えてもらえる。間違っていればもう一度同じことを聞かせてもらいやり直す。
武術の道とは本当に術に従い進む。術とは物事の本質や原理原則のようなものでもある。形を教えてもらったら自分でそれを何度でも繰り返す。そのうち身体から答えが滲み出てくる。滲み出てきた答え(原理原則)に従って次の教えを受け次の道を進む。武術を学ぶこととは、自分自身に術をかけ、術を染み込ませることだったりする。ただ身体を動かして進むのでは術は身につけられないのだ。
先生から教えて頂くようになって5年。引退してから12年。古流の時代の身体常識は現代とは違うことが少しずつ分かってきた。だからこそ現代からは思いも寄らないような技が現実に可能となるのだ。
古流の時代には筋肉という概念はない。概念どころか言葉すら存在していなかった。筋肉という言葉は江戸時代に杉田玄白による翻訳で広まった『解体新書』によって初めて日本に登場した。それまでの日本的な身体常識に筋肉という言葉は存在していなかった。存在していたら、新しく言葉を作る必要などないのだ。言葉が無いものを使っていたはずがない。
『解体新書』以前の日本の身体常識は筋という概念で構成されていた。筋肉と骨格ではなく、筋絡と骨絡という別の概念が古流の時代の身体常識。筋肉は更に細かく筋という単位で表すのが常識だった。西洋医学が解剖で実際に見て分析したのに対して、日本人は腑分け(解剖)を民族的に忌み嫌った。


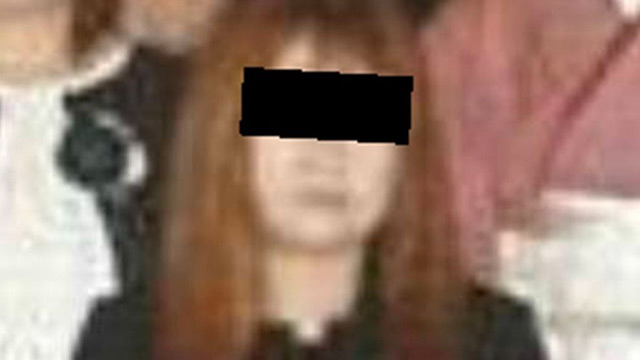

コメント
コメントを書く