小説『神神化身』第二部
第三十二話
「サンタクロースなんているわけないだろ」
三言(みこと)が呆れたように言うので、陣営が二つに割れた。三言と遠流(とおる)のサンタ否定派の二人と、タブーを犯した者を見る目をしたまま固まる比鷺(ひさぎ)と僕のサンタ肯定派の二人にだ。まさか、三言がそんな無体なことを言うとは思ってもみなかった。それに、眠たげな目を擦っているほわほわの遠流まで。ショックだ。遠流なんか絶対信じてそうな顔してるのに。比鷺も僕と同じくらい……いや、それ以上にショックを受けているようで、手をわたわたと動かしながら必死に反論をする。
「えーっそれ、み、三言が言うのぉ? いや、言いそうではあるけどさあ! 敢えてそれ言う必要ある!?」
「別にみんな分かってることだろ。そんなにぴーぴー言う必要あるか? 低学年ならまだしもさ。俺らもう高学年だぞ」
「みんな分かってるって……と、遠流は!? その絵本から出てきたようなすやすやネコちゃんも信じてないの!?」
「……サンタに手紙書くの、そもそも幼稚園の頃から……めんどうでしてない……でも、プレゼント来るから。おかしい……。僕の頭の中のプレゼントが見えるような超能力があるなら、手紙なんかいらないだろうし……」
遠流は現実的なのか何なのかよく分からない主張でサンタの存在を否定してくる。
「お母さんがプレゼントをくれてるんだとして……それはそれで、嬉しい……サンタじゃなくていい……」
それは確かに僕も同意だ。一理あるよ! と遠流の頭を撫でると、眠いからか唸(うな)られてしまった。機嫌がいい時はむしろ遠流の方から寄ってくるというのに、本当に気まぐれである。
分かっている。僕だって、サンタクロースは親らしいなんてこと、十分に分かっている。でも、それを敢えて口に出す必要なんてないはずだ。世界平和だって、現実には色々難しいかもしれないけどみんなが口に出して願っているじゃないか。敢えて「そんなのは無理だよ」なんて誰も言わないじゃないか。
そんなことを三言に言うと、三言は面倒臭さと興味の両方が混じった顔をして尋ねてきた。
「じゃーお前は、サンタに何お願いすんの?」
少し悩んでから真面目に回答すると、三言が軽く吹き出した。
「お菓子頼むのかよ! ハロウィンじゃあるまいしさ。そういうもんより、もっとここでしか頼めないデカいもん頼めよ」
何を言う。僕にとってお菓子のプレゼントは結構大きなものだ。普段は買えないようなちょっと豪華なお菓子とか、たっぷり入った大袋とか……そういうものが気兼ねなくねだれるのは嬉しい。
あと、なんだかんだでクリスマスケーキも僕にとってはプレゼントの一部だ。ブッシュ・ド・ノエルみたいな見た目も楽しいケーキが手に入るのは本当にありがたいことだよね……。
「ていうか、こっちはともかく比鷺までそんなの信じてんのかよ。お前一応賢いキャラなはずじゃん」
「……あのね、俺だって分かってんのよ。サンタクロースなんてもんが存在しないってことはさ。全世帯にプレゼントを行き渡らせなきゃいけないなんて、クリスマスイブの六、七時間では絶対に無理。そもそも子供の定義ってどっからどこまでか、プレゼントの単価が安い場合は平均プレゼント額に合わせて二つ貰える場合はあるの? てか日本には煙突のある家が少ないから、窓から入ってきてるの? 集合住宅だと警備システムと契約してるパターンが多いと思うけど、クリスマスに誤作動が多くなるって事例が報告されそうだし」
「お前は本当にめんどうな奴だな……」
遠流がしみじみと言う。声が比較的優しいのは、比鷺をちょっとは可哀想だと思ってあげているからだろうか。僕もこういうなんだか生きづらそうな比鷺は可哀想だし、頑張ってほしいなと思う。自慢の賢さがずーっと比鷺自身を追い詰めているような気がして、ちょっと不憫だ。
「そういう各種の『サンタいないかもポイント』に加えて、俺のところに来るプレゼントが絶対舞奏(まいかなず)関連の本とかなのも、不信感を煽るわけよ。一度でも俺の欲しいゲームソフトくれたりしないの!? まあ、普段からゲームとかは買ってもらってるけどさ、サンタさんという大いなる意思、そういう子供が逆らえない権威に舞奏を載せてくるのがすげーヤダ……。サンタさんはいるもん。俺がいい子じゃないから来ないだけなんだもん」
「自分が悪い子になるのはいいのか。この低燃費低評価人間」
「ぐ、サンタさんがいないってことになるくらいなら、俺がクソ家に生まれた悪い子ってことでいいもん!」
遠流のことをぽかぽかと弱い力で殴りながら、比鷺が悔しそうに言う。その振動がとどめになったのか、遠流はすやすやと眠り始めてしまった。これだけ健やかに眠ってくれるのなら、サンタもさぞかし仕事がしやすいだろう。
僕はサンタのことを信じているし、聞いているとこっちが寂しくなるようなことを言う比鷺のところにも来てくれればいいと思う。何なら、生意気なことを言う三言のところや、誰よりも熱心に眠っている遠流のところにも来てほしい。
幼馴染のところにプレゼントをくれないようなサンタさんなんて、ちょっと節穴が過ぎると思うから。
*
三言が知っている洋館といえば、比鷺の住んでいる『九条(くじょう)屋敷』くらいだ。浪磯(ろういそ)では殆ど見かけないし、浪磯の外に出た時でさえ、こんな洋館は見かけなかったような気がする。
譜中(ふちゅう)にある『昏嶋(くらしま)館』は、遠目から見ても目立つ、そうそうたる屋敷だった。まるで絵本か何かから抜け出してきたような、なんだか見ているだけでワクワクしてしまう。
これが昏見有貴(くらみありたか)の住んでいる──いや、所有しているが正しいのだったか──場所だというのは、彼の雰囲気も相まってとても似合っているような気がした。九条屋敷が全体的に白を基調にしてデザインされているのに対し、この洋館が落ち着いたシックな色合いで構成されているのもあるだろう。この館は夜に似ていた。
「どうですか? 六原(むつはら)くん。なかなか居心地のいい場所でしょう?」
「はい! 今日はお招き頂いてありがとうございます!」
「クリスマスパーティーというのは、サンタに因んだ七百七十七人の招待客を呼ぶのが慣例ですが、今回は櫛魂衆(くししゅう)のお三方に、私達だけということで」
「七百七十七人……だとしたら俺は、本物のクリスマスパーティーをやったことがないのかもしれません」
全力食堂で催したことのあるクリスマスパーティーでさえ、確か参加者は七十人程度だったはずだ。あと七百七人も足りない。そう思うと、本物のクリスマスパーティーがどれだけ凄いものか分かる。昏見が自分達をここに呼んで、簡略化されたクリスマスパーティーを催してくれたことの重さを、三言は改めて感じた。
遠流と比鷺もきっととても喜んでいるだろう。そう思って振り返ると、遠流は警戒した猫のように昏見を睨みつけており、比鷺は比鷺で何故か怯えていた。
「三言……何かあったら僕が守るからね」
「ありがとうな! 遠流!」
「それじゃあ八谷戸(やつやど)くんは私こと昏見有貴が守らせていただきますね! 素晴らしい連携です。これならいつ城攻めが行われても安心。戦をするなら私は孔明の役でお願いします!」
「心強いです! それで、俺達は何と戦うんですか?」
「己の心ですかね!」
「昏見さん。これ以上三言を惑わせないでください」
「俺は惑っているのか? その、遠流は概ねいつも通りとして、比鷺はどうしたんだ? 比鷺?」
比鷺は本棚の間と間に挟まるようにして、細い身体を更に細く見せようとしていた。人の家で、どうして存在感を消そうとしているのだろうか。そんなことをしても、比鷺はなかなか目立つので難しいだろうに。
「いやいやいやおかしくない!? 昏見さん家でパーティーって話だったのに、なんでこんなゲーム用語じゃない方のガチパーティーに参加させられてるわけ!? 俺かなり普段着で来ちゃったんだけど! 家具とかも一々最強に良いもんっぽくて、そこがもうワーッポイントっていうか」
「あら、分かります? 嬉しいですね」
「分かるよ~。分かっちゃうんだよ~。あと、食器が良いのはもうめちゃくちゃ分かる。何故なら俺ん家で使ってるやつと同じブランドだから……」
「くじょたんくんはとっても良い目をしていますね。物の良さを理解出来る子は好きですよ。その点所縁(ゆかり)くんはレトルトと手作りの違いすら怪しいですし、最近やっとフェルメールの真作と贋作(がんさく)が区別出来るようになったくらいで」
「それハヤシライスの話だろ……いや、袋麺の話だっけ? 悪かったってば……美味いレトルトだから手作りかと思ったんだって……。というか、フェルメールの真贋鑑定が出来たらもう別にいいだろ!」
自分の話をされていることに気がついたのか、皋(さつき)がそう言って近寄ってきた。
「なんか、クリスマスまで都合付けてもらって悪いな。どうかと思ったんだけど……ここまで来たらいいだろって昏見が言うもんだから」
「そんな……嬉しいです!」
「そうですよ所縁くん! 毒を喰らわば皿までと言いますから! これだけ仲睦まじく過ごしてしまったら、もうとことんまで仲良くしちゃうべきなんですよ!」
「それ用法あってんのかなぁ~?」
比鷺が首を傾げるのに合わせて、三言もとりあえず首を傾げておく。何やらよく分からないが、とりあえず楽しいことには乗っておくのが吉だろう。
「あっちにはクリスマスツリーも飾ってありますからね。ある程度パーティーに必要な食べ物とか未成年用のノンアルコールは用意してありますが、萬燈(まんどう)先生が張り切ってしまって厨房を借りてるんですよ」
「まさか、作ってるんですか?」
「そのまさかです」
昏見が頷く。すると、三言の身体もうずうずしてきた。昏見がそんな三言の内心を察したのか、笑顔で厨房のある方を指差した。
「どうぞ。萬燈先生も待ってらっしゃると思いますよ」
「ありがとうございます!」
そう言うと、三言は勢いよく厨房に向かって駆け出していった。
出来上がった料理達は絢爛(けんらん)の一言に尽きた。赤みがかったソースが掛かった肉だの、ゼリーのようなものに野菜らしきものが閉じ込められたものだの、なんかやたらツヤツヤしたプラスチックのようなドーム状のものだの皋には名前の分からない洒落た料理が五品以上あるので、きっと手間が掛かっているのだろう。それが十六人は掛けられそうな長机に所狭しと並べられていた。慣れ親しんだエビフライや、丁寧に盛り付けられた刺身なんかは見ると少し安心する。これは六原の担当だろうか。
探偵時代に豪勢なホームパーティーはいくつも見てきたが、今回はそれらに負けず劣らず素晴らしいものに見えた。贔屓目かもしれないが、心からそう思う。
これだけのものを作るのは大変だっただろうが、萬燈も六原も楽しげに調理していた。昏見も何品か作ったり、あるいはこれはこうした方がいいだのと言い合いながら笑っていた。全員料理が好きなのだろう。特に、六原三言の表情は修祓(しゅばつ)の儀の時に忌避(きひ)感すら覚えたあの自我の無さを感じさせないほどに生き生きしていた。
舞奏競(まいかなずくらべ)や舞奏披(まいかなずひらき)が六原三言に良い影響を与え、あの表情を引き出したのだとすればいい話だ。よかったな、と素直に思う。櫛魂衆の三人の為に用意されたやたら美味しいブドウジュースを飲みながら、ちょっと笑いそうになってしまった。
ああして楽しそうにしている六原三言を見ると、なおのこと頭の中に奇妙な像が浮かぶ。海と少年に、どこか見覚えがあるような気がする。そんなことはあるはずもないのに。
デジャヴという言葉で片付けるには重すぎる既視感。覡(げき)になる前の自分と六原三言に関係があるとしたら、それは探偵と依頼人の関係でしかありえない。何しろ、人との交流が極端に少ない人生を歩んできたのだ。六原に、自分は何かを依頼されただろうか? いや、皋は自分の呪わしき記憶力が事件のことを忘れない──忘れさせてくれないことを知っている。
「あらあら、こんなに参加者が少ないのに壁の花を決められましてもね。そろそろ皆さんで乾杯しようってお話になっているんです。こっちに来てください。それとも、またお得意の人見知りですか?」
そんなことを考えていると、昏見が話しかけてきた。頭の中の像を追うのをやめて、苦々しい顔で応対する。
「うるせーよ。俺はいつもこんなんだろ」
「やだー、開き直られちゃいました。折角のクリスマスなのに。私がこの場を用意した甲斐がありませんよ」
昏見はにこにことしながら皋の顔を覗き込んでくる。そこで皋は、ずっと疑問に思っていたことを口にした。
「ここ、昏嶋貴子(たかこ)……昏見貴子の家だろ。櫛魂衆の奴らっていうか……そもそも俺もだけど、入らせて良かったのかよ」
ここは昏見にとって大切な思い出の場だろう。何でもあけすけに話すようでいて、大事なことは何一つ語ろうとしないこの男が、昏嶋館に足を踏み入れさせることの重さに、皋は少し気後れしている。自分は、それほどの人間であるだろうか。
「ええ、勿論ですとも。この館は人間が大好きですから。お祖母様も喜んでいます。私の類い希なる霊力によってさっきヒアリングしてきましたから完璧ですよ!」
「お前さー……しっとりとした空気をそういう与太で崩す必要ある?」
「ちゃんと手入れはしているんですけど、お祖母様がいた時よりも少し古びてしまったような気がして」
昏見が不意にそう言って目を細めた。
「人が住まないと死んでしまう、というのは本当なのかもしれませんね。今では私も住んでいるわけではありませんし。月に二度ハウスクリーニングを入れるだけでは、折角の昏嶋館が可哀想です。この館は持ち主に似て人が好きだったのに」
皋が何も言えずにいると、昏見はひらひらと手を振りながら笑った。
「そうですね。所縁くんの言う通りでもあります。敢えて手の内を明かす必要も無いでしょうが、明かしてもいい手の内から花が出てきたら嬉しいじゃないですか」
そう言って、昏見が結んだ手からパッと小さな草を出してみせる。草花に疎い皋でも分かる、クローバーだ。ご丁寧に四つ葉であるのが小憎らしい。
「……花じゃねーじゃん」
「クローバーは花も咲かせますから。あげますね、それ」
「あげますねっつわれても、持ち帰るのに適当なもんとか無いんだけど。あ、ハンカチでいいか」
受け取った幸運の証をハンカチに載せ、磨り潰すことにならないよう丁寧に畳む。すると、昏見が嬉しそうな顔をするので居心地が悪い。こういう時にこそ何を考えているのか分からない顔をしてくれればいいのに。
「これがクリスマスプレゼントかよ」
「いえいえ、私のクリスマスプレゼントは煩悩の数に合わせて一〇八個用意してありますから! ああでも、君の幸運を祈るそれが、最初の一つ目かもしれませんね」
そう言うと、昏見は皋の持っていたグラスに目を向けた。
「この席でも、まだお酒は飲めませんか?」
「オーダーにケチつけんのかよ、マスター」
「ふふ、ここでもアルコールを飲まない君のこと、割とかなり大好きですよ。そうじゃない時もありますけどね。さ、そろそろみんなと交わりましょうか」
昏見が有無を言わせない様子でそう言うので、皋はゆっくりとその後に続く。
「ああ、そうだ」
昏見が振り返る。見慣れているはずの瞳が、何だか違った輝きを宿しているように見えた。
「なんだよ」
「私は所縁くんを昏嶋館に紹介することが出来て、よかったと思っていますよ」
紹介。まるで人に対するような言い方だ。だが、何故かその言葉がごく自然に馴染んでいた。
*
「ところで、食事はどうだった。八谷戸」
「……美味しかったです。そこは敢えて嘘を吐く必要が無いので。貴方は本当に何でも出来るんですね」
「気に入ってもらえて幸甚だ」
萬燈が笑う。勿論、三言が担当していた料理が一番美味しかった。けれど、萬燈が作った料理も負けず劣らずの味がした。何より、彼が心から調理を楽しんでいることが伝わってくるのが良かった。自分達に美味しいものを食べさせたいと思ってくれているのだ、と思わずにはいられなかった。
改めて、前よりはずっと見知った男のことを見つめる。
彼をこうして引っ張り、二人で話すのは修祓の儀以来だ。番組で共演した時を入れれば三回目。その都度、遠流は萬燈にあれこれを尋ね──彼は遠流によく分からない返答をする。
振り返ってみれば、遠流の知りたいことに対してまともに返してもらったことの方が少ないのではないだろうか。そう思うと、遠流はどうして自分は何度も同じ過ちを繰り返しているのだろうとうんざりしてしまう。
それでも、萬燈なら自分には見えていないものが見えている。その信頼が故に、こうして対話を試みるのがやめられないのだ。
「こうして大勢いる場で二人きりで話すのも久しぶりだな」
「そうですね。修祓の儀以来です」
「ああ。お前のスタンスが随分記憶と違って驚いた時か」
この人はどうしてわざわざそういうことを言うのだろうか。遠流が不快そうに眉を寄せたのを見て、萬燈が笑う。
「別にそういう顔をさせたいんじゃねえよ。お前は見る度に違う面を見せてくる」
「萬燈さんに対してはいつもこんな感じだと思いますけど」
「態度の話じゃねえよ。お前、アイドルとしても最近は面白えな。ウチの昏見は効いたか?」
萬燈が言っているのは、きっと櫛魂衆と闇夜衆(くらやみしゅう)の合同舞奏披の話だろう。……確かに、あの時の舞奏仕合(しあわせ)のお陰で──もっと言うなら、昏見有貴との対話のお陰で、遠流はアイドルとしての自分に迷わなくて済むようになった。
もしあそこで昏見が遠流の罪を、この居場所を見定めてくれると言ってくれなければ、遠流は動けなくなってしまっていたかもしれない。その点は、不本意ながら感謝している。
だが、それを目の前の萬燈に誇らしげに言われるのは癪(しやく)だった。ウチの昏見はなかなかのもんだろう、とその目が言っている。前々から分かっていたことだが、この男は自分のチームメイトのことが結構大好きなのだ。
「……僕らの比鷺もなかなか効いたでしょう。色々な意味で」
意趣返しのつもりで言ってやると、萬燈はあっさりと「大分な」と言った。何を言っても萬燈には流されてしまうらしい。溜息を吐きながら、遠流は尋ねた。
「あなたは今度の舞奏競で、水鵠衆(みずまとしゅう)と御斯葉衆(みしばしゅう)、どちらに期待してますか?」
「期待ってんなら、どっちにも期待してるさ。舞奏衆(まいかなずしゅう)なんざ、どうあったって面白え。各々に俺を喜ばせるに足るものがあるだろう」
「……そうでした。貴方はそういうことを言うタイプの人でしたね」
そこに嫌みや忖度が無いからこそ、萬燈夜帳(よばり)なのだ。萬燈は純粋にその二衆の対峙を楽しみにしている。化身(けしん)持ちだろうとそうでなかろうと、舞奏衆の来歴がどうであろうと、ただそこにある舞奏だけが、萬燈の評価の対象なのだ。
「意外でした。貴方は九条鵺雲(やくも)のいる御斯葉衆に思い入れがあるのかと」
「そう思うか?」
「だって、貴方は九条鵺雲を個人的に見知っているようでしたから」
以前、修祓の儀の時──萬燈は九条鵺雲について触れていたのだ。しかも、舞奏ではなく人となりを知っているような口振りだったから、気になってはいた。九条鵺雲が覡として舞奏競に出ることを知った今となっては、あの時に深く聞いておけばよかったと思わざるを得ない。
「見知るのと思い入れるのは別だろう」
萬燈があっさりと言う。それはその通りだが、あっさりと答えられても困る。そこで遠流は、別の方面から話をしてみることにした。
「前、九条鵺雲よりは九条比鷺の方が好き、みたいなことを言っていましたよね」
「ああ、そうだな。そこは変わっちゃいねえよ」
「それは……九条鵺雲のことは九条比鷺に比べたら好きではない、ということではなく、そもそも九条鵺雲のことが嫌いなんですか?」
その瞬間に浮かんだ奇妙な表情を、どう形容していいか分からなかった。単純な否定でも肯定でもない。好悪で割り切れるものでもなく、そもそも遠流がそれを解釈する言葉を持っているかも怪しい複雑な感情がそこにはあった。
「そういうわけでもねえな」
そして萬燈はどこか可笑しげに言った。
まったく、何もかも分からない男だ。言葉も分からないが、別の方面でも訳が分からない。溜息を吐いて言葉を続けた。
「まあ、……はい。僕はお手軽にこの二衆に関する鋭い洞察を頂きたかったのですが、それは叶わなかったというわけで、もういいです。ありがとうございました」
「率直な言葉は嫌いじゃねえぜ。特にお前からのものはな」
「そうですか。喜んで頂けて幸いです。それでは」
「七生千慧(ななみちさと)、っつったな。水鵠衆のリーダーは」
不意に出された名前に虚を突かれる。
「……彼がどうかしましたか?」
「あいつだけはちっと違うぞ。実際に会ってみねえと何にも言えねえが」
「違う……っていうのはどういうことですか?」
「俺はこれでも作家の端くれだ。どんな人間だろうと、一目見りゃそれまでの人生の有り様がある程度見えてくる。だが、こいつに限ってはそれが無え。どうなったらこんなことになるのか分からねえけどな」
確信に満ちた萬燈の言葉に、心臓が跳ねる。
それは……一体どういうことだろうか? 三言と同じように記憶喪失であるという意味なのかと思ったが、萬燈は逆に三言にはそんなことを言っていなかった。
長らく舞奏衆を擁立してこなかった上野國舞奏社(こうずけのくにまいかなずのやしろ)が突然出してきた、ノノウ混在の舞奏衆。そのリーダーは、来歴というものが存在しない……そんなことがあるだろうか?
「ねー、二人で何の話してんの? 楽しそうじゃーん」
その時、不意に比鷺が話しかけてきた。大方、遠流と萬燈の組み合わせが物珍しくて寄ってきたのだろう。本当のことは教えてやりたくないので、遠流は溜息交じりに言った。
「お前が小学五年生までサンタを信じてた話だよ」
「えっ! ちょっ……なんでそゆこと先生に言うのぉ!? 幼馴染だけの秘密にしとくもんでしょ!」
「いいじゃねえか。俺もそういう時節のイベントには全力でのっかんのが好きだぜ」
「そりゃ萬燈先生はそういうタイプのお祭り大好き人間だろうけどぉ……てか、俺だってそんな夢でキラキラみたいな感じの信じ方してたわけじゃないからね!? もっとこう……未来に託すような……俺の人生をよりよく生きる為のような……そういう信じ方を……」
しどろもどろにそう言っていた比鷺が、そこで不意に「あ」という間抜けな声を上げた。忙しい奴だな、と思っていると、比鷺はそのまま思いがけないことを言い始めた。
「そういえば、クリスマスといえば面白い思い出があって」
「ほう。どんな話だ?」
「クリスマス……?」
「え、遠流も覚えてるでしょ? 確か、サンタがいるとかいないとかで俺と三言が話しててさ、お前は……寝てたか。寝てたかも。いや! でもその後の作戦の時は流石に起きてたはず!」
「何の話かさっぱり分からない」
溜息交じりに言った瞬間、遠流も思い出した。そういえば、寒い中、三言に半分背負われるような形で比鷺の家に向かった覚えがある。
「あれだよ。俺がサンタさんなんか来ないーってあれこれ言ってたからさ、一度くらい夢叶えてやろうってことで、お前らが夜にこっそり俺ん家来てさ、裏から侵入してプレゼント置こうとしたんだよ。俺の部屋とか二階にあんのにさー、木登りが得意だからってんで乗り込んできて、ほんと馬鹿でしょ」
「……そうだった。お前がサンタがいないのは自分が悪い子だからとか馬鹿なこと言い出して……まあ、お前は悪いんだけど……」
「ちょっと!」
「……だから、一回くらいサンタが来てもいいんじゃないかって思ったんだよな」
眠い目を擦りながらの計画は面倒だったけれど、これで比鷺がちょっと喜ぶのなら、それでもいいかと思ってしまったのだ。あの夜は三言と……もう一人の幼馴染もいたのだし。
そう、あの日は幼馴染もいたはずなのだ。彼はサンタを信じていたのだろうか? それとも、自分や三言のように否定的だったのだろうか? どちらにせよ、その幼馴染も、比鷺にクリスマスプレゼントを──彼が『いい子』である証をあげたかったに違いない。
「なかなかの大冒険だな。お前も嬉しかったろう」
「聞いてよ先生。それがさー、駄目だったのよ」
「駄目?」
「知っての通り、俺の部屋って二階にあるわけ。てことは、屋根を登っていかなくちゃいけないんだけど……実は微妙に身長が足りなくて。連携したらいけるかもーってなったっぽいんだけど、結局無理で。どたんばたんやってるのに俺が気付いて、窓開けたらそういうことになっててさ。バレバレ」
「お前が夜更かしなのが悪い。わざわざ少し遅くに行ったのに」
「九条比鷺、お前そんな頃から夜型だったのか」
遠流と萬燈が揃って言うと、比鷺は「だって冬休みだったから……」ともごもご言い始めた。
「まあ、そんなわけで結局俺はこっそり裏から出て、サンタじゃない幼馴染からプレゼントを受け取ったわけ。確かお菓子の詰め合わせかなんかで、俺の欲しいゲームソフトじゃなかったんだけど」
「文句を言うな」
「でも、そのお菓子美味かったな」
比鷺が顔を綻ばせる。あの時から随分な時間が経ったけれど、遠流達が比鷺にあげたかったクリスマスプレゼントはあげられたのかもしれないな、とそれを見て思う。……きっと、あのクリスマスも、それが見たくて寒い中を歩いて行ったのだ。
「ま、今でも俺はサンタに来て欲しいけどね! こうしてある程度大人になっちゃうと、真相がどうであろうと、普通にプレゼントが欲しいし、宝くじ感覚で信じちゃうね! 今年の俺はかなーり良い子だったでしょ? 頼むよサンタさん!」
「そうか。なら、俺がサンタに口添えしておこう」
「ひゅー! 出た萬燈ジョーク! 段々萬燈先生が言いそうなこと分かってきた! ていうか萬燈先生なら、余裕で人の家とか侵入出来ちゃいそう──……なんつって…………あれ? ていうか、あの時ってどうやってたの?」
比鷺が不意に遠流のことを見る。さっきまでのふやけた表情じゃなく、どこか理知的な──名探偵のような表情だ。
「どうやってたのって……」
「俺の部屋に侵入する為に、まず一階の窓を足がかりにするだろ。だとすると、誰か一人が足場になって、その上に誰かが乗るわけじゃん。三言はそんなに背がおっきい方じゃないけど、身体がしっかりしてたからさ。きっと三言が足場だよね。じゃあ、遠流が乗ってたのかなーって思うんだけど……」
「……思うんだけど?」
「お前、俺ほどじゃないけどあの頃から割と背高かったじゃん。そんなお前が三言に乗るかって……や、ひょろひょろの遠流に三言が乗っかるのも危なそうだけど。冷静に考えたら、プレゼントの袋って結構大きかったし、足場になってる三言と、それに乗って二階に行こうとする遠流の他に、プレゼントの袋を投げ渡す役割必要なんじゃって……や、三言が投げ渡せばいいんだけどさ。そもそも、遠流が木登り成功してたの見たことない……いてっ」
不遜な発言に容赦無くデコピンを喰らわせつつ、考える。……確かに、自分が登ったはずはない。そんなに疲れることはしたくないし、木登りも確かにしない方だった。
なら、多分登ったのは幼馴染だ。どんな背丈か分からないが、あの当時の三言よりも背が低く、恐らくは木登りが得意で身軽だった少年。ややあって、比鷺は言った。
「なら、あの場って、もう一人いたのかな」
幼馴染の影は色々なところに残っている。消されてもなお、溶けては積もる雪のように、比鷺の中に現れている。
「でも、だとしたら忘れるはずないか。もしかしたら、サンタさんかも。それで、二人のこと手伝ってくれてたりして」
萬燈は何かを言いたげに口を開いたが、思い直したかのようにゆっくり笑った。
「そいつは夢のある解釈だな」
「あ、萬燈先生面白がってるでしょ。俺は本気よ本気」
比鷺が不服げに唇を尖らせる。その様は、まるでサンタクロースがいないと言われた時のようだ。幼馴染のことを忘れるはずがないという比鷺の意識が、それ以上を考えるのをやめさせている。それとも、比鷺の意識だけではないのだろうか?
だって、比鷺はもう肉薄(にくはく)している。本当のことに。遠流にさえもう分からない真実に。
その時不意に、水鵠衆の七生千慧のことを思い出した。
彼はとても小柄な体格に見える。幼い頃から彼が小柄な方だったなら、きっと三言を足場にして二階に乗ろうとするのには適役なはずだ。幼馴染の中で一番背が低いのなら、きっとそうなる。
それに、お菓子。三言はプレゼントにそういうものを選ぶタイプではないし、自分のチョイスとも思えない。だとしたら、その詰め合わせはもう一人の幼馴染のものなはずだ。彼はお菓子をよく食べていたのだろうか。
萬燈夜帳が『違う』と言っていた、水鵠衆のリーダー。来歴の──今までの人生の片鱗の無い覡。来歴が──本当はあったのだとしたら? クリスマスの思い出が、彼の空っぽな部分に嵌まるのだとすれば?
相変わらず見覚えはない。彼のことを見て、劇的に心に響くものはない。もし言葉を交わせたとしても、何一つ思い出せないかもしれない。
ただ、今の遠流は水鵠衆に──七生千慧に会ってみたかった。
自分は多分良い子と呼ばれる側の人間じゃない。ただ、もしクリスマスに奇跡が起こるとして──こんな自分にもサンタが来るのなら、たった一度でいいから、もう一度もう一人の幼馴染に会う機会が欲しかった。
その願いが一体どんな意味を持っているのかすら知らずに、遠流は密かにそう願っていた。
著:斜線堂有紀
この物語はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。
※当ブロマガの内容、テキスト、画像等の無断転載を固く禁じます。
※Unauthorized copying and replication of the contents of this blog, text and images are strictly prohibited.
©神神化身/ⅡⅤ



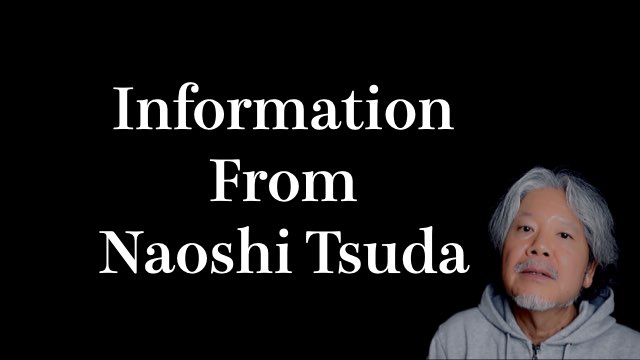


コメント
コメントを書く