序
1
桜の花びらが、舞いおりてくる。
満開の桜であった。
その満開の桜が、朝の光の中で散ってゆくのである。
風はない。
風もないのに、桜の花びらが、自らの重さに耐えかねたように枝からはなれ、光の中を散ってゆくのである。
その桜の下に、ひとりの少年が立っている。
いや、見た眼は少年なのだが、その面立ちの中には、もはや少年とは言えぬような大人びたものが漂っている。
肌の色が白い。
その薄い皮膚のすぐ内側の血の色が、透けて見えそうな肌の白さだった。
濃紺の細いズボンの上に、麻の白いシャツを着ている。
髪はゆるくウェーブしていて、眉が細い。
眸(ひとみ)は黒だが、やや灰色がかっている。その灰色の中に、わずかに碧い色が溶けているようでもあった。
それは、碧というよりは、その少年の内部にある哀しみの色が、そうやって見えてきてしまっているのかもしれない。
西城学園へ向かって登ってゆく、古い石段の上――そこに、この桜の古木が生えているのである。
小田原城が見え、その向こうに小田原の街が見えている。
もう少し向こうには、相模湾が陽光に光っている。
街は、まだ動き出したばかりだ。
四月――
ちょうど、この日から新学期が始まることになっている。
しかし、まだ朝が早いため、誰も登校してきてはいない。
その朝の光の中で、少年は桜の樹の下に立っているのである。
久鬼麗一(くき れいいち)であった。
学園は、すでに卒業式を終えている。
しかし、久鬼は、三月に行なわれたその卒業式に出ていない。
不思議なことがあった。
桜の枝からはなれた花びらが、しきりと久鬼の上に注いでいるというのに、その花びらが、一枚も久鬼の上に積もっていないのだ。その黒い髪の上にも、白いシャツの上にも、花びらが一枚もない。
よく見ていると、久鬼の上に落ちてきた花びらは、まるで、眼に見えない透明な力が久鬼を包んでいるかのように、触れそうになると、その身体を避けて舞い落ちてゆくのである。
久鬼の、その紅い唇が、かすかに微笑している。
ほんとうに笑っているのかどうか。
何かをなつかしむような、愛しむような、そんな微笑だ。
もう、帰れない。もう、もどれない。それがわかっている。
帰れない、もどれない、それがわかっているからこそ、黙って、だから、なつかしむようにそれを眺めている。
電車が動く。
クラクションが鳴る。
街のざわめき。
どこからか届いてくる人の声……
もう、そこへ、もどれない。
わずか三年だ。
わずか三年、久鬼はここにいた。
あの大鳳吼(おおとり こう)が入学してきてからは、やっと一年が過ぎたばかりだ。
しかし、そのわずかな時間のあいだに、なんと多くのものが詰めこまれていることか。
九十九三蔵(つくも さんぞう)――
真壁雲斎(まかべ うんさい)――
阿久津(あくつ)――
灰島(はいじま)――
そして、菊地良二(きくち りょうじ)。
そこへ、もう、帰ることはできない。
もう、十年、二十年の歳月が、過ぎ去ってしまったような気がする。
昨年の秋、自分は獣と化し、山の中を彷徨した。
それも、本当に昨年のことであったのだろうか。
石段の下方から、人が登ってくるのが見えた。
学生服を着ていた。
今年の、新入生が、独りだけ、早めに登校してきたらしい。
その時、背後に人の気配があった。
久鬼は、後ろを振り返った。
そこに、亜室由魅(あむろ ゆみ)が立っていた。
「行きましょう」
亜室由魅が言った。
久鬼は無言でうなずき、もう一度だけ、振り返って街を眺めた。
「行きましょう」
そう言った久鬼の唇からは、もう、あの笑みは消えていた。
2
その少年は、ゆっくりと石段を登ってきた。
一番上にたどりつき、ようやく、そこに生えている桜の樹の下に立った。
十六歳――
その顔には、まだおさなささえ残っている。
あれ?
と、思った。
さっき、下から見あげた時、誰かがこの桜の下に立っているのが見えたような気がしたのだが。
桜の下には、誰もいなかった。
そこには、透明な虚空(こくう)が張りつめているばかりであり、そこに舞い落ちてくる花びらが、光の中できらきらと光っているのみであった。
その虚空の中に、さっきまで立っていた人間のぬくもりのようなものが、何かの残り香のように、わずかにそこに漂っていた。

初出 「一冊の本 2013年6月号」朝日新聞出版発行
■電子書籍を配信中・
ニコニコ静画(書籍)/「キマイラ」・
Amazon・
Kobo・
iTunes Store
■キマイラ1~9巻(ソノラマノベルス版)も好評発売中 http://www.amazon.co.jp/dp/4022738308/

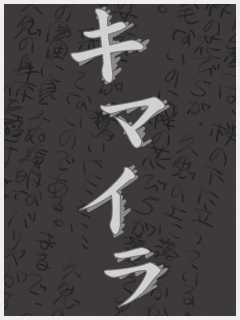 キマイラ鬼骨変
キマイラ鬼骨変

コメント
コメントを書く(ID:756130)
無理やり完結させなくてもいいです。
書きたいように書いてください。
書きたいように書いて、完結してもらえれば一番いいんですけどねw
(ID:1299096)
天野喜孝さんのイラストのイメージが・・・ まぁしょうがないのか。とにかく書いてくださればおk
(ID:24266540)
中学から読み始めてもう40過ぎちまったよ・・・でも劇中じゃたった一年の話か・・・
あとがきの、四十の男でも悩むということに安心なさい。て言葉に勇気付けられて若いころを過ごしてきたけど、
もうあの頃の獏さんと似たような歳になったわ・・・作品楽しみにしてるよ。
最後まで付き合うからさ。