
文芸批評家・福嶋亮大さんが、様々なジャンルを横断しながら日本特有の映像文化〈特撮〉を捉え直す『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』。『少年マガジン』をオタク的な感性で総合化した大伴昌司が大きな影響を受けていたのは、『暮しの手帖』を編集し、家庭の「暮し」の向上を訴えた花森安治でした。一見対照的なイメージを持つ大伴と花森の間にある共通点を明らかにします。
2 子供を育てる子供
花森安治から大伴昌司へ
以上のように、大伴昌司の情報化と視覚化の企ては、四至本八郎譲りのテクノロジー志向に加えて、アメリカのグラフ誌、戦争報道とともに成長した画報、児童向けの絵物語や絵本、マルチチャンネルのテレビといった諸々のメディアを背景としながら、サブカルチャーのオタク的受容(情報化/二次創作化)の下地を整えた。と同時に、大伴の原点にはオタク的な虚構愛好とは異なるドキュメンタリーやジャーナリズムへの関心があった。彼は一九七〇年には「一日も早く、『タイム』『ライフ』のような巨大なウィクリーが、少年週刊誌のなかから現われるよう努力します」という抱負を記した年賀状を送っている[27]。オタク的な二次創作(編集)の欲望と非オタク的な報道(記録)の欲望が交差したところに、つまりジャーナリスティックなオタクであったところに、彼の仕事のユニークさがあった。
さらに、ここで強調したいのは、大伴が先行する雑誌編集者を意識していたことである。例えば、大伴にまつわる証言を集めた『証言構成<OH>の肖像』(一九八八年)の執筆者は、彼が「『アサヒグラフ』の伴俊彦を尊敬し、『新青年』的モダニズムの機知を感じさせる伴のエディトリアル・シップに学ぼうとしていた」ことを指摘しつつ、こう続ける。
大伴が、すぐれたエディターとして尊敬していた人物には、ほかに『暮しの手帖』の花森安治(故人)と『週刊朝日』時代の扇谷正造(評論家)がいる。彼は後に『少年マガジン』で日本人の戦争中の生活を特集したとき、『暮しの手帖』を意識したレイアウトをして、見出しも花森安治ふうの手書きのレタリングにした。特集の発想そのものも、暮しの手帖刊『戦争中の暮しの記録』と同じだった。[28]
『暮しの手帖』の創刊者である花森安治は一九六九年の『戦争中の暮しの記録』で、戦時下の衣食住の様子を再現しつつ、戦争体験者から寄せられた多くの手記を収録した。それを受けて、大伴は翌七〇年に『少年マガジン』の特集で「人間と戦争の記録 学童疎開」と銘打って、自分もその一員である「少国民世代」(小学生時代に愛国主義教育を受けた世代)の疎開先での体験を、読者からの投稿をまじえて再現した。その後も、大伴は『暮しの手帖』をパロディ化した「料理の手帖」という特集を組んだ。
むろん、花森と大伴の振る舞いは一見すれば対照的である。花森が長髪でスカート(実際は半ズボンかキュロットであったという説もある)を穿いた異性装者として自己演出しながら、家庭の「暮し」の向上を訴えたメディア・アイコンであったのに対して、大伴は自らを「構成者」や「企画者」のような裏方に留めながら、家庭人とは真逆の男性オタクの源流となった。誌面のデザインについても、花森の『暮しの手帖』が原弘らの新活版術運動にも通じる「タテ組みのうつくしさ」(津野海太郎)を発明したのに対して[29]、大伴の『少年マガジン』の特集は垂直的な軸を見せるよりも、絵と文字を平面的に組み合わせることを選んだ。
にもかかわらず、この両者は「大人の男性の社会人」ではなく、会社組織に属さないいわゆる「女子供」に呼びかけて、その知識や技術の教育に注力したという一点で重なりあう。ちょうど円谷英二が「貧者の技術」として特撮を利用したように、花森は『暮しの手帖』で乏しい素材で生活をやりくりする技術を読み手に教え、大伴は『ウルトラマン』の二次創作を介して子供たちに怪獣の遊び方、いわば「オタクの暮し」のモデルを提供した。花森と大伴はともにたんに敏腕の編集者であっただけではなく、受け手にも自らの生活世界を「編集」する能力を与えたのだ。
そもそも、戦前の講談社の『キング』のモデルになったのがアメリカの婦人雑誌『レディース・ホーム・ジャーナル』であったことを思えば[30]、戦後の『暮しの手帖』が講談社の『少年マガジン』の先行者になったのも決して不思議ではない。大衆消費社会の最前線に生きる編集者として、花森と大伴はそれぞれ「女性」と「少年」という宛先を出版メディアの進化の担い手に変えてみせた。してみれば、大伴昌司をオタク化した花森安治と呼んでも、あながち言い過ぎではないだろう。

 ■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…

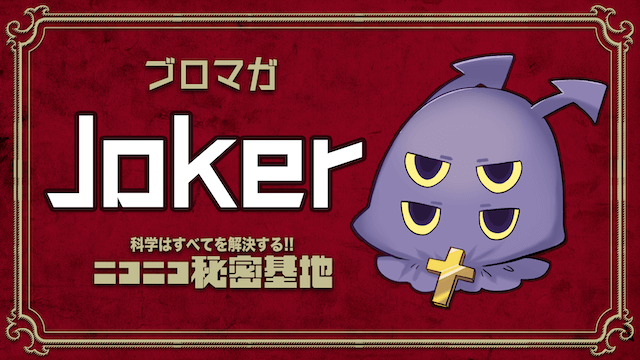

コメント
コメントを書く