その日は、朝から嫌な予感がしていた。
……誤解されないようにあらかじめ言っておくと、僕はいわゆる『第六感』とやらの存在を信じていない。あんなものは、論理的思考が不得意な人間の逃げ口上にしか過ぎないだろう。
ついでに言えば、UFOや超能力の存在もまったく信じていない。人類が映像機器を発明した途端に急増した宇宙旅行者や、素人の前でしか能力が発揮できないエスパーなど、信頼する方がどうかしているってもんだ。
そんな僕のことだから、この嫌な予感にはちゃんとした理由があった。いや、“予感”なんて表現を使うからややこしいのかもな。要するにだ、その日は不愉快な予測を立てるのに充分な事象が、朝から発生したのである。……余計にややこしいか。
とにかく、それは午前七時半過ぎのことだった。
すっかり夜更かしに慣れてしまっている堕落した大学生からすれば、えらく早朝と言っても過言ではない時刻だ。なので、突如鳴り響いたスマホの着信音によって起床させられた僕の気分は、まるで講演でメガネのことしか質問されなかったビル・ゲイツのように不愉快であった。
スマホを手に取ってディスプレイを見てみると、そこには『山岸 祥平(やまぎし しょうへい)』という名前が表されていた。これが、まず嫌な予感の根拠その1だ。こんな時間にあまり親しくない人間から電話が掛かってきたら、そりゃあ誰だってロクな想像を浮かべないだろうさ。
「……もしもし」
「おう、ザキ。今何してた?」
通話口から聞こえてきたのは、なるほど、山岸のねちっこい声だった。スマホのディスプレイは故障していないらしい。ちなみに、この『ザキ』という相手を死に追いやってしまいそうな単語は、僕のあだ名である。
「寝てたよ」
「そうか。でも、電話に出てるってことは、今は起きてるんだな」
「まぁな。……で、どうしたんだ。UFOでも見たのか?」
僕とは正反対で、超常現象の類を心から信じているらしい山岸にそう聞いてやると、
「残念ながらUFOじゃないけど、まったく外れって訳でもないぜ」
予想に反して含みを持たせる台詞が返ってきた。おいおい、軽いジョークなんだからそっちも軽く流せよな。嫌な予感の根拠、その2。
「意味がわからん」
「おまえ、確か今日は大学が午前中だけだったな」
よく知ってるな。親友って訳でもないのに。「ってことは、昼から暇なんだろ?」
いやはや、なんて失礼な男だろうか。そんな方程式は、僕が友達も少なくて、ましてや帰りを待ってくれている恋人など卑金属から貴金属を精錬する技術並みに存在していないという係数がないと成立しないぞ。
「暇と言えば暇だけどな」
あいにく成立してしまうんだけどさ。
「それなら、昼からうちに来てくれ。いいものを見せてやるよ」
「いいもの? 何だそりゃ?」
といった質問を無視して、山岸はさっさと自分が住んでいるマンションの住所を口にした。
「ザキが住んでいるアパートからなら、自転車で三十分もかからないだろ」
確かにそうだけどね。どうしてほとんど遊んだことのない、それどころか大学でも週に一、二回しか会わない人間の家に、僕がわざわざ三十分近くかけて行かなければならないのか。スマホ番号を交換しているだけでも不思議なくらいなのにさ。そういえば、僕の住むアパートをよく覚えていたな。一度話しただけなのに、やっぱり名称のおかげで強い印象を与えていたんだろうか? そもそも、おまえがうちに来るという選択肢はないのかよ。
そんな心の叫びに気がつく訳もない山岸は、
「じゃあ、待ってるぜ!」
やけに楽しげな声だけを残して、素早く電話を切っちまった。こいつのこんなにテンションが高い様子は、それまで見たことがなかったね。
ああ、もちろん嫌な予感の根拠その3、である。
※
それでも僕は、大学の帰りに自転車で山岸の指定してきた場所へと向かってしまうのであった。あまり交流のない奴の誘いは、余計に断りづらい。やっぱり友達も少なくて、ましてや帰りを待ってくれている恋人など卑金属から貴金属を精錬する技術並みに存在していない僕にとっては、あれでも数少ない知人の一人なのである。ちょっとは大事にしないとな。
山岸が住むマンションは、案外簡単に見つかった。のどかな周囲の風景に溶け込むことを頑なに拒否しているかのごとく、なかなか近代的かつ豪勢な造りの建物であった。親が金持ちだという話を本人から自慢げに聞かされてはいたが、どうやらあながち嘘でもないらしい。そこは嘘だったとしても全然腹が立たないのにね。
「おう、待ってたぜ」
無駄に重厚感のあるドアを開けて出てきたのは、言うまでもなく短髪でこずるい顔の山岸祥平だった。「遅かったな」
「昼からとしか指定されなかったからな」
今は午後三時半。確かに昼だ。「あがっていいのか?」
「どうぞ」
彼の手招きに誘われて最新AV機器が揃う居間へと足を踏み入れると、そこで予想外の光景に出くわした。
どうやら、今日の訪問者は僕だけじゃなかったらしい。
「ああ、こいつは俺の彼女だ」
先客である女性を指差して山岸が言った。
「彼女?」
「その、なんていうか、恋人だよ」
僕が『彼女』というフレーズを単なる三人称だなんて勘違いするとでも思ったのだろうか。ヤツは少し照れたような表情を浮かべながらそう訂正した。非常にムカつく。
「あ、はじめまして」
ムカつきながらも、軽く頭を下げる僕に対して、
「はじめまして」
ニコリともせず、彼女(ここでは、本当に三人称だ)は淡々と口を開いた。とりあえず、せめて目線くらいは合わせようぜ。
「この子は、幽霊が見えるんだ」
意味ありげな笑みを浮かべながら、山岸は彼女の肩を持った。「小さな頃からよく霊現象に遭遇していたらしくて、最近じゃあ死者の声も聞こえるらしい」
……おいおい、いきなりそんな紹介があるかよ!
あっけにとられた僕がしばらく言葉を失っていると、
「そう、私は幽霊が見える」
ようやく彼女が視線をこちらに向けてくれた。どちらかと言えば幽霊が見えているのは僕の方なんじゃないかと思えるほど、不気味な表情だった。「私は幽霊を感じることができるの。私の名前は悠子(ゆうこ)。私は霊の声を聞くことができるのよ。よろしくね」
名前を教えてくれるタイミングがいささかおかしい。
じっと僕を見つめてくる悠子さんとやらを観察してみると、なるほど、細身に今時珍しい超ロングヘアー、そして整っているとはいえ陰影を強く印象付けさせる顔立ちなど、いかにも幽霊に縁がありそうな女性ではあった。年齢は、同い年か、あるいは少し上くらいかな?
なんにしたって、発言内容からいってもあまりお近づきにならない方が良さそうな人物なのは間違いなかった。
「で、今日は一体何の用だ。彼女を自慢する為にわざわざ俺を呼んだのか?」
呪われそうな視線から目を逸らしつつ、僕が山岸に尋ねると、
「そうじゃない。……ただ、こいつもある意味必要なんだ」
「意味がわからん」
本日二度目の台詞を発した僕に、彼は一枚のDVDを手渡してきた。
「まずはこれを見てくれよ」
そのDVDには、こちらを凝視している不気味な女性の画像がプリントされていた。間違ってもファミリー向けほのぼのアニメではなさそうだ。
「『実際にあった! 呪いのビデオ16』……何だよ、これは」
馬鹿正直にタイトルを読み上げた僕が、当然そんな質問を投げかけると、
「これはな、一般の視聴者から投稿されてきた、つまり実際に撮影された心霊ビデオを検証する作品なんだ」
待っていましたとでも言わんばかりに、得意げな顔で答える山岸であった。「三年前にパート1が発売されてから、その筋ではかなり人気のあるシリーズなんだぜ!」
こらこら、ちょっと待て。その筋ってのはどこの筋なんだ? だいたい、三年前から始まって十六作品出ているってことは、一年で五本も出ているって計算になるよな。巷では、それほどまでに心霊ビデオが氾濫しているのだろうか? その割には、ニュースや新聞で大々的に取り上げられたところを見たことがないし、周囲でそんな代物を撮影したって話も聞かないぜ。そりゃあ、僕が友達も少なくて、ましてや帰りを待ってくれている恋人など卑金属から貴金属を精錬する技術並みに存在していないからだけかもしれないけどさ。
「……で、このパート16は、つい三日前に発売された最新作って訳だ」
過去の作品について長々と語った後、彼は最後にそう付け加えた。
「ふうん。でも、『呪いのビデオ』って言ってる割にはDVDなんだな」
わざと素っ気ない声で指摘してやると、
「『呪いのDVD』じゃあ、なんかしまらないだろ」
言われてみればそうだ。『呪いのフィルム』、『呪いのレコード』なら怖そうだが、『呪いのMP3』なんかはたいして怖くなさそうだもんな。科学の発展に伴い、どんどんと『呪い』が住みにくい世の中になってきてるんだろうね。
もちろん、科学的かつ論理的な僕は、最初から斜に構えた態度で山岸がDVDをセッティングする様子を眺めていた。
『幽霊の見える女性』と『心霊ビデオ』を鑑賞する、か。夏休み直前の退屈な午後の過ごし方としては、別に最悪って訳でもなさそうかな。
そうこうしているうちに放映が始まったこの『呪いのビデオ』とやらを解説すると、山岸の説明通り、視聴者から投稿された『幽霊らしきものが映っている』映像を、製作委員会が時には撮影された現場にまで赴いて検証するといった趣向の作品だった。とはいえ、そこに収録されていた映像は、『よくこんな部分を見つけたな。最初から何か映ってるのを知ってたんじゃないか?』とか、『明らかにその部分だけ画質が違うんですけど……』とか、『これって、たぶん遠くにいるだけで、普通に生きてる人ですよ』なんて突っ込みどころ満載の、ひらたく言えば『ヤラセ』としか言いようがない代物であった。
「おい、もっと真面目に見ろよ」
ニヤニヤしながら画面に突っ込みを入れる僕に対して、まさしく真面目くさった顔で不満を漏らす山岸。
「真面目に見ているからこその指摘だろ」
「そんなふざけた態度で見ていたら、本当に呪われるぞ」
笑えることに、どうやら彼はこの作品に出てくる映像全てが本物だと思っているらしい。こんなチャチなCGや合成に騙される男が二十一世紀に存在するだなんて、ジョージ・ルーカスが知ったらさぞかしショックだろうな。いずれにしても、『すみません、実際にあった! 呪いのビデオ製作委員会なんですけど……』なんて感じに取材を申し込むスタッフや、それに対して真剣に応じる学校の校長が出てくるドキュメンタリーなんか、どうやって信じればいいんだよ。全ての放送局で結果の違う朝の血液型占いの方が、まだすがりつきようがあるってもんだ。
僕の隣で鑑賞している悠子さんも、ちょっと困惑気味な様子だった。たまに、「これは、ニセモノだと思う」という空気の読めない発言を行って、彼氏から思いっきり睨み付けられたりしている。これでは、幽霊より生きている人間を観察している方が面白そうだね。
そういった僕の余裕綽々な表情が一変したのは、作品も終盤へと差し掛かった辺りのことであった。自分でそんな風に描写するのもちょっと変だが、きっと第三者から見てもわかりやすいくらいの変化だったろうから仕方がないさ。
三日連続失恋したかのような暗いナレーションが最後の投稿映像だという旨を伝えた後、画面には投稿者の名前と住所が表示された。
この時点で、僕は胸騒ぎを覚えた。アニメ好きだってことが丸わかりな投稿者の仮名に、ではない。僕が驚かされたのはもう一つの方、つまり、住所の方だった。
〈登草具(とそうぐ)町〉――。
どう考えたってこの変わった地名は、僕が半年前、生まれ育った町から大学に近い場所へと、要するに今住んでいるアパートへと引っ越して来る際に、何かにつけて書類に書き込まされたものと同一であった。
回りくどい言い方が嫌いな方には、こう説明しよう。
早い話が、それは僕が今住んでいる街の名前だったのである。
いやいやいや、偶然の一致かもしれないぜ。日本にはまったく同じ地名が複数存在していたりするからな。
ところが、続けて画面上に映し出された光景は、僕のささやかな願望を打ち砕くのに充分なインパクトを放っていた。
「投稿者によると、ここ最近、このアパート周辺で若い女性が殺されるといった事件があったらしい。その事件と今回の映像に、何か関係があるとでも言うのだろうか……」
あいかわらず陰鬱な声のナレーションが続く。殺人事件があっただって? これは初耳だな。
「では、問題の映像をご覧いただこう。アパートの入り口付近に注目して、ご覧頂きたい」
やけにかしこまったセリフの後、音声は完全に投稿映像のものへと切り替わった。誰が、いつ、どのような目的で撮影したのかはわからないが、とにかくそのカメラのフレームはずっと古びれたアパートの一部を捉えていた。
脇にある寂れた道路を、たまに車が通過する。そのライトによって、ようやくアパートの外観がおぼろげにわかる。
三台ほど車が通り過ぎていってから、映像に明らかな変化が現れた。アパートの入り口辺りに、何やら白いモヤのような物体が出現したのだ。
やがて、その物体は徐々に形を持ち始めた。……そうだな、例えるならば、動物界・脊椎動物門・哺乳綱・霊長目・真猿亜目・狭鼻下目・ヒト上科・ヒト科・ヒト属・ヒト種に属する生物の一種に、似ているような形だったね。
都合良く通り過ぎていった車のおかげで、さらに白いモヤの正体が半分にまで絞り込める。
女性だった。
「……これは、ほんもの」
唐突に隣にいた悠子さんが声を発したので、僕は驚愕のあまりのけぞりそうになってしまった。「この世に怨念を持った、女の霊」
ほんもの、だって? 急に何を言い出すんだこの人は。毎年ドラフトに出てくる『十年に一度の怪物』の方が、まだ信頼できるよ。
そりゃあ、僕だってこの映像が良く出来ているって点には異議を唱えないさ。収録されていた他の作品に比べて、あからさまな合成の跡も窺えないし、見間違うにしてはくっきりと映し出されすぎている。だけどそれって結局、最後を鮮やかに飾る為、下世話な話をすれば次回作も買ってもらう為に、ここだけは気合いの入ったCGを使ってみましたってところだろ。今や宇宙戦争だって魔法合戦だってリアルに創り出せる時代なんだ。一人の幽霊を画面上に出現させるくらい、朝飯前どころか前日の夕飯前くらいに簡単な作業だろうよ。
ゆっくりと問題の箇所をアップにしていくといった悪趣味かつありふれた演出によって、僕はその女性に関するある程度の情報を得ることができた。あえて陳腐な表現を使うと、彼女は恨めしげにも見える顔でじっと一点を凝視していたのだ。なおかつ、ただでさえ解像度の悪い映像なのではっきりとは判別できなかったが、少なくともそこまで年齢を重ねているようには見えなかった。
さらにもう一台車が通り、そのライトによって全身が照らしだされた瞬間、彼女は突然カメラの方に顔を向けた。
――それはまるで、太陽を見失った向日葵のような表情だった。
そこで、映像は途切れていた。後は、お決まりの砂嵐。ナレーションによると、ここでカメラが故障していまったらしい。こんなにタイミング良く故障するとは、おおかた某大手家電メーカーの製品でも使ってたんだろうな。
「……こういうことだ、ザキ」
不覚にも、僕はひきつったような顔をしてしまっていたんだろう。山岸はしてやったりという感じの顔でそう言葉を掛けてきた。「ぜひ、これを見たおまえの感想を聞きたいと思ってな」
肩をすくめながら、彼をきつく睨み付けてやる僕。
やれやれ、長いフリだったが、ようやく山岸の思惑が判明したよ。すなわち、彼がわざわざ僕を家に呼んでこのDVDを見せてくれた理由が、ね。
なにしろ、まだリプレイされて画面上に映し出されているその古びれたアパートは、紛れもなく僕が現在住んでいるアパート、『ツタンカーメン』なんだからさ。
……ああ、そうそう。
冒頭で言い忘れたけど、僕は『幽霊』なんて存在もまったく信用していない。




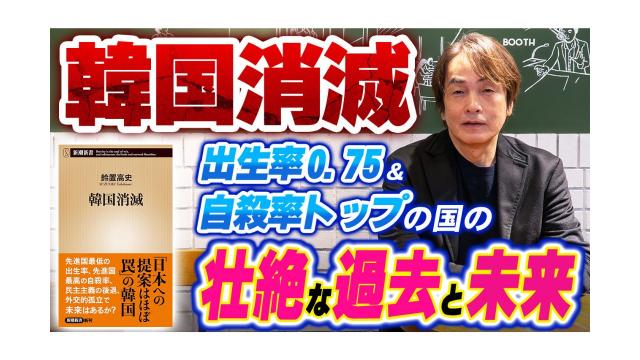
コメント
コメントを書く