ニコニコゲームマガジンで配信中の
「銃魔のレザネーション」のシナリオを担当した
カルロ・ゼン自らがノベライズ!
「銃魔のレザネーション」のシナリオを担当した
カルロ・ゼン自らがノベライズ!
ゲームでは描ききれなかった戦争と政争の裏側が明らかに。

いつからだろうか。
いつから、この国は間違えてしまったのだろうか。
エリーゼ・ユニマールは考える。
いつから、この国は後戻りできなくなってしまったのだろうか、と。
ハイマットの壮麗な白い宮殿。
その内奥、一室に集う貴族『諸賢』の中に混じって微笑の仮面をかぶり列席するエリーゼの内心は暗澹たるものだ。
黒い瞳を微かに揺らしつつ、彼女はままならぬ状況に目を伏せる。
染み一つないシルクのテーブルクロスが上に並ぶは贅を極めた正餐(フルコース)。ちらり、と目線をサーブされた磁器へ向ければまた呆れたこと。
オードブル一つとっても『富』を誇示せずには居られないのだろう。
場所が『こんなところ』でなければ素直に堪能したくなるに違いない。
……ここが、今、エリーゼ自身の招かれている場が『飢饉の対策会議』でないとすれば、の話だが。
おおよそ、まともな倫理観と道徳心をもつ人間ならば、それだけで罪悪感からフォークとナイフを手元から取りこぼしそうになる。
シュヴァーベン地方は、収穫期を迎えつつある。豊穣の秋、お腹いっぱいに子供たちが食べられるべき秋。にも関わらず、早くも……酷いところでは餓死者を出しつつあるというのに。会議と称して、王政府の高官らが浸るのは『飽食の宴』。
顔面に貼り付けたる笑顔にヒビが入らなかったのは、奇跡に近い。
現状は、深刻極まりない。エリーゼは、嘆かわしい現状を前にいつも顔で笑い、心で泣き続けている。
喫緊の課題である飢饉の問題。
だが、とエリーゼはいっそ『不作』であればと皮肉な思いすら抱いてしまう。
事実は、まったく逆だ。
ユニマール朝の農業収穫は、隣国、コモンウェルスより導入された魔法技術の活用により、年々、堅調に増加している。今年とて、収穫高は最低でも例年並みか微増が確実だろう。
にも拘らず、とエリーゼは歯噛みする。国内の貧困層どころか、平民層全般が穀物を購えていない。穀物そのものは収穫されているのに、である。
その理由は、極めて単純だ。生産された穀物の大半は輸出に振り当てられ、国内市場に十分な量が行き渡らないにすぎないのである。
自由都市同盟の方が、『高く買い取る』という理由でもって『徴収』された穀物は恐るべき規模で国外へ流出していく。
わずかに国内に流通する穀物は、物不足を反映して大幅な値上がりを示し始めていた。
悪いことは重なるもので、値段が上がるとふんだ商人たちの売り惜しみまで始まりつつある。このままでは、餓えた貧困層を中心としての暴動や打ちこわし騒動もありうるだろう。
もはや、まともに生活しようにも食料価格は、とても手の届くところにないのだ。
飢え死にを大勢が迫られているとあらば、倫理的にも、青い血の義務としても、放置することなど本来は許されるはずがない。
だからこそ、山積している所領での職務すら投げ打ってエリーゼはハイマットの会議へ駆けつけていた。
そして、案内された『会議室』が『正餐室』であった瞬間に全てを諦めざるを得ないと悟り、彼女は幾度なく味わってきた絶望をまた一つ重ねる。
華やかな会場にあってエリーゼの苦悩を理解し、分かち合える人物は一人としていないだろう。
理解者であり、師でもあったヨハンナ先生すら『貴族にあるまじき軽率さ』を口実にハイマットより追放される始末なのだ。
壊れた世界で、一人、正気を保つのはたやすいことではない。
「おや、エリーゼ殿下。杯が進んでおられません様だ。お口に合いませんでしたかな?」
「……いえ、ルメーリア公。良いワインだとは思うのですが、なじみが薄く。やはり、統治に追われる身では学ぶ機会が乏しいからでしょうか?」
ホスト役であるルメーリア公爵の言葉に、エリーゼはポツリと苦言を呈してしまう。随分と迂遠なことだ、と自分でも思わざるを得ないが。
統治に忙しい、という嫌味と取られかねない一言。されども、というべきか。嫌味とて、彼らには通じないのだ。エリーゼ自身、とうの昔に諦めている。
「なじみが薄い?」
「殿下、お言葉ではありますが……そのように下々に関わるなどと」
「さよう。ご趣味に苦言を呈するのは無粋ではありますが……」
まるで、学者より自身の専門領域での無知を告白されたかのように大様な驚きを見せる貴族ら。
誰もが、この場に並ぶ誰もが『ワインの知識』を誇り、『統治』という義務は省みもしないのだ。毎度のコトながら、教養こそが全て。実学とは、下々のいやしむべき所業と断言して憚らないおつもりなのだろう。
だからこそ、エリーゼのように数少ない良識人はいたたまれない。
されども、この場に会って、ホスト役であるルメーリア公だけはエリーゼの発言を笑い飛ばさない。それどころか、なじみが薄いという発言に頷いて見せていたのをエリーゼは視野の端で捉えている。
そして、好々爺然とした笑みとともに会場へルメーリア公は問いかける。
「皆々様は如何でしたかな?」
どのワインと見ましたか、と公爵からワイン通ぶりを問われれば……誰もがこぞってその知識を疲労しようと鋳物なのだろう。
王政府の施策に対する下問は聞き流すというのに。
「良いワインだとは思うのですが……さて」
「ポルトールの10年物! ヴァヴェルですら中々に流通しない代物でしょう?」
「いや、この仄かな土の柔らかさは……トラジメーノの限られた環境の代物に違いありますまい!」
喧々諤々、まるで、ワインの試飲会もさもありなんとばかりに語り始める彼ら。
「エリーゼ殿下、殿下はいかが思われますかな?」
「……残念ながら、と申し上げます。お恥かしながら、私は飲んだことがないと」
奇異の視線を一身に浴びてなおエリーゼは、しかし、恥じることはないとばかりに微笑み返してみせる。
『苦しいときこそ、笑いなさい、エリーゼ』
ヨハンナ先生の教えが、こんなときに活かされることを喜ぶべきだろうか? それとも、ヨハンナ先生を初めとする改革派がごっそりと失脚してなお『血統』故にハイマットに地歩を残せた自分の運命を呪うべきであろうか?
「殿下のワイン教育係は、更迭されたほうが宜しいでしょうな」
さらり、と隣のアンジャール公がしたり顔で寄越す助言。そのなんとも的外れな内容に、エリーゼの乏しい気力がどれほど削がれたことだろうか。
ワインの教育係?
そんな人を雇う余裕など、ない。限られた家産でもって、荒れ果てた国土を支え続ける家産は限界まで酷使している。
必要なお金も物も持ち出しばかり。
最低限の対面を保つ以外に、資金は全て内治につぎ込まざるを得ないのだ。そうでなければ、明日にでも破綻は避けがたい。かくほどまでににこの国は荒れ果てているというのに。
「いやいや、アンジャール公。むしろ、その人物を賞賛すべきでしょう」
「ルメーリア公?」
ぽかん、としたアンジャール公爵らに対し、ルメーリア公が典雅に笑ってみせる。面白がるような表情と、ちらり、とエリーゼへ寄越す賞賛の眼差し。
「殿下のお言葉が正しいのですよ」
お見事です、と此方へ語りかけてくるルメーリア公。
「ルメーリア公?」
「はて?」
訝しげな面々に対し、ご老人は高らかとボトルを取り出して胸をはる。
「皆々様、ご紹介させていただきましょう。モルヴィッツの地所にて……我が半生を賭して作り上げた国産のワインです」
誰もが、信じたがたいとばかりに、隣席と言葉をささやき交わす。
ルメーリア公その人の自慢げな笑みに、室内が一瞬の内にざわめき始めていた。
これでは、ワインの試飲会ねとエリーゼは小さく溜息を零すほかにない。
「こ、国産?」
「モルヴィッツで、これほどのものを作れた……と!?」
列席者がぽかん、と手元のグラスを覗き込む光景。
「さよう。いや、コモンウェルスと自由都市同盟の連中から技師やら何やらを確保するのは苦労しましたが」
「では……これを飲んだことがあるのは……」
「我が一門の面々を除けば、今日、皆様が初めてでしょう」
ルメーリア公が重々しく頷けば、ああ、なんという皮肉だろうか。貴族らによる、『賛嘆の声』が私へと飛んでくるではないか。
彼らは、私が、『未知のワイン』と見破ったと思い込んでいる。
「ははは、これは一本取られましたな」
「いや、エリーゼ殿下の御前でお恥ずかしい。知ったかぶりをいたしました」
『なじみがない』という自分の言葉を、誰もが『初めて飲むワイン』と『見破った』と讃えてくれるわけである。
……そもそも、ワインに通じる間もないだけなのだけども。
「ワインに通じていないが故のまぐれでしょう。皆様のように深い知識がある方々ならば、似たような味に思い当たられるのも道理かと」
「ははは、そう顔を立てていただけるのであれば実に幸いです」
「エリーゼ殿下に、ご叱責を賜るのではないかと。いやはや、お優しいお言葉に安堵するばかりであります」
皮肉ね、と心中でぼやきつつの言葉は品の良い謙遜と受け取られる始末。
そもそも、エリーゼ自身にワインの教育係が居ないといえばどれ程周囲が驚くことだろうか。いっそ、吐露してしまいたいほどだ。
衝動を飲み込み、敢えてエリーゼは本題へと話題を何とか引き戻す。
「さて、ご列席の皆様と優雅に酒宴と参りたくはありますが……国王陛下と王政府より信託された責務を果たさねば」
こんな面々とでも、飢饉対策を共にしなければならない。
そうしなければ、王政府の握っている金穀でもって餓えている人々を救済することすらおぼつかないのだ。
この会議が、権限握っているという超現実。そうである以上、どれほど不毛で徒労感に塗れようとも遣り遂げるほかになし。
「エリーゼ殿下のお言葉とあらば、いたし方在りませんな」
「左様、さて、今回の議題は何でありましたかな?」
「ああ、それならば確か……北部の治安悪化と飢餓問題でしたな」
ようやく、始まる会議の本題。
されど、されど。
「北部の治安悪化? 奇妙ですな。どなたか、ご存じですか?」
「いや、そのようなことは特に。私の所領も北部ですが、聞いたこともありませんな。北部は静謐そのものですぞ」
「ハンボーホ要塞からも異常の報告がありませんでしたが」
誰もが、真顔で疑問を浮かべるという異常な状態。けれども、彼らにしてみればそれが当たり前なのだ。
現地に足を運んだこともなく、経営の実務を下に任せきりになっている貴族ら。そんな人々に、判断をゆだねざるを得ないことのなんと無謀なことか。
無論、というべきなのだろう。貴族らとて愚かに生まれるのではない。貴族としての環境が、彼らを知的に異形な生き物とならしめるのだろう。
エリーゼの知る限り、知的に誠実な貴族が真っ先にこの違和感に耐え切れなくなる。多くは匙を投げ、自領に隠遁してしまう程だ。無理もないだろう。
とは思うものの、しかし、ここで投げ出すこともエリーゼには許されない。なればこそ、違和感に揉まれつつも彼女は最善を尽くし続ける。
「諸卿のお言葉にやや反するようですが……ドッガーランドにて騒乱が起きているようです。現地よりは悪質な盗賊と貴族崩れが暴れている、という報告が」
エリーゼが取り上げるのは、少数の官僚らと協力して自身で手を回して手配させた現状をまとめた報告書。これですら、元となった報告書からすれば、相当に抑制的な表現に切り替えられている。
悪質な盗賊どころか、正規軍の武装した脱走兵が部隊ごと放浪。貴族崩れと形容される連中に至っては、『本物の貴族』すら混じっていることが確認されている。それも、紋章院に記録されているような家柄の連中まで、だ。
憚りや配慮を延々と繰り返し、極端に薄めた報告書となったそれですら……会議へ上げることには相当な苦労を強いられている。
「誠なのですか? エリーゼ殿下、お言葉ですが……誣告なのでは?」
「もしくは、誤報か大げさな慌て者の痴れ事でしょう。そのような報告、現地の貴族からは飛び込んできていない」
恐るべきは、というべきか。ユニマール朝の疲弊しきった官僚機構制度は、機能させるだけで大仕事。それらを乗り越えて、辛うじて上申させている危機の報告はあっけなく、それこそちり紙のように脇に追いやられてしまう。
「となると、ふむ。残るは食糧不足の問題ですか」
「失礼ながら、どちらかと言えば過剰な輸出が原因です。輸出制限を検討すべきと王政府からは」
まともな提言、良識こそが、この場に置いては『異端』なのだ。
「また、困ったご意見を聞きましたぞ」
「自由都市同盟の業突く張り、ああ、失礼。商人共との貿易も契約がありますからな。平民相手とはいえ、金を持っている連中を軽視するわけにも行きますまい」
「全くですな。そもそも、いかに王政府といえども貴族の所領に介入されるのは如何なものか。貴族の忠誠心を蔑ろにされるのも困りものですな」
誰もが、真顔で、それを口にする。
エリーゼにとって、冗談でしょうと問いかけたい内容。しかして、彼女は同時に知っている。貴族達は、どこまでも、大真面目にこの言葉を口にしているのだろう、と。
「王家に列なるエリーゼ殿下に申し上げるのも誠に恐れ多くはありますが、王政府と王家にご諫言いただけませぬか」
「『それは、許されない』と。ずばり、申し上げるべきでしょうな」
沈黙しつつ、かすかに拝聴していますよと顔を動かすエリーゼの所作をどう解釈したのだろうか。
「とはいえ、殿下。殿下とて、国王陛下に申し上げにくいことではありましょう」
「急ぎではありませぬ。貴族らの総意としては、反対であるとのみお伝えくださいませ」
「折を見て、苦言を呈していただければ、それで宜しいかと」
さも、鷹揚そうに伝えられるは戯言。エリーゼにとって、しかして内容は暗澹たる結論を意味するものでしかない。
会議の出席者は、権限を持つ人間らは、誰一人として『問題に取り組む』ことを一顧だにせず、王政府へのクレームでもって結論としているのだ。
「ふむ、名案ですな。では、この気まずさをワインで洗い流すといたしましょう」
「ルメーリア公の逸品、そのような用途に使うのはちと気が引けますな」
「なに、諸賢の好評を頂ければそれが何より」
笑顔を保ち、ただ、時が過ぎるのを待つばかり。
エリーゼの心は、早くも、悲鳴を上げ始めていた。
……飢饉、飢餓、餓死者。
豊穣な大地を持つはずのシュヴァーベン地方で『また』、『農民』が餓えて斃れていく。青い血を引くと称する人々、ノブレス・オブリージュを果たすべき自分達のなんと無能なことだろうか。
何も、何もできない無力さ。
そして、会議という形式すら放棄された空間に広がるのは……『飢饉対策』という建前すら忘却された会話だ。
青い血、ノブレス・オブリージュ。
その全てが、呪わしくすらある。
私の属するユニマール朝は腐りつつある。
否、根底は朽ち果てた。
……過剰な形式主義、過剰な貴族特権、過剰な貴族主義。
華やかさの直下に、何が潜んでいるかを見ようともしない。
それが、現状。
なんと、素敵なんだろうか。
◇
いつからだろうか。
モーリス・オトラントはたまに考える。
いつから、何事も楽しくなくなったのだろうか?
そこで、彼はいつもちょっと訂正する。
楽しさというか、驚きがなくなったのはいつからだろうか? と。
コモンウェルスが王都、ヴァヴェル。
壮麗さと威厳、そして積み重ねられてきた歴史がかもし出す荘厳さ事態は決して嫌いではない。
けれども、とモーリスは嘲笑する。
ヴァヴェルの立派さと裏腹に、その地に住まう人間はどうにも愚鈍極まりない。分類してみれば、実に多様な愚か者どもを見つけることが可能なほどだ。
オーソドックスに行けば、極めて愚かという連中が数的主力だろう。
ついで、どうしようもなく愚か者、辛うじて人間の真似事が出来る愚か者という連中が我が物顔で戯言を叫んでいるのも目の当たりにできる。
世界の不思議というべきか、ある意味では謎なのだが……文明圏で呼吸できているのが不思議なレベルの愚か者や、森にでも帰らせた方が当人の為ためとでもいうべき愚者まで平然とそろっている。
ヴァヴェル政界を眺めれば、愚者の国際博覧会も良いところ。
「……かかしの相手をする方が、まだしも愉快でしょうね」
どいつもこいつも愚鈍で、しかして、自分こそがもっとも英知に富んだとすまし顔。馬鹿馬鹿しいことこの上ない。モーリスが認めうるような知恵者、あるいは辛うじて人間的知性を保つ存在は『愚者』どもに疎まれて辺境行きだ。
愚かなくせに、プライドだけはペガサスの飛行限界よりも高いところにあるに違いないのだから片腹痛い。
その親玉こそが、眼前で踏ん反り返っているともなれば。ユーモアの一つも胸中で零さなければやっていられるものではなし。
やれやれ、とモーリスはそこで表情を取り繕い恭しく拝跪してみせる。
「国王陛下、モーリス・オトラント辺境伯、御前に参上いたしました」
眼前におわしますは、ジョナス・ソブェスキ陛下。
コモンウェルス国王にして、ソブェスキ一門の家長。セイムとの協調関係を重んじつつ、大陸における秩序の憲兵としてコモンウェルスを率いる保守主義者。
『稲妻』と号されるほど卓抜した雷撃魔法の使い手であり、即位以前は周辺国との紛争において武名をとどろかした武人でもある……ということは。
実に、つまらない男である。
「ご苦労、オトラント辺境伯。南方情勢は、いかがか」
「陛下の武威とご威光あればこそ、恙無く。オルハンの越境襲撃も絶えて久しくございません。我が辺境は、静謐を保っております」
「さようか」
秩序の憲兵とは、つまるところ何事も変えられない無能の言い換え。
保守といえば、日々を保つことを意味するのだろうが……『進取の精神なき保守』ならばただの度し難い退嬰だ。
揚句、稲妻と讃えられる雷撃魔法の使い手であるのは『一武人』としてはまことに結構なことではある。武人としてならば、それを誇るも宜しいだろう。
だが、『即位』してからすら『尊号』が『稲妻』という一介の武人から変化しないという一事の裏を悟れないのは度し難い。
それは、『統治者』として『称えられる値しない』ということの何よりも雄弁な証拠だろう。それを、理解できないのだ。
おお、愚者の展示品、ここにも見つけたり、ということである。
統治者、行政官、外交官としての資質ははるかに平々凡々。セイムとの協調関係を重んじる姿勢にしたところで、政治の舵取りが出来ぬがゆえの消極的帰結。
こんな男に、才幹を捧げて仕えるのかと幻滅する日々ばかりだ。とはいえ、好き嫌いだけで仕事を怠ればまた厄介ごとも生まれるというもの。
「ですが、奇妙な兆候が」
「何? いかがした」
「オルハンより、ユニマール朝へ幾つか軍需関連の輸出があったと」
流石に、戦功を残した軍人だけに『戦』のことならば少しは話も早いのだろう。ぴくり、と眉が動く様からして……セイムや政経といった話題の時よりも食いつきは悪くない。
「軍需関連の輸出? 捨て置けんな、詳細を」
「西方軍需工廠より、旧式のマスケット銃とその製造設備が発送された模様です」
オルハン神権帝国にもぐりこませている、モーリスが情報網の一端がつかんだ兆候だ。
軽視するには、余りにも重大すぎる情報だろう。
まともに考える頭があれば、まともに物事を見通す眼があれば。だれだって、軽んじたりはしないだろう。
『旧式の武器』を『オルハン』が『ユニマール』に『輸出』!
それだけで、モーリスは欣喜雀躍して面白い陰謀を嗅ぎ取ったほどである。
「詳細は不明なのですが、ポーラ港へオルハンの船が向かっています。シャウエンブルク港や近隣地域にもです」
あの化石じみたユニマール朝の似非貴族どもについて、少しでも知っていれば嫌でも想像ができた。眼前の陛下ですら、ユニマールの愚物共と比較すれば世紀の大賢者に見え来ることである。
ユニマール朝の貴族評議会と比較すれば、度し難く愚かとモーリス自身が見下す在ヴァヴェルのセイム議員共を『英知の人々』と呼んだって許されるに違いない。
それほどまでに愚かしく、手がつけがたいほどに傲慢なユニマール朝の連中だ。
何をどうすれば、連中が『嫌いぬいている』オルハンから『旧式』の武器など買うものか。面子にかけて、断固拒否することに決まっている。オルハンからの輸入を発議した政務官など、次の一時間後には隠遁に追い込まれていても不思議ではないだろうに。
「まて、オトラント辺境伯」
「はっ、何事でありましょうか」
ジョナス陛下の知性に期待はしていない。それは、早々に見切りをつけている。しかして、武人としての勘はどうだろうか?
仕事をするだろうか? モーリスとしては、そこだけが楽しみな謎だ。
しかして、少しばかり、ほんの少しばかりだけ期待して言葉を待てども結果は……いやはや、予想通り。
「卿は旧式のマスケット銃とやらで、そのように大騒ぎするのか?」
浴びせられるは、呆れ声。
拝跪した手前、察するばかりだが……ジョナス陛下の御気には召さないらしい。ああ、と恭しく拝跪し表情を隠しつつモーリスは侮蔑も明らかに小さく哂う。
なんと、まぁ、予想の範疇だろうか。
「イェニチェリ共ならばいざ知らず、魔法も使えぬ無能者どもぞ? あんな代物では、使い道などさしてあるまい」
全く、目の前で何事が進んでいるかも理解できないとは。無能者を哂う、無能な国王陛下というわけだ。
魔法が使えるオツムの軽い国王陛下。よりにもよって、これが、コモンウェルスという壮麗な魔法文明のトップ!
やれやれ、毎日がつまらなくなるとはこのことだろう。来る日も、来る日も、愚か者の国際展示会へ顔を出すのも楽ではない。どうせ鑑賞するならば、愚か者の実物展示ではなく、壮麗な芸術なり音楽なりを堪能したいものなのだけれども。
「大方は、治安情勢の悪化している北部の治安回復用だろう。無能者共の武器一つで、騒ぐまでもあるまい」
マスケット、それは『無能者』の為のちょっとした出来の悪い武具。大した使い道もなく、軍事的な脅威でもない。捨て置け、と一蹴されるのは……まあいい。
ある程度までならば、仰ることも理解できる。
「ですが、オルハンの意図が気にはなりませんか? ご許可を頂ければ、少し探りを入れてみますが」
けれども、軍事的な側面はさておき『政治や外交』という要素を考慮するのがまともな統治者の責務なのである。モーリス自身、不真面目な統治者という自覚はあるが、そんな自分ですら違和感を抱くオルハンの『動向』を聞き流すのはありえない。
流石に、ここまで噛み砕いて説明すればジョナス陛下にも五分五分の確率で理解できることだろう。
重要なのは、とさり気なくモーリスは強調する。
「旧式とはいえ、武器を提供するオルハンの意図。探りを入れてみる価値もあるやもしれません」
「無用だ、無用」
「は?」
今、なんと?
無用、と即座に断言されるとは思っていなかった。それだけにモーリスとしては思わず顔を起こし、ジョナス国王の表情を直視してしまう。
発作的に幻滅しましたと嘲笑しかけるのを堪えるのも、中々に大変だというのに。
「さして重要にも思えん案件で、オルハンを刺激する必要もあるまい」
「刺激いたしますでしょうか? 大変に失礼ながら、陛下。このような外交方針に関する調査を目的としての接触程度であれば……」
「セイムの面々を煩わせる価値のある案件でもあるまい。オトラント辺境伯、進言はそこまでとしてもらいたい」
つまるところ、セイムが苦手なだけではないか!
これが穏やかな保守主義者、良識的な国王陛下のご実体というわけだ。子供が好き嫌いを口にして、嫌いな野菜を取り除くがごとき幼稚さ。
おお、神よ、と発作的に笑い出さなかったのは殆ど奇跡に近いほどだろう。
とはいえ、南方防衛を司るオトラント辺境伯としてのモーリスは、やはり、言上せざるを得ない。徒労に終わるとは思うにしても、やはり、職責というのがあるのだ。
「さりながら、陛下。この程度の調査ならば」
「ひかえよ。セイムの貴族諸君といい、軽々しく対外政策を語るが……我々のような超大国の動きは針小棒大にみられるものと心得よ」
「……出すぎたことを申し上げました」
恭しく再び拝跪し、御前より退出。私宅に下がったモーリスは政務を放り出すと独り自室にこもる。馬鹿馬鹿しい連中を相手にした後、しばし、飲まねばやってはおれないのだ。
一人酒、というのも物思いに耽る上では存外に悪くない。
「さて、何にしますかね?」
机の上に取り出すは、愛用している酒器。
「いつものは悪くないけれど、少し、変化も欲しいところです。……そうだ、あれがあったな。試してみますか」
考えた末に注ぐは、ルメーリア公が育て上げたモルヴィッツ産のボトル。
あまり期待してなかったのだが……予想以上のものだ、というべきだろう。シュヴァーベンが大地の地味を丁寧にブドウとして結実させ、それを念入りな仕事でワインにたらしめたと確信しえる代物だった。
ルメーリア公の家令を買収していた際に、手土産としてもらったものだが……ユニマール朝のお貴族様連中が楽しむには、なるほど、過ぎたものである
「とはいえ、このワインを来年も楽しめるかは微妙ですね」
ユニマール朝情勢は、激動が予期しうるだろう。オルハンの策動や、積もり積もっている内部の政治的課題は爆発寸前との兆候もある。ワインのように繊細な管理が必要な趣向品を、果たして陰謀の渦中にあっても確保できるかは運任せになる。
そして、運に物事を任せるというのは人事を尽くした上での選択肢たるべきだ。
「ふむ、悪いものではない。何より、希少な価値がある。……今少し、横流しさせるとしますか」
さて、とモーリスはそこで頭を切り替える。
ワインを楽しむのも良い。
けれども、そろそろ本題を考えるべきだろう。
「……やれやれ、あの陛下はやはり駄目だな。旧式の武器を『オルハン』が『ユニマール朝』に『輸出』という異常さをご理解いただけないとは」
あの化石じみたユニマール朝の似非貴族どもが、『嫌いぬいている』オルハンから『旧式』の武器など買うものか。
まして、『銃』を下賤な装備と蔑む連中だ。整合性が揃わないと気付くはずなのだが。なんだって、そんな単純な疑問すら抱かないのか自分には理解が出来ない。
おかしなこと、陰謀の匂いがこれほどに立ち込めているのに。
……『無用な刺激』を避けるために、調査するな、と。本音の部分では、セイムを敬遠してだろう。なんとも、器の小さい男だ。
そんなジョナス陛下に忠誠を捧げる?
馬鹿馬鹿しい。なんと、退屈極まりない。
否、否、否。
これでは、目の前で楽しい悪だくみに首を突っ込むなといわれるようなもの。全く、オルハンとユニマール朝の外交関係が改善でもしたらどうなるのか?
あるいは、とモーリスはそこで視点を変えてみる。銃の輸出は、そもそも、本当に『ユニマール朝』への輸出なのだろうか?
ふむ、と考え込めばそれほど悩む必要のある問題もない。
ユニマール朝が正式に手配することは、かの国の政情からして不可能。
ならば、一部の軍人の独断か? しかし……そのメリットがあまり思い浮かばない。
はた、とそこでモーリスは気が付き微笑んでいた。
「……いや、『ユニマール朝』への叛乱を煽るとも見れますね?」
ユニマール朝への輸出品だが、別に、ユニマール朝が最終受取人であるという話もなし。
それこそ、かの国の情勢を考えれば『火種』はいくらでもあるようなもの。燎原を焼き尽くす火を起こすこととて、現状ならば不可能ではないだろう。
そして、オルハンにはそれを行う能力がある。
成功すれば、『少なくとも』今よりは親オルハンとでもいうべき国家体制がシュヴァーベンの地にできるだろう。失敗したところで、『少なくとも』今よりも無能者や貧困層に対する『ユニマール朝』の抑圧は強化されるだろう。
そうなれば、間違いなく多数の流民が自由都市同盟と我々コモンウェルスに飛び込んでくる。
この点で、モーリスの念頭に浮かぶのはコモンウェルス西方を預かる二人の辺境伯。
「……イグナス女辺境伯は、この点、お甘い。入れる、間違いなく入れるでしょうね」
奇妙なまでに、善良であることに拘泥するタイプの女性だ。モーリスには理解できない世界に生きているタイプであり、何がしかの強迫観念すら感じられるが……そこは、まぁ、今回は関係ない。
重要なのは、イグナス女辺境伯は『絶対に』流民へ甘い態度を示すだろうという読みだ。
「加えていうならば、『彼女』の性格は広く知られてもいますね。オルハンの連中が知っていたとしても、驚くには値しません」
さて、と思考を続ければ問題はここから。酒器を傾けつつ、モーリスは少し記憶を漁る。
「アッシュ辺境伯は、どうだろうか。……わからないとはいえ、不確実が残る」
正直に言って、アッシュ辺境伯のことをモーリスは通り一遍にしか知らない。調べた限りでは、武人だ。しかし、一方でジョナス陛下ほど『愚か』そうでもない。
存外、頭の根幹は悪くないのだろう。
だが、気質的に戦場を好みすぎるという点では陛下の同類だ。
「ということは、『敵』以外には特にこれという方針がないということですね」
……そういう意味では、流民の流入に対してこれといった政見を抱いているとも思えない。
通過を許すということは、用意に想像されうる。あの手の武人は、敵以外には比較的甘い。甘いというよりも、変な誇りがあるというべきだろうか?
どちらにしても、結論は同じだ。
「流民、地方情勢不穏……いや、違いますね。ヴァヴェルに流入するでしょう」
モーリスの知る限り、動乱にあって歴史的事実として人々は『望まぬ移動を強いられる』。生まれ故郷を逃げ出す人々の大半は、寄る辺がない流民だ。
だからこそ、彼らは一縷の望みを抱いて『都市』を目指す。
コモンウェルスの場合は、ヴァヴェルに代表される大都市がその対象だ。或いは、自由都市同盟の『ポリス諸都市』も候補だろう。
「ふむ……そういう意味では、厳格な国境管理を行っている自由都市同盟よりもわれわれの方が国境は脆弱ですね」
やれやれ、と嘆きたいことではあるものの。コモンウェルスの国境はあまりにも広い。壁を築いているとはいえ、スキマもまた無数にあるのだ。
軍隊のような大規模かつ組織的な人的移動を食い止めることは出来るだろうが……。
「困ったな、流民の浸透までは阻みようがないでしょう。いったい、その内のどれほどが『手に職』を持っているのでしょうね?」
魔法文明と称する我らがコモンウェルスは『無能者』の居場所がない。
流民のように、貧しく、かつ、魔法も使えない層は都市での生活一つとってもままならないだろう。
手に職を持つものならばいざ知らず、故郷から命からがら逃げてきた『無能者』は自ずと生きるために手を汚さざるを得なくなる。
そうなれば、とモーリス・オトラントは苦笑する。
「第五列、潜在的なスパイ層、或いは我々への叛乱。オルハンにとって、随分と都合の良い手先が出来上がるわけですね」
どちらに転んでも、オルハンに損がないという寸法か。
意図を読めば読むほど、手堅い賭け。
「やれやれ、南の方々が羨ましいことです」
遊び相手に事欠かない上に、遊ぶことを許されているとは。
……思わず、悪戯に自分も加わりたくなるほどじゃないか。
第一章
モルヴィッツにおいて、主将たるエリーゼ・ユニマール将軍は天を仰ぎ、一言、胸中で恨み言を零して溜息。濡れ羽色の髪を苛立たし気に撫で、逡巡を払うように一瞬だけ目をつむり、小さく口を開く。
「……ここまでね」
後世に曰く、モルヴィッツ会戦と称されるに至る戦い。
それは、ユニマール朝滅亡に至るまでにおいてシュヴァーベン革命軍が直面したただ一度の大きな戦いとして知られるに至る。
歴史書ならば、そこでページを閉じれば終わるだろう。
しかし、未来を知ることなど叶わぬものだ。当時の指揮官であるエリーゼ・ユニマール将軍もまたしかり。
その当時、敗北を知るや否や、彼女は『敗北のあと』に『起こるであろう』惨事を予見し、諦観のうちに覚悟を定めざるを得なくなっていた。
「撤退します。少しでも、兵を逃さなければ」
「エリーゼ将軍!?」
まだ、我が軍は、と反駁してくる貴族将校ら。
「我が軍はまだやれます!」
「光輝溢れる王軍が、退くなどと!」
「王家のご威光に泥を塗るが如き所業など!」
なんと、おめでたいことかしら。眼前の光景は、とても『まだ』踏ん張れるなどという有様ではないというのに。
「我が軍の組織戦闘能力はもはや瓦解しています。これ以上は、無駄な犠牲でしょう。軍曹、将校諸君。撤退戦の支度を」
「なりませんぞ! エリーゼ将軍!」
こちらを咎めようと叫び声を上げてくる連中には、もうウンザリ。
「……心のままに振舞うことが許されるのが、こんなときになるとは」
「何ですと?」
「衛兵! 諸卿をお連れ出ししなさい! 多少手荒でも許します!」
「馬鹿な!? 衛士如きが、貴族を!?」
モガモガと叫ぶ連中は、しかし、本営の選抜衛士らに取り囲まれ、抵抗というほどの抵抗もなせずにつまみ出されていく。
「初めから、こうするべきだったわね……。せめて、こうなる前に」
彼らに足を引っ張られ、揚句、望まぬ場所で会戦を余儀なくされたとは繰言だろう。
敗軍の定め。
それは、弱者の定めだ。いつだって、勝者からの報復におびえながら逃げ出のびる夜逃げのようなものだろう。まして、とエリーゼは暗澹たる思いで『叛乱軍』、今はシュヴァーベン革命軍と称している敵軍へ視線を向けるなり嘆息を零す。
自分達は、『討伐軍』として出兵していた。激発するほどに追い詰められていた人々を鎮撫する意図だったとはいえ、叛乱軍からしてみれば……『抑圧者』だ。
叛乱軍は、自分達ら討伐軍の将兵にどのような感情を抱いているか……想像は容易だろう。甘い見通しなど、抱きようもない。
「斥候を送り出す余力すらなかったとはいえ、王政府からの情報を盲信したツケね」
暴動だと聞いていた。
だからこそ、少しでも状況をマシにするために自分で兵を率いた。エリーゼ自身の主観としては、他の貴族が暴威を振るうよりはと願ったのだ。
だが、革命軍と称している叛乱者たちは規律訓練ともに行き届いた精鋭ら。政治に足を引っ張られ、足並みもそろわぬ自軍でとても戦える相手ではなし。戦うべきでない相手を前に、将兵が狩られていく光景はエリーゼをして愕然とせざるを得ないものだ。
「……撤退します。間に合うかはわからないけれども……これ以上、無益な犠牲を出すわけには。殿軍は、私が指揮します」
「殿下、どうかお先におさがりを」
頭を垂れ、どうか、と懇願してくれる部下の心意気は在り難い。けれども、私が逃げるわけにはいかないのだ。
「指揮官の義務とは、そういうものではないわ。さ、貴方達こそお先にお行きなさいな。そうしてくれると、私も逃げられるから」
撤兵の指示を下しつつも、エリーゼは悔悟の念と共に馬上で苦悩する。
銃兵に何ができると……私は、侮った、と。それ以上に……『士気』を読み違えていたのも致命的であった。
「破れかぶれの暴動とばかり思っていた。……私も、間違えていたというの?」
いや、とエリーゼはそこで嘲笑する。
「朱に交われば赤くなる。私も、知らぬ間に立派なユニマール朝の愚かな貴族と化していたわけね……」
暴動だと聞いたとき、それ以上に思考が進まなかった。虐げられてきた人々の怒り、不満、嘆きを知っているはずだったのに。
……何が起きているかすら、気づきもせずに烏合の衆で討伐軍を起こす始末。
私は、間違えたのだろう。
「討伐戦、鎮定軍として出兵し……挙句、敗北」
悲しいかな、ユニマール朝に泥を塗ったのだ。……勝てる戦いでなかった、という弁解は意味をなさない。貴族らにしてみれば。『無能者』と見下す魔法も使えぬ暴徒に正規軍でもって挑み、挙句、多数の貴族を討ちとられた私は、『敗戦の戦犯』だ。
「刑死は避けがたし。ならば、せめて……部下だけでも。ここまで付き従ってくれた将兵だけでも、逃げ落とさせないと」
それは、ノブレス・オブリージュを謳う最後の矜持。士官として、将軍として、そして、ユニマール朝の連枝として。誰か一人くらいは、責任を取るべきなのだろう。
ならば、それは、私でなければならない。
覚悟を決めたエリーゼは、だからこそ、別の道をついぞ予期し得なかった。彼女は、思わぬ来客によって己に訪れる未来を、まだ、知らない。
◇
そして、知らぬという点ではヴァヴェルの私室で、モルヴィッツ会戦の顛末について報告を受けている一人の男もまた同じだった。
彼、モーリス・オトラント辺境伯は珍しく心の底から驚嘆する。
「は? ……エリーゼ殿下が投降された、と?」
「はい、叛乱軍はユニマール朝の討伐軍第一陣を打ち破りました」
コモンウェルスにおいて、いち早くエリーゼ将軍の運命を聞きつけたモーリス。それは、入念に情報を得るべく手筈を整えた成果だ。
先見の明、と誇っていいだろう。
だが、結果的にせよ入手できた情報は、心底、予想外であった。
「よもや、そんなことが起こりうるとは……」
感情を人に読ませぬべく老獪さを涵養してきたつもりでも、ぽろり、と本心は零れ落ちるものだ。とりわけ、本心から驚愕した場合は。
「双方ともに激戦で疲労したのですか?」
「いえ、討伐軍は一瞬で瓦解したとのことです」
ほう、と小さく何気さを装って頷きつつも、心中では大いに興味を惹かれてしまう。
『瓦解』の二文字で、十分だ。その言葉を耳にした瞬間、モーリスの脳裏では事態が急変したことが確定事項として理解される。
ユニマール朝の討伐軍について、内訳を聞いたときは『鎮圧しうる』と踏んだのだ。なにしろ、『エリーゼ将軍』というユニマール朝が持ちうる最高の切り札を切ったのである。
オルハンの陰謀も潰れるものとばかり解釈したのだけれども。
……その討伐軍が瓦解とは?
「辺境伯閣下、それと、叛乱軍ですが……非常に不遜ながら……」
「叛乱軍が何か? そこまで言われると、気になってしまいます。言い出しにくいとしても、続けてもらえればありがたいのですが」
興味を押し殺し、単なる会話の弾みであるかのように問う。促された密偵頭はためらいつつも口を開く。
「いえ、どうにも無能者の集団らしいのですが……自分たちをシュヴァーベン革命軍と称して『無能者』の為の革命を為すと」
「革命軍に革命……? ふむ、ああ、ご苦労様です。下がってください」
「は、失礼いたします」
恭しく一礼し、去っていく密偵を見送るなり、モーリスはうすら笑いを引っ込めて、本心から笑い出していた。
「ははははは! 驚きました、驚きましたよ! 無能者の為の、革命? ……これは、想像以上に『やる』ようですね」
シュヴァーベン革命軍と命名した人間が誰かは、調査させねばならないだろう。だが、『無能者』の為の革命というフレーズは、実に蠱惑的だ。
魔法使いは、眉を顰めることだろう。つまるところ、我々コモンウェルスのおバカどもを刺激するには最適だ。それでいて、人口の大多数を占める『無能者』への訴求力も抜群である。きっと、『無能者』の大多数は感涙すら零して革命の大義を奉じるのではないか?
「一石二鳥とはこのことですね。いやはや、何とも欲張りな方たちだ」
この計画を考えた人間は、きっと、自分の同類に違いない。
楽しそうに遊んでいることだろう。なんとも、羨ましい。妬ましさすら、感じてしまう。そろそろ、自分も混じることを考えてしまうほどに、楽しそうで仕方がない。
とはいえ、楽しそうだと憧憬の眼差しを無邪気に向け続けることもできはしない。
コモンウェルスは、ユニマール朝の隣国なのだ。対岸の火事は見ていて楽しいが、こちらに延焼する恐れがあれば、話も違ってくるのは道理だろう。
辺境伯でもあるモーリスとしては、革命騒動が予想以上に強力な軍事力をこれほど急激に兼ね備えたという事実にも注目せざるを得ない。
……まぁ、黒幕は単純だろうけれども。
「エリーゼ将軍の部隊だけは、少なくとも『まともな軍隊』。となると……ふむ、困りましたね。思った以上に、厄介な状況過ぎる。オルハンの肝いりが、我々の隣国ですか」
オルハン神権帝国の旧式マスケット銃が、こんな結果をもたらすとは。随分と、費用対効果の高い投資を彼らは、『オルハンの同業者諸君』は行ったということだろう。
賞賛に値する賢明さだ。
ユニマール朝が国内で動かしうる最大にして唯一の『まとも』な軍事力を『瓦解』させしめる実力。土地の名前ではなく、『ユニマール朝』の支配領域すべてに対して挑戦する気概。ここまで揃えば、ユニマール朝の滅亡は必然だ。
世人というのは、奇妙なことにこんな単純な帰結にも疑義を挟むがモーリスにとっては、結論はもはや揺るがない。
「……さて、この状況、私ならばどう遊びますかね?」
玩具は、大事に使う。
子供のころから、誰でも教わったちょっとしたルールだ。一度使って、それっきりなどとはマナー違反。玩具は、壊れるまで大切に使うものである。
ユニマール朝という玩具で、オルハンの指し手が遊んでいると仮定しよう。
自分が、遊び手であれば次の一手は決まっている。まだ、残っている貴族らを焚き付けて弄ぶまで。例えば、コモンウェルスに亡命させて『討伐軍』を出すように請願させるのも面白いだろう。
亡命貴族どもは、口先だけにせよ盛大な利権を約束してくれるのだ。暇を持て余しているセイムの貧乏騎士は、こぞって参戦を叫ぶことだろう。セイムに影響力を及ぼしたいと考えられているジョナス陛下も釣れるに違いない。
さて、とモーリスはそこで苦笑交じりにボヤいてしまう。
「……相手が待ち構えていると考えれば、そうそう簡単に勝利もできますまいに」
となれば、苦戦を前提に遊びへ混ぜてもらうべきだろうか。
仲間はずれにされるのは寂しいのだ。ちょっと強引にでも、割って入って新しい遊び友達と出会うのも悪くはない。
「ううむ、迷いどころですね」
とはいえ、感情のままに動けないのもまた世の常。
率直に言おう。
『国境防衛』を担う貴族としてみれば、泥沼化する戦争にコモンウェルスの遠征軍が引きずられるなど『とんでもなく良い迷惑』だ。これで、コモンウェルスは対岸の火事に自分から首を突っ込み……火傷を負うことになるわけだ。
百害あって一利なしの典型例である。南方を考えてほしいものだ、とモーリスは嘆息すら零してしまう。確かに、現状、オルハン神権帝国との小競り合いは絶えている。とはいえ、少し探りを入れれば眉を顰めたくなる兆候は山ほどにあるのだ。
第一に、オルハンの奇妙な対外政策。連中はユニマール朝で起きている叛乱を煽っているが、どうにも意図が読めないのだ。
モーリスの知るトリル・オルハン皇帝の性格は息苦しいほどの堅実な戦略家。
よく言えば、手堅く、悪く言えば『遊びを全く解さない』。付け火をして楽しむよりは、目的があるために付け火を行うタイプだろう
第二に、増強されているオルハン軍の動向。
タダでさえ、オルハンのイェニチェリ軍団は精強だ。精強さでは群を抜く近衛なれば、我が方の有翼魔法重騎兵にすら匹敵するとみていい。
「それが、倍に増強されているとなれば……トリル帝を単なる『内治』の人と片付けるわけにはいかないでしょうに」
度々警告を発してはいるのだが……どうにも、コモンウェルス内部に危機感は乏しい。
オルハンとの長い平和。
『小競り合い』が続くだけで、『本格的な武力衝突にはいたっていない』というだけの理由で。誰もが、明日もまた今日と同じだろうと高を括っている。
ヴァヴェルの連中、南方と西方の重大な変化にも気が付けないらしい。
実に、馬鹿げたことだ。とはいえ、気付いているからと言って身動きできないのもまたつらいことだ。
「ままなりませんか……。やれやれ、お預けを食らうのは楽しくありませんね」
◇
近衛騎士にして国王陛下の帯剣従士であり、誉れある黄金法理騎士団に列なりし、ユニマール王朝藩屏であった神と途絶えることなき正統な王家の恩寵深き正義と真理の忠実な擁護者であるエリーゼ・ユニマール将軍閣下に告ぐ!
清らかな忠誠、節操を屈せざるを得ないやむなき事情があれかしことは自明なれども
忍耐の日々、賊を討つ好機がなかりしことを嘆かれているのは重々に承知申し上げる!
しかして、近衛騎士にして国王陛下の帯剣従士であり、誉れある黄金法理騎士団に列なりし、ユニマール王朝藩屏であった神と途絶えることなき正統な王家の恩寵深き正義と真理の忠実な擁護者であるエリーゼ・ユニマール将軍閣下!
お嘆きは正当であり、われらもまた同じく悲劇により悲嘆に沈まずには居れないであることをお伝えいたします。
どうか、衷心をお受けいただきたい。
正統なシュヴァーベン地方の統治者にして、神と正義と真理の元に万民に対し恩寵深かりし壮麗にして正気に満ち溢れし正義と公正の統治者、万国の善良なる友にして助言者であり、真によき隣人で在りし我らが忠誠を誠心より誓いし尊厳に満ち溢れしユニマール朝の高貴にして慈父の如き先帝陛下がお隠れあそばすという鬼神をも悲嘆せずには居れぬ天地開闢以来の一大悲劇に対し、しかして、正義はなされずにはおれないでありましょう!
すなわち、これ、正気の噴出であります!
我ら義軍を集い、鋭気、正に鋭く、仰ぎ見れば我らが義挙を天と神と正義が言祝ぐことは、青々とした空がものの見事に示してくれることでありましょう!
近衛騎士にして国王陛下の帯剣従士であり、誉れある黄金法理騎士団に列なりし、ユニマール王朝藩屏であった神と途絶えることなき正統な王家の恩寵深き正義と真理の忠実な擁護者であるエリーゼ・ユニマール将軍閣下!
正義を、為すべき時期はついに訪れたのです!
王家の為、国王陛下に捧げられ祝福されし聖なる刃を唾棄すべき反乱者共に、秩序と正義の名の下に振われたし!
我らは、大儀に集いしコモンウェルスの兵らを引き連れ、一躍、軍旅につくことでしょう。
近衛騎士にして国王陛下の帯剣従士であり、誉れある黄金法理騎士団に列なりし、ユニマール王朝藩屏であった神と途絶えることなき正統な王家の恩寵深き正義と真理の忠実な擁護者であるエリーゼ・ユニマール将軍閣下!
勝利と再会を恋しく思います!
正義と栄光を共に、麗しき壮麗な宮殿で言祝がんことを願い。
正統ユニマール朝義士盟約同盟
手元の紙にあるのは、モーリスの読む限り戯言だ。
ヴァヴェルという愚者の国際展示場に、新たに展示されるに至ったアホ共の手紙。確か、正式名称を『正統ユニマール朝義士盟約同盟』とかいっただろうか?
身の程を弁えず、文明圏で生活できるのが不思議なほどの愚かにして大仰な亡命者らの団体である。そんな連中が、セイムや王政府当局の頭越しにエリーゼ将軍へ送りつけた『内応』を求める書状は……読めば読むほどに笑いがこみ上げてくる代物。
これを、愚者どもが本気で書いたと納得するまでには、流石に時間を要したほどである
そもそも、出兵の事実を漏えいされているだけでも、本来であれば言語道断。
なのに、『コモンウェルスの兵力』をアテにしておいて、こっそりと手紙を書くという魂胆が理解できない。事後報告すらなければ、ふざけた話と激高しても良いほどだ
「やれやれ、随分と我侭なお客様だ。大人しく、お茶菓子でも齧っていればよいのに礼儀正しくガマンすることも出来ないとは」
コモンウェルスは……このモーリス・オトラントの庭である。お客人の分際で、こそこそと陰謀を企もうなどという魂胆は全く感心しようがないほどだ。
愚者にして、礼節もマナーもならない連中である。
さてさて、とモーリスが考えるのは、此処からの対応策が一手。マナー違反のお客様がこっそり『出した積もり』のお手紙は入手済み。
折角なので、交渉相手の確保を兼ねた接触の一環として、『エリーゼ将軍』に対する旧ユニマール朝亡命貴族らの接触を『シュヴァーベン革命軍』へ知らせてやったが。
「これで、エリーゼ将軍が処罰される……というのは、流石に期待しすぎでしょうね」
……エリーゼ将軍が、多少でも先の読める人間であれば『即座の寝返り』など期待できまい。
なにしろ、と苦笑してしまう。文章の内容は、まともな知性ある人間ならば笑い出してしまう代物。読めば読むほど、こんな手紙に運命を賭すアホが居るとは思えない。
ユニマール朝が『装飾過多、実質過少』だと知っていてもわざわざ羊皮紙にあのようなもったいぶった筆記体でペンを走らせるとは想像の範疇外だ。
「まぁ、驚かされたという意味では楽しかったですけれどもね。愚か者のいうのも、時には面白い。展示の仕方が大事なのでしょうね」
さてさて、とモーリスはそこで溜息と共に思考を一先ず棚上げする。どうせ結局のところ、とモーリスは醒めた眼で現状を見ているのだ。
自分が本格的に妨害すればさておき、そんな義理もモチベーションもない。だから、もう、興味本位で『何が起こるか』を見てみようという腹だった。
事実、傍観に徹した結果は予想通りに進んでいく。セイムとジョナス国王陛下はニンジンに突進する奔馬のごとき単純さで介入を決定。
大いに、『勝利』を重ねるに至っていた。
国境線に位置するロスバッハ要塞の電撃的な攻略に始まり、稲妻のごとくジョナス陛下の軍勢はシュヴァーベン地方を制圧していくというではないか。
とはいえ、モーリス自身は『勝利』という言葉を疑っているのだが。いや、疑っているというよりはそもそも信じていないというべきだろう。
堅牢極まりないロスバッハ要塞を、形だけの抵抗で陥落させたことは高くついた……というのがモーリス自身の算盤だ。
「ふむ、騎兵による補給線襲撃と」
自室で報告書に眼を通し、モーリスは小さく笑みを零す。革命軍の指導部は、やはり、相当に『戦略』というのをオルハンに叩き込まれているのだろう。
緒戦の優勢により、国王陛下らは随分と楽観的になっていたらしい。その間隙を突かれた、といえば突かれたのだろう。
『無能者の叛乱』と侮っている王政府には申し訳ないが。
……オルハンの糸引きは相当に狡猾だ。
「最初から、そのつもりだったのでしょう。だとすれば、当然の様にロスバッハ要塞に続き、ボージュまで無抵抗で取らせるわけですね」
報告によれば、移動中の補給部隊が襲われている。幾つかの街道も遮断されていた。連絡線を狙っての徹底したハラスメント攻撃。
「古典的で、教科書的ですらある。いやはや、戦争のやり方もよくよくご存知ですね」
シュヴァーベン革命軍の騎兵隊とやら、こちらの有翼魔法重騎兵とは戦わず、有翼魔法重騎兵の居ない部分に全力で攻撃をかけているというではないか。
お陰で、というべきだろう。
補給の混乱により、ボージュ地方に侵攻している先鋒と後続の主軍の連絡まで途絶えている。一時的な混乱にせよ、侵攻した主軍と先鋒集団までもが切り離されたとは驚かざるを得ない手際の良さだ。
「被害そのものは、決して大きなものではないですがね。実に効果的な嫌がらせです。こうなると、身動きをとるのが難しくなる」
無能者が主たる構成要員である革命軍は、軍事組織としては『コモンウェルス』のそれに到底及び得ない。
だが、それは正面衝突に至れば……の場合だけだ。シュヴァーベン地方を知り尽くした彼らには地の利がある。戦うも、決戦を回避するも、彼らが主導的に選びうる立場だろう。
他方、我らがコモンウェルスの状況は非常に苦しい。なまじっか国王陛下親征ということで、大兵を引き連れているのだ。
我が方の補給は、敵地に踏み込めば踏み込むほど非常な困難を増していくだろう。
「補給線、連絡線を延ばさせるのが目的と読んでいましたが……お見事」
こうなると、有翼魔法重騎兵こそ多くとも『点』に過ぎないコモンウェルス軍では拠点制圧は困難だろう。
「ジョナス陛下におかれては、未だに勝利を確信されておいでというけれど……戦えば、勝てる? だが、相手が戦ってくれるという保証もないでしょうに」
ジョナス陛下の妄言、馬鹿馬鹿しい限りだ。ヴァヴェルで愚かさを誇示するに飽き足らず、戦陣で己の愚者ぶりを世界に知らしめたいと見える。
「やれやれ、正面で勝てないから、側面を突く。革命軍とやらのそれは、実に、まっとうな努力ではないですか。それを、理解できないとは……」
自分の都合で戦えと叫ぶのではなく、自分の都合を相手に強要する策の一つも立てればよいのに、その素振りもなし。
「策を立てる頭がないならば、せめて撤兵を決意するぐらいの知性もあれば宜しいのですが。それすら、望めませんか」
まぁ、察しはつく。
これほどの大兵を起こして『魔法も使えぬ無能者ども』に追い返される? プライドの高いジョナス陛下にはとても耐えられないだろう。
ああ、とモーリスはそこでふと残念な事実に思い立って苦笑していた。
「ははは、渋面を見れないのが残念です。あの傲慢な陛下が、どんな表情をされているのやら。帰国された際には、真っ先に拝謁しなければなりませんね」
無目的に滞陣し、あげく、無意味に損耗を重ねるのがオチだ。行き着くところは、王権に対するセイムの不信任だろう。
帰国した負け犬の顔を見るのが、今から楽しみでしかない。
そうなれば、また、随分と『遊ぶ』空間も出来てくる。ついでに、シュヴァーベン革命軍とやらと講和することもできるだろう。
「なればこそ、問題は……オルハンの意図です」
この事態を引き起こしたのオルハンだ。これほどの結果を得るために、色々な費えを投じたことだろう。
問題は、何のためにその投資を是としたのか。
ただ、その一点だ。
「国境地帯の部隊に増強の兆しはなし。糧秣の蓄積も通常通り? これほどの大きな仕掛けをなしておきながら、オルハンは何をしているのでしょうかね?」
念のために、と国境地帯の守りを強化させているのだが、どうにも徒労に終わりそうな気配すら感じられるほどである。
「……もしや、我々に仕掛けてくる腹ではない?」
ぽつり、と自分の口から呟かれた可能性にモーリスは思わず考え込んでしまう。
「わかりませんね。トリル皇帝の人なりからして『領土欲』があるタイプとは思いにくいのですが」
ふむ、とモーリスは言葉を弄びながら状況を考える。
オルハンの仕掛けた壮大な陰謀。手際のよさ、全てに漂うプロの技量。いやはや、ユニマール朝の青い血を称するお猿どもではとても対処できないに違いない。
別段、それはよい。
けれども……問題は、『オルハン』の真意だ。いったい、何のために?
◇
「は?」
知らせを受け取った瞬間、モーリスは思わず疑問を口から零してしまう。
「今、なんと?」
取り次ぎ役の顔は、見慣れた自家の人員。
冗談や軽率な妄言を口にする類いでないとは知っている。
だが、だからこそ。
俄かには、その言葉が信じかねるのだ。
「はっ! ロスバッハに置いて我が軍と革命軍が激突! 目下、大会戦中です!」
『大会戦』?
それだけは、起こらないと思っていたいのだけれども。
「ご苦労。ああ、下がってくれて結構です」
「失礼いたします」
恭しく去っていく取り次ぎ役を見送り、独り、モーリスは疑問を口の中で転がす。
「馬鹿な。ここまで、定石を保っていた連中が……何故?」
破れかぶれ?
強硬論を抑えかねた?
現場の暴走?
率直に言えば、可能性は何れもありうる。
だが……『モルヴィッツ会戦』に至るまで『革命軍』は規律正しい軍隊として振舞っている。ハイマット攻略時にすら、略奪騒動がなかったのだ。
勝算すら見込めるゲリラ戦を投げ打ち、破れかぶれの会戦を選ぶなどということがありえるのだろうか?
「何がしかの意図、理由、必然性があると? しかし……解せません」
判らない。
それは、即ち気持ち悪さだ。
何事かが、自分の知らないところで進められている。
また、なんとも不愉快なことだろう。
知りたい。
何が、起きているのだ?
なればこそ、モーリス・オトラント辺境伯は続報を一日千秋の思いで待ち望む。
そして、我慢という努力の成果を彼は堪能することが、程なくして許される。
「お、お、オトラント辺境伯! 閣下! 緊急です!」
飛び込んでくる取次ぎ役の表情は蒼白そのもの。
自分の、このモーリスの使う人間だ。そうそう容易には動じたりしないであろう人間が、慌てふためく?
「いかがしました? オルハンに越境の動きでも?」
立ち上がりつつ、オルハン軍の動向を捕らえそこなったかと舌打ちしかけたモーリスの脳裏に浮かぶのは、越境してくるであろうイェニチェリとシパーヒーらの大軍。
コモンウェルス中の有翼魔法重騎兵が粗方、シュヴァーベン地方に出向いているとすれば。ああ、とそこでモーリスは得心する。
ロスバッハで、革命軍が無謀な会戦を選んだのも。
すべては、『オルハン』の攻勢を成功させる為の盛大な陽動か?
一瞬の内に、策謀の線画を引いて見せたモーリスの思考。しかして、彼の予想は完全の動じつつも言葉を重ねようとする取次ぎ役の言葉で覆される。
「ち、ちが、ちがいます、ちがいます!」
「落ち着きましょう。ええと、では、どこからの報告でしょうか?」
「ろ、ロスバッハ、ロスバッハより急使が!」
「急使? すでに、会戦に至ったとの知らせならば受け取っていますよ? 続報でしょうか? 戦勝時になにか、トラブルでも?」
誰か、主要な貴族が戦死でもしたか?
はたまた、奇跡的な巡り会わせでジョナス陛下辺りが死んだか?
「ち、違います! 辺境伯閣下!」
「落ち着いて。何事ですか?」
「お味方が! お味方が、お味方が!……お味方は、大敗北!」
大敗北?
……それは、大きな敗北ということだ。
敗北?
……負けた?
どこが?
我々、コモンウェルスが?
「……なんですって?」
「遠征軍は壊滅いたしました! 陛下、王太子殿下、王子殿下らは、皆さま、お隠れあそばされました!」
「は? お隠れあそばした? 言葉の意味を問わせてください。不敬を承知で確認しますよ。それは、『戦死』ということですか?」
「は、奮戦むなしく……陛下を初め、皆様が討ち死になされました!」
討ち死に。
全滅。
戦死?
ああ、それは。
それは、なんとも。
「っと、いけませんね。動じてしまいました。……誤報の線を調べなさい。伝令は? 第一報を持ち帰ったばかりですね?」
「は、はい」
「では、別の急使が情報を持ってくるまで事実確認を。それと、王都残留の諸卿を招集します。報告書を預かります。その間に、手配を整えてください」
ああ、全く。
なんと、愉快なことだろうか。
こんな日が、こんなにもびっくりする日が来るなんて。
ワクワクが止まらないじゃないですか。
「会戦の報告が入っている、と。とまれ、手筈を整えて戦勝、敗北のどちらにも対応しましょう」
「と、取り乱してしまいました。すみません」
「なに、構いませんよ。確報が届くまで、案じるしかないのですからね」
では、手筈をよろしくなどと続けて部下を部屋から追い出すなり、モーリスは椅子に深々と腰を下して笑い出す。
「ははははは! なんてことでしょう! なんてことでしょうね!」
確報が届くまで、案じるしかない?
よくもまぁ、とモーリスは心中で笑いだす。
「……なんてことでしょう!」
勝敗に関わらず、結果を知らせよと命じてあるのだ。自分の手配した情報網の正確さは、他ならぬ『モーリス・オトラント』自身が担保できる。
敗北は、つまり、確定だ!
うっとおしい国王陛下諸々、まとめて全滅!
コモンウェルス史上、初の敗北。
正直に言えば、『多少』、やけどをすればよいだろうとは思ったが……『大敗北?』。
「……こんな、こんな『楽しくなること』を……『見過ごしていたなんて!』。なんという大失敗でしょうね!」
そして、喜色満面に報告書に眼を通せし……彼は、心の底から喝采を叫んでいた。
「お見事です!」
人形には、魂が宿っていた。
操り糸は、とっくの昔に外れている。
「分断、補給線荒らしは……消耗戦に引き込むと見せかけ全てが、『自分達の戦場』で決戦に持ち込むための布石」
挑発と嫌がらせ。
そして……本命はジョナス陛下の弱み、こらえ性のなさを突く為の策謀。
「あげくが、ロスバッハ要塞から『我が軍』が飛び出さざるを得ない状況を作り出す!」
城外で、革命軍に嘲笑されたジョナス陛下が憤怒のままに飛び出していく有様。匹夫の勇を大いに奮わんとすることだろう。
なるほど、想像が容易にできて仕方がない。
「そして、いやはや、性格の悪い人も居たものだ。なんなんですか、この地雷とは?」
報告書に記載されているのは、戦場観察の殴り書き。地面が、破裂し、ペガサスが混乱の坩堝に取り込まれる光景だ。
あきれるべきか、感嘆すべきか迷うところだが。
「有翼魔法重騎兵をここまでして、殺しに来る。いや、オルハンのイェニチェリ共ですら思いつきますまい」
これは、『魔法』と『銃』を組み合わせて戦うイェニチェリの流儀などではない。もっと泥臭く、無能者が、無能者の力だけで有翼魔法重騎兵に挑むための戦法だ。
「私としたことが、なんと迂闊な」
ちょっとした余興、戯れに考えていた。
大したことには育つまい、と。無聊を慰めてくれるであろうちょっとしたお祭りぐらいの気持ちで呼んでいたのだけれども。
なんという愚かな失策だろうか。
「『オルハンの道具』だと侮りましたよ。私としたことが、『無能者』の叛乱ということで随分と既成概念に囚われていましたね」
無能者という単語一つとっても、非常に危険だなとモーリスは反省をこめて苦笑する。無能者という響きは、『能力がない』かのような響きだが。
実際のところは、魔法を使えないから無能であるという魔法至上主義が言わしめたにすぎない言葉だ。
『無能者』とは、魔法が使えないという意味でしかない。
「ああ、そうか。『無能者』でも『頭』はある。……思考できるわけですね」
なればこそ。
魔法技術をすべての価値体系に置いて『唯一無二』のものと位置づけるコモンウェルスにあってなお。
モーリス・オトラント辺境伯だけは理解できてしまう。
『魔法がつかぬ無能者』とて、『遊び相手』たる資格たるや、十全に、完膚なきまでにかねそろえていると。
「はははは、これは素敵ですよ! なんてことだ!」
狭い世界。
退屈な遊び友達。
遊び相手に欠き、戯れに火をばら撒いていたけれども。
よもや!
まさか!
友達候補がこんなにも身近にいたとは!
「……まったく、今日はなんて素敵な日なんでしょうね!」
平民、もっと直截かつ侮蔑的にいうならば無能者。
そんな連中について、自分も今の今まで『道具』としかみてこなかった。しいて言うならば、他の魔法使いが活用法に気がつきもしない『便利な道具』だろうか? 魔法を使える人間というのは、往々にして『魔法』で物事を解決する。
だからこそ、『無能者』に何かを期待するということが非常に低かった。
せいぜい、教育された平民であっても『小間使い』程度。
モーリス自身は『小間使い』が何処にでもいることに注目し『情報源』として大いに活用しては来た。
だが、考えようによっては。
「……いやはや、道具として使い慣れていたが故に読み違える羽目になるとは!」
道具使いしていたが故に、思考力に気が付くのも遅れてしまったのだろう。
「なんとも、いえ、なんと、本当に愉快なことでしょうね!」
世の中において、モーリス・オトラント辺境伯が真っ先に『驚愕』しつつ面白がった情報は受け取り手ごとに異なる反応を招くものでもあった。
出来事に対する反応は、十人十色。
それぞれ、立場、利害が異なるのだ。
無理もないだろう。
喜んだ、という意味においては当然のごとく革命軍が勝利を最も言祝いだ。
そして、あるオルハンの当局者は、『予想外の成果』にほくそ笑む。
これで、陛下の南進はなるだろう、と。
好機をかぎ取ったのはオルハンに限らない。
マルグレーテ朝は、一様にその知らせこそが『活路』を見出す転機であると理解し、『そうあれかし』とすら願った。
オスト=スラヴィア大公国に至っては、早くも、コモンウェルス内部に接触の手を伸ばそうとする始末だ。ある辺境総督が嘆いて曰く、『また、私が苦労させられる』である。
他方で唯一、好意的とも同情的とも言いうるのは……自由都市同盟の反応だろう。
ある自由都市同盟の老人は、知らせを受け取るなり眉を顰めて『厄介ごとの臭いだな』、とぼやいたという。
そして、ある意味では最も当事者中の当事者であるコモンウェルスにおいてソブェスキ家の残された最高位に相当する人物も知らせを受け取る羽目になっていた。
その日、というべきだろうか。
運命に日において、ヤーナ・ソブェスキはいつもと変わらず念入りにフランツの誕生日会へ向けた手筈を確認している最中であった。
そんな彼女の大切な時間に飛び込んでくるのは、イグナティウスの爺。彼が、血相を変えて全力疾走と共にもたらすのはとんでもない凶報だった。
「ひ、姫様! た、大変です! 大変なことがおこりました!」
「爺?」
「議会(セイム)から使者が知らせをもってまいりましたぞ!」
ヴァヴェルの煩い連中が、私に何事かとヤーナはイグナティウスから書状を受け取るも、内容は先に爺から告げられる。
「お味方が……。お父上の軍勢が壊滅されました! 陛下ほか、姫様の兄君らもうち死にあそばされたと!」
爺から告げられる重大な内容に、ヤーナは一瞬、眉を顰める。
……父王、ジョナス陛下はろくでもない父親だった。
正直に言えば、フランツの育児放棄でげんなりさせられるに十分。あげく、権力欲の塊のような性格は理解したくなかったほどだ。
父と娘としての情はお互いに抱きようもない関係。
だからこそ、頭によぎるのは王位継承に関するごたごたを招いてくれるとは困ったことねという程度の悩み。
だからこそ、局外中立、不干渉を決め込むべくヤーナは言葉を紡ぐ。
「あら、大変。議会の皆さんで頑張ってとお伝えしておいて。あ、私、お兄様とお父様がなくなって悲しすぎてなにもする気がないと伝えてね?」
「殿下、そのようにおふざけになって……!」
煩いわね、と返しかけたヤーナの言葉は、しかし、その瞬間に重々しく割ってはいる男の言葉で遮られる。
「その通りです。失礼ですが、殿下。他人事ではありません」
「ほえ?」
言葉を発したのは、アウグスト・チャルトリ。ヤーナの持つソブェスキ家領土にて封建騎士団長を勤める豪の者。
それほどの勇者が、かすかに表情を強張らせての進言?
なんでよ、アウグスト? と問うまでも無い。爺は、いつでも、おしゃべりが大好きなのだろう。
「チャルトリ騎士団長の申しあげるとおりです! 姫様、いまや姫様とフランツ殿下だけが、正当な王位継承者なのですぞ!」
「いや、まってまって。姉さんがいるじゃん。それも、確か二人。どっちでもいいじゃない?」
「殿下、議会は外国の貴族とご成婚された王女は継承権を放棄したとみなしております。したがいまして、現状では殿下とフランツ殿下のみに継承権が」
事態を把握した瞬間、ヤーナ・ソブェスキは激怒した。最悪の一報が飛びこんできたと理解しえたとき、ヤーナ・ソブェスキは激怒したのである。
「(……今ならば、メロスの気持ちがよく分かる!)」
必ず、かの邪智暴虐(じゃちぼうぎゃく)の不正をのぞかなければならぬと決意した。
ヤーナには政治への興味がわからぬ。ヤーナは、可愛いものを愛でる趣味人である。
騎士団に号令し、フランツと遊んで暮らしてきた。
けれども自分の理想的な生活をおかさんと欲する邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。
『もうすぐフランツが10歳になるのよ!? フランツがむかえる二分の一成人式をお祝いする準備もしているの! フランツへのプレゼントやらをはるばる遠方から取り寄せているのよ!? そのおだやかで、平穏な自分の生活がおびやかされるというの!?』
そこまで考えた瞬間、ヤーナの忍耐力は限界だった。これ以上、手をこまねけば面倒事の嵐が訪れると感じ取った彼女の行動は迅速を極める。
激怒をたずさえたまま、ぷっつんきたヤーナは有翼魔法重騎兵にまたがり、面倒事をもちこんだセイムに向かう。
文句の一つでも怒鳴り込んでやると駆け出したのだ。
慌てて有翼魔法重騎兵を駆るアウグスト・チャルトリにイグナティウス・ポトツキーの二人。彼らを遥か後ろに引き離したヤーナは駆けに駆け、そして議会に飛び込んでいく。
そして、コモンウェルスが首都、ヴァヴェルのセイムに乗り込んだヤーナは……あろうことか、驚愕と呆れのカクテルを飲まされたかのように硬直していた。
「(さ、最悪だ! こいつら、何ひとつとして決められていない!)」
眼前の光景を前に、ヤーナが抱くのは心からの驚愕。
ジョナスという父王以下、統治機構の主要な人間がこぞって戦死した影響は軽視すべきではない。そうだとしても、しかし、『どうするべきか』すら決められない?
ありえない、という言葉が思わず喉から出かけたほどだ。
「(それどころか、支離滅裂にお互いの責任を糾弾しあうばかり!? 非常時なのよ!? 他にやるべきことがいくらでもあるでしょ!?)」
非常時にすべきことには何一つとして手を着けず、すべきでないことは全て繰り返しているような醜態。
ヤーナにとって、それは、想像をはるかに下回る現状というほかにない。
ヴァヴェルの連中、セイムの議員共、どいつもこいつもアホだとは聞いていた。
だが、『政治家』の悪口なんて時候の挨拶のようなもの。それこそ、今日は天気が悪いですねと語りつつ、今の政治家がいかにダメかを語るのもコモンウェルスでは珍しくない風習。……そう思い込んでいたのだ。
あまりといえば、あんまりだ。
茫然と立ち尽くし、眼前の光景を形容する言葉すら見当たらないのもやむなし。ただ、というべきか。だからこそ、ヤーナは何時もならば鋭敏に気が付き避け得たであろう人物と遭遇してしまう。
「おや……そこにいらっしゃいますのはヤーナ殿下ではありませんか」
その声に、さっと顔を動かすヤーナの視線の先には……珍しい人物に気が付いたとばかりに微笑む、モーリス・オトラント辺境伯の顔。
「(げっ……よりによってこいつ!? いや、ああ、もう、性格破綻者でもこの際いい!)」
緊急事態を乗り切るべく、というべきだろう。面倒くさがりなヤーナとしては珍しいことに、実務に重きを置いた問いかけを彼女は発していた。
「この混乱をどうして、誰も収拾しようとすらしないの?」
「責任をとりたくないのでしょうな」
「は? ……はぁ!?」
理解できない言葉を吐くモーリスの表情を凝視し、ヤーナは視線で追加の説明を求める。
その視線を受けて、かしこまりましたと慇懃に頷いてみせるこの男の所作は全てが礼法にかなった『挙措正しい動作』。
こんな時だからこそ落ち着きを保つ、と言えば賛辞なのだろうが……ヤーナとしては胡散臭い物腰としか思えないのがまた忌々しい。
「大敗北ですぞ、殿下。国王陛下以下、主要な方々がおうち死に。このような大惨事、過去に前例がございません。軽挙妄動は、大いに指弾されましょう」
この局面にあって、まるで他人事のように嘆いてみせる素振りも……また礼儀正しい。なればこそ、ヤーナの脳裏に浮かぶのは『慇懃無礼』の四文字。
だが、とヤーナは気を取り直す。
今ばかりは、モーリスに腹を立てる時間すらも惜しいのだ。
「……あきれた! 何も決められないのね! あきれた議会だ。もう、まかせてはおけない!」
「はて? で、殿下?」
ぽかん、とほうけた隣の議員をよそにヤーナは議場の中央、演説台にて右往左往している議長から木槌を取りあげるなり、これでもかとたたきつける。
響き渡る木槌の音で、漸く議場には一定の沈黙が取り戻され、その瞬間、ヤーナは吼えていた。
「非常時に、一体なにをほうけているの! やるべきことぐらい、はっきりしているでしょう!」
「で、ですが、この混乱ですぞ!? なにぶん前例がない!」
「あなたたち、ばかなの? いいこと!? 問題を前に、あーだこーだ言い争う暇があれば対策! 対策よ、対策をだしなさい!」
「殿下、おっしゃることがわからなくはありませんが……。しかし、正統な王政府がない状況で、独断専行もまた……」
議員らの反論に対し、ヤーナは頭痛を堪えるように一瞬だけ沈黙する。
責任者がいないから、何も決められない。だから、代わりの代理人を選ぶ必要がある。けれども、責任者の代理人を選ぶための責任を取れる人間がいない。だから、何も決められない。けれども、決めないといけない?
ここまで典型的な循環論法で思考を停止しているというのは、驚きだった。
結論、『こいつらは、もう、だめだ』。
「分かった。分かった! もういいわ、私が責任をとる! 私が命令も出す。私が指示も出す。いいから、行動しなさい!」
「し、しかし、越権ですぞ!?」
決められず、さりとて、責任者を選ぶことすら出来ない無能共。
ぶち切れそうになるヤーナの怒りは、しかし、噴火寸前のところで口を開いた一人の男によって静められる。
「いえいえ、皆々さまお待ちを。……国王陛下に変事が生じた際、王族の方々が政務を代行するのは前例があります」
この混乱の最中にあって、なお、動じない曲者のすまし顔。
モーリス・オトラント辺境伯は、何を考えているか窺わせない笑顔のまま、賢しげに言葉を重ねていく。
「そうですね、ヤーナ殿下におかれては臨時の摂政をつとめていただけばよろしいかと」
いかがですか、と問う男がモーリスという人物でなければ。きっと、ヤーナは心から感謝していたことだろう。
だが、今ばかりは。
ヤーナとしては、胡散臭い男による好意的な言説の裏を読むことで精一杯になってしまう。はっきり言うならば、不気味なのだ。
「確かにおっしゃるとおり。では、ヤーナ摂政殿下の就任を決議いたします! 反対のある方はご起立をねがいます」
だからこそ、だからこそ、だ。
議事進行役が、モーリスの意のままに自分の摂政位就任を議決にかける様は……至極自然だ。なればこそ、ヤーナ自身の摂政位就任へ誰もが反対し得ない。
セイムの議員らが反論を胸中に抱いていようとも、では、反対したとすればどうなる?
満場の議員らが、手をこまねいている状況下に置いて、責任をヤーナが担うと申し出ているのだ。それに反論するとなれば……『責任』という要素を背負うことになるだろう。
責任者を選ぶか、リスクすら判らぬ責任を負うかとなれば、誰だって責任者に任せようか、と一時的にしろ考える。
「……反対者はおりません。全会一致にて、殿下の摂政就任は議会の承認をえました。さて殿下、いかがされるのですか?」
そして、誰もが……『モーリス・オトラント辺境伯』が『ヤーナ』の摂政位就任の口火を切った、と認めるのだ。なればこそ、何時の間にか……モーリスが主導者のような顔をしている。それを、誰も、否定しない?
これで、また、セイムにおいてオトラント辺境伯の権威が高まることだろう。自分も、相応に遠慮させられることになる。
……とはいえ、とヤーナは思案を一時的にしろ棚上げせざるを得ない。
「決まっているわ。まずは、前線の建てなおし。出せる兵を全部貸しなさい。行くわよ、私に続きなさい!」
国難、あるいは危機にあっては、時間を失うべきではないのだ。
次回、2016年1月29日(金)更新予定!
原作ゲームがいますぐ無料で遊べる!新作自作ゲームがダウンロードできるニコニコゲームマガジン!

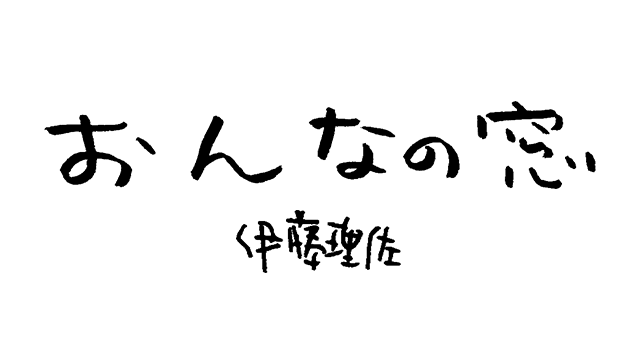

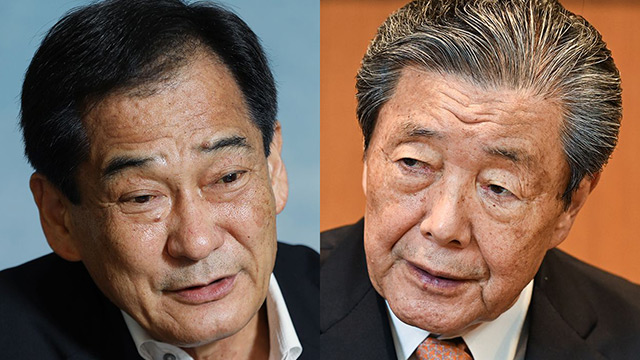
コメント
コメントを書く