
まさか勇者がさらわれた!?「序」はこちら
33人の娘が全員レベル1に!「第一話」はこちら
娘の本音が勇者に刺さる!大反省会?「第二話」はこちら
5
「じゃあ皆、適当に四人パーティ組んでねー。アヤメさんが抜けるから三十二人になってキッチリ割り切れるはずだから。じゃ、よろしく」
ラルフィーの発言の後、酒場は一気に喧騒に呑まれた。
普段、パーティを決めるのは全てラルフの仕事であり、娘達はそれに従っていただけに過ぎない。本来、編成とはあくまで主人公にだけ許された特権なのだから。
しかし、今回は主人公不在という特殊な状況だ。
無駄に拠点に人員を残していく必要もないということで、娘達は四人組パーティを八つ編成し、効率よく「ラルフ救出」もとい「兵士撃滅」に向けて動き出すことになった。
酒場の中はまるで修学旅行のときの班決めの様相を見せていた。
ラルフィーの適当な号令に適当に従い、各々が仲の良い娘に声を掛け、パーティを作り始めたのである。
『フェリーチェ。もし良かったら、あたしと組みませんか?』
『ふえええええ!? あ、あたしでいいんですか、ユメルさん!? あ、あたしって、そんなにユメルさんにとって特別で個性的な存在だったんですか!?』
『えっと……特別かどうかは分からないんですけど、フェリーチェは裏表がないし、心も綺麗で……一緒にいて凄く過ごしやすいです。だから同じパーティを組めたらな、って思って。あ……もちろん断って貰っても、いいです。だって、あたしは心が読めてしま――』
『うえっ、うえええぇ……ありがどうございまずううう……』
『えっ、な、なんで泣いてるの!?』
『だ、だって、あたし普通ですし、てっきり、この前みたいに、一人だけ仲間はずれになって余り物になるに決まってると思ってたので……う、嬉しいですぅ……!』
『そこまで喜んでくれるなんて、あたしも、なんだか……!』
これは読心能力を持つ少女「ユメル」と、超絶普通が故に日々個性的になりたいと願っている変な村人「フェリーチェ」のコンビだ。
余り物にならずに済んだことに感極まったフェリーチェが泣き崩れ(事実、魔王ヘイティとの一件で「影が薄かった」というあまりに残酷な理由でフェリーチェはヘイティに気付かれず、娘の中で唯一、魔王病に感染しなかったという体験をしている)、しかも彼女が心から喜んでいることが読心能力でヒシヒシと伝わってしまうため、ユメルまで微妙に涙ぐんでいる始末である。
『この僕をパーティに誘うとはお目が高いね。さすが王の名を持つ存在だ、精霊王!』
『ヒッヒッヒ。これは、とんでもない組み合わせだね。ねぇ、エリナ』
『赤の魔女……。精霊王、どうしてこんな思わせぶりなパーティを?』
『うぇーーーーい! 辛気臭い顔をするのはやめよーよ、エリナちゃん! ほら、その死神の眼で私を見ない! ほら、よくよく考えたんだけどさー、またこつこつ地道にレベル上げするとかすっごくつまんないよね。退屈だよね。だから、このレベル1でも戦えるパーティでさっさと兵士倒して来ようぜーーー! いえぇーーーーい!』
『うわ、酒臭……』
『さあさあ、君らも飲みたまえ! このカシスオレンジは王の奢りであるぞ!』
ここは反則級とも言えるくらい超強力なパーティだ。
相手が強いほど強くなる天才スク水剣士「シオン」。共に同じ異世界から召喚されてきた因縁の二人、過去に数多の惨劇を体験してきた「赤の魔女」と、死神の眼を持つ少女「エリナ」。そしてリーダーは大陸どころか惑星一つ消し去るほどの力を持っているが、常に手を抜きまくっている酔っ払い――森羅万象を統べる者「精霊王」。
ユメル達のようにまず二人組が出来上がり、それからペア同士がくっついて四人組が出来上がる場合もあれば、精霊王達のようにすぐさま四人組が出来上がる場合もある。
大概の者に仲の良い相手の一人や二人ぐらいはいるし、どう見てもコミュ障にしか見えないような娘ですら案外スルスルとパーティを組んでいるようだった。
そして、だ。
この状況でララがどんな行動を取ったかというと、
「(なんだか新鮮な光景っ)」
――特に誰かを誘うこともせずに、他の娘達の間をウロウロしていたのである。
ララはまだ誰ともペアを組んでいなかった。既に半分近くの娘達が所属するパーティを確定させているというのに依然として一人のままだった。
ただ、これは組まなかったというのが正解だ。事実、前々から親交の深かった娘の数人に「パーティに入ってくれないか」と誘われたりもしたのである。が、ララはその時点では、パーティへの参加を断ったのである。
理由は簡単。
実は、もうちょっとだけ――一人でこの場を見て回りたいと思ったから。
「(ストレーガさんとホーリーさんがラルフのことなんてどうでもいいって言いだしたときはどうなることかと思ったけど……皆、別にラルフのことを考えていないわけじゃないんだよね)」
ララは小さな耳をピクピクと動かし、あまり行儀は良くないが、他の娘達がどんなことを話しているかに意識を張り巡らせていたのである。
ララがそんなことを始めたキッカケは、話し合いが終わってすぐ、パーティを自由に決めることになったときのラルフィーの一言が原因だった。
議長役になって話し合いを仕切っていたラルフィーが(最終的にラルフの救出よりも「兵士です!」の撃破を優先すると決めた本人だ)、噛み締めるように、こう呟いたのである。
『レベル1になるのって……こんなに心細いことだったんだね、お父さん』
このときのラルフィーは本当に不安そうな顔をしていた。唇をキュッと結び、視線は俯きがち、背中も丸まり、あまりにも心細そうな――先程までの話し合いでは一切おくびにも出そうとしなかった強い感情がその一言に込められていた。
少なくとも、ララはそう感じた。そしてララは、少なからずその言葉に共感した。
レベル1で在ることへの不安感――それはララ自身も口にこそ出さなかったものの、先程からずっと感じていたことだったのだから。
「(ずっとラルフはこんな気持ちだったんだ。しかも、あたし達と違ってどんなに頑張ってもレベルが上がらないのに……!)」
レベル1は、あまりにも心細い状態だ。
だって一言でレベルと表現するとソレは非常に大雑把な概念に思えるが、言うなればレベルとはこの世界における「すべて」なのだから。
レベルが1になれば身体能力は驚くほど減少する。体内を巡っていた魔力は消失し、その影響は脳や身体に蓄えられていた「知識」や「経験」にすら及ぶ。これまで積み上げて来た様々な大切なものが風に飛ばされる塵のように、フッと、自分の中からなくなってしまう。
それは、あまりにも、過ぎた絶望に違いない。そしておそらく、それまでに積み上げて来たモノが大きければ大きいほど、この反動は破壊力を増す。研ぎ澄ました刃のようになって、たった一つ、たとえレベル1になっても変わらないもの――「心」を抉るのだ。
レベル1になる前のラルフは、すべてを持っていた。そしてレベル1になり、心以外のすべてを失った。
けれど彼は折れなかった――自らのレベル1をネタにし、笑いを取ることで、周りの人間にこの計り知れない絶望を悟られないようにしたのである!
「(思ってたより、ラルフはずっと、ずっと、すごかったんだ!)」
そして、ララは思いついた。
もしかして自分やラルフィーと同じようなことを、他の娘達も感じているのではないだろうか、と。
実際、その予感は大当たりだった。娘達の間をフラフラと歩き回っていたララは、娘達がレベル1という状態に不安を覚えていることを、パーティを組んだ仲のいい娘と話しているところに何度も遭遇した。
彼女達は一様に自らの喪失感を嘆き、そしてラルフがこれまでずっとレベル1の状態でもほとんど弱さを見せず、それどころかエロサモナーと共に道化に徹していたことに驚いているようだった。
ララはラルフのことが好きなので、ラルフが皆に褒められるのを聞くことも同じくらい好きだ。娘達はラルフをあまり面と向かっては彼のことを褒めようとしない者がほとんどなので、この経験は非常に新鮮であり、同時にララにとって非常に興味深くもあった。
とはいえ。
「――そろそろ、遊んでるわけにもいかないよね?」
立ち止まり、自らに語りかける。
今のララがやるべきことは「兵士です!」の撃破と「ラルフの救出」に向けてもう一度レベルを上げることだ。そのためにはパーティを組んでダンジョンに潜る――改めて「ハック&スラッシュ」の精神を思い出すことが必要なのである!
よし、行動開始だ!
となれば、まずペアを捜す必要がある。こういうときはララが一番仲の良い相手のところに行くべきだろう――つまり、メイドの「リリア」を捜すに限ると考えた。
リリアはエロサモナーがラルフの元に召喚した二人目の娘であり(つまり、ララの次だったのだ!)、ララにとっても最も付き合いの長い相手である。彼女の能力はララとも非常に相性が良く、パーティを組む相手としては申し分ないわけで――
「あ、リリアさんいた!」
栗色の髪、そして真っ白いエプロンドレスとホワイトブリム。娘達の中にリリアの後ろ姿を発見したララは、にこやかに声を掛けながら彼女の元に駆け寄った。
「リリアさーん、あたしと組もうよー!」
「えっ、ラ、ララちゃん!? ま、まだ誰とも組んでなかったんですか……!?」
「はえ?」
振り返り、ララの姿を見咎めたリリアは大きく瞳を見開き、驚愕の表情を刻んだ。加えて、ララにもリリアが今、どんな状況にいるのか見えて来た。
リリアは一人ではなかった。いや、それどころか……!
「おっーと一足遅かったな、ララ! リリアはあたし達が貰ったぜ!」
「リリアの技は超強力やからなー。回復と、何よりも『メイド・イン・へヴン』の『全体鉄壁化』はレベル1のこの状況で最も活きるスキルや! 渡さへんで!」
「済まないっす! ララさんがリリアさんと仲良しなのは分かってますけど、他を当たって欲しいっす!」
「ええええええーっ!?」
――もう仲間が三人いて、四人組パーティが完成していたわけで。
「す、すみません、ララちゃん。私もご主人様を救い出すのなら、今回は同じく恋のライバルであるララちゃんと手を組むのが緊急事態っぽくていいかなと思って捜してたんですけど、全然姿が見えなくて、他の人と組んでしまったのかとばかり……。そこでレナさん達に誘われて、こちらのパーティに入ってしまいました……」
リリアが非常に申し訳なさそうに頭を下げた。
彼女をヘッドハンティングしたのは好戦的な性格の三人娘だった。
金髪で拳にメリケンを嵌めた「レナ」は超格闘タイプの喧嘩屋。関西弁を操る「アクアータ」は扇情的な格好をしている者の多い娘達の中でも露出度ナンバーワン、常に水着で過ごす支援タイプの水使い。その童顔とは裏腹、全身に鋼のような筋肉を備えた「ルージュ」は圧倒的攻撃力の筋肉ムキムキのマッチョ娘だ。
この三人に防御支援特化のリリアが加わると、中々バランスの取れたパーティが出来上がる。彼女達三人がリリアを欲しがるのも無理はない。
し、しかし、そうは言っても……!
「そ、そんなっ!? あたしもリリアさんと同じパーティがいいよー!」
「んー、そうは言ってもなー。ララが悪いんやで。リリアはララのこと、ずっと捜しとったのに。どこほっつき歩いとったんや?」
「えっ。あたしは、その辺りをぶらぶらーっと、ね?」
いやはや。
これが本当に真実なのだから、困ったものである。すると、ここでレナが鮮やかな金髪を掻き上げながら、呆れた様子で言う。
「まったく相変わらず、お前は呑気な奴だな。とにかくヨソを当たってくれ。ま、次に何かあったら組もうじゃねぇか。アクアータがいなけりゃ、あたしとルージュの鉄拳ペアにアンタとを加えて、最強の『鉄拳トリオ』を結成するのも面白そうだしな。いつかここにワゴコロも加えてカルテットを組むのも悪くねぇし!」
「なんや、レナ! まるで、うちがあんまり要らんみたいやないか!」
「はー? アホ。実際、お前、あんまり要らねーだろ。全然能力噛み合わねーぞ」
「能力的にはアクアータちゃんは魔法使いの皆さんと組んだ方がいいですからねぇ。魔力ブーストがアクアータちゃんの一番の武器っす。あたしとレナさんは魔法なんて使いませんから」
「せ、せやかて二人とも! その辺りは、なんや、友情パワーで補えると思わんか!?」
「ああ? 全然思わねーけど、いつも連んでるのにこういう時だけハブるのも気持ちわりーし、本気でオマエを抜くつもりはねーよ。こんなことわざわざ言わせんな、バーカ」
「別に完全に要らないわけじゃないですからね。アクアータさんの支援能力は十分効果的っす! 改めてよろしく頼むっす!」
「っ……おおきに! 二人なら、そう言ってくれると思っとたで!」
「ララさん。そういうわけで、今回は……」
チラリとリリアがまたしても気まずそうな顔でララの方を見た。ララはこれはどうしようもないな、と思い直し、力強く頷いた。
「うん、わかったよ。他の子に当たってみる!」
「すみません。この事件が片付いたら、普段より念入りにお世話をしますので……」
「あはは。じゃあ、期待してるねー。それじゃあ、皆も頑張ろうね!」
そしてリリア達に別れを告げ、ララは少しだけ離れた場所へと足を運んだ。
このとき、ララは事態を大して重くは考えていなかった。
ララは娘内でも最古参なこともあって、知り合いはそれなりに多い。パーティに誘ってくれた娘も他に何人かいた。だから、その子達の誰かにもう一度お願いして、今度こそ自分を加えて貰えばいい――そんな風にいつも通り適当に、ゆるーく考えていたのである。
ところが、だ。
「……あっれー?」
不発。不発。不発。
気ままに室内をぶらぶらし過ぎていたことが祟り、仲の良い娘に限って既にパーティが完成してしまっている状況が多発したのである。
完全に、出遅れてしまった。
むしろ、完成しているパーティが多数派で、まだ誰と組むかを決めていない者は片手で数えられるのではないか――そんな状況である。自然と、ついさっき普通娘のフェリーチェが口にしていた悲痛な単語がララの脳裏を過ぎった。
曰く…………「余り物」。
「あ、あたし、メッチャ余ってる……!?」
自分がフラフラしていたせいだとはいえ、なんだかとっても悲しくなるララだった。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
そして、運命の時が訪れる。
「アヤメさん! アヤメさんはパーティは……」
とにかく、まだパーティが決まっていない物を捜していたララは、丁度、酒場の壁に凭れ掛かって事の成り行きを眺めていた少女に声を掛けた。
彼女の名は「アヤメ」。
アクアータと並んで娘達の中では過激な衣装に身を包んだ少女であり、その正体は過去に何人もの人間を音もなく殺してきた生粋の暗殺者である。
「あたしは単独行動をさせて頂く予定なので、パーティは組めないのです。すみません」
ララの呼び掛けに気付くと、アヤメが小さく頭を下げた。
そういえば、初めにラルフィーがアヤメは一人で色々と動くのでノーカウントだと言っていたような……。
「実はここは一つ、闇討ちを、してこようかなと思うんです」
ニヤッ、とアヤメがダークな笑みを浮かべる。
闇討ち!
つまり「兵士です!」を――密かに「アヤメが斬る!」というわけだ!
「で、でも、一人でなんて危なくないかな?」
訊いてみる。この世界ではパーティを組んで行動するのが当たり前だ。いくらアヤメの能力が単身での戦いに向いているといっても限度はあるはず。
けれどアヤメは平然とした様子で、
「大丈夫です。本来暗殺とは一人で殺るものですからね。ラルフさんに独り身での暗殺は止められていたんですが、この状況であたしに出来ることはやはりこれしか」
「わ、すごい! それじゃあ一番乗りかもしれないね!」
アヤメが得意げに頷いた。
「もちろん、そのつもりですよ。ですが、ララさんも早くパーティを組んだ方がいいのでは。とりあえず目立つところに行ってみたらどうです?」
「ふむむー」
パーティが作れないなんてことは、有り得ない。
そんなわけで、ララはアヤメの助言に従い、先程の話し合いでラルフィーが立っていた酒場の中心部辺りに足を向けることにした。周りを見回すと、既に完成したパーティが今後のダンジョン攻略に関する計画を練っている姿がいくつも飛び込んで来る。
故に、分かり易くなるのだ。
――未だにパーティが組めていない「余り物」の存在が!
「む……」
いた。
そこでは、分かり易いくらいに「まだ誰とも組んでいませんよ」オーラを携えた少女が二人、腕を組み、非常に不満げなムスッとした表情で立っているではないか。
「えー!」
だが、その二人を見て、ララは正直ビックリしてしまった。
だって――このあまりにも過酷な四人パーティ作りで最後まで余ってしまうようなタイプには到底思えなかったから。
「……なによ、ララ。あたしの顔を見て驚くなんて失礼じゃない?」
「そうそう。ストレーガが余るのも別に不思議じゃないし、あたしが余るのも案外想像し易いケースだと思うもの」
「ッ――ホ、ホーリー! 貴女、なんてこと言うのよっ。あたしがここにいるのはその…………ちょ、ちょっと巡り合わせが悪かったからだって! 常に何だか近寄りがたい雰囲気を出してる貴女と一緒にして欲しくないんだけど!」
「そうかしら。あんたも大概だと思うけれど。ごめんなさいね。それにあたし、謝るのも謝らせられるのも、あんまり好きじゃないのよ。あんたと違って」
「な、な、なぁっ――な、なんなの、その言い草!? いいです。どっちにしろあんたに謝って貰おうなんて思ってないから……!」
いや…………案外妥当、なのかもしれない。
短気な魔術士、ストレーガ。
ドS天使、ホーリー。
そこにいたのは娘達の中でも特に当たりが強く、過激で、先程の話し合いの場でも特に荒ぶりまくっていた二人だった。二人の「兵士です!」討伐に掛けるやる気は相当なもので、むしろ、やる気というより殺る気としか思えなかったとも言う。
「だそうですって。でも、あたし達と違ってあんたが余るなんて意外ね、ララ」
自身から顔を背けたストレーガのことをくすくすと笑いながら、ホーリーがララに話し掛けて来た。ララはわずかに首を傾げて、
「え。あたしが?」
「そうよ。だって、あんたって結構社交的なタイプじゃない」
「うーん、そうなのかなあ」
「だと思うわ。特に、あたしみたいなのとは真逆にいるんじゃないかしら。自然と皆の中心になる人間……ラルフに近い、みたいな?」
「わっ。ラルフに似てるって言って貰えるのは嬉しいかも!」
「……ま、そのラルフのせいで、あたし達三人って今まで一度も同じパーティになったことないし、本当にそうなのかは、まだちょっと分からないけれどね」
一度も同じパーティになったことがない。
言われてみると、その通りだ。
「ん~。なんでだろうね。結構ラルフって定期的に色々な組み合わせでパーティを組んでた気がするのに」
「決まってるじゃない、そんなの」
ホーリーが真顔で言った。
「明らかに相性が悪そうだからでしょ。色々な意味で」
「「……」」
一切の冗談の色もなく超ドストレートに、だ。
ホーリーが続ける。
「言っとくけどあたし、組んだことない子のが少ないわよ。片手で数えられるくらい。一応、誰とでもそれなりに組めるバランスタイプだもの。それにね、ラルフってレベル1だけど、ああ見えて結構優秀なところもあるのよ? 特に他人との関わり方とか、あたし達の人間関係については相当気を遣ってるもの。そんなあいつが、それでも一度も組ませようとしなかった相手――そりゃあ噛み合うわけがないわ」
「え、そ、そんな……」
ララはビックリしてしまった。自分達の相性が悪い? そんなこと、今まで全く考えたことも――
「ふぅん……なんだ。やっぱりあんたもそう思ってたわけ」
「!?」
ストレーガが納得した様子で深々と首を縦に振った。
一方、ホーリーは口元を歪め、嘲るように、
「当たり前じゃない。あたし、そこまで鈍感じゃないわ」
「能力的に相性が悪過ぎるララはともかくとして……あたし達二人が一度も組んだことがないのは――当然、ラルフの意図があったんでしょうね」
「ええ。それは間違いないわ。あいつ、みんなが寝静まった頃によくパーティの編成に悩んでウンウン言ってたもの。あんた知ってる? ラルフってね。レベル1だから無力ではあるのだけれど、決して無思慮で怠惰な男じゃないんだから」
眉を吊り上げ、ムッとした様子でストレーガが答える。
「……ホーリー。そんなこと、わざわざ言われなくても知っていますよ。ラルフはあたし達のことを、いつも一番に考えています。自慢げに言うほどのことでは、ないかと」
「あら、そう」
「だ、大体、ラルフはレベル1なんですから、それぐらいやって当然です……」
「へぇー」
「……だけど、あんたも大したものよね。ラルフのことは置いておくとして、相性が悪いと思っている相手にここまで面と向かって接するとか、正直凄いわ」
「ばかね。それを言っちゃうのがあたしなのよ」
「ねえ。威張られても困るんだけど、それ」
「…………」
ギスギス。
さすがのララも、このパーティがちょっとヤバそうなことは強く意識させられた。
おそらく、ララに関して言うなら、そこまでではない。ヤバいのは――ストレーガとホーリーだ。この二人の相性の悪さは、どうやら相当な危険域に達しているらしかった。
と、そのときだった。
「なんということでしょう。このパーティには決定的なまでに『和』が欠けているのですね……」
「「「!?」」」
まるで一迅の涼風が通り抜けたかのような錯覚をもたらす声が、ララ達三人に投げ掛けられたのである。
四人目――
瞬時にその事実へと至ったララ達は、すかさず声のした方へと振り向いた。
そこにいたのは、藍染めの着物に牡丹色の帯を結んだ少女だった。佇まいからして極めて落ち着いた和の雰囲気を漂わせ、深い紫色の髪もそのイメージにマッチしている。
そんな少女の名は――
「……ワゴコロさんも、まだ誰ともパーティを?」
「はい。我々が最後の四人のようで……是非とも私をパーティに加えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします」
その問い掛けに深々と和流娘「ワゴコロ」が頭を下げた。
彼女が……?
ララ達三人は互いに顔を見合わせた。自然と、瞳が、それぞれの意志を代弁する――やっぱり彼女も一度もパーティを組んだことがない相手だったのだから!
――何とも、奇妙な展開である。
ララも、ストレーガも、ホーリーも本来ならば今すぐにでも「兵士です!」の居城に乗り込んで、彼と再戦したいと思っているのだ。
しかし、それは侭ならない。
明らかに、この出来上がったパーティはメチャクチャだった。四人目のワゴコロは非常に典雅で落ち着いた雰囲気を持った美少女なのだが、困ったことに「和」という概念をひたすらに重視する一風変わった性格の人物なのである。
言うなれば、超マイペース。いや、やっぱり同じくマイペース系なララが言えたことではないが……ともかく!
これでは、あまりにもバランスが取れていない!
余り物パーティだから、と言えばそうなのだろうが――それでも!
「(もう、ラルフってば! もっとちゃんとあたし達のことを考えて色んなパーティを組んでくれないと困るよ! こんな調子じゃ、ラルフを助けにいけないよー!)」
一番側に居て欲しいときに彼方の地にて囚われの身となっているラルフを恨みがましく思うララだったが、そんな心の叫びが彼に届くはずもなくて。
いったい、ラルフは今、何をしているのだろう?
自分達は何だかんだでラルフのことを想い、自分達のレベルを下げた「兵士です!」に恨みを果たすついで(ということになっている)ではあるが、彼を助け出そうと再始動したと言うのに!
この事実を出来ればラルフ本人にも知って貰いたかった。そんな願いを、前途多難にも程があるパーティに入ってしまったララは強く胸に抱くのだった。
「ふーむ……八番目のララちゃんパーティはメンバーの相性が悪いようじゃのう」
杜撰な扱いをされ、心に傷を負ったラルフが不貞寝をしてしまった後も、エロサモナーは一人でマジックボールの画面をずっと眺めていた。
もちろん、合法的に娘達を盗撮出来るのだからエロサモナーに画面から目を離す理由があるはずもない。が、特にエロ心を擽られるようなシーンに遭遇することもなく、娘達が八つのパーティを組んだところでマジックボールの「遠見」は終了してしまった。
とはいえ、事態が中々興味深い方向に転がり始めたのはエロサモナーから見ても明らかだった。
ラルフの不在と、娘達だけで構成された八つのパーティ。
今まで彼女達は街の隣に聳え立つ練習用のタワーダンジョンを攻略するときを除き、ラルフという明確なリーダーに率いられ、数多の戦いを繰り広げて来た。
だが、本当の意味でラルフがいない状況を彼女達は経験したことがない。
これは初体験なのである。ラルフにとっても、娘達にとっても、別にエロい意味ではなく――
「もしかして、この奇妙な状態を作り出すことが、あの兵士の目的だったり……?」
何も映さなくなった遠見の魔法球を睨みつけながら、エロサモナーは独りごちる。
考えてみれば、こんな都合のいいアイテムが牢屋に置かれているのも不自然だ。
城主である「兵士です!」が娘達の現在の行動を見せつけるために設置したと推測するのが自然である。
だが、その目的とは? どんな効果を彼は狙っているのだ?
「…………どちらにしろ、皆には『ついで』でもいいから、早くわし達を助けに来て欲しいところじゃのう。色々な意味でララちゃんのパーティは論外として、バランスには精霊王ちゃんのところか、レナちゃんのパーティが一番有望かの」
とはいえ、「兵士です!」の目的が何であれ、自分達にはどうすることも出来ない。とにかく今は男二人で娘達がレベルをもう一度上げてこの城に乗り込んで来る機会を待つことしか出来ないのだから……。
6
「……う」
目を醒ましたラルフが最初に意識したのは、相反する二つの感覚だった。
一つは――堅い。
これは寝床の問題だ。ラルフが横になっていたのは石畳の上に乾燥させた藁を敷き詰めただけの粗末な寝床である。職業柄、野宿には慣れているはずだったが、一つの街に定住するようになってから、不確かな場所で寝る機会が減少していたわけだ。
身体の節々を襲う痛みに思わずラルフは眉を顰めた。これは中々、慣れそうもない。そしてもう一つは――
「…………やわら、かい……だと?」
柔らかい。
けれど、それは状況を考えれば極めて不可解な感触である。牢屋の中に柔らかいモノなどあるわけがないのだ。牢屋とはその身柄を拘束された者が収監される忌むべき場所。冷たい空気が吹き抜け、粗末な設備しかない窮屈で屈辱的な暮らしを余儀なくされる空間なのだから。
だが、事実として、柔らかいのである。
具体的に言えば左の掌に柔らかみを感じる。まさに掌サイズの柔らかさがハッキリとラルフの掌で自己主張をしているではないか。
これは、いったい?
寝起き故に視界が晴れないラルフはその未知の感触を脳内で処理することが出来なかった。まさか鉄格子の隙間を縫って、ブルースライムか何か夜襲を掛けて来たとか――
「ラルフさん。さすがに、そろそろ起きて下さい」
「っ……?」
しかし、そんなぼやけた感慨は見事に消滅することになる。
何故かラルフの耳に、女の子の声が飛び込んで来たからだ。
ラルフは頭をシャッキリとさせるべく瞼を擦った。
依然として、左手は柔らかい部分に添えたままで。
「おはようございます、ラルフさん」
「えええええええええええええええええええ!?」
すぐ側に――アヤメが、いた。
黒羽色のショートヘアー。超露出度の高い衣装に華麗に、そしてしなやかに鍛え上げられた肢体。暗殺や闇討ちを得意とするラルフの仲間の一人――アサシンのアヤメだ。
そんな彼女が、何故かラルフの捕らわれていた牢屋の中にいたのである!
いや、それどころではない。
隣、というか、まるで抱き枕に寄り掛かるような形で、ラルフはアヤメの身体にもたれ掛かってしまっていた。しかも、ラルフの左の掌は思いっきりアヤメの胸を掴んでしまっているではないか。少女の最も柔らかい部分に、手を――
「っ……す、すまないッ! 眠っていたとはいえ、俺はとんでもないことをしてしまった!」
現状を理解したラルフは凄まじいスピードでアヤメの身体から離れると、恥も外聞も殴り捨てて完璧なフォームで彼女に土下座をした。
眠気が一瞬でブッ飛んだ。俺は大切な仲間に対して、なんて破廉恥なことを……!

「ああいえ、別にあたしは大して」
「すまない……すまない……なんて詫びればいいのか……! ああああああ! 俺はなんてことをしてしまったんだぁあッ!」
と、ラルフが涙を流し、アヤメに全力で謝罪していると、本来の牢屋メイト――エロサモナーがマジギレしながらラルフを怒鳴りつけた!
かつて無いほどのキレっぷりで、だ!
「ラルフ! ようやくお目覚めみたいだね! 良い夢が見られたんじゃないかい? アヤメちゃんの胸を寝ながら揉むなんて……とんでもないことだよ! 今度こそ君は『エロラルフ』に改名するべきじゃないのかい!? このエロラルフ! エロラルフ! エロラルフ!」
「エ、エロサモナー! 見ていたなら、止めてくれよ!? っていうか、なんでアヤメが牢屋の中にいるんだよ! 意味が分からないぞ!?」
「すいません。ラルフさん、エロサモナー。ちょっと聞いてください。っていうか、エロエロうるさいんですが」
「ええい、ラルフよ! 頭を上げるでない! 反省の態度が足らんぞ! もっとアヤメちゃんに心から謝るのじゃ! クッ、今でも目に焼き付いておるわ……この牢屋にやって来たアヤメちゃんが、泣き疲れて惨めに寝ていた君を発見してスッとその傍らに腰を下ろした瞬間――君が都合良く寝返りを打って、ラッキースケベに及んだ光景を! 勇者ともあろう者が無意識の内に仲間をその毒牙に掛ける決定的瞬間がね!」
「お、俺が、寝ながらそんなことを……!?」
「…………あの、二人とも」
「いよいよ『ラルフのエロい本性が出始めた』ということさ! これだからハーレム主人公の言うことは信用出来ないのよ。実際君達サァ、謝れば何しても許されると思ってんじゃない? ちょっとこの業界、舐めてない? ぶっちゃけ調子乗ってんじゃないの?」
「君達っていったい誰のことだよ!? 大体、俺は仲間に触ったりなんて、ほとんどしたことないぞ!? セクハラしまくりのエロサモナーとは違う!」
「わしのせいにするんじゃない! それにほとんどだって!? これだよ! 皆さん、聴きましたか!? これから徐々にエロい経験を積んで行こうっていうわけだ!」
二人だけでエキサイトするラルフとエロサモナー。
エロの称号を押しつけたい男とエロの称号から逃れたい男。だが――そんな男達の醜過ぎる争いも、一瞬で幕を閉じることになる。
「あの、いい加減黙らないと…………暗殺、しますよ?」
「「!?」」
――アヤメの暗殺宣言によって。
「暗殺……だと……」
「はい。エロサモナーを」
「えっ、わしだけ!?」
「ええ」
「……ラルフは?」
怖々と尋ねたエロサモナーをアヤメが明確な殺意を込めて睨みつける。
「は? なんでラルフさんをあたしが殺さないといけないんですか。というか、ラルフさんなら別に胸くらい触られても何とも思いませんし」
「な……ふ、不公平じゃ……! 年寄りを労るという精神が君にはないのかい!?」
「へー。そういえば、エロサモナー。あなたはこの前、完全に自分の意志であたしのお尻を触りましたよね? やっぱり暗殺していいですか?」
「………………ラルフも男じゃからの。そこにおっぱいがあったら眠っていても触りたくなってしまうのは仕方がないことじゃ。男は皆、登山者なのじゃよ!」
露骨に視線を逸らし、意味の分からないことを力説し始めるエロサモナーだった。
う、うむ。
ひとまず、このエロ老人のことはいいとして……。
「アヤメ、本当にすまない……その、なんだ……無意識とはいえ、そういうことをしてしまったみたいで……」
「あたしは構いません。尊敬するラルフさんのすることですから」
「そうか。悪い」
「いいえ。次は、お互い起きているときに是非」
「……」
真顔でこの発言……どこまで本気か分からない。
スルーだ。
「…………ところでだ。アヤメ、どうして君がこんなところにいるんだ? こんな、冷たい牢屋の中に女の子が……」
「大丈夫です。牢屋と拷問は、ラルフさんよりずっと慣れてますから」
「……そういうことを言ってるんじゃないんだ」
「おやおや」
ラルフの芳しくない反応を察したのか、アヤメが真顔で答えた。
「ま、特に奇妙なことはありません。『兵士です!』に倒されて、ここに放り込まれたんです。あたしは一人で正々堂々と奴を暗殺しに行ったんですが、まさかイベント戦闘にならず、普通の戦闘になるなんて……とんでもないことです。こういう場合、空気を読んで暗殺されるべきでしょうに……」
「待ってくれ。つまり奴に負けて、捕縛されたということか?」
「ええ。そうです」
「それは……妙な展開だな」
ラルフは思わず首を傾げた。
娘を捕まえたいのならば最初に娘達をフルボッコにしたとき、一網打尽にすれば良かったはずだ。今になってからわざわざアヤメを捕まえる理由が全く見出せない。
どうなっているんだ?
「随分と、辛気臭い顔をしてますねぇ」
「っ……この声は……『兵士です!』か!?」
と、ラルフが首を傾げたときだった。城主にしてラルフ達を牢屋の中にぶち込んだ張本人――「兵士です!」が現れたのである。
丁度いいタイミングだ。
すぐさまラルフは声を張り上げた。
「どういうつもりなんだ! 俺以外の子を捕まえるなんて!」
「は? 何が不満なんですか?」
「不満に決まっているだろう! 女の子を牢屋にぶち込むなんて!」
「でも彼女、あなたより断然、捕まるのに慣れてるみたいですけど」
「…………」
「あ。もしかして牢屋を男女別にして欲しいってことですかね。でしたら――」
「ちょっと待ったああああ! 兵士よ、それは止めた方がいいぞい! 牢屋を分けてしまっては脱獄の危険性が増す! 男女を分けるなど、以ての外! どう考えても同じ場所に閉じ込めるべきじゃて!」
「……相変わらず、不埒な男ですね」
クワッと眼を見開き、しょうもないことを力説するエロサモナーを軽蔑の眼差しで見つめるアヤメ。相変わらず、娘達の彼を見る眼は大体容赦がない。
だが、まあいい。
――ラルフにとって最も気に懸かっているのは、別の事柄なのだから。
「お前、何を考えている? 俺達を、どうするつもりなんだ?」
彼の真意について、問い掛ける。
単にラルフを捕らえ、娘達のレベルを下げただけではない――その先で、明らかに彼が策謀していると思わしきナニカについて。「兵士です!」が答える。
「あえて言うなら、あなたに俺と同じ苦悩を味あわせたい、というところですかねぇ?」
「なんだって?」
「ふふふふふ。真相は追々伝えさせて貰いますよ――おっと、そういえば」
ラルフ達の前から立ち去ろうとした「兵士です!」が一瞬足を止めた。
そして露骨に悪そうな笑みを浮かべると、
「エロそうな爺さんのご要望通り、皆さんには同じ牢屋で過ごして貰おうと思っているんですが、もう少ししたら、別の牢に移って貰おうかなぁと」
「……いや、ここで十分じゃないか? 結構広い部屋だし」
「いえいえ、直に狭くなりますからね。さすがに三十人近い人間を捕まえておくには別の牢屋にしないと」
三十人!? そ、それはつまり……!
「お、お前! まさかアヤメだけじゃなくて、俺の仲間を全員捕まえるつもりで――」
「いや。全員ではないですねぇ」
「は……」
「理由はすぐに分かりますよ。それでは」
ひらひらと掌を振って、「兵士です!」は牢のある地下室から出て行ってしまった。
ラルフ達は互いに顔を付き合わせ、議論を始める。
「……分かるか、理由?」
「いえ。さっぱり」
「どういうことなんじゃろうな」
「全員じゃないってことは、何人かは捕まえないでおく、という風に聞こえたが……」
「でしたら、いくつかパーティを泳がせるという意味ではないでしょうか?」
「……それっぽいな。そういえば、さっきパーティを八つに分けたって言ってたけど、その中に変なパーティがあったりとかはしないのか? 例えば、捕まえる価値もないほど弱いところとか」
ラルフの問い掛けにアヤメが小さく頷いた。
「弱いチームは、ありますね。ユメルさんがリーダーのところなんですが、四人とも回復タイプか支援タイプばかりで、一人も攻撃技を持ってる人がいないんです」
「随分とバランスが悪いんだな」
「はい。あとは、そうですね。戦力的には精霊王さんのところが図抜けて強いですが、良い感じに分散している気がします。ただ……四人の相性がメチャクチャ悪いパーティが一つありますね。ララさんのところなんですが」
「おお、あそこか……ええと確かメンバーはララちゃん、ストレーガちゃん、ホーリーちゃん、ワゴコロちゃんだったかの。問題児揃いじゃ」
「な、なんだ、そのパーティ! どういう組み方をすれば、そんなハチャメチャなパーティが出来るんだ……!?」
それだけはないだろう、とラルフは強く思った。
まずストレーガとホーリーは互いに気性が荒過ぎて、相性が非常に悪い。
彼女は少し意地っ張りで、そして凄く不器用なところがある。逆にあまりにも器用で達観し過ぎているのがホーリーの欠点なのだが、おそらく今回のケースで問題になるのはストレーガの方だ。何か良いキッカケが出来るまで、この二人は出来るだけ別々に行動させた方がいい――一緒のパーティになってしまったようだが。
ワゴコロは娘の中でも飛び抜けてマイペースな子であり、和の体現者であるが、ぶっちゃけ和を取りなす能力は皆無である。ああ見えて結構暴力的な彼女は、出来る限り常識的な娘達と組ませるべきだ――非常識人揃いだが。
ララは天真爛漫なお気楽娘なので、彼女から目を離さずにいられるしっかり者、例えばリリア辺りと組ませたい。あまり彼女が責任を負うポジションに立たされる組み合わせは良くないだろう。ララにはいつだって自由でいて貰いたい――この面子では、消去法的にララがリーダーをやることになるだろうが。
しかも、ラルフの記憶が確かならば…………この四人は、今まで一度も同じパーティを組んだことがないのではないだろうか?
要するに――最悪だ。
こんな困ったパーティが出来上がった理由とは、いったい……!?
「四人とも余ったのじゃよ、ラルフ」
「…………そうか」
あまりに切ない理由に涙が出てきそうになるラルフだった。肩を竦め、エロサモナーが続ける。
「でもま、ラルフもそう思うか。さすがにストレーガちゃんとホーリーちゃんは真っ向からやり合っちゃうもんね。ここが一緒なのはマズいよねぇ」
「――いや。それは違うぞ、エロサモナー。このパーティで一番マズいのは、その二人じゃないからな」
ラルフがゆっくりと首を横に振った。エロサモナーは眼を丸々と見開き、キョトンとした様子で訊き返した。
「え。違うの? マジで?」
「違う。そりゃあ二人の相性はお世辞にも良くないけど、そこまで悪いわけでもない気がする。俺としては案外仲良くなれる可能性だってあると思ってるしな。あの二人はちょっとタイミングが悪くて、一緒に冒険に付いて来て貰ったことはなかっただけなんだ」
「へええ。じゃあ、誰と誰が厳しいわけ? ワゴコロちゃん関係?」
ラルフは言った。
「――ララとストレーガだよ」
「…………ああ、そういう」
自分から口に出しておきながら、ラルフは頭を抱えたい気分になった。
だって、この二人の関係というのは、つまり――
「なるほど。問題なのは『ラルフさんのことを好きだと公言しているララさん』と『ラルフさんのことが好きなのは誰が見ても明らかなのに、絶対にそれを認めないストレーガさん』の何とも言えない困った関係、というわけですね。前々からストレーガさんはララさんのことをかなり意識してますし、確かに揉める気がします。恋の一大事ですね」
「……」
「おや。どこか違いましたか?」
「い、いや……」
むしろ詳し過ぎてビビったというか……。アヤメが肩を竦めた。
「大したことではありません。皆、これくらいなら知っています。ラルフさんはお忘れかもしれませんが――我々は一応全員、女子ですからね。恋バナは好物なのですよ」
「アヤメも恋バナなんてするのか!?」
「はい。情報収集は暗殺の基本ですし」
「……その情報、仲間のも集める必要があるのか?」
結局、全てが暗殺に結びつくアヤメに頭を抱えつつ、ラルフはため息をついた。
とはいえ、だ。
さすがに、このパーティが最後まで残るとは考え難い。
それだけは不幸中の幸いと言えるだろう。
戦力的には十分だが、パーティの空気が悪ければ連携も侭ならないものだ。彼女達は案外早い内に、この牢屋にやって来ることになるだろう。
少なくとも、このときのラルフはそう思えてならなかった。
続きは7月1日発売の文庫本で!
『Hero and Daughter Lv1からはじめる勇者奪還作戦』7月1日発売!

株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫
原作/tachi 著/高野小鹿 イラスト/吉沢メガネ
原作ゲームがいますぐ無料で遊べる!新作自作ゲームがダウンロードできるニコニコゲームマガジン!


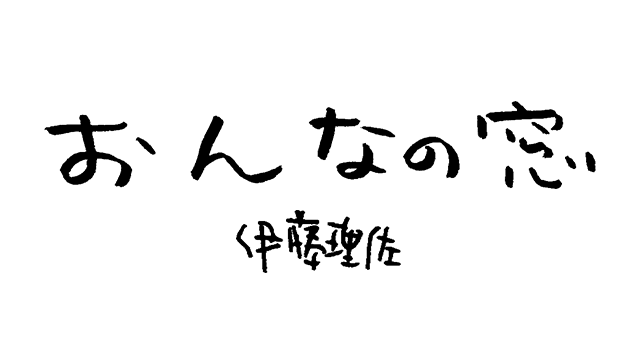

コメント
コメントを書く(ID:256937)
ネギま状態!!
(ID:128853)
今後に期待(本当に期待しているとは言っていない)
(ID:197350)
もっと女の子増えてもいいのよ
ただ確かゲームのアプデの方は7月中で終わるんだっけ