小説『神神化身』第二部
第四十二話
「果ての月すら仰ぎ見よ」
舞奏競(まいかなずくらべ)・星鳥(せいちょう)の結果を聞いた時、比鷺(ひさぎ)は落胆と安堵の入り混じった奇妙な感情に襲われた。上野國(こうずけのくに)の水鵠衆(みずまとしゅう)が御斯葉衆(みしばしゅう)を打ち倒すところが、化身(けしん)が無い人間でも──血を継いだ名家の集団に勝てるところが、見てみたかった。
現に水鵠衆は多くの観囃子(みはやし)の歓心を集め、御斯葉衆までかなりの勢いで迫ったらしい。実力の面で、水鵠衆は御斯葉衆に全く劣っていなかったと聞いて比鷺は素直に驚いてしまった。そんなことがあるのだ。なら、水鵠衆が勝ってくれても良かったのに。とすら思った。彼らの敗北を目の当たりにして、比鷺は思っていたより自分が水鵠衆に肩入れしていることに気がついたくらいだ。
水鵠衆がどんな舞奏(まいかなず)を奉じるのか見てみたい、と比鷺は自然と思った。舞奏から距離を置いた人生を送っていたのに、これじゃあまるで舞奏のことが大好きな人間みたいだ。
比鷺に『舞奏には人間性が出る』と最初に教えたのは兄の鵺雲(やくも)だった。
それ以外にも、鵺雲からは舞奏の尺度で測られた様々なものを教え込まれてきた。鵺雲の中には舞奏で出来た天秤があって、彼はその忠実な守人だった。比鷺の味方でいてくれた時も、そうでない時も。
あれはいつだっただろうか。随分小さい頃だった気がする。比鷺が舞奏を辞めた、その直後くらいだっただろうか。急に舞奏の道を外れた比鷺に対し、周囲は容赦無く冷たい視線と言葉を浴びせかけた。所詮控え子、という囁きをはっきりと認識したのもこの頃だ。
比鷺はその意味を正しく理解していたわけじゃなかったが、自分が所詮鵺雲のスペアでしかないことだけは伝わってきて、自分の人生の虚しさに泣いた。
泣いている比鷺を慰めてくれたのが鵺雲だ。
「どうしたの? ひーちゃん。誰かに酷いことを言われたの?」
比鷺はもう既に鵺雲に対する苦手意識を持っていたし、彼が比鷺とは全く違う価値観を持った人間であることも理解してしまっていた。それでも、この頃の比鷺は自分を撫でる兄の手を振り払うことも、目線を合わせて困ったように笑う彼を撥ね除けることも出来なかった。弱かったんだ、と比鷺はわざわざ自分の心に刻みつけるように思う。
「……控え子のくせにって言われた。所詮控え子のくせに生意気だって。控え子のくせに舞奏をやらないなんてって……」
「控え子を蔑みの意味で用いるなんて愚かだね。的外れな言葉で僕の比鷺を傷つけようとするなんて、身の程知らずにも程がある」
鵺雲は冷たい声で言った。自分に向けられた言葉ではないと分かっているのに、比鷺は思わずびくっと身体を震わせてしまったほどだ。すると、鵺雲は何を勘違いしたのか比鷺のことをぎゅっと抱きしめてきた。
「気にすることはないよ、ひーちゃん。控え子というのは決して悪い意味じゃないんだから。むしろ、ひーちゃんがいてくれるからこそ、僕が頑張れるようなものなんだから。ひーちゃんのお陰で、僕は大祝宴(だいしゅくえん)に到達出来る。だから……ね、泣かないで」
鵺雲は舞奏という絶対的な尺度を持っている。その彼が控え子でしかない自分に意味があると言ったのだから、きっと意味はあるのだ。単に九条(くじょう)家の血を次代に繋げられるとか、鵺雲に何かあった時のスペアとして機能できるとか、本当にそれだけの意味かもしれないが。
それとも、もっと他の意味があったのだろうか?
今更ながらその部分を考えようとしたのだが、この思い出を反芻しようとすると、どうしても兄との思い出したくない場面まで思い出すことになるから苦手なのである。
最悪なのは、兄がそうやって抱きしめてくれることに、あの頃の比鷺がほんの一匙の嬉しさを覚えていたからである。自分達がただの兄弟でいられるんじゃないかと、僅かな期待を寄せていた自分が苦々しくて、憐れだ。比鷺は小さく溜息を吐く。
こうして水鵠衆に歓心を向けていた一方で、御斯葉衆が勝ったことに対して安堵を覚える自分もいた。そりゃあそうだ、と比鷺は一人で呟く。何せ、御斯葉衆のリーダーはあの九条鵺雲なのだから。鵺雲がリーダーを務めている舞奏衆が負けるはずがない。
鵺雲の舞奏は、正しい舞奏だ。今後千年舞奏の『正答』として語られるような、完成形の舞奏である。鵺雲くらいの実力があるなら、むしろ舞奏衆を組んで誰かと舞う方が枷(かせ)になるんじゃないか。そう思ってしまうくらいだ。
そんな鵺雲が負けなかったというだけで、比鷺の中には『安心』が生まれてしまった。ああ、自分が正しいと教えられてきたものは──自分がずっと目映いと思っていたものは、負けなかった。
今の比鷺は鵺雲の舞奏を追っていない。櫛魂衆(くししゅう)の九条比鷺として、自分の舞奏を奉じている。だからといって、かつて自分の半身であったもの、自分が目指すべき道標だったものが揺らがないのは、──……安心した。
彼が相模國(さがみのくに)を出奔してから、鵺雲とはまともに会話をしていない。今話をしてみたら、一体どうなるだろう。どうせろくなことにはならないよ、と比鷺の中で声がする。
「三言(みこと)はさぁ……あの人と舞奏やってたでしょ。どうだった」
そんなことを考えていたからか、比鷺はつい三言にそんなことを尋ねてしまった。今日は三言が部屋に遊びに来てくれたというのに。生憎遠流(とおる)はお仕事だけど、折角のお休みだ。比鷺は一緒に楽しいことだけをするつもりだったのに。
だが、三言は嫌な話をされたという気もしないようで、笑顔で言う。
「どうだったって言われると難しいけど……楽しかったぞ!」
う、と思わず言葉が漏れた。三言のあまりの屈託の無さが眩しい。舞奏が大好きな三言だ。そんな三言があの九条鵺雲と舞えたときたら、それはもう楽しくて仕方がなかったことだろう。
それによって比鷺の価値が下がるわけではないと分かっていても、なんだかあんまり嬉しくない。俺の舞奏とあの人の舞奏どっちがいい? って面倒臭いことを聞いてみたくなる。
「鵺雲さんの舞奏と俺の舞奏は、やっぱりかなり違うからな! 鵺雲さんの舞奏に合わせると、俺の方も結構変わるから面白いんだ!」
「もー! そんなにあいつのこと褒めないで! 俺の舞奏とあいつの舞奏どっちが好きなの!?」
「今俺と櫛魂衆を組んでいるのは比鷺だからな! 勿論比鷺の舞奏だ!」
「う、それは本当に素直に嬉しいけど……。ぐーっ、こんなめんどいこと言うつもりじゃなかったのに結局言っちゃった俺の性よ」
「そういえば、鵺雲さんの率いる御斯葉衆は無事に勝利を収めたみたいだな!」
「うん、まー……そうね」
「流石は鵺雲さんだ! 凄いな!」
「ん……」
素直に同意したくなくて、クッションに声を吸わせる。確かに凄い。凄いけれど、そう言いたくはない。
「俺はどっちかっていうと水鵠衆を応援してたから、まあそんな……別に」
「水鵠衆も凄い舞奏衆だって聞いているからな! 俺も水鵠衆の舞奏が見てみたいし、阿城木さんとはまた会いたい」
「えっ、会ったの? それ初出し情報じゃない!?」
思わずクッションから顔を上げて叫んでしまう。すると三言は事もなげに言った。
「そう言われたらそうだな……。阿城木さんは甘い物が好きみたいで、しらすシュークリームの為にわざわざ浪磯まで来たって言ってたぞ! 良かったな! 比鷺の開発したしらすシュークリームに惹かれて遙々人がやって来るようになって!」
「えっ、しらすシュークリームってそんなに人気なの!? 俺開発してからはほったらかしのノータッチだから、そう言われると嬉しいけどちょっとビビるわ」
ということは、阿城木入彦(あしろぎいりひこ)は甘党なのだろうか。比鷺自身は甘い物がそんなに好きじゃないけれど、何となく甘い物が好きな人には好感が持てる。悪い人間じゃないような気がするのだ。
「えーじゃあ今度水鵠衆と会ったりとかしてみる? 水鵠衆側がなんて言うか分かんないけど、少なくとも上野國の舞奏社(まいかなずのやしろ)は九条家の人間からの申し出なら断らないと思うよ」
「そんなことが出来るのか?」
「うーん……闇夜衆(くらやみしゅう)とあれだけ仲良くやっていけてるわけだし、それで合同舞奏披(ごうどうまいかなずひらき)にも人が集まったわけだし、説得は出来なくないと思うよ」
勿論、正式に会うとなれば色々と面倒な手順を踏まなければならないだろうが、不可能ではないはずだ。水鵠衆はインターネットで有名になった舞奏衆(まいかなずしゅう)である分、そこまで排他的でもないだろう。そんなことを考えていると、三言がにっこりと笑った。
「なんだか比鷺、少し変わった気がするな」
「えー、何? カリスマ性出てきた? 可愛くなった? どっちにせよ照れるなー」
「前は、あまり家のことを出さなかっただろう。九条家の、っていうのは比鷺にしてはなんだか珍しいからな」
「う、確かに」
意識していなくもないところだったが、改めて外から指摘されると身構えてしまう。だが、比鷺はしばらく悩んでから、意を決したように言った。
「俺はね、そんなにあの家のことも……この身体でやけに高値を付けられてる血のことも好きじゃなかった。今でも好きじゃない。だから、それに呑み込まれないよう、意図的に距離を置いてきた」
自分が九条鵺雲のような人間にならないよう、幼馴染と仲の良い自分のままでいられるよう、比鷺は自分を守り続けてきた。
「でも今は……俺は俺のままでいられるんじゃないかなって。そう思えるようになってきて。多分、舞奏競とか舞奏披で自信が持てるようになってきたからだと思うんだけど。俺は俺、みたいな」
自分が遠ざけてきたものが自分を楽にしてくれた。何だか不思議な気分だけれど、それが本音だ。三言と遠流の隣で誇れる自分でいることが、ちゃんと指針になっている。
「そうなんだな。……うん。俺は、比鷺の変化がとてもいいものだと思うぞ! 比鷺がどう思っていようと、比鷺の家が受け継いできたものは凄いなって思っているからな!」
「そんな元気よく言われると、なんかちょっと照れるんですけどー……うん。でもまあ、ありがと」
「そうだぞ。比鷺の言っていることは正しいんだ」
少し引っかかるところがなくもなかったが、それは割り切れていない比鷺の気持ちの所為だろう。もし比鷺が本当の意味で自信を持てるようになったら、三言の言葉もすんなり受け容れられるだろう。
「……てなわけで、俺はこれからも程々に頑張るから、三言も程々に期待しといてね」
「ああ! 分かったぞ!」
「はーあ、真面目なこと話したらなんかむずむずしてきた。今日はあと俺のイチオシ動画の鑑賞会だけしてようね」
「舞奏の動画か!?」
「あ、いや、そういうわけじゃないんだけど……」
比鷺は違和感の正体を追うこともないまま、スマホの方に向き直った。
*
片付けをして社の外に出ると、既に辺りは暗くなっていた。最近は舞奏社でこなさなければいけない業務が多く、帰りはこうなってしまうことが多い。今日は鵺雲が秘上(ひめがみ)家を訪れる日だ。なるべく早く仕事を済ませ、迎える準備をしなければいけなかったというのに。
明日以降に回す仕事を頭の中で数えながら、佐久夜(さくや)はふと、先日行った温泉のことを反芻した。
あれは、佐久夜の記憶の中でも有数の『楽しい思い出』になった。佐久夜は多分、あの和やかで楽しい思い出のことを忘れないだろう。むしろ、佐久夜はあの温泉でのことをただ一度きりの思い出にはしたくない。出来ることならまた次の機会が欲しいくらいだ。その為にはやはり、御斯葉衆として勝利することが必要だろうか? いや、巡(めぐり)なら案外誘えば乗ってくれるのかもしれない。
今までの佐久夜らしからぬことを考えていたからか、それとも相手が悪かったのか、佐久夜はその男に話しかけられるまで、彼の存在に気づかないままだった。
「こんばんは。夜分遅くもない時間にすみません。秘上佐久夜さんですよね?」
こんな夜によく似合う、奇妙に明るい声だった。声の主は艶やかな長髪に、仕立てのいいジャケットを合わせた、容貌の美しい男だった。月夜に照らされて、彼の瞳が猫のように光っている。佐久夜は彼に見覚えがあった。
「あっ、申し遅れました。私、武蔵國(むさしのくに)闇夜衆で社人(やしろびと)兼覡(げき)をやっている皋所縁(さつきゆかり)と言いまして。いやはや、お初にお目にかかります」
「……貴方は……皋所縁さんではないはずだ。貴方は闇夜衆に所属されている昏見有貴(くらみありたか)さんでしょう。それに、貴方は……社人でもないはずです」
「えっ、この完璧な変装が見破られるなんて……びっくりしちゃいました! 流石は遠江國(とおとうみのくに)舞奏社を背負って立つお方なだけはあります!」
「変装をされているようには見えませんが」
昏見の格好は佐久夜が知っている通りの昏見有貴の外見をしていた。他の人間ならいざ知らず、これほど目立つ容姿の人間を見間違えるはずがない。彼が、まるで悪魔のようににんまりと笑う。
「……私に何のご用ですか」
「やだなあ。私にお手紙をくださったのは貴方の方じゃありませんか。お返事を書くのが面倒だから、直接会いに来ちゃいました。よろしければ内容についてお話しちゃおうかなと思いまして」
「……読んだんですか、あの手紙を」
確かに佐久夜は昏見有貴に手紙を送った。それも──九条鵺雲に依頼されて、だ。鵺雲は手紙の内容を指示し、封筒の裏に『御斯葉衆が負けた場合のみ開封してください』と書いておくように命じた。つまり、御斯葉衆が勝利した今、あの手紙は読まれずに破棄されたはずなの、だが。
佐久夜の疑問に先んじて答えるかのように、昏見が笑った。
「この世は楽園じゃないんですから、注意書きを正しく守ってくれる優しい人間ばかりじゃないって分かるでしょう? みんなが洗濯機で身体を洗わないのは、説明書にそう書いてあるからじゃないですよ。私はあなた方の思惑とか、一昨日の天気くらいどうでもいいんです」
「……そうですか」
どうやら佐久夜は、昏見有貴という人間を見誤っていたようだった。佐久夜の想像する昏見有貴は、こういった類の人間ではなかった。相手のことをわざわざ挑発するような好戦的な態度は、ある意味で巡に似ている。だが、昏見の方がより、相手への悪意が洗練されている。
「まあ、貴方はお喋りをしていて楽しそうなタイプでもありませんからね。手短に用事を済ませてしまいましょう。私が尋ねたいのはただ一つです」
その質問の内容を、佐久夜は容易に予想出来た。果たして、それは当たった。
「私が闇夜衆から抜けて遠江國に下ったら、一体どんな良いことがあったんです?」
下る、という表現は正しくない、と佐久夜は思う。自分が出した手紙には、あくまで武蔵國闇夜衆からの離脱を求めるとだけ書いたはずだ。そんな戦国時代のような言い方はしていない。そもそも、カミに見初められし化身持ちがそんなに簡単に自分達の支配下に置かれるとは思えない。佐久夜は社人として、それがどれだけ特別なものかを説かれて生きてきたのだから。
「それに関するメリットについても、私達は手紙で提示しておいたはずです」
「あれだけじゃ全然納得出来ませんよ。もっと簡単に簡潔に、メリットとデメリットをパワーポイントに纏めて二分以内の動画にしてくださらないと」
正直、どう答えていいものか迷った。何故なら佐久夜は、昏見が求めている回答を用意出来ないからである。鵺雲から昏見にこの奇妙な手紙を──御斯葉衆が舞奏競で負けた場合、昏見有貴に闇夜衆の離脱を打診する内容のものを──送れと言われたから、送った。佐久夜の行動原理はそれ以上でもそれ以下でもない。鵺雲がそう指示したのなら、佐久夜は送る。覡主(げきしゅ)に従うとはそういうことだ。たとえ崖から身を投げろと言われても疑問を持たないのが、本来あるべき姿である。一応、佐久夜の中にはそういう考え方があった。
黙ったままの佐久夜に対し、昏見は一歩も動かなかった。彼は彼で、自分の思うようにするタイプの人間なのだろう。納得がいくまでは佐久夜を解放しないつもりだ。差し当たって佐久夜が何かを言おうとした瞬間、声がした。
「流石に驚いたよ。衝動と共に生きている昏見の血筋であれば、品位と礼節を無視して手紙を読むことも無くはないと思っていたけれど──まさか、ここまでやって来て僕の大切なチームメイトを詰問するだなんて思わなかったな」
振り返ると、そこには九条鵺雲が立っていた。恐らくは、佐久夜がなかなか舞奏社から家に戻ってこないので、様子を見に来たのだろう。昏見の目に微かな驚きの色が滲んだ。
「やあ、初めまして。僕は遠江國御斯葉衆の覡主にして、九条家の長男、九条鵺雲だよ」
「わあ、初めまして! お会い出来て光栄です。九条くんのお兄ちゃんの方ですね! 私、武蔵國闇夜衆・昏見有貴と申します!」
「そうだ。君達は僕の比鷺と戦ったんだったね。相手が比鷺なのだから、負けたことは恥ではないよ」
端から聞いていて、佐久夜はぞっとする気持ちを抑えられなかった。鵺雲がこうして誰かに敵意を向けるのを見るのは初めてだった。七生千慧に散々酷いことを言われていた時でさえ、鵺雲は怒る素振りも見せなかったというのに。昏見に敵意を抱くような理由が何かあるのだろうか? だが、昏見の反応からして、二人は初対面だろう。
「……分かりました。私に手紙を送ってきたのは貴方ですね。とんだシラノ・ド・ベルジュラックです」
「佐久夜くんの鼻はあれほど長くはないけれど。まあ、そうだね。僕が書くと余計なことまで書いてしまいそうだから」
「あら、照れちゃいます。私に対してそんなに情熱的な感情を抱いてくださっていただなんて。赤裸々に告白してくださってよかったんですよ! 私に対してやたら当たりが強いのが好意の裏返しだとしたら、そんな負けヒロインみたいなムーブはやめて正攻法できた方がいいと思います! まずは髪の毛を一本で括るところからですね!」
昏見の表情は全く変わらず、晴れやかなまでの笑顔だ。だが、その声からはこちらに対する警戒と疑念で満ちている。これほど表情と心の内が繋がらない人間も珍しい。その様は──それこそ、九条鵺雲に似ている。
「僕は君と無為に時間を過ごすつもりはないんだ。だから、君の持っている疑問には端的に答えてあげる。御斯葉衆が仮に敗退していた場合、一人ばかり協力してくれる人間が必要になっていたんだ。適する人間が君しかいなかった」
「そんな消去法で選ばれたんですか!? 全くもう、マークシート式回答試験じゃないんですから! 傷ついちゃいます! まあ、確かに所縁くんは所縁くんですし、萬燈先生は萬燈先生ですから、私くらいしかフレックスしてくれなさそうなのは分かりますよ。でも、私だってそんな安い覡じゃないんですからね!」
「安かろうと高かろうと、支払うべきものが定まっているのだからレートは関係が無いでしょう? 君は目的の為なら手段を選ばない」
「私の目的の何がわかります?」
さっきまで明るく流暢に話していた昏見の声のトーンが、一瞬で低くなる。
「正確なことはわからない。君こそイレギュラーだからね。でも、僕は皋くんのことはよく知っているんだ。そうして、皋くんがこうなった瞬間に君がしゃしゃり出てきた。なら、君の目的がそこにあると予想はつく」
「所縁くんのことを知っている? ネットの百科事典に載っている以上のことをご存じなんですか? だったら私、所縁くんクイズ百問出しちゃおっかなー。私はマークシート式なんてぬるいことは言いませんよ。全部完ッ璧に記述式で揃えちゃいます。……貴方、どこで所縁くんのことを?」
「ふふ、それは教えてあげない」
鵺雲が笑うと、昏見が初めて笑顔を浮かべるのをやめた。じっと鵺雲のことを見て、言葉の裏側を探ろうとしている。そんな昏見に対し、鵺雲は続けた。
「だから、いざとなったら君を動かすのは簡単だった。けれど、君はもう必要ない。それだけの話だよ。その選択肢はもう無くなったんだから」
「私のことをタミヤ製RCカーばりに操ろうとしても無駄ですよ。そう簡単にドリフトしたりしないんですからね」
「君の本願は、皋所縁に紐付いている。それは君の大きな枷になる」
鵺雲が言うと、昏見はいよいよ黙った。これ以上何か言えば不利になると踏んだのか、それとも何も言えないほど、鵺雲の言葉が的確だったのだろうか。ということは、鵺雲の言葉はある程度まで昏見の図星を突いているということだ。戦っているわけでもないのに、一転攻勢という言葉が過る。
「それにしても、君と皋くんの舞奏衆に、まさか萬燈先生が加わるとは思わなかったよ。彼のことだから一時の気まぐれだと思ったのに。まだ君達に飽きていないだけなのか……それとも、叶えたい願いが生まれて、抜けることが選択肢に入らなくなったのか。萬燈先生なら……後者かな?」
「知ったようなことを言う割に、萬燈先生の解像度が低いですね。萬燈先生なら欲しいものはご自分の力で手に入れるに決まっているじゃありませんか」
「うん、僕もそう思うよ。人間に叶えられる願いならね。萬燈先生なら、きっと僕の予想通りのことを願う」
まるで予言者のような口ぶりで、鵺雲が言う。佐久夜には鵺雲が言っていることの意味がまるで分からない。彼が萬燈夜帳の本願のことも、昏見有貴の目的も、まるで見てきたかのように正確に話していることしか理解出来ない。
「……萬燈先生が何を願っていると?」
「僕と彼はよく似ているからね。彼が舞奏に興味を持ったなら、一度は考えるはずだ。永遠に続く舞奏競を。千年に研鑽された至高の芸術を。合っているかな?」
鵺雲が言う。それもまた、まるで見てきたかのような自信に満ちた口調だった。
だが、昏見は少しだけ驚きの表情を見せた後、思いもよらない反応を見せた。昏見は──気の利いたジョークを聞いた時のように、笑い出したのだ。今度は鵺雲の方が訝る番だった。
「何か僕がおかしいことを言ったかな?」
「いえいえ、ジョークとしては全然冴えてませんよ。問題ありません。私が笑ったのは、安心と侮りの二重奏です。よかった。貴方は全部を見通しているわけじゃなく、ちょっとばかりの鋭さで探偵ごっこをなさっているだけなんですね。はー、これで安心です。その根拠がどこにあるのかは気になるところですが、先に解決編(本番)からいきましょう」
「どういう意味か分からないのだけど」
「確かに萬燈先生と貴方には似たところがあったのかもしれません。いえ、その似たところは今でも確かに存在している気がします。けれど、人間の変化って不可逆なんですよ。永遠に続く夢の舞台なんて、もう萬燈先生のトレンドじゃないんです。萬燈先生と目指せる唯一の目標だったかもしれないのに、彼はもう一夜の夢を最高にすることだけを求めています」
鵺雲が驚きの表情を浮かべる。それは、今までに見たことのない種類のもので、佐久夜の胸に微かな嫉妬の念が起こるほどだった。
「あの萬燈先生が? 彼が変わるなんて信じられない」
「ええ。ユニークなことに、萬燈先生の考えを変えたのは、恐らく貴方の弟さんですよ。貴方を挫くのが九条比鷺くんだなんて、なんか運命的ですよね」
昏見が心底楽しそうに言う。
「僕は挫かれたとも思っていないよ。むしろ、やっぱりひーちゃんは凄いなって。ひーちゃんが萬燈先生と仲良くなるのは嬉しいな。同じ血が流れているから。でも……そうなんだ。そう違いが出るんだね」
「まるで見てきたように予想を立てるのはどうしてですか? もしかして、鵺雲さんってば未来人だったり、平行世界の方だったり、タイムリーパーだったりします?」
冗談めかした口調で昏見が言う。だが、降って沸いたSFめいた発言に対し、鵺雲は奇妙な表情を浮かべた。佐久夜の感じ方が正しいとすれば──鵺雲もまた、その発言を楽しんでいるようだった。ややあって、鵺雲が続けた。
「そうだよ。僕は未来からやってきたんだ。そうして、これから起こることを知った状態で今を生きている」
「そうなんですね! びっくりです。未来が毎秒今になっていることを考えれば、私も未来人と言えますけどね!」
「だから、これから君が何で挫折するかも知っている」
鵺雲の発言に、昏見が息継ぎのように口を噤んだ。ややあって、彼が笑みを浮かべながら言った。
「……奇遇ですね。実は私はタイムリーパーで、貴方と話すのも既に九百九十六回目なんです。だから、私は貴方がこれから挫折することを知ってますよ。私は毎回貴方を助けようとしているんですが、どうしても歴史の修正力に負けてしまいまして」
「わかっているよ。僕には僕の発言を証明する手立てがない。僕は君のことが嫌いだから、君の精神を攻撃したくて出任せを言っているのかもしれない。でも、僕はこのままだと君の目的が達成されないことを知っている。とはいえ、僕らが勝った以上、僕が別の道を君に示すことはない」
「ご忠告痛み入ります。平行世界の私に会ったら教えておきます。やっぱりこれからはバーよりも探偵事務所をやるべきですって!」
そう言って、昏見は一礼した。話はこれで終わり、ということだろうか。そう思った瞬間、昏見が口を開いた。
「私は誰が何を言おうと、自分の思うままに最後まで成し遂げますよ。予告をしたのに奪えなければ名折れですから」
昏見はそう言うと、目の前から消えてしまった。消えてしまった、という表現が正しいのかはわからないが、気づけばそこからいなくなっていた。まるで、今話していた相手は何かの幻だったかのようだ。鵺雲は小さく溜息を吐くと、ようやく佐久夜の方を見た。
「ごめんね。困ったことに巻き込んでしまって」
「いえ……。むしろ、こんなことになってしまったのは俺の落ち度です」
「ふふ、佐久夜くんは優しいね。でも、いい機会だったかもしれない。彼のことを避けていたお陰で、今の今まで言葉を交わすことすらなかったものだから。避けられないことだった」
「あの方は……」
「やっぱり僕とは合わなそうだね。でも、君に似ているところもあるよ。君が巡くんの為に魂を擲てる程囚われているように、彼もまたたった一人の人間に囚われている」
「なら、幸運な人間と言えるかもしれません」
佐久夜が言うと、鵺雲はようやく普段通りの笑顔を見せた。
「……一つ、お尋ねしても構いませんか」
「うん? どうしたの?」
「意図は分からずとも、昏見有貴に手紙を出した意味は分かりました。なら、もう一つは?」
あの時、鵺雲が佐久夜に頼んだことは二つあった。一つがこれだ。なら、もう一つにはどんな意味があったのか?
すると、鵺雲は涼やかに言った。
「それは、これからだね。三言くんがもう少し、繋いでくれたら」
著:斜線堂有紀
この物語はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。
※当ブロマガの内容、テキスト、画像等の無断転載を固く禁じます。
※Unauthorized copying and replication of the contents of this blog, text and images are strictly prohibited.
©神神化身/ⅡⅤ




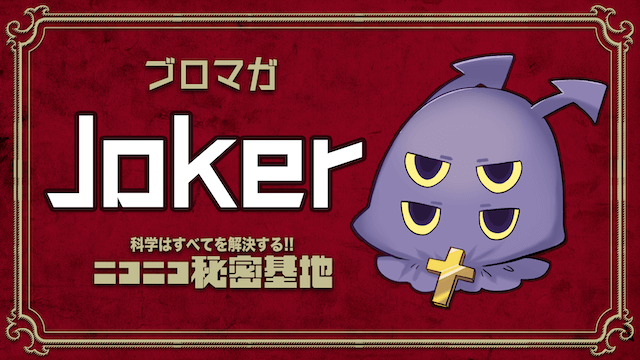

コメント
コメントを書く