小説『神神化身』第二部
第三十話
七生千慧(ななみちさと)を中央に据え、阿城木(あしろぎ)と去記(いぬき)は長刀(なぎなた)を構える。廃神社で舞っていた時とは違う立ち位置だ。ある意味で、阿城木が想定している本来の『水鵠衆(みずまとしゅう)』の舞奏(まいかなず)のフォーメーションだった。
七生を中心とした舞奏を奉じる、という方針は、三人での稽古を始めて早々に決まったものだった。
「え、僕が中心……? というか、物理的な中心ってだけじゃなくて、本当に舞奏の構成的にも僕がメインなの?」
「ああ。その方がいいだろ」
「我もそう思うぞ。なんてったって、我らのリーダーは千慧なのだからな」
「でも、別に僕……特別舞奏が上手いってわけじゃないし」
七生がもごもごと言葉を濁らせる。
確かに、七生の舞奏はそう上手いわけではない。実力でいったら阿城木と同等だろう。何となく、七生の自信の根源はその胸にある化身(けしん)だけで、実力の面では不安が残るように見える。もし華やかさを追求するのなら、去記の方をメインに据えた方がいいはずだ。
だが、阿城木はそうしなかった。
「お前ちっこいんだから真ん中いないと埋もれるぞ」
「は!? ちょっ……そういうこと!? 馬鹿にしないでくれる!? 去記はともかくとして、阿城木と僕はそんなに身長変わんないでしょ!」
「それは無理があるだろ」
冷静に返しながらじっと見つめると、七生は不安げに目を伏せた。
「僕が中心の舞奏なんて、やったことないし」
「俺だってお前が中心の舞奏なんかやったことねーよ。全員初めてだろ」
「そういうことじゃなくて……。……僕の所為で、水鵠衆の舞奏が駄目だって思われるのは嫌だ」
「そうはならぬよ」
去記がきっぱりと言う。
「我は全てを見通す九尾の狐じゃ。我は千慧を中心にした舞奏が、きっと多くの観囃子(みはやし)を喜ばせると思っておる。千慧はかわいくて賢いが、千年を生きた狐ほど先見の明に長けているわけではない。ここは一つ、我を信じるといい」
「去記……。……分かった。僕も流石に、千年は生きてないしね」
「そうであろう! 我には一〇二四年の経験があるのだ!」
「あー……まあ、そうだな。だから、信じとけよ」
「む。こういう時だけ入彦(いりひこ)が我の設定に優しい。普段からそうやって盛り立ててほしいぞ」
「お前、今設定って言ったじゃねーか」
阿城木が呆れたように言うと、去記がからからと楽しそうに笑った。それに釣られて、七生も表情を解す。
こうして、水鵠衆の舞奏が生まれたのだ。
斜め前に立つ七生は、手製の狭い舞台の上で、集まってくれた観囃子のことだけを見ている。その背はまっすぐと伸びていて、普段より少し大きく見えるくらいだ。これから、自分と去記はこのリーダーを支える舞をする。そして、観囃子の心を得る。
七生が長刀を軽く振り下ろし、舞奏が始まった。
七生にはこの舞台を最大限自由に使って舞奏を奉じていいと言っている。息を合わせるのは自分と去記だけでいい。七生が最大限に映えるよう、自分達だけは寸分違わず呼吸を合わせる。
この方式にしたのは、七生の舞奏に奇妙な癖がついていたからだった。
どこで舞奏を覚えたのか知らないが、彼の舞奏にはそう簡単には拭い去れない過去の面影がある。それを無理矢理矯正して新しく水鵠衆の舞奏に合わせようとしたって、どうしたって不自然になるだろう。
なら、七生の舞奏に自分達が合わせればいい。阿城木も去記も、たった一人で舞ってきたのだ。七生に合わせたところで、歩んできた道、舞奏の中に宿してきた我はそう簡単に消せやしない。七生を軸に、それらを少しずつ混ぜ合わせ、波立たせ、水鵠衆の舞奏にすればいい。個性は後からついてくる。今、この瞬間に。
七生のことを見つめる観囃子は、彼だけを見ているようでそうではない。波に境があるものか。自分達は決して混ざり合わず、海の果てにいる。だが、立てる波は一つだ。それを束ねるのが七生だった。
阿城木が長刀を軽やかに回転させると、去記が悪戯でも思いついたような顔をして、長刀を放す。落としてしまうのではないか、と一瞬危ぶんだが、次の瞬間にはもう既に長刀は去記の手の中にあった。まるで化かされたみたいだ。観囃子だって同じ感想を覚えただろう。楽しそうに笑う九尾の狐に絆(ほだ)されて、怒りの一つも覚えられない。
一見野放図に見えるこの動きも、七生が器用に束ねてくれる。中心であり、バランサーでもある。七生は他人の動きをよく見ているのだ。こうして観囃子にだけ視線を向けていても、なお感じ取っている。小さな背が跳ね、軽やかに着地する。この背に付いていけば、安心だと心の奥底で思う。
阿城木が七生を中心に据えたかったのは、そして去記がそれに一、二も無く賛成したのは、先のような技術的な話だけじゃない。
水鵠衆が、七生千慧によって引き合わされた舞奏衆(まいかなずしゅう)だからだ。七生が自分達を覡(げき)にしてくれた。
だから、水鵠衆の舞奏は七生のものなのだ。自分達は、居場所を与えてくれた七生に、舞台の上で返そう。きっと一生かかっても返せないものを、舞に載せよう。
カミに嫌われるのも無理はない。自分も去記も、突き詰めれば七生千慧の為に舞っているのだ。上等だ、と阿城木は思う。何しろ、自分達を掬い上げてくれたのは、カミではなく七生だったのだから。
この景色に出会わせてくれたのは、カミではなかった。
曲が終わった瞬間、拍手の圧に押された。
ノノウとして舞奏披(まいかなずひらき)に出た時とは比べものにならない程の熱が、この小さな会場に集まっている。一番はしゃいでいるのが遠目に見える自分の母親であることは気恥ずかしかったが、それでも集まった一二〇人余りが惜しみなく拍手を送ってくれるのは嬉しかった。
最前列でカメラを向けている去記の古参ファンは、涙を流しながら舞台を観ていた。思わず声を掛けてしまう。
「……大丈夫か? それ、拭わなくていいのかよ」
「いぬきちの晴れ舞台だから! ちゃんと撮らないと! あっ、ここちゃんと編集してアップするからね! だから、拭ってる暇とか無いの! ちゃんと……撮らなきゃ!」
「我の為にありがとうな。それ、コンコン」
「あーっ、そのコンコンはGIFにするね!」
何か良くわからないが、楽しそうなのは何よりだ。それに、こうして記録して広めてもらえるのもありがたい。水鵠衆の看板を下ろした今、どれだけ反響があるかは知らないが、一人でも多くの人間に、自分達がここにいることを教えたい。
息を整えながら次の準備をしていると、門の近くに集団が見えた。
上野國舞奏社(こうずけのくにまいかなずのやしろ)に所属する、ノノウ達だ。舞奏社でやっていた舞奏披が終わったのだろう。ぞろぞろと阿城木家の敷地内にやって来ている。そちらの観囃子の入りや、彼らが舞奏を披露していた時の気持ちを想像し、一瞬だけ胸の痛みを覚える。だが、彼らが沈鬱な面持ちでありながら、それでもこの場に来てくれたことに、敬意を表した。
彼らの内の一人と阿城木の目が合う。その瞬間、叫んでいた。
「上がってこい! 俺達と競おうぜ!」
ノノウ達がハッとした顔をする。それに対し、阿城木は大きく頷いた。
阿城木はノノウである彼らのことを知っている。化身が無いが故に覡になれず、いつかの日を夢に見ながら稽古を重ねてきた実力者達だ。舞奏披では相手無きまま、三人での舞を披露してきた。阿城木はその一部であった時があった。
彼らは戦えるのだ。
ノノウ達の顔に戸惑いが過る。その不安を先に掬い上げるべく、阿城木は続けた。
「この舞台に上がったら、上野國舞奏社を追放されるかもな! けどな! それが何だってんだ? ここには舞台も観囃子もいる! 倒すべき俺らもいる! 高月(たかつき)! 御橋(みはし)! 廣末(ひろすえ)! お前ら、どんな覡にも負けないって言ってただろ!」
彼らの名前を呼んで発破を掛ける。阿城木は彼らを上野國舞奏社から追放させてしまうかもしれない。だが、構っていられなかった。彼らはここで舞いたいと思っている。その目が、競いたいと言っている。
高月がゆっくり前に進み出て、舞台に上がってきた。その後に、残る二人も続く。去記が口を開いた。
「ほほう、なかなか良い面構えをしておる。我らも主らも共にはぐれ者よ。なればこそ、純粋に競おうではないか。ここが我らの舞奏競(まいかなずくらべ)よ。ただ真に観囃子を魅了する舞を奉じる、勝負の場よ」
去記の言う通りだ。ここが舞奏競の本番で、舞台だ。誰からも認められずとも、自分達は舞奏衆で、競り合っている。歓心を得るために戦っている。負けたくない、と心底思った。目の前の高月達にも、そしてこの世界にいる全ての舞奏衆にも。
阿城木は、自分達に向けられたカメラに向き直る。そして言った。
「化身持ちだかなんだか知らねえけどな! 俺らの方がずっと歓心を集められるかもしんねーぞ! 悔しかったらかかってこいよ! 誰でも相手してやる!」
「我らは誰も拒まぬ! この波にて、果てまで我らの名を轟かせよう!」
「我ら水鵠衆。カミの加護受けぬはぐれ者。であろうとも、それだからこそ、僕達は大祝宴に辿り着く!」
合わせて、二人も叫ぶ。そして、世界の全てに挑みかかるように、長刀を掲げた。
それから一ヶ月が経った。
七生千慧は、芸術的なバランスでクラッカーにあんこと生クリームを載せている。突然クラッカーパーティーがしたい、と言い出したので、急遽こうして用意をしてやったというわけだ。あまりの甲斐甲斐しさに涙が出そうになる。その隣では、去記もクラッカーに生クリームとさくらんぼをトッピングして楽しんでいた。
「平和だの。お天気も良いし、あんこも果物も生クリームも美味しいし」
「ねえー。平和だね。こうしてクラッカーにあんこを載せることだけに集中出来る日は良い日だよ」
「なあ七生。お前、それもうクラッカーに載せないで、そのままあんこと生クリーム飲んだ方が早いだろ」
「それじゃあクラッカーパーティーにならないでしょ!」
七生がそう言いながら、あんこで出来た入道雲を口の中に放り込む。じっと目を凝らしたが、クラッカーの姿がよく見えなかった。意味あるんだろうか、あれ。
「……確かに平和ではあるよな。何かトラブルが起きたってわけでもねーし」
「平和が一番であるぞ。我は日常系の九尾の狐であるからな」
「日常系の九尾の狐って何だよ……」
「日常系の九尾の狐はぬくぬく人の子と戯れて、コンコン言ってかわいいって言われながら、たまにフィギュアになったりぬいぐるみになったりするのだ。我、まんがで読んだ」
「そんな具体的な展開プランのある九尾の狐があるかよ」
阿城木家の敷地内で催された私的な舞奏披は大成功を収めた。
観囃子達は惜しみない拍手をこちらに送ってくれたし、上野國舞奏社に所属するノノウ達は全力で戦ってくれた。結果は自分達が競り勝っていたような気がするが、負けたノノウ達にも達成感があったらしく、最後は共に挨拶をした。他にも、別の三人で組んでいるノノウ達や、今年ノノウになったばかりの舞い手なども舞台に上がり、共に競い合って歓心を集めた。
去記のファン達が拡散した動画の広がりは凄まじく、上野國の外でも反響があるらしい。
水鵠衆という名前が大っぴらに出していないからか、ノノウの集団だの、かつて存在した伝説の舞奏衆だの、舞奏サークルの発表だの、好き勝手に勘違いされているようだが、何にせよ関心を持たれていることは嬉しかった。去記のお狐ポーズや、堂々と覡主を張る七生の姿、それに啖呵を切る自分の姿なんかが広まっていくのは妙な気分だったが、悪くはなかった。
少なくとも、自分達がここにいたことを忘れないでいてもらえるのはありがたかった。あの日の舞台は、阿城木にとってかけがえのないものだ。あの輝きを、自分以外の心にも留めていてほしい。
だが、特に上野國舞奏社からの働きかけは無かった。お叱りの言葉もその逆もまるで無い。全くの音沙汰無しだ。
あの日舞台に上がったノノウ達も揃ってお咎め無しなのはよかったが、あまりにも反応が薄すぎやしないだろうか、と阿城木は思う。横瀬(よこせ)なんかは始まる直前にわざわざ当てこすりにやって来たというのに、全くの無反応である。
自宅の敷地内で行った私的な行為なのだから、何かを言われる方がおかしい。そのことは分かっている。分かってはいるけれども、釈然としない。もっとこう……何かが、状況が変わるような何かがあっても良かったのではないだろうか。
「なぁんかもっとこうさー! 状況が変わるようなことがあっても良かったんじゃないの!? まさかこれほどまでに何も無いとは思わなかったよ!」
「うわ、俺の考えてることにシンクロすんなよ。パクんな」
「はー? 阿城木の考えてることなんか分かんないんですけど! そういう変な言いがかりやめてよね!」
七生は憤懣(ふんまん)やる方ないといった様子で、あんこを呑み込む作業に勤しんでいる。そんなに口の中を甘くしたまま怒れる七生のことを、少しだけ尊敬した。
「やっぱりお前が堂々と水鵠衆って名乗ったのがいけなかったんじゃねーの? 俺はなんとかぼかしたりしてたけどさ、お前がはっきり言ったわけじゃん。それが不興を買ったんじゃ」
「へ!? え!? ぼ、僕の所為なの!?」
「やっぱり水鵠衆って言うのはな……」
「い、去記ぃ……」
「これ入彦。そんなことを言ったら千慧が可哀想ではないか。めっ! であるぞ」
去記が珍しく唇を尖らせて叱ってくる。そして、そのまま続けた。
「まあ、何も無さ過ぎるといえば無さ過ぎるのだが……冷静に考えれば、我らのやったことって、我の神社でみなに舞を見せていたのの豪華ばーじょんってだけで、特に舞奏社の人達に喜ばれるものではないのよな」
「おっ前、いつもふわふわコンコンしてるくせにこういう時だけ正論言うなよ」
「えっ、我もっとふわコンしてた方がいい?」
「去記はふわコンしててもしてなくてもいいよ!」
七生がそうフォローして、二人は楽しそうにきゃっきゃと笑い始めた。……平和ではある。本当に。
あれからも三人で稽古は重ねているし、小規模ながら人前で披露したりもしている。だが、上野國舞奏社が自分達を水鵠衆として認めてくれる気配は無い。上野國舞奏社に所属しているノノウ達と比べても、遜色の無い舞奏は披露出来たはずなのだが、全くお褒めの言葉が出ない。
おまけに阿城木は未だに──正式に言い渡されてはいないが──上野國舞奏社を出入り禁止になっている風情がある。舞奏社に正面切って楯突いたのだから当然だが、そのままなのだなあとちょっと思ってしまう。
自分達はあの日世界を変えた。阿城木にはその手応えがある。けれど、その世界の中に、上野國舞奏社は入っていなかったと、そういうオチだったらしい。
「このままだとやはり駄目かの。今度は舞台じゃなく、舞奏社を作るべきかもしれぬ」
「うーん……なんか、こう……まだ猶予はあるし、様子を見ようと思ってたけど、正直、なんかしないとまずいよね……」
七生と去記がぼそぼそと作戦会議をしている。明らかに、こんなはずじゃなかったと言いたげな感じだ。こんなはずじゃなかったのかもしれないが、あれくらいしか出来ず、されど達成感があるのだから始末に負えない。そんなことを考えながらクラッカーにクリームチーズを載せていると、インターホンが鳴った。
「あら、今回はあなたがお出迎えというわけね。いやはや、席を立たせてしまって申し訳ないわ」
玄関口に立っていたのは、きっちりとした和装に洒落た中折れ帽子を被った横瀬貞(さだ)千代(ちよ)だった。呆気にとられる阿城木の横を「お邪魔しますよ」の言葉と共に通り過ぎていく。向かう先は、あの朝にベビーカステラを食べた居間だ。
「う……横瀬……さん」
ポーカーフェイスがまるでなっていない七生が、嫌そうな様子を隠そうともせずに言う。横瀬は横瀬で「はい。上野國舞奏社総掌(そうしょう)、横瀬貞千代ですよ」と真顔で返す。このやり取りが既に恐ろしい。
「い、一体何をしに来たのだ……? クラッカーなら、まだあるけども……」
おずおずとクラッカーを差し出す去記に対し、横瀬が静かに首を振る。
「ご相伴に与りたいのは山々ですけれど、今日は業務で来ましたもので」
「業務……?」
横瀬は頷くと、中折れ帽を外して手に持った。そして、朗々とした声で言う。
「上野國舞奏社総掌の責において、七生千慧、阿城木入彦、拝島(はいじま)去記からなる舞奏衆を、上野國所属舞奏衆・水鵠衆と正式に認めます」
場が水を打ったように静まり返った。まるで、物音一つでも立てれば、今の言葉が無かったことになってしまうかのようだ。阿城木ですら息を詰めてしまっている。
どのくらいそうしていただろうか。ようやく、七生が口を開いた。
「え、えええ、な、なんで今!? 僕らの舞奏と頑張りを認めて心変わりしてくれるならもっと早い時期でしょ!? というか舞奏披の直後じゃないの!?」
「七生、おい七生、言いたいことは分かるが素直過ぎんだろ」
「ほ、本当に認めてくれるの……? 横瀬さん、我達のことそんなに好きじゃないでしょ……?」
去記が恐る恐る横瀬に尋ねる。右目には今日も化身を覆い隠すコンタクトレンズが嵌まっていた。
「私がどうこうという話じゃありませんからね」
横瀬は困ったように肩を竦めてみせた。……随分意味ありげな言い方だ。舞奏社総掌である横瀬の気が変わったのでなければ、一体何があって自分達は水鵠衆として認められるに至ったのだろう?
「横瀬さんがどうこうって話じゃないなら……どういうことだよ。まさかお偉いさんがどうとか? カミからのお告げか? 生憎と、俺にはまだ化身が出てねーけど」
「理由を説明する義務はありませんのでね。お生憎と」
横瀬はさらりとそう言って流す。疑問は尽きなかったが、それに答えるつもりは無さそうだ。
ややあって、七生が口を開く。
「……じゃあ、僕達は正式に上野國水鵠衆を名乗り、上野國舞奏社の後ろ盾を以て舞奏競に出るけれど……それでいいの?」
「ええ、勿論。貴方達は正式な舞奏衆なのですから。私がどうこう言う筋合いはありませんとも」
横瀬はにっこりと笑った。にっこり、と形容したものの、表情が完璧に作られているというだけで、全く好意の感じられない笑みではあった。
それでも、去記はみるみる内に目を輝かせ、頬を赤くしながら七生に抱きついた。
「やったあ! 我らは水鵠衆として舞奏が出来るのだな! これで、共に舞うことが出来るのだな!」
「うん、そうだよ去記! これからも……ちゃんと……」
七生の声が段々と小さくなっていく。心のどこかでは信じられない気持ちがあるのだろうか。阿城木だって、未だに何が起きたのか理解出来ない。だが、横瀬は話はこれで済んだと言わんばかりの顔をして、さっさと結論に向かう。
「これからは上野國舞奏社の稽古場を自由に使って構いませんし、社人(やしろびと)の協力を得ることも可能です。勿論、舞奏競の手配も致しましょう。健闘をお祈り申し上げます」
「舞奏競……」
「この件に関しては上野國舞奏社総掌である私がちゃんと伝えなければということで、僭越ながら伝書鳩の役割を担わせて頂きました。これにて失礼」
そう言って、横瀬がさっさと立ち上がった。帽子を被り、こちらを振り返りもせずに出ていってしまう。阿城木は慌ててその背を追った。
「待ってください」
横瀬がゆっくりと振り返る。
「まだ何か?」
「まだ何かって……話しに来たのはそっちじゃないですか……」
「今の貴方は正式な水鵠衆の一員ですからね。覡としての立場から社人総掌に対する言葉であれば何を言っても結構。さて?」
横瀬はしらっとした顔つきのまま、鷹揚に言う。滲み出ている余裕に、敵わないな、と一瞬だけ思ってしまった。
「……未だに俺のことは認めていないはずですよね。個人的にどう思ってるか教えてください」
横瀬が答えてくれるだろう言い方で、そう尋ねる。果たして、横瀬はあっさりと頷いた。
「個人的には全くですね。いやはや、分かりきったことをこうして尋ねられるのも様式美的で面白いこと」
「いやー……ブレないわな、横瀬さん」
「あなたがノノウだった時はそれなりに良好な関係を築いていましたからね、私の複雑な胸の内もお察しなさいな。まあ、こうして一対一で話すことはありませんでしたけれど」
そう言って、横瀬は一度言葉を切った。そして、改めて言う。
「あなたと同程度の舞奏を奉じられるノノウなら、いくらでも見てきました。阿城木入彦、あなたの舞奏は並外れて素晴らしいものではない」
「……はい」
その点については、阿城木も納得出来る。阿城木の舞奏は上手い。だが、何者にもましてと形容されるほど、化身の有無を実力で覆せるほどではない。重ねた努力と熱意だけが支えとなっている、実直な舞奏だ。
「あなた一人を認めることは、上野國舞奏社にかつて存在した才あるノノウ達を踏み躙ること、ひいては上野國舞奏社の重ねてきた歴史を軽んじることでは?」
横瀬はまっすぐな目で阿城木のことを見つめていた。その揺るぎなさには、上野國舞奏社が重ねてきた年月がそのまま載っている。だからこそ、阿城木もそのまま応じた。
「軽んじてるかもしれない。けど、もうこんなちっぽけな壁の前で棒立ちしてられるかよ」
今日ここで舞奏社に承認されたからじゃない。七生千慧があそこで自分を覡にしてくれたから、阿城木はもう鏡の前で項垂れたりしない。
「そうですか。いずれにせよ、もう私がどうこう言える話でもありませんからね」
特に阿城木の言葉が響いた様子も無く、横瀬が言った。そして、沈黙が過る。阿城木が言いたかったことも粗方言い終えてしまった。横瀬は何も変わらない。たとえ水鵠衆が舞奏競で結果を残したとしても、依然として化身を持たない阿城木入彦や、呪われし拝島去記を本心から認めはしないだろう。
なら、別にそれで構わない。
阿城木は会釈をし、きっと一生相容れないだろう上野國舞奏社総掌に背を向ける。
「七生千慧という、水鵠衆の覡主(げきしゅ)ですけれどね」
背を向けたのを見計らったかのように、横瀬が言った。振り返るな、と言外に言われているような気がして、阿城木はそちらを向けないまま言葉を受ける。
「彼は確かにれっきとした化身持ちなのでしょう。これでも私は社人として長いこと勤め上げてきましたからね。化身持ちかそうでないかは分かります」
「……そりゃ凄い。俺はわざわざ見せてもらいましたんで」
「不意に現れた化身持ちにしては、彼の舞奏は不自然なところが多すぎますね。こちらもそれなりに見てきましたが、見るからにおかしい。呪われた拝島よりも、よっぽど化生です」
背中を冷たい汗が流れた。仲間を侮辱されているのか、と反射的に思ったが、そういうことじゃないだろう。横瀬はこちらを不快にさせようとは思っていない。むしろその逆だ。全く以て気に食わないだろうに、それでも敢えて忠告してやろうという慈悲の気持ちがそこにあった。
「よほど彼のことを信頼しているご様子ですけれど、おすすめはしませんね。舞奏という世界において、蛮勇が評価された試しは無い。いざという時はお逃げなさいな」
逃げる。七生から逃げる。自分が共に戦うべき相手である七生の名前と、逃げるという単語が結びつかない。第一、あの小さな七生をどう警戒して逃げればいいというのか。化生なんか大仰過ぎる。あんなものは精々ネズミがいいところだ。
なのに、そう笑い飛ばせない自分もいる。
七生千慧のことは心から信頼している。──あいつは悪い人間じゃない。七生は阿城木や去記のことをわざと害したりはしない。水鵠衆のことを大切に思ってくれている。自分達の居場所を出来る限り守ろうとしてくれている。
だが、七生の意思とは反するところに『何か』があるんだとしたら?
七生は来歴を語らない。何が目的なのかも言わない。たまに見せる物憂げな表情や、何かに追われているような態度は? 体温の無い身体。ここではない場所で稽古をつけられたのだろう舞奏。
僕なんか存在しないという言葉。
あいつは──いや、あれは、一体何なのだ?
七生千慧が、阿城木の想像を絶する破滅の一端だとしたら?
「……あれが化生なわけないですよ」
全ての不安を覆い隠し、阿城木はそう答えた。たとえ化生だとして、水鵠衆のリーダーは七生以外にいない。阿城木は絶対に七生を追い出したりしない。
横瀬はもう何も言わず、砂利を鳴らす草履の足音だけが辺りに響く。
家の中では、去記と七生が待っているはずだ。そのことが分かっているのに、阿城木はしばらくその場に立ち尽くしていた。
著:斜線堂有紀
この物語はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。
※当ブロマガの内容、テキスト、画像等の無断転載を固く禁じます。
※Unauthorized copying and replication of the contents of this blog, text and images are strictly prohibited.
©神神化身/ⅡⅤ





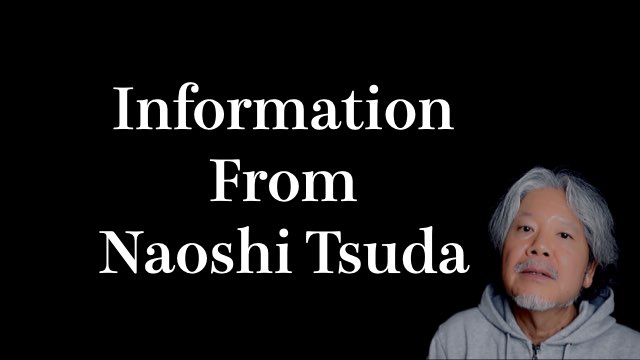
コメント
コメントを書く