
 弱いなら弱いままで。
弱いなら弱いままで。
【無料記事】同人誌『戦場感覚』第七章「ポルックス――タナトスのエロス」。(7107文字)

1.ゴシック。
いつの時代も変わらない。燦々と輝く太陽を忌み、たそがれと夜を快とする人々がある。かれらは光の世界にあって異端であり、しばしば世間から後ろ指さされる。しかし、かれらにしてみれば世間や大衆といった大多数こそ最も嫌悪すべき存在にほかならない。
猥雑な生命にあふれたこの世界に背を向け、どこかにあるかもしれない理想世界を夢見る暗い浪漫の使徒たち。タナトスのエロスに心ひかれてやまぬかれら闇の住人たちの文化を称し、ゴシック(GOTHIC)と呼ぶ。
そもそもゴシック文化とは「ゴート族ふうの」を意味する形容詞である。名刺ではゴス(GOTH)。ゴート族とは4世紀にローマ帝国へ侵略してきたゲルマン人部族のひとつ。そのなかでも最も野蛮かつ残忍であったという。
そして千年の時を経てルネサンス時代、中世的なものを否定するルネサンス人たちは中世の建築様式を「野蛮」と蔑んだ。こうして、今日のゴシックのイメージは形づくられた。暗黒、野蛮、残酷、中世、過剰、恐怖――ゴシックカルチャーの印象はそんな暗い言葉で表される。
高原英理『ゴシックハート』によると、ゴシックとは、ロックがそうであるようなひとつのスピリットである。それは具体的には血、疵、薔薇、骸骨、十字架、少女、吸血鬼、眼帯、義肢、繃帯、人形、天使、悪魔、魔法、畸形、廃墟、墓地、鎖といったものを愛でる。
しかし、このようなアイテムを好んで身につけたり、髑髏がらのTシャツを着て歩くことがゴスなのではない。ゴスとはあくまで生き方であり、無形の精神なのだ。だから一切このような意匠に興味がなくとも、ゴスの暗黒精神を持つものはゴシック者である。
それでは、そのゴスが戦場感覚とどのようにかかわるのか。いうまでもない。戦場と死は兄弟の関係にあるのだから、戦場感覚とゴスもまたきわめて近しい間柄といえる。
わたしは、戦場感覚者のグランドテーマとは「戦場である世界でいかに生き抜くか」であると書いた。しかし、「世界は戦場である」というグランドルールからは、自然、負けても良い、死んでもかまわないというもうひとつの価値も導きだされるはずである。
あくまで勝ち抜き、生き抜くことを前提とした価値がエロスの価値であるとすれば、それはいわばタナトスの価値だといえよう。死に惹かれ闇に親しむタナトスの価値――それが、ゴスなのだ。
ゴスはエロスという覇権価値に対する対抗価値である。光あふれる進歩と発展の時代、それはどこまでも異端であるに留まる。しかし、世界が不安にゆらぎ、あらゆる「正しさ」が疑わしく思えてくる時代、ゴスは、広く浸透する。
見よ。現在、ゴスはさまざまなかたちで文化に影響を与えているではないか。ひとつは音楽。特にロックミュージックにゴスは入り込んでいる。バウハウスとジョイ・ディヴィジョン、日本ではX JAPANとマリスミゼルあたりが代表的なゴシックロックアーティストであるようだ。
X JAPANを初めとする一群のアーティストたちが「ヴィジュアル系」として、人気を集めたことはご存知のとおり。かれらは特に若い女性を中心に支持を集めた。
ひとつは文学。前章で紹介したように、乙一は『GOTH』というそのものずばりの作品を物しているが、それ以外にもゴスの作家は少なくない。
澁澤龍彦と三島由紀夫というゴスの英雄たちが落命して数十年、厳密にゴスな世界観を提示している作家は多くないかもしれないが、広くタナトスの空気をただよわせる作家ということなら、たとえば京極夏彦もそんな作家のひとりに数えられるだろう。その暗黒、その残虐は、博覧強記の衒学とともに、ゴシック者の心を強く惹きつける。
またひとつはファッション。あるいはゴスの正統ではないかもしれないが、ゴシックロリータと呼ばれるファッションは、いま、若い女性を中心にわりあい一般的なものになっている。とにかく、ゴスはあらゆる文化シーンに浸透しているのだ。
もっとも、ゴスはやはりどこまで行ってもマイナーカルチャーではある。この世で最も強力な覇権価値である「生」を正面から否定するその思想が、大衆の支持を得られるはずもない。
否。それどころか、ゴスはこの世界そのものを否定する。ゴスはこの世界を退屈で醜悪な牢獄だとみなすのだ。その意味で、第六駅で語った「ひとでなし」の物語と、ゴスは深い関係にある。
そしてまた、ゴスは猟奇とは似て非なるものがある。ひとむかし前、『羊たちの沈黙』を初めとするサイコサスペンスが流行したことがあった。そこではしばしば凄惨きわまりない猟奇趣味が描かれたものだった。そういった趣味と、ゴスはたしかにどこかでシンクロしている。
また、スプラッターパンクなどといわれる小説もある。そこではゾンビやらヴァンパイアやら、さまざまなモンスターが凄惨きわまりない物語を展開している。これも、ゴスと全く無縁だとはいえない。
しかし、それらはやはり、ゴスそのものではない。こういった作品群とゴスを分かつもの、いうまでもなく、それは「洗練された美意識」である。ゴスはどこまでも「美」を愛するのだ。それが、世間一般の「美」とはかぎりなく異なっているにせよ。
ゴスの耽美趣味は、あるいはいまの時代に合わないものでもあるだろう。しかし、時代の空気におもねる精神こそ、最もゴスから遠いものだ。どれほど時代が変わっても、ゴスの精神は変わらない。それは、ときとして、時代精神への批判というかたちを採るかもしれない。また、時代に迎合しきれないものたちは、ゴスを求めてやって来ることだろう。
2.ゴシックミステリ。
ゴスは開祖エドガー・アラン・ポーを経て、本格ミステリ小説にも大きな影響を与えている。だれもがしるように本格ミステリの舞台といえば、絶海の孤島、そうして古びた洋館である。これは、あきらかにゴスから来ているものなのだ。
小栗虫太郎『黒死館殺人事件』は、日本におけるゴスの達成のひとつだろう。『ドグラ・マグラ』、『虚無への供物』と並び称えられる本格の大伽藍にして、「ボスフォラス以東にただ一つしかないと云われる降矢木家の建物」黒死館を舞台にした凄惨なる連続殺人事件の物語、ではあるのだが、この小説は一般的なミステリのイメージからあまりにも大きく逸脱している。そこには膨大な量の衒学が蕩尽されていて、読者を幻惑するのである。
これはヴァン・ダインの『僧正殺人事件』に影響を受けたものだといわれるが、質的、量的に『僧正殺人事件』を大きく上回っているともいう。もちろん、ほかにもペダンティックなミステリは存在する。
しかし、たとえば京極夏彦の衒学趣味が、最終的には物語にそれなりの意味をもってかかわってくるのに対し、小栗虫太郎の衒学は、まさに衒学のための衒学としか思えない。常識的な作家なら、同じ物語をはるかに少ないページで書きえただろう。
が、この「過剰」こそが、まさにゴスである。のちの研究によると、小栗のこの妖しい知識の数々には、たぶんに間違えたもの、それにハッタリやら法螺も含まれているらしい。しかし、その得体のしれない怪しさこそが、ゴシック者を強く魅了する。
もっとも、相当に気合の入ったゴシック者といえども、この本を読み終えるためには多大な忍従を強いられることであろう。それくらい、一般的な娯楽小説の文法から遠い書き方をされている作品なのである。
江戸川乱歩はこの作品を称揚して述べた。「論理の貴族主義者、抽象の詩人の比類なき情熱と、驚嘆すべき博学と、凄愴なる気魄をもって、世界の探偵文学史上に、あらゆる流派を超越した一つの地位を要求する事が出来る」。いかにも乱歩らしい大仰な賛辞が、この作品にはよく似合っている。
そうして、このゴシック趣味は、やがて綾辻行人や麻耶雄嵩といった「新本格」の作家に受け継がれる。即ち、『館』シリーズであり、『翼ある闇 -メルカトル鮎最後の事件-』である。特に「蒼鴉城」を舞台にした麻耶雄嵩の作品は『黒死館』へのオマージュといえないこともない。
しかし、これらの作家はゴシックの使徒と呼ぶには、いまひとつ優雅さに欠けるところがあったことも事実である。かれらにとって最も重要なものは、サプライズに満ちたトリックと、そのトリックを成立させるためのロジックであり、ゴシック趣味は、あくまでその装飾であった。かれらはかれらなりにゴシック趣味を愛してはいたが、いかにも技術的な洗練が足りなかった。だからこそ、新本格は批判されたのである。
トリック重視派にとってはそれはいかにも的はずれな批判とも思えたであろうが、全く的を外していたわけでもない、といまなら思える。やはり、ゴシック耽美を貫くには、当時の新本格の作家たちは技量が足りなかった。
ところが、いま綾辻行人が発表する『ANOTHER』などを見ると、格段に上達した小説技術によって、やはりゴシック的な世界が構築されていることがわかる。
もっとも、新本格のゴシック趣味の拙劣さを、単なる技量の問題と見ることは間違えているかもしれない。ひっきょう、犯罪という「闇」に知性という「光」をあてるものが本格ミステリだとするならば、「闇」そのものに耽溺することは、ミステリ作家の矜持が許さなかった、ということであるのかもしれないのだ。
とはいえ、『霧越邸殺人事件』や『翼ある闇』はそれはそれとしてやはり傑作である。ゴシックとはだいぶ異なる文脈での傑作ではあるにせよ。
新本格四半世紀の歴史の「晩年」、脱本格と呼ばれる作品が流行した。新本格から本格ミステリ的な要素を除き、そのキャラクター小説部分を拡大したともいえる本格の鬼子であったが、そこにもかろうじてゴシック趣味がのこってはいる。
脱本格の代表的作家である西尾維新や佐藤友哉はいかなる意味でもゴスではないが、たとえば北山猛邦の『『クロック城』殺人事件』に始まる一連のシリーズは、色濃くゴスの空気をただよわせている。気合の入ったゴシック者の目から見れば、新本格以上に未熟、拙劣な「建築物」であるにしても。
一方、タイトルに『GOTH』と冠し、その圧倒的なセンスの良さでゴシック者を感嘆させるのが、第六駅でも取り上げた乙一の『GOTH リストカット事件』だ。
ここでいうリストカットとは、文字通り手首を切り落とすことなのだが、この作品で乙一は、あらゆるゴシック的なファッションを排除してゴシックワールドを構築するという離れ業を見せている。この小説を読むと、ゴスが単なるファッションでないことがあらためてよくわかる。
もちろん、ファッションとしてのゴスをわたしは否定しない。しかし、その暗黒精神を見失ってファッションだけを拡散していくならば、ゴスは、根を失った樹のように枯れてしまうのではないだろうか。それはいかにももったいないことであるようにわたしには思える。
『GOTH』の主人公はおよそ人間的情緒というものを持たない「ひとでなし」の少年だが、かれに共感するゴシック者は少なくないのではないか。
およそ「人間的」とされるものすべてがわずらわしく、ただ、暗黒と耽美にのみ耽溺できるのが真のゴシック愛好者だとすれば、乙一の「ぼく」はまさにその道を究めたゴシックヒーローである。
そこには、「ひとでなし」の淡い哀しみがそこはかとなくただよう。
3.テクノゴシック。
科学の夢を追いかけているようなサイエンスフィクション小説にもゴシックの血は流れている。SFとゴスを半ばずつ混ぜあわせたようなそれを、テクノゴシックと呼ぶ。
日本にはテクノゴシックの名を冠せられた作家は少ないが、たとえば牧野修の『傀儡后』はその名で呼ばれることとなった。最先端の科学と、いかにもオカルティックな暗黒文化、かみ合わさるものでもないようにも思えるが、意外に相性は良いらしい。
そもそも、SFの起源をブライアン・オールディズがいうようにメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』に求めるのなら、SFはその歴史の初めからゴスの青い血をひいていることになる。
もちろん、英米のいわゆる「黄金時代」のハードSF作家たち、ハインラインやクラークの作品にはゴスの影などまるで見れない。日本でも、小松左京や筒井康隆の作品にゴス的なものを見いだすことはむずかしい。それは、ときに文化を揶揄し、相対化しながらも、基本的には人類の進歩と、人間の尊厳とを信頼しているように見える。
しかし、長い時を経て80年代に入ると、深いところでゴシックスピリットを感じさせる名作が表れる。ウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』である。
それまでのSFに比べ格段にディテールにこだわり抜いたこの作品は、そこはかとなく「死」と頽廃の匂いをさせていた。麻薬中毒の主人公、廃墟めいた都市、「棺桶(コフィン)ホテル」――『ニューロマンサー』に始まるサイバーパンクとゴスは近しい関係にある。
それからさらに二十年後、その名も『テクノゴシック』と題した評論集において、小谷真理はハリウッドSF映画『マトリックス』のヴィジュアルイメージがはっきりとゴスのそれであることを指摘している。
また、日本でも、80年代から現代にかけて、ゴスと深い関係にある名作が生み出されている。士郎正宗『攻殻機動隊』である。この作品の主人公は全身サイボーグの美女、草薙素子。
作中の2030年代では、二度の大戦を経た結果、「義体」と呼ばれるサイボーグ技術が異常に進歩し、「電脳」と呼ばれる情報処理技術と合わさって、超高度情報化社会を築きあげている。
素子はその戦後社会で、通称「攻殻機動隊」の異名を持つ公安九課を指揮し、さまざまな難事件に挑んでゆく。この作品そのものは80年代末期のものだが、90年代に入って押井守が映画化し、またゼロ年代にいたって『STAND ALONE COMPLEX』と題するテレビシリーズが開始している。
それは自我の不安と情報化を見事に取り入れ、だれも見たことがない未来のヴィジョンを提示してゆく。ひとと機械が融合し、なおかつその融合が常識となった超未来社会。そこでもなおひとは自我を維持し、犯罪は起こり、そのために正義が要求される。
しかし、記憶と自我すらいつハッキングされ書き換えられるかわからないというこの未来社会は、樹木のように屹立する超高層ビルのあいだに「闇」を生み出し、そこには「悪霊(ゴースト)」たちが乱れ歩く。そしてその「自我の不安」は本質的に「不安の文化」であるゴスと繋がるのだ。
ミステリ作家/評論家の小森健太朗は、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』に「あやつり(マニピュレーション)」の構造があることを指摘している。この作品では、自由意志で行動しているつもりでも、だれかに操られているという構造がしばしばくりかえされる。
それはエラリー・クイーンが得意とした「あやつり」の構造である。そこではもはや自由意志は信頼できず、常に自分がだれかの「人形」として利用されている可能性を考慮しながら動かなくてはならない。
この危機的不安に草薙素子はどう対抗するか。大金を蕩尽して電脳に高度な「攻性防壁」を張りめぐらすことによってである。ハイテクが本質的に孕む不安をさらなるハイテクで封じ込めようとするこの態度は、あたかも太古の呪術合戦を思わせ、何ともゴシックだ。
いまたしかにここにある「わたし」は何ものかによってコントロールされた偽の「わたし」であるかもしれない。その実存的不安は映画版『攻殻機動隊』では重要なテーマであるが、時代を下ったテレビ版では、もはや常識的認識であるに過ぎない。
何者かに記憶をハックされている可能性は常にある。つまり、一瞬で目の前の「現実」が揺らぎ、見しらぬ「現実」に放り出される可能性はいつも存在している。
あるいは草薙素子などという人物はいないのかもしれない。公安九課など存在しないのかもしれない。すべては電脳のウィザードたちのハッキングが見せる一瞬の幻であるに過ぎないのかもしれない。
「自分」という存在が一瞬で崩壊するかもしれないというアイデンティティ・クライシスの罠。まして素子たちの「肉体」は機械であり、まったくもって信用するに足りない。これはわたしたち現代人の抱える不安を戯画化したものだろう。
しかし、それでもなお、素子は強靭な意志力でその「不安」をねじ伏せる。目の前の「現実」が電脳の見せる幻であろうと、あるいは本物の現実であろうと、彼女には関係ない。彼女は現実と仮想現実を二項対立的に並べる次元を遥かに飛び越えている。
もし目の前の現実が崩壊したとしたら、彼女はすぐさまその事実を受け入れ行動を開始するだろう。多彩な人物が登場する『攻殻機動隊』シリーズにあって素子が主人公であるのは、単に「エスパーより貴重」とされる超絶指揮能力の持ち主であるからではなく、その意志が自我の不安にあえぐ同僚のバトーやトグサ、そして視聴者たちを魅了するからである。
少なくともテレビ版『攻殻機動隊』を見るかぎり、彼女は決して完全無欠ではない。そして彼女ですら何ものかの「人形」としてコントロールされている可能性はゼロではない。しかし、それでもなお、素子は湧きあがる不安をねじ伏せねじ伏せ、自らの正義を遂行しようとする。
草薙素子こそは、まさにテクノゴシックヒーローである。
この記事の続きを読む
ポイントで購入して読む
※ご購入後のキャンセルはできません。 支払い時期と提供時期はこちら
- ログインしてください
購入に関するご注意
- ニコニコの動作環境を満たした端末でご視聴ください。
- ニコニコチャンネル利用規約に同意の上ご購入ください。
2013/05/09(木) 15:37 きのうは沖縄、あしたは北海道。日本を転々としつつノマドな人生を送ってみたい!(1940文字)
2013/05/09(木) 16:53 すべてが99円になる!? 日本の電子書籍は価格破壊を超え未来を見出すことができるか。(2063文字)


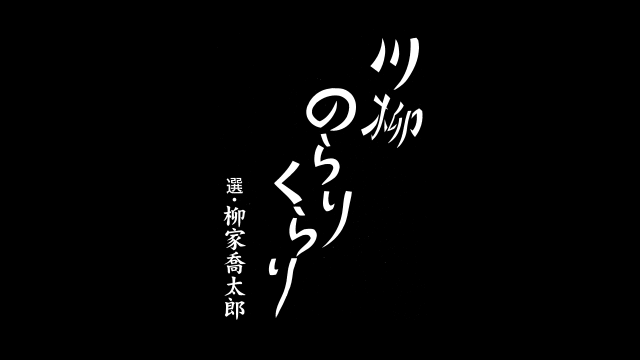

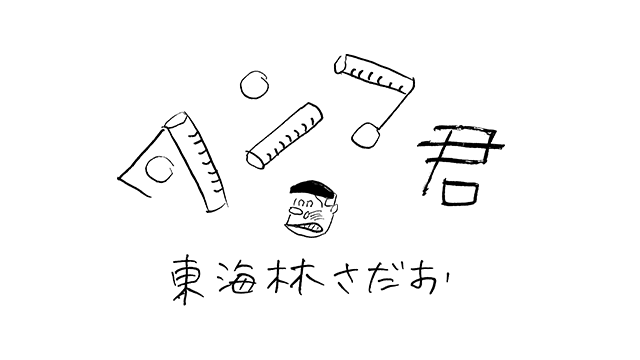
コメント
コメントを書く