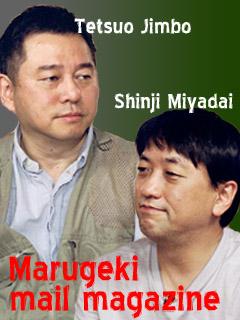 マル激!メールマガジン
マル激!メールマガジン
橋本淳司氏:八潮市だけではない全国に広がる老朽水道管をどうする
- 登録タグはありません
マル激!メールマガジン 2025年3月19日号
(発行者:ビデオニュース・ドットコム https://www.videonews.com/ )
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マル激トーク・オン・ディマンド (第1249回)
八潮市だけではない全国に広がる老朽水道管をどうする
ゲスト:橋本淳司氏(水ジャーナリスト)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県八潮市の道路陥没事故からすでに1カ月半が経った。住民への避難要請や下水道の使用を控える呼びかけは解除されたものの、依然として転落したトラックの運転手は取り残されたままだ。
八潮市の陥没事故は、腐食した下水管に周囲の土砂が取り込まれ、舗装面の下の地中に空洞ができたことが原因とされている。水道管は40年から50年を目安に更新の必要があると言われるが、この下水管は42年前に敷設されたものだった。
八潮市の事故は大きなニュースになったが、実は老朽化した下水管に起因する道路の陥没事故は日本全国で起きており、その数は2022年度だけで2,625件にのぼる。上下水道の老朽化は日本中で進んでいて、国交省によると、2040年には全国約74万kmの上水管の約41%、約49万kmの下水管の約34%で、建設後50年以上が経過する見通しだという。
高度経済成長期以降、日本は上下水道の敷設を急ピッチで進めたことで、日本の上下水道の普及率は他の先進国並の9割を超えるまでに上がっていった。しかし、その後、日本の経済成長が鈍化し、人口増加にもブレーキがかかるようになると、耐用年数を迎えた上下水道管を維持管理し必要に応じて付け替えることが財政的に困難になっている。お金の問題だけではなく、水道行政に関わる職員の数も大幅に不足しているという。
水道事業は基本的には市町村が担い、原則として水道料金で運営されることになっている。しかし多くの自治体が水道料金だけでは賄いきれず、毎年、公費による補填を受けている。そのような中、1kmに1億円以上かかると言われる水道管の更新を進めるのは極めて困難だ。
この状況を打破するために、2018年には水道の民営化を促す水道法の改正が行われた。法改正により、個別の業務を委託する従来の官民連携とは異なり、長期にわたり民間企業に水道事業の運営権を譲渡する「コンセッション方式」が可能になった。
民間企業なら効率的に利益を生み出せるとして水道管の老朽化問題に対処できることが期待されたが、これまで自治体が独占してきた水道事業のノウハウを持った民間企業がほとんどないことや、そもそも水道事業には他のサービスを付加して顧客を拡大するという余地がないことなどから人気がなく、現在も民営化は宮城県や浜松市など限られた自治体でしか導入されていない。
しかし、かといってこれまでのやり方で日本中の水道管の更新費用を賄おうとすれば、莫大な費用がかかり、それは水道料金の大幅値上げという形で大きな負担がユーザーにかかってくることが避けられない。
特に人口が大幅に減少した地域の水道管をどうするかという問題が深刻だ。ユーザー数が減ったからといって上下水道を止めるわけにはいかないからだ。しかし、かといって日本中で老朽化した水道管を放置し、陥没事故が日常化するような事態を看過するわけにもいかない。
水ジャーナリストの橋本淳司氏は、生活排水を個々の家庭で処理する合併浄化槽の導入や、地域単位で地下水や井戸水を共有することによって、上下水道に代わる選択肢も検討すべきだと言う。同時に、ドローン技術を用いて水道管の点検を効率化したり、新素材を用いて水道管の中に新たな水道管を作る技術など、水道管の点検・更新に関わる技術革新を進めることで、保守点検や更新コストを削減する努力も必要だ。また、上下水道事業に携わる人々の就労環境を改善することも必要だと橋本氏は指摘する。
八潮市の事故が鳴らしている警鐘とは何なのか。日本の道路の下に張り巡らされた上下水道は今どのような状態になっていて、このままそれを放置すると何が起きるのか。日本はこれから人間の生存に不可欠な水をどうやって確保していくのかなどについて、水ジャーナリストの橋本淳司氏と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
今週の論点
・八潮市の陥没事故が他人事ではない理由
・人手もお金も足りない上下水道事業
・水道民営化は解決策になるのか
・上下水道事業に携わる人材をいかに確保するか
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ 八潮市の陥没事故が他人事ではない理由
神保: 今回の入り口としては、老朽化した下水管問題になります。八潮市の事故では人も落ちたということで大騒ぎになりましたが、実は全国でこれが起きています。
宮台: 2012年に笹子トンネルで崩落事故がありました。昭和OSと呼ばれているようなトンネルや鉄橋など、鉄を使うようなものがたくさん作られましたが、日本のコンクリートは30年くらいで建て替えなければなりません。
なぜ日本のコンクリートのスペックが低くなっているのかということは、なぜ道路の舗装のスペックがこれだけ低いのかということと同じです。昔の建設省や通産省の役人が考えた図式で、補修や保全の経済になったそうです。しかし持続可能な図式ではなく、全ての昭和OSで補修が必要なのですが、人もお金も足りません。これは構造的な問題だと思います。
神保: 当時は一定の人口見通しに基づいて計画をしていたのですが、その通りにならなかった時にどうするのかということは考えていませんでした。70年代に出した人口予想が過大だったということもあり、それに届かないということであればそれだけ歳入も減ります。あまりにも見通しが甘かったのですが、その時の官僚はもう天下っています。その構造がまずく、総無責任体制のようになることで後の世代が背負うことになります。
下水は私たちの目に見えないので、ああいうふうに破断して始めて重要性が分かりました。水は臭くお風呂も入れず、浄水場できれいにせずに川に流して環境汚染もひどいということが現実に起きてしまっています。それがこれからもしょっちゅう起きる可能性があります。
八潮では道路にトラックが落ちるという不幸な事故がありましたが、これがたまたまではなく、構造的な問題があるという視点から考えてみたいと思います。ゲストは水ジャーナリストの橋本淳司さんです。2018年に来ていただいた時は水道民営化の話をしましたが、その時の議論と今起きていることにはどのような関連性があると思いますか。
橋本: あの時は誰に任せるのかという議論をしていたと思いますが、その時に置き去りにされていたのは古くなった水道管をどうするのかという問題です。新しい仕組みを作れば修繕も上手くいくと考えられていたのですが、そちらの方には手がつけられないままでした。老朽化がどんどん進み今回のような事故が発生しましたが、その予備軍的なことは全国のあちこちにあるという状況です。
神保: 民営企業が参入した場合、古い水道管の付け替えを自分たちのコスト負担で行おうとは普通は考えないですよね。
橋本: 日本の場合はコンセッション方式で運営権だけ任されます。20年や30年という契約をし、契約に水道管の更新もするということが盛り込まれていればやりますが、実際に行われているかどうかモニタリングするのは複雑で、うまくいくのかという問題があります。
神保: 今回の八潮の事故についてですが、落ちたトラックの運転手を救出するために大変な作業が行われていて、いまだに救出はできていません。
橋本: 地盤が非常に崩れやすい場所だったので、穴が空いたところに周りの土砂がどんどん入ってしまい穴が大きくなりました。
神保: 1月28日はトラック1台が落ちるくらいの穴でしたね。
この記事の続きを読む
2025/03/12(水) 20:00 山極壽一氏:学問の意義を理解しない日本学術会議の新法案は間違っている
2025/03/26(水) 20:00 中村裕二氏:地下鉄サリン事件から30年 日本がオウム真理教の暴走を止められなかった原因をあらためて考える
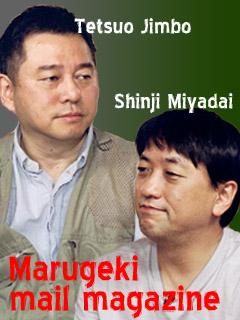


コメント
コメントを書く