 マル激!メールマガジン
マル激!メールマガジン
デービッド・アトキンソン氏:日本が東アジアの貧乏小国に堕ちるのを防ぐための唯一の処方箋はこれだ
- 登録タグはありません
マル激!メールマガジン 2023年11月29日号
(発行者:ビデオニュース・ドットコム https://www.videonews.com/ )
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マル激トーク・オン・ディマンド (第1181回)
日本が東アジアの貧乏小国に堕ちるのを防ぐための唯一の処方箋はこれだ
ゲスト:デービッド・アトキンソン氏(小西美術工藝社社長)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
冷徹にデータを見れば、これ以外に手がないことは明らかではないか。
日本がいよいよ先進国から転落しようとしている。過去30年間、ほとんど経済成長できず賃金も伸びなかった日本は、今やあらゆる経済指標で先進国の最下位に転落している。日本が停滞している間に他国は紆余曲折を経ながらも毎年成長を遂げているため、日本の国際的な地位が下がり続けるのは当然のことだ。
しかも、日本にとっての真の修羅場はこれから来る。日本では1995年をピークに生産年齢人口が減少に転じているが、その傾向は少なくとも向こう40年間は変わらないばかりか、減少に拍車がかかることが確実視されている。実際、15歳から64歳までの生産年齢人口は1995年のピーク時の8,726万人から2060年には5,078万人まで、約3,600万人減ると推計されている。3,600万人はイギリス1国の生産年齢人口に匹敵する。つまり、日本には向こう40年の間にGDP世界第5位の国イギリスと同規模の人口減少が待っているのだ。
そもそも戦後の日本の経済成長のほとんどは、実は人口ボーナスの恩恵がもたらしたものだった。日本の人口は終戦時の1945年に7,200万人だったものが、1990年には1億2,361万人まで爆増した。その間、特に生産年齢人口、つまり若者の人口の増加が顕著だった。人口が増えれば生産力も増すし、消費力も増す。それが日本の経済成長の主たる原動力だった。
しかし、日本人は人口増加のおかげで成し遂げた経済成長を、エコノミックミラクルなどと自らをもてはやし、その特殊な期間、つまり人口の増加を前提とできた時代に作られた様々な制度を、人口増加が止まり減少に転じる局面になっても、変えることができずにいる。元ゴールドマン・サックス証券のアナリストで現在、文化財の修復を専門に行う小西美術工藝社の社長を務めるデービッド・アトキンソン氏は、これが日本の成長の足を引っ張っていると指摘する。
年功序列、終身雇用、企業別労組と労使協調、専業主婦に第三号被保険者制度、新卒一括採用、護送船団方式等々は、いずれも戦後の人口ボーナス期に、これからも人口増が続くことを前提に作られた制度だった。しかし、これらの日本固有の制度が、日本のエコノミックミラクルの立役者だったかのようにはやし立てられた結果、その大前提だった人口が減少に転じても、それを変えることができないでいる。それがことごとく日本の成長の足を引っ張っているとアトキンソン氏は語る。かつて美談や美徳だったものが、今や因習となっているのだ。
そして数ある因習の中でも、もっとも日本の足を引っ張っているのが中小企業の乱立だとアトキンソン氏は言う。言うまでもないが、生産年齢人口が減少に転じた局面で経済成長を実現するためには、1人1人の生産性を上げるしかない。そして日本企業の労働生産性は先進国でも最低水準だ。これを上げない限り、日本は人口減少に呼応してノンストップで貧しくなっていくことが避けられない。
ところが、日本の労働者の7割、企業数では99.7%を占める中小企業にとって、生産性を上げることは容易ではない。日本では製造業は社員数300人以下、卸売業とサービス業は100人以下、小売業は50人以下が中小企業、それ以上が大企業と定義され、中小企業は1964年に制定された中小企業基本法によって税制面などで大企業よりも優遇されているとアトキンソン氏は言う。
結果的に平均社員数が4人にも満たない日本の中小企業が、全企業の99.7%を占め、そこで働く労働者も全労働者の7割を占める。そして小規模な中小企業の大半は大企業と比べて生産性が低く、賃金も低い。これが日本の全体の生産性の足を引っ張っているとアトキンソン氏はいうのだ。
アトキンソン氏によると、日本の経営者は従業員を減らしたり、コストを削減すれば生産性が上がると誤解している人が多い。確かに社員を減らしたりコストを削減すれば一時的に利益は上がるかもしれないが、そもそも平均社員数が4人にも満たない中小企業でどれだけの持続的な社員数削減やコストカットが可能だと言うのだろうか。結局のところイノベーション(技術革新)を実現できなければ持続的に生産性を上げることはできない。そしてそのためには、より付加価値の高い新製品や新サービスの導入を図る必要がある。
現在の閉塞と低迷から日本が抜け出るためのアトキンソン氏の処方箋は明快だ。やるべきことは2つ、中小企業の規模を大きくし、とにかく生産性を上げることと、そして人口増の時代にできあがった神話とも言うべきさまざまな商習慣や因習を根本的に見直すことだ。
今のままでは日本の未来は決して明るいとは言えないが、アトキンソン氏は意外に楽観的でもある。彼が知る日本には、変化に対して臆病であり、ギリギリまで抵抗を続けるが、ある転換点を超えた瞬間に一夜にしてこれまでのこだわりを捨て、新しいものに飛びつくような国民性があると言う。江戸末期に尊皇攘夷派が一夜にして開国派に転向したり、戦後、昨日まで天皇陛下万歳を声高に叫んでいた天皇主義者が一夜にして我先にと民主主義者に転向してきた歴史をわれわれは身をもって知っている。
アトキンソン氏自身、委員を務めていた政府の規制改革会議などで常識的な改革案を主張すると、最初は他の委員全員が口を揃えて反対し、中には彼の人格否定や個人攻撃まで繰り広げる委員もいたほどなのに、ある程度議論が進むと、反対派がなだれを打って彼の提案に賛成するようになり、提案者の彼自身が当惑したことが何度もあったという。そういう時、反対から賛成に転向した人は決まって「私は最初からそう思っていました」と真顔で言うのだそうだ。
また、アトキンソン氏は日本の行き過ぎた形式主義にも警鐘を鳴らす。自身が茶道をたしなむアトキンソン氏は、型(かた)の重要性を認めつつも、型というものは元々何らかの合理的な理由があってできあがっているものであることを忘れてはならないと言う。前例に則り形式を繰り返しているうちに、そもそもなぜその形式になっているのかを忘れてしまうきらいがわれわれにはある。
人口爆増の時代にできた様々な制度を人口減少時代になっても捨てることができないのは、日本の行き過ぎた形式主義の反映だとアトキンソン氏は言う。手遅れになる前に日本は産業構造や制度を人口減少の時代に合ったものに変えていかなければならない。
人口減少時代に突入しても日本が没落し、東アジアの隅の貧乏な小国に成り下がらないためには、人口減少を相殺してあまりあるほど顕著な生産性の向上を実現するしかない。また、そのために何をしなければならないのかも、わかりきっている。あとはそれを実行する勇気と、日本人特有の「ある日突然転向する変わり身の早さ」を活かして、手遅れになる前にそれを実行できるかどうかにかかっていると語るデービッド・アトキンソン氏とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
今週の論点
・戦後日本の経済成長は人口ボーナスによるものだった
・日本の賃金はなぜ低いのか―中小企業の1964年体制とは
・労働生産性を上げなければ賃金は上がらない
・「変わり身の早さ」を活かして変わるしかない
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ 戦後日本の経済成長は人口ボーナスによるものだった
神保: 今日は2023年11月24日の金曜日、1181回目のマル激です。本日のゲストは小西美術工藝社社長のデービッド・アトキンソンさんです。前回のご出演から4年くらい経ちましたが、その後の日本が歩んできた道のりをどのように見ていますか。
アトキンソン: 何も変わっていないですよね。問題も変わっていないですし解決策も変わっていません。多少良くなっているかもしれませんが、残念ながらそこの認識や分析は足りていません。最近になって賃上げをどうするのかということが話されるようになりましたが、それもここ1、2年のことじゃないですかね、
神保: 賃上げは必要だと言いつつ、まだ実現しているわけではありませんよね。
アトキンソン: 実現していないどころか後退していると思います。
神保: 今回岸田政権が経済政策を出しましたが、世の中は冷たく反応しました。これは、さすがに騙されないぞと国民が思い始めたと見てよいのでしょうか。
アトキンソン: 個人的な見方ですが、結局は賃金が上がるか上がらないかという話だと思います。例えば、消費税がなくなるというのは108円で買えた大根が100円で買えるようになるということですが、最近は100円だったトマトが300円になるということが起きています。消費税がなくなれば多少は楽になりますが、トマトは税金で200円分上がったわけではないですし、324円のトマトが300円になっても本質的な解決にはなりません。
この記事の続きを読む
ポイントで購入して読む
※ご購入後のキャンセルはできません。 支払い時期と提供時期はこちら
- ログインしてください
購入に関するご注意
- ニコニコの動作環境を満たした端末でご視聴ください。
- ニコニコチャンネル利用規約に同意の上ご購入ください。
2023/11/22(水) 20:00 古賀茂明氏:末期症状を呈する自民党政治を日本の終わりにしないために
2023/12/06(水) 20:00 鶴見太郎氏:被害者意識の強いイスラエルが国際社会を信用できるようにならない限りパレスチナへの攻撃は続く


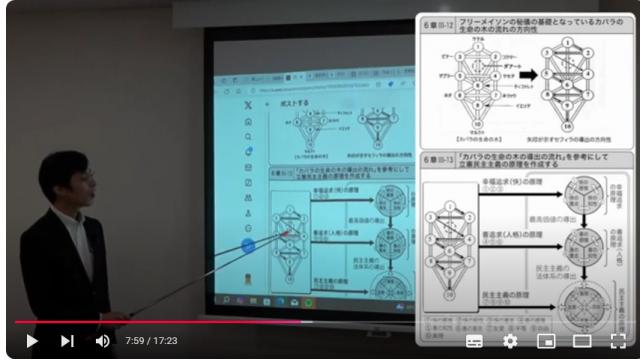

コメント
コメントを書く