『日米開戦の正体 上』内記述。
小説家は人間の真実を追求していますが、彼らが社会現象に目を向けた時、社会学者より、端的に真実を指摘することがあります。
夏目漱石がそうです。
夏目漱石は『それから』(1909年著)で、日露戦争後の日本を実に見事に描写しています。
*********************************
「大袈裟に云うと、日本対西洋の関係が駄目だから働かないのだ。第一、日本程借金を拵らえて、貧乏震いをしている国はありゃしない。この借金が君、何時になったら返せると思うか。そりゃ外債位は返せるだろう。けれども、そればかりが借金じゃありゃしない。日本は西洋から借金でもしなければ、到底立ち行かない国だ。それでいて、一等国を以て任じている。そうして、無理にも一等国の仲間入をしようとしている。だから、あらゆる方面に向って、奥行を削って、一等国だけの間口を張っちまった。なま

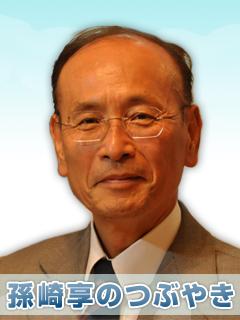


コメント
コメントを書く(ID:18367902)
権力者が、社会の活力を削ぐ場合もあるが、ピラミッド型の人口構成がいびつになり、高齢者が多く社会の自然な変革を止めてしまい社会の活力を阻害する場合がある。自然法爾の在り方が、不自然な人口構成によって社会的変革を意図的に止めてしまうというより、悪い経験したことのない現象が起きてきて対処できないのです。経験則が通用しないのです。
社会的改革が促されなければ、政治、経済、学問などあり方が、経験したことのない現象に対して有効な対策をとれないのです。AIとかロボットなど非人間的なスツールが経験的人間の能力を超えていくわけであり、人間の本来的な相互移入心が欠けてしまい、直接的な言葉が支配することになる。逆に「慈悲」とか「思いやり」という人間本来の暖かい気持ちが、忖度などという悪い意味での表現にしか受け取られなくなっている。
働き方改革などは、悪く解釈すれば、票に結び付く高齢者票を目当てにした悪平等政策ともいえる。何故か。若い人の活躍する場を高齢者が譲らなくなってしまい,旧態然とした制度が支配し、新しい改革機運が沸き上がってこないからです。