おはようございます。年に一度の人生の洗濯旅行で御蔵島に行こうとしているマクガイヤーです。
このブロマガを書いている時点では無事に辿り着けたかどうかわからないのですが、いや楽しかったなあ! 楽しかった、はず!!
マクガイヤーチャンネルの今後の予定は以下のようになっております。
○4月29日(土)20時~
いつも通り、最近面白かった映画や漫画について、まったりとひとり喋りでお送りします。
その他、気になった映画や漫画についてお話しする予定です。
○5月4日(木)20時~
「クトゥルフ神話と『映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』」
3/4より『映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』が公開されております。
この映画、最近の大長編ドラえもん映画の中でみても面白いばかりか、どうみてもクトゥルフ神話の一編である『狂気の山脈にて(狂気山脈)』をネタ元にしているのですよ。
そこで、大長編ドラえもん映画とクトゥルフ神話双方の視点からみた『のび太の南極カチコチ大冒険』について解説致します。
是非とも映画本編を視聴した上でお楽しみください。
○5月20日(土)20時~
「最近のマクガイヤー 2017年5月号」
いつも通り、最近面白かった映画や漫画について、まったりとひとり喋りでお送りします。
詳細未定
お楽しみに!
さて、今回のブロマガですが、前回の続き、科学で映画を楽しむ法 第4回として、『攻殻機動隊』(と『シャブ極道』)その2について書かせて下さい。
原作漫画を『攻殻機動隊』
95年に発表された押井守監督のアニメ映画版を『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』
先日公開されたルパート・サンダース監督の実写映画版を『ゴースト・イン・ザ・シェル』と表記します。
●サイバーパンクとしての『攻殻機動隊』
89~91年に発表された『攻殻機動隊』は、SFとしてそれほど目新しい話では無かった――という話は以前書きましたが、もう一度書きますよ。
http://ch.nicovideo.jp/macgyer/blomaga/ar1056869
「脳を部分的に機械化したサイボーグがネットを介してハッキングし合う」という話はウィリアム・ギブスンやブルース・スターリングなどのサイバーパンク作家が既に書いていましたし、「知的生命体が進化すると生身の身体を捨て去り意識だけ情報だけの存在になるのでは」という話はアーサー・C・クラークが『幼年期の終わり』や『2001年宇宙の旅』で50、60年代から発表済みでした。科学技術や社会システムが発達した世界で、肉体のどこまでが「自分」なのか、「自分」とはいったい何なのか――すなわち実存の問題は、SFというジャンルでいえば(『ブレードランナー』の原作者である)フィリップ・K・ディックが、もっと広い文学という分野でいえばカミュやサルトルといった実存主義作家たちが既に扱ってきたものでした。更にSFでは、「人間とは何か」をテーマとするために、機械のような人間や、人間のような機械(サイボーグやAI)を扱うのはごくごく普通のことでした。
では何が新しかったかというと、マンガというジャンルにおいて、当時最先端の絵柄とコマ割りでサイバーパンクというネタを存分に描ききったことが新しかったわけです。
このことは士郎正宗もしっかり自覚していて、「表層をなめただけの軽いサイバーパンクもどきで、サルまねっぽい一面もある」なんて表3に書いていたりします。
士郎正宗としては、それまで単行本を出していた青心社のようなマイナー出版社ではなく、ヤングマジン海賊版とはいえ講談社という「メジャーリーグ」のバッターボックスに立つにあたって、「サイバーパンクと電脳」「未来警察」「ハイレグ刑事」……等々、できるだけ分かり易くて一般読者に受け入れられ易いネタを選んだつもりだったのだと思います。本当に分かりやすかったかどうかは別問題ですが。
もっといえば、『攻殻機動隊』が士郎正宗の既作品より突出しているのは、単行本1巻できちんと完結しているまとまりの良さでしょう。いかにもサイバーパンク的な巨大都市を舞台としつつ、公安9課の創設から始まり、教育工場や択捉島での活躍といった様々な事件の中で人形使いと出会い、最後は人間でもAIでもない(しかし「ゴースト」ではある)より高次の存在となる……未完作品が多い士郎正宗にしては、もの凄い完成度です。
●『攻殻機動隊』における素子の変化
特筆すべきは、終盤の展開でしょう。
漫画版の草薙素子のキャラクターは、任務の一環として平気で殺人を犯すプロである一方、友人の同性のセックスフレンドとバーチャルAVみたいな違法電脳ソフトの製作を行ない、そして自分のやっていることになんの後ろめたさもない明るさがあります。人殺しをしているのにプロフェッショナルすぎてなんの後ろめたさも感じていない――ある意味、漫画でしかありえない嘘みたいなキャラクター、といって良いでしょう。
ところが終盤、そんな素子のキャラクターが変化します。
漫画で描かれる公安9課の仕事は、事故や犯罪の犠牲者を助けるといったいわゆる「正義の味方」の仕事ではありません。犯罪捜査をしつつ、それをネタに他の警察組織や権力組織に圧力をかけたり取引をしたりする――権力闘争です。
そして素子は、だんだんと権力闘争に疲れていくのです。
まず第8話「DUMB BARTER」、素子には「珍しく3ヶ月以上続いた」公安1課の彼氏がいることが示されます。ところが、彼氏のあずかり知らないところで1課の課長は9課の素子の情報を素子に恨みを持つテロリストとの裏取引に使ったらしく、1課と9課が敵対します。『ロミオとジュリエット』の如く、あるいは『Mr.&Mrs. スミス』の如く、武器を向け合う二人。

この彼氏、以後二度と登場しないことから、二人はこのエピソードをきっかけに分かれたことが分かります。つまり、組織や体制のせいで分かれたのです。
続く第9話で素子は人形使いと出会います。このエピソードは映画化もされたので省略しますが、次の第10話「BRAIN DRAIN」がまた秀逸です。
ある任務で素子は組織のリーダーを射殺するのですが、殺人の瞬間が誰かによって撮影され映像が公開されるというスキャンダルが起こります。これは6課と外務省(とイスラエル)が9課を陥れるために仕組んだ罠だったのですが、きちんと礼服仕様の軍服を着て、裁判所で殺人の是非について釈明させられるという茶番につき合わされ、草薙素子は冷めてしまうのです。
素子は、自分はこの社会を守るために生死をかけて暗殺やらハッキングやらをやってきたのに、結局これは正義も悪も関係ない人間同士の権力闘争でしかなかったのだということに気づいてしまいます。

結果として、素子はまるで神の様な、俯瞰した視点で「生命」や「人間」を捉えなおすことになります。あまりにも俯瞰すぎる視点なので、検察も傍聴人も理解できません。

第1話の、希望に燃えて明るかった頃の素子とはえらい違いです(しかも、作中時間では1年間も経っていないという設定だそうです)。
草薙素子は生き延びるために人質をとり、9課を去ります。これまで公安9課は体制側の組織でありつつも、必要があれば閣僚や他の警察組織と抗争を繰り広げてきましたが、とうとう体制側から脱し、組織よりも個人の自由を選んだわけです。
そして、いよいよ最終話です。草薙素子は史上初めて「ゴースト」すなわち「魂」を持ったAIである人形使いと融合します。
電脳化した人間の魂はもはやプログラムと区別がつかない。そして、高度に進化したAIは「ゴースト」すなわち「魂」と区別がつかない。両者の区別ができないのであれば、融合することもできるし、融合で「進化」することもできる

「多様性があれば1種類のウイルスで全滅することはない」これは、素子が自分の部下として様々な人間――電脳化も義体化もされていないトグサを含めた様々な人間――を選んだのと同じ理屈です。素子は多様性を、人形使いは電脳空間でのパワーを提供し、融合することで新たな存在となる……理屈では分かりますが、現在の価値観ではとうてい理解できません。

未来社会を舞台にした作中でも同様で、バトーですら理解できません。
しかし、草薙素子は選択します。
体制からの脱却、自由と不服従、既存の価値観とは全く異なるオリジナルな価値観の追求……
これをパンクといわずしてなんというべきでしょうか。
最後の「ネットは広大だわ」という有名な台詞に、「インターネットがあれば人間は自由になれる」と信じられていた牧歌的な時代を思い返してしまいます。それはまさしくネット黎明期の90年代前半から中盤に漂っていた雰囲気でした。
●サイバーパンクとしての『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』
「このままだと家のローンが払えない」という奥さんの訴えにより映画化依頼を引き受けた押井守ですが、映画『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のどこが新しかったかといえば、以下の三点にまとめられるでしょう。
・アニメでサイバーパンクを本格的に扱った作品は初めてに近かったこと
・『機動警察パトレイバー the Movie』から引き続いてきたレイアウトシステムによる画面作りが最高潮に達したこと
・「押井守の映画」としてもの凄い完成度だったこと
もっといえば、この三つはすべて関連しています。画面のサイバーパンクっぽいカッチョ良さ以外は、話を含めて、いつもの「押井守の映画」であったし(勿論、押井守が予算をかけて作る映画はどれもこれもカッチョ良い画作りが魅力なわけですが、ここまでサイバーパンクな画作りは初めてでした)、押井守が学生運動で得た「反体制」や「個人の自由の追求」といったテーマは、「パンク」そのものでした。
これを理解してもらうためには、まず「押井守の映画」というか「押井守の考える映画」について説明しなくてはならないでしょう。
●押井守の考える映画とはなにか(物語編)
「眠い」「間が空きすぎてタルい」「話がよく分からない」……等々、時にディスられまくる押井映画ですが、「主人公の成長物語」という点では一貫しています。
主人公が旅に出て、世界の秘密を発見する。そして、映画の冒頭と最後とでは、主人公の精神の一部分あるいは全てが、後戻りできないほど変質してしまう……これが押井映画の「物語」です。
押井映画の演出は、この「物語」を演出するためだけにあります。
たとえば、『攻殻機動隊』では素子とバトーそれぞれに彼氏や彼女(?)がいます。バトーは素子の恋愛を茶化したりさえします。

(↑思わず義眼に表情が出るバトー)
これが『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』になると、バトーは素子に特別な感情を抱いている……というか、ホレているわけです。身体のシルエットが浮き出る光学迷彩服を着ている素子にそっと上着をはおらせたり、人形使いの入っている上半身だけになった女性用義体は乳首むき出しの裸のままなのに同じく上半身だけになった素子には上着をかけたり、普段は「少佐」と呼んでいるくせにここ一番の時になると「素子ォォォ!」と名前で呼んだりするのは、「好きだ」とか「愛してる」とかいった直接的な台詞に頼らずホレていることを示す、分かり易い演出なわけですね。こういった演出は、ハードボイルドものなどでよく使われています。
で、何故「バトーは素子にホレている」という設定にしたのかというと、押井守は原作漫画を素子と人形使いの婚礼劇として読んだ、というかラブストーリーとしての要素を強調したからです。
(「申し出」に「プロポーズ」のルビをふり、二人の融合を結婚に重ね合わせる表現は原作にもありますね)
『攻殻機動隊』では8話目くらいから疲れがみえはじめた素子ですが、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』では映画が始まる前から疲れています、というか、人生に飽き飽きしています。いつもクールというか仏頂面で、台詞は必ず皮肉が混じっています。押井守としては素子の実年齢を47、8歳と考えていたそうです。
暗殺に諜報に権力闘争……もうこんなブラックすぎる仕事辞めたくて辞めたくて仕方がないのですが、9課を辞めることは自分の脳や記憶が失われること――自分が自分で無くなることに他なりません。そもそも、義体化し、電脳化している自分が、自分の思っている自分かどうか――「ゴースト」のある人間かどうか――すら分からないのです。
『攻殻機動隊』では死のリスクの高い任務(サイボーグなのでフロートが故障したら浮かび上がれない)として描かれたスキューバダイビングは、映画では趣味として描かれます。つまり、素子はダイビングの途中で死んでも構わない、と思っているくらい生きていることに飽きているわけです。
(この「生きていることに飽きている」というテーマは、その後『イノセンス』や『スカイ・クロラ』でも扱われることになります)
そんな時、人形使いという気になる存在が現れます。

漫画ではジョークの一つとして(↑)しか描かれなかった「機械の身体に情報としての魂(ゴースト)が入っている自分はどこまでが自分か」という未来世界(だけど現在に通じている)における実存的問いは、映画版ではシリアスな問題となって素子を悩ませています。
一方で、機械の身体に情報だけが入っている人形使いは自らを「生命体」と主張し、「政治的亡命」を持ちかけてきたりするのです。自分は周囲から人間扱いされているにも関わらず、生きているか死んでいるか実感が持てないのに、6課に作られたAIでしかないあいつは、自らを「生命体」と主張している。なんでそんなこと断言できるの?!……ちょう気になる!……いきなり気になる転校生が現れたわけですね。
あれよあれよという間に、素子は人形使いとデートし、「融合しよう」とプロポーズされ、素子はそれを受け入れます。
これら一連の出来事は、すべてバトーの目の前でおこります。
つまり、バトーは素子をNTRれたわけですね! NTRのインパクトを大きくするために、原作にはない「バトーは素子にホレている」という設定に改められたわけです。
また、押井守の長編映画は、台詞無しで川井憲次の音楽だけがかかるモンタージュのシーンが後半に用意されているのですが、本作でかかる『謡』は「よばひに かみあまくだりて」すなわち「結婚に 神降りて」と、ずばり神との結婚を表す歌詞だったりします。
●押井守の考える映画とはなにか(クロニクル編)
押井守は東京出身、1951年生まれ、60年代後半~70年代前半の青春期に新宿アングラ文化にどっぷりつかった世代です。更に「学生時代はピンク映画含めて年間数百本もの映画を観ていた」と豪語するシネフィルでもあります。



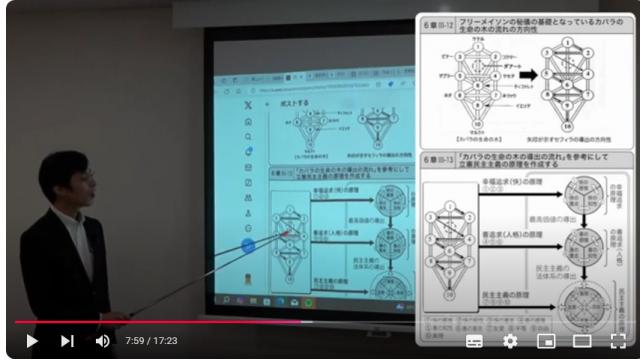


コメント
コメントを書く(ID:46211992)
押井版の公開された1995年というのは私にとって思い出深い年です。神戸市灘区で阪神大震災にあい、震災義援金でWin3.1のパソコンを買ってパソコン通信を始めた年でした。そこで出会ったのが旅先通信なるもので、そこに集う人々は小型ノートパソコンやPDAを使って、音響カプラーを使ったり、灰色の公衆電話のモジュラージャックを使ったり、時にはホテルの電話機回線をばらしたりして、メールのやりとりやパソコン通信のフォーラムに書き込んだりしてました。「今、ここ」での情報を発信することで、単に情報の共有のみならず、何か新しい知のあり方や集団的知性の発現を夢見ていたのではないかと思われます。当時の熱狂ぶりは富士山の山頂から東芝リブレットと音響カプラーでアクセスする者までいたほどです。その後携帯電話の普及、スマートフォンの出現により、集団的知性の発現はおろか、コンビニのおでんをツンツンする様子を世界に発信するほどネットは愚者のデバイスと成りはてました。しかし95~98年ぐらいはネットに何かの可能性を信じていました。ADSLによるネットの常時接続が始まる前に、限られたリソースで如何に繋がるのかを試みた時代には押井の描いた世界は格別のリアリティがあったものでした。ドクターより少し年上の繰り言です。