
※この記事は、およそ10分で読めます※
今回短いです。つっても、前回と同じくらいですが。
どうも、ことにnoteでは時事評めいたモノの方が食いつきがよさそうなので、これからはこうしたものを増やしていこうかと思います。
逆に、がっつり読み込んだ書評などは頻繁に更新することが難しくもなってきているので……。
ジャニー喜多川が死にました。
何で死んだとかは、知りませんし、興味もありません。
それより確か、数ヶ月前も死亡のニュースが聞こえてきた記憶があるのですが、何だったんでしょうね、あれ。或いはその時死んでいて、死亡日が操作されてたりするんでしょうか。
おわかりかと思いますが、本件でぼくが興味を持っているのは、ジャニー喜多川が長年に渡って男児虐待を続けてきた薄汚い老人であるという点についてのみ(これについては疑惑や噂などではなく明確に「黒」であることも、述べるまでもないでしょう)。そしてそれを、長年に渡ってマスコミもフェミも軒並みスルーし続けてきたという点についてのみです。まあ、フェミが男児への虐待に対して怒りを表明するなど、あるはずもないのですが(リンクと本論は一切関係がありません)。
長年に渡って男児のレイプを称揚し続けて来た伊藤文学も薄汚い老人に変わりはありませんが(リンクと本論は一切関係がありません)、「実行」に移していたジャニー喜多川(そしてそれをスルーし続けて来た人々)がその何百倍も薄汚いのは、言うまでもないことでしょう。
さて、とはいえ、ここではこれを機に、ずっと気になっていた「とある歌」についてのレビューをしたいと思います。
TOKIOがもう二十年以上前に出していた「ぼくの伯父さん ~My uncle is a nice guy~」という歌で、NHKアニメ『飛べ! イサミ』の主題歌、「ハートを磨くっきゃない」とのカップリング曲でした。詩は以下のような感じです。
ぼくの伯父さん ~My uncle is a nice guy~
いかがでしょう。もう、全体から得も言われぬ腐臭が漂っていて、目を開けているのも辛いですね。
……あ、いや、安易に共感を求めてしまいましたが、或いはそこまでこれに嫌悪を覚えるのはぼくだけなのかもしれません。
ちょっとその嫌悪感について分析して、ご説明申し上げることにしましょう。
ぼくがこの曲を聴いた時に感じるたまらないキモさは、作り手のあどけなすぎるナルシシズムと、それを年少者に押しつける体育会系気質にあるのです。
TOKIOといっても当時はまだ二十やそこらでしょう、多分。年若い男性に、こうした歌を歌わせ、そのボスがジャニー喜多川。もちろん、この歌が作られたバックをぼくは知りませんし、別に喜多川が「こういうのを歌え」と発案したわけでは、恐らくないでしょう。しかしジャニーズアイドル、即ちお稚児さんにこうした歌を歌わせること自体が、ぼくには何か悪質な冗談のようにしか思えません。
少年の視点で、「伯父さんは格好いい」と歌っていますが、これはどう見ても「老人が少年に欲情しながら、少年に愛される自分を夢想しつつマスターベーションをしている」歌ではないでしょうか。
そして、このぼくの嫌悪感というのを分析していくと、いつものオタク論に辿り着くわけです。
この歌で連呼されている「アメリカン・グラフィティ」というのがまず、象徴的。この「アメリカン・グラフィティ」そのものは一般名詞(即ち、「アメリカにおける人間模様」とでもいった意味)で使われているのか、同名の映画を想定しているのかは判然としませんが、いずれにせよここには反体制文化のカラーが色濃く表れています。
一般名詞だとしても、そもそも「グラフィティ」そのものが壁に描かれた落書きの意で、ヒップホップ文化と親和性を持っています。映画とするならば、これは60年代、まだベトナム戦争という「大人になるための通過儀礼」を終える前のアメリカを舞台にした青春(それも、青春の終わりを描いた)映画。
また、歌詞には60年代後半のロックンロールの名曲が挙げられ、伯父さんが「今のヤツらにはこうしたいい歌がない」と嘆く様が歌われていますね。
この「伯父さん」がいくつかは判然としませんが、いい歳のおっさんが昔を忘れられずに若者ぶっている様は、どう見ても醜悪奇怪です。
かつてのアメリカ文化を至高とする世代が、若者にそうした「サブカルチャー」を押しつけている……否、若者がそれを喜んでいる形を取りながら、実際には押しつけているじいさんの顔しか、この歌からは見えてこない。その老人はまさに、自分がレイプした男児のセコハンを、女性たちに卸す業務を続けていた、あの汚い老人と同じ顔をしているのです。
ちょっと歌詞を読み変えれば、どうでしょうか。
「平成ライダー観て喜んでる今の連中は可哀想だ、昭和ライダーのような男気を学ぶ機会がないんだから」。
そんなことをもしツイッターでつぶやいたら、いがでん氏以上に炎上してしまうことになるでしょう。
オタクの本質はニヒリズムにあります。自分の愛好する文化が、決して他者には理解してもらえないものであることに対する、諦念。そうした状況を常識としてしまっているぼくの目からは、この歌に歌われる「伯父さん」のドヤ顔は、極めて奇異な、奇怪なものに映るのです(そもそもいが氏の「女児を叩け」も、オタク文化を愛好する者は叩かれて当然、という大前提があるからこその発言であることに、『トクサツガガガ』を見て何かわかった気になっている人たちは、思い至るべきでしょう)。
岡田斗司夫氏は上の世代のカウンター文化が格好悪すぎるので、それに対するさらなるカウンターとして子供番組を観ていたのだ、と主張していたことがあります。これはオタク文化の発祥を、極めて端的に言い表しているといえましょう。
古株のオタクならばご承知の通り、80年代のオタク文化においては、「ビキニ型の鎧に身をまとった美少女が、怪物やメカと戦う」といった内容のビデオアニメが佃煮にするほどに作られておりました。「サブカルチャー」とはあくまで「青年」による文化でしたが、「青年」というものが肯定的に見られ得なくなった時代に、オタク少年たちは美少女へと自らを仮託し、怪物やメカと戦うという形で男性性を密かに開放していたのです。
90年代以降、恋愛ゲームの流行などを経て、男性性はなおのこと描かれることがなくなり(KEYの主人公など、比較的マッチョなのですが、それも『けいおん!』的な流行にとって代わられ)、近年では「バブみ」なんて言葉がはやり出しつつある、といった具合です。
しかし、こうした経緯を実体験しておきながら「オタクはマッチョだ」とか言ってしまえる東浩紀師匠*1って、やっぱ脳に水が詰まってるんですかね。
ともあれ、オタクというのは世代的にも、(そしてまた、多くがスクールカーストで下位存在であったろうという個人事情的にも)そこまでナルシシズムを断念させられた存在であったわけで、その目からこの歌を見ると、老人のナルシシズムを感じ、キモいと言わざるを得ないのです。
*1 東浩紀「処女を求める男性なんてオタクだけ」と平野騒動に苦言(その2)
――或いは、とも思います。
年少者が年長者を敬うというのは健全な姿かもしれません。ナルシシズムそのものもそれ自体は健全なものでしょう。
オタク自体に非はなくとも、その感受性自体が健全なものではないぞ、との反論も考えられます。まあ、男性性を過度に抑圧することが正しいとも思えないので、最終的にはそれが結論にはなるとぼく自身、考えますが、ここではそれは置いて、もうちょっとぼくたちが「男性性の断念」に至った過程について、見ていきましょう。
巷では「キモくてカネのないオッサン」などという言葉が流布しています。実際、ぼくたち(の世代)は、「おじさん」、「オッサン」というだけで問答無用でキモい、格好の悪い、ネガティブな、否定してしかるべきもの、とのイメージをまず、どうしようもなく持っています、しかし、そうした感受性は、かつては普通のものではなかったのです。
月光仮面などが歌で「おじさん」と呼ばれていることは有名です。ヒーローが青年になっていったのは「若者の時代」である70年代以降と言っていいでしょう。何しろハヤタ隊員ですら劇中では「おじさん」呼ばわりだったりするのですから。そして、(特撮ではいまだ青年が変身しているとは言え)、80年代以降、ヒーローは「少女」になった。
こうした男性の地位の失墜についてはあまりにも話が大きくなりすぎるので、詳しくは論じませんが、一つにはサブカル世代が上の世代へのカウンターを旨としてきたことが理由であることは、論を待ちません。彼らがフェミニズム(=ミサンドリー)と親和的であることもまた、それが理由です。
言わば、この歌は上の世代の権威を否定してきた者が、自分が年を取ると、平然と自分たちの権威を下の世代へとナルシシスティックに押しつけている、醜悪奇怪な姿が描かれた歌なのです。しかも、(日本人が作り、歌っているクセに)無邪気にアメリカを礼賛しているのもポイントです。岡田斗司夫氏は「サブカルは全部海外からの借り物」と指摘して、サブカル陣営から親の仇の如く憎まれたといいますが、少なくとも日本のサブカル連中が借り物文化を振りかざし、自分たちは何も生み出せず、目下はオタクに「間借り」しようとしているということは否定ができません*2。
そう、この歌そのものは「オタク文化」については全く歌われていませんが(まあ、アニメのopのカップリング曲であったことは見逃してあげるとして)、ぼくがここにことさらに「サブカル/オタク」の図式を見て取ってしまうのは、この「老人」のアメリカ頼みがあまりに空疎だからです。
*2 間違ったサブカルで「マウンティング」してくるすべてのクズどもに
ご承知の通り、日本のマスメディアでジャニー喜多川を批判する声は、ほとんど聞かれませんでした。もちろんそれはSMAPを例にとるまでもなく、ジャニーズが日本の芸能界にあまりにも強い影響力を持っているからでしょうが、もう一つ、サブカル世代を支持層とする左派がメディアを牛耳っているからでもありましょう。彼らはホモに盲信といっていい信仰心を抱き、彼らは決して過ちを犯さないのだと深く信じきっています。だから、その一端である(ごっちゃにしちゃ、ホモに失礼だと思うのですが)少年愛者にも、ひれ伏し続ける。
そして、その心性が彼ら彼女らが根底に持つ、男性への憎悪の裏返しであることも、何度か指摘してきたかと思います。そう、彼らは男である自分の性欲に深い嫌悪感を抱き、それを持たぬ男であるホモに「羨望」しているのですね。そしてまた露骨なエロ文化を持つオタクへと自分自身へのヘイトを「投影」している。もちろん、実際にはホモは性的にかなり放埒な部分があり、また少なくとも子供に手を出している少年愛者に擁護できる部分など全くないのですが、彼ら彼女らはそうした現実を絶対に認めることがありません。
しかしこうした心性って、少年愛者と、そしてまたこの歌とそっくりではないでしょうか。
ペドファイルとは、子供時代に「負債」を抱えた人です。その時にしておくべき「宿題」をすることができず、その「子供時代」からの借金取りの取り立てに苦しめられている存在です。
ちょっと抽象的でわかりにくい物言いかも知れませんが、まあ、その時期に十全に愛情を得られなかったとか、そういう感じでご理解いただいていいかと思います。
だからこそ、その年齢の子供に自分自身を見て、ナルシシズムの捌け口にする対象にしてしまう。彼らは子供を虐待しながら、「自分は子供を愛してあげている崇高な存在だ」と信じきっています。
これって、実際には弱者をいたぶることしかしていないのに、弱者なりマイノリティなりに自分自身を「投影」し、我こそはそうした人々を守る正義の味方なりとの自意識を振り回す左翼といっしょですよね。そう考えると、左翼が少年愛者であるジャニー喜多川を神の如くに称揚するのは当たり前、としかいいようがない。
そしてそんな、彼らの「ナルシシズムの捌け口として弱者を利用する」振る舞いに対する応援歌として、この歌は今こそ聴かれるべきなのでしょう。
……という辺りが結論で、まあ、いかがでしょうか。
■補遺■
「アメリカン・グラフィティ」を普通名詞か映画のタイトルかわからない、と書きました。しかしよく見ればわかることですが、二番の歌詞ではこれに対応し、「ウエスト・サイド・ストーリー」とありましたね。となると先のものも映画が想定されていることは自明でした。
後者の方も60年代のアメリカ映画で、こうしたものを邪気なく若者に押しつける感覚、やはり好きになれません。



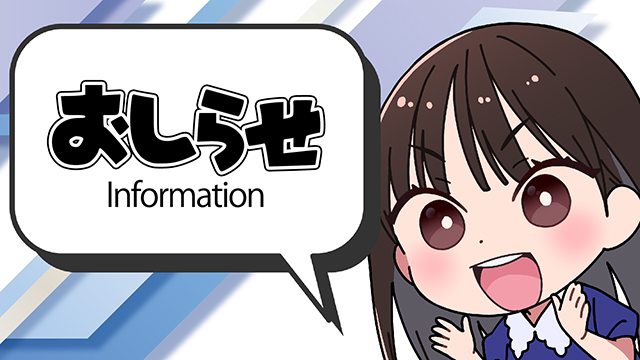

コメント
コメントを書く(著者)
四角佳浩様>
こんにちは(^^
>NAMBLAは体罰・強姦・誘拐に反対し、性的搾取にも反対している、とウィキペにはありますが、やはりというか必然というか
>買春の仲介や情報提供などを行う闇社会の団体と勘違いされていたことがあるというある種ロックな組織ではあります。
なるほど、体罰にも反対しているとは知りませんでした。
一応、「法的な筋を通してから子供とやろう」と言っているんですね。こそこそやるよりはまだ正々堂々としていてマシとも言えますが、逆に「子供とのセックスが本当にいいことであり、いつかは世間の馬鹿どもも俺たちの述べる真実に気づく」と考えているキチ○イであるとも言えます(もっとも、こそこそやっている日本のペドが子供とのセックスをいいことと考えていないかとなると、疑問ですが……)。
>NAMBLAの存在以上におかしなことだと改めて思わされますね……
そうですね。
喜多川を神の如く崇めつつ、「日本人は子供とのセックスを容認していない(キリッ」といくら言っても信用されるはずがありません。
(ID:5326147)
超お久しぶりです。
ジャニーズの中でも売れてない方のグループの知名度の低い曲をピックアップするセンスが面白いけど、確かにお稚児を可愛がる旦那様の視点って感じ…。
というかジャニーズのグループって冷静に見るとこれホントにいいのか?といった人たちも多く、その究極が光GENJIだったように思います。
またアメリカ文化への憧憬という視点も確かにありますよね。ジャニーズってアウトプットされたものは兎も角として、かなりブロードウェイとマイケル・ジャクソンからの影響が強烈ですし(あっ…)。
当時の「伯父さん」たちのアメリカへの憧れって世代的に仕方ないとしても、チェッカーズの頃はまだよかったけどTOKIOあたりになるとジェネレーション・ギャップで通用しなくなってきて、そのせいで売り上げ面では苦戦してましたから。長瀬というイケメンがいたにも関わらず。
なんか、ビジュアル的には90年代なのに音楽的にはアメリカングラフィティなバッドボーイズというギャップがあるらしく、そういえばSMAPもデビューした頃はなんか曲もビジュアルも痛々しくて、
レコード会社に任せたら一気に垢抜けたのがジャニーさんのセンスの限界を感じさせましたね。
(その方法論が90年代型の海外コンプレックスと言ってもよかった渋谷系文化だったのが悲しいところですが)
とはいえジャニーさんの遺志を継いだのがジャニーさんのお稚児趣味の権化みたいなタッキーであるところが少し不安もあるんですが…。
(彼のソロ曲でそのセンスが分かります)
とはいえ現在はすっかりジャニーズ1強時代は過去のものとなり、テレビに全く出なくてもCDを売りまくりドームツアーもできるK-POPが台頭していますが、
結局はK-POPだって花郎文化の亜種で、五十歩百歩じゃねーか馬鹿馬鹿しいという感じ。
彼らの人形のように整えられた要旨と非人道的な訓練を経て「製品化」されたパフォーマンスを見て喜ぶ女性たちを見ると、ジャニーズに無邪気に喜ぶ女性と同じようになんだかなぁという気分になります。
そう言うと女性たちはイケメンに嫉妬していると決めつけますが、彼らに憧れる男ってあまりいませんよね。むしろ同じ男として何だかかわいそうとまで感じてしまう。
>彼らは男である自分の性欲に深い嫌悪感を抱き、それを持たぬ男であるホモに「羨望」しているのですね。そしてまた露骨なエロ文化を持つオタクへと自分自身へのヘイトを「投影」している
これ、ツイッターでアイコンやヘッダを萌えキャラにしておきながらオタクを親の敵のように叩く連中そのものじゃないですか!彼らの萌えの動機そのものが単なる自己嫌悪であることはうすうす感じていましたが、そうなると叩きながらも二次元にょたいにハァハァする自分自身のことは何とも思わないのでしょうか…いや、思ってるからこそオタク叩きで晴らしているのか。
蛇足ですが「伯父さん」のような男を女から見た感覚が森高千里「臭いものにはフタをしろ」だったのかなーなんて思ったりもします。
(著者)
お久し振りです。
どうも、音楽には随分詳しいんですね。
ぼくは全然知識がなくて……。
しかしジャニーズはまず、何かリーゼントと化してて、80年代文化、まだまだアメリカの真似をしている感じの文化という感じがしますね。
TOKIOはバラエティタレント的に成功しましたが、やはり音楽としてはジャニーズそのものの感覚があの辺りで寿命だったんですね。
(まあ、テレビそのものの変質もありましょうが)
K-POPというのがまた強くなってるんですよね。
一時期は平成ライダーが幼児虐待老人からお稚児さんを助け出す、正義の味方となってくれていましたが。
>これ、ツイッターでアイコンやヘッダを萌えキャラにしておきながらオタクを親の敵のように叩く連中そのものじゃないですか!
二十年ほど前までは、こうした人たちがオタクのデフォでした。
みんながみんな、「オタクの中でも俺は違う、問題意識を持っているちゃんとした人間だ」と称し、他のオタクを見下していたんですよね。
本当、少数派に転落してざまあみろといった感じですw