 ゲーム妖怪ジーコの、創作小説とかブロマガとか。
ゲーム妖怪ジーコの、創作小説とかブロマガとか。
『不落の重装戦術家』 静かな日【終】
その日も、朝から静かな一日だった。
星明りが硝子窓を抜け、傷んだ木床を撫でるように照らす、静寂に支配された兵舎。歩くたび擦れる鎧の音を耳障りに感じながらも、軋む廊下の先、暗がりに溶け込む見慣れたドアは、いつもと変わらずに私を迎えてくれた。魔力を籠めながらゆっくりとドアノブを捻る。侵入者の形跡なし。誰もいないとわかっていながら誰にも聞こえないように漏らした溜息には、湿った土煙が混ざっているような気がした。
ドアの隙間から滑り込ませた照明魔法が、室内と調度品の輪郭を淡く浮かび上がらせる。普段ならランプのいくつかに火を入れるところだが、今はそれすらも面倒だ。努めて音を立てないよう後ろ手にドアを閉め、しかしその後は放り出すように身を椅子に預けると、【巡回警備】とだけ書かれ詳細は手付かずの報告書を机に投げつけた。
この記事の続きを読む
ポイントで購入して読む
※ご購入後のキャンセルはできません。 支払い時期と提供時期はこちら
- ログインしてください
購入に関するご注意
- ニコニコの動作環境を満たした端末でご視聴ください。
- ニコニコチャンネル利用規約に同意の上ご購入ください。
新着記事
- 『不落の重装戦術家』 静かな日【終】 5日前
- 『不落の重装戦術家』 静かな日【5】 1ヶ月前
- 『不落の重装戦術家』 静かな日【4】 2ヶ月前
- 『不落の重装戦術家』 静かな日【3】 3ヶ月前
- ニンテンドーミュージアムに行ってきたぞー! & それを語る放送を明日6日に予定! 3ヶ月前



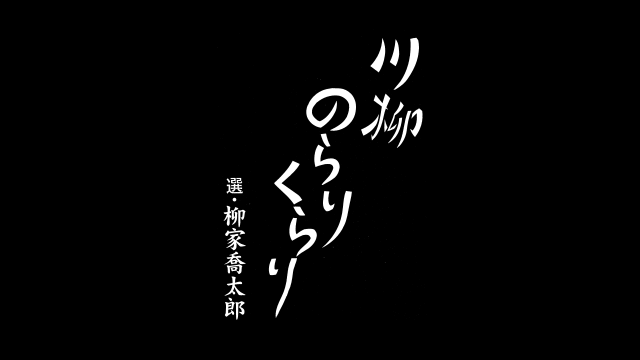

コメント
コメントを書く(ID:647161)
お疲れ様です!
あくまで「何も起きなかった静かな日」というわけですなあ…
(ID:10449601)
1エピソード完結お疲れ様です。
傍から見たら十分な事件簿でも、聖騎士団や『不落』さんとしてはよくある出来事、なんだろうな