***
話を聞くにしても、授業の合間の休みでは時間がとても足りそうにない。昼休みになるまで待つしかなかった。
もうすぐ四時限目になろうとしている。メルティが受け持つ現代国語だ。
ひとまずはあの魔女の授業がどんなものか、見定めようと思った。楽しみでもあるし、ちょっと怖くもある。
「先生の授業って、どんなの?」
前の席の御笠に尋ねてみる。よくぞ聞いてくれたとばかりに彼は微笑んだ。
「難しい言葉など何も使わず、時にはユーモアを交えた語り口で、聞く者を飽きさせないんだ。特徴としては、積極的に質問をしてくるな。ここはどう思うか、とか。生徒とのコミュニケーションを積極的に取ろうとする。いきなり雑学が入ったりもするし。教科書を読み、板書を書き留め、問題に答えるだけの授業ではないってことだ」
ふむ、と頷く。今の話を聞く限りでは、お固い感じではなさそうだった。
チャイムが鳴り響く。何かの教材だろうか。重そうな紙袋を抱えたメルティが入室してきた。
クラスメイトたちは彼女の授業をとても楽しみにしていたという風な顔で、めいめい着席していく。
「起立、礼」
授業前の号令はクラス委員長である崇城の仕事だ。今日これを聞くのは四回目。クールな声はとても心地よかった。
静まる教え子たちを前に、メルティはよく響く、けれどやっぱり幼い声で言った。
「さあ、二学期最初の授業だ。気合いを入れていくぞ……と言いたいところだけど、初日くらいは肩慣らし的に、のんびりとやるのもいいかと思う。国語があまり得意じゃないという転校生くんもいるわけだしな」
おおー、とおおげさに感嘆する生徒たち。さすが我らのメルティちゃん! なんて言葉が誰かから飛び出した。
「というわけで教科書もノートも開かないでそのまま。……それでは国語を好きになれる方法、まずはそこからみんなで考えてみようと思う」
教室全体を見渡すメルティ。キリッと真面目な顔だ。とはいえ幼さはそのままで、教育者としての雰囲気はさっぱりだったが。
「国語はすべての勉強、いや人生の礎そのものともいうべき大切なもの。言葉がわかるから、家族や友人と語り合えるし、スポーツができるし、仕事ができるし、恋人と愛を囁けるんだ」
意外とまともだ。零次はそう思った。国語……言葉がわかるからこそ何かをできるというのは、誰も否定できない事実だろう。
「でも、みんな普段はそこまで深く国語というものを考えていないんじゃないかな? 御笠、君はどうだ。国語は好きか?」
「おおう、参ったな~! 新学期で最初に指名されるとは感激の至り」
「他のクラスではすでに何人も指名してるんだけどね」
「ぐお、そうか、しまったあ!」
ひとり賑やかに叫ぶ御笠。メルティの授業のときはいつもこんな調子なのだろう。
「ぶっちゃけ中学までは嫌いだったっす。でもメルティちゃんの授業を受けてから、たちまち好きになりました!」
「私の授業がきっかけで好きになったというのは、ありがたいことだ。教師冥利に尽きるぞ。さて、ヒントを御笠が出してくれた。じゃあ今度はいいんちょに聞こうか。どうすれば学生は国語を好きになれるのか?」
「わかりません」
間髪を容れない即答だった。
国語が不得意なのかな? それにしたってほとんど考える様子がなかったのはどうだろうと零次は思ったが、メルティは軽く頷き、咎めることはなかった。
「メルティちゃんみたく、いい先生に巡り会えればいいんじゃないですか?」
「テストの成績がよかったらご褒美とか!」
「テレビ番組みたいにクイズ形式だったら……」
質問された生徒たちは自分なりに答えていく。頃合いを計ってメルティは言った。
「その答えはな、エンターテインメント的刺激を受けることだ」
「どういうことですか?」
誰かがすぐに問い返す。教師と生徒の頻繁なキャッチボールだ。
「ま、国語に限ったことじゃないね。歴女という言葉を聞いたことがあるだろう。戦国時代を題材にしたゲームなどの影響で、歴史好きな女性が増加したという話だ。同じような例は昔からある。漫画の『三国志』で中国の歴史に興味を持った人は、この日本にどれだけいるだろう? 学問の世界にも留まらないぞ。人気漫画がきっかけで一躍ブームになり、部員数が急増したスポーツもいくらか挙げられる。このように何かを好きになるには、脳味噌ばかりか精神にもビビッと来る、エンターテインメント的刺激が何よりも有効なんだよ」
ほー、と息が重なった。
なるほど、聞く者を飽きさせないというのは確からしい。説得力もある。
この人の授業は……かなり面白そうでいいんじゃないか? 零次はすっかり聞き入っている自分に気づいた。
「それでは深見!」
「は、はい?」
「国語を好きにさせてくれるようなエンターテインメント的刺激は、何から得ることができるだろう?」
満を持して、という感じにぶつけられた質問。
零次はうーんと唸る。御笠はメルティが教えるから好きになったと言った。彼にとっては、あの幼女教師そのものがエンターテインメント的だということになるのだろうが、今回は一般的な答えが求められるはず。
要するに、面白い文章作品があればいいのではないだろうか。
となると小説? いやさらに具体的に、若者受けする……。
「ライトノベルとか?」
「うん、よろしい」
メルティがパチパチ拍手する。どうやら理想的な答えだったらしい。ちょっと嬉しくなった。
「若者の活字離れなどと以前から言われているが、それは真っ赤な嘘だね。現在のライトノベル業界の充実ぶりは素晴らしい。魅力あふれる作品がたくさんあり、少年少女の読者が増えている。まあ書き手や出版社は熾烈な競争でヒーヒー言っているんだと思うけど、読み手にとってはこれほど嬉しいこともないはずだ」
零次は自己紹介で言ったとおり、小説よりも漫画アニメゲームというタイプだ。姉の本棚には一般小説に混じってライトノベルもあるが、読ませてくれと言ったことはなかった。
だが、嫌いというのではなく、なんとなく読まないというだけの話だ。そんなにいいのかな? 零次は生まれて初めてライトノベルに興味を持った。
「良質なライトノベルは、読者にこの上ない刺激を与えてくれるんだ。文章を読むことは、言葉とはこれほどまでに面白いのかとね。国語教師が百万の言葉を費やそうとも、たったひとつの物語に敵わないことがある。私もこの日本に来てから、多くのライトノベルを読んだ。若者向けなどとバカにはできない。優れた物語性、そして魅力的なキャラクターのなんと多いことだろう!」
そこでだ、とメルティは紙袋から一冊の文庫本を取り出した。
それはカラフルな表紙で……というか、なぜか刀を持った幼い女の子がドンと描かれていて……。
「先日FM文庫というライトノベルレーベルから出た『チヌことと見つけたり!』。これは非常に良質なロリっ娘が出ていてな、巧みきわまる文章表現で幼女の美と情感を描いていて……」
「なんでそーなるの!」
たまらず叫ぶ零次。
恐るべきことに、これまでの問答はすべてそのロリラノベを紹介するための前振りに過ぎなかったらしい。
「というわけでおすすめだから読め!」
メルティは次々に同じ本を紙袋から出す。こともあろうにクラス全員分、持ってきていたのだ。
勢いよく前から配られてきたそれを間近で目にして、零次はちょっとした頭痛を催した。とりあえず裏表紙の作品紹介を見てみる。
夜、芹沢有樹は怪物に襲われた。
わけもわからず逃げる彼の前に現われた、
華麗な和装をまとい、きらめく刀を振るう……幼女?
「いや普通は高校生とかじゃね?」
「小学生が悪を斬って何が悪い」
彼女の名前は雪宮チヌ。
波瀾万丈のロリ武士ストーリー、ここに開幕!
ヒロインがロリである必然性がどうにもわからなかったが、ニッチな市場をターゲットにした意欲作なのだろうと納得することにした。折り返しの著者紹介を見ると「真面目にヒットを狙って書きました」とある。なるほどライトノベル作家も大変のようだ。
「さあ、ライトノベル史上に残るロリを目に焼き付けるんだ!」
その言葉を合図に、ページをめくり出すクラスメイトたち。
隣を見ると、崇城もクールに読書を開始している。
ま、まあ、読むだけ読んでみよう……案外面白いかもしれないし。零次は頭を真っ白にして臨んだ。
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。



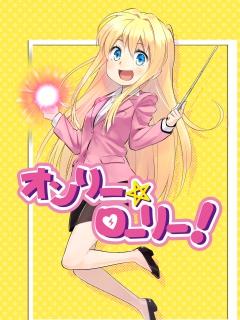

![mitsu&ヒィロ(ν[NEU])×seek(Psycho le Cému / MIMIZUQ)対談インタビュー!第2回(全2回) 『バグサミのあともサプライズライブをやったり……(ν[NEU]の)活動は見ていて面白い。(seek)』](https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/blomaga/material/channel/article_thumbnail/ch1047/2205217)