
以前紹介した「【分析】カメラワークでわかる『羊たちの沈黙』の名シーンでの力関係」や「テレビも映画も苦戦するネット/テキストメッセージの表現の正解は ...」の動画を作った「Every Frame a Painting」のトニー・ゾウさんが、今度は「ジャッキー・チェン映画はなぜこんなに面白いのか?」を分析したとSploidが伝えました。
これを見たら、ジャッキー映画が見たくなること間違いなし! インタビューに応じるジャッキーの発言に感動するあまりに、作品を全て集めたくなるかもしれません。
【大きな画像や動画はこちら】
アクションが得意なフィルムメーカーもコメディが得意なフィルムメーカーも存在しますが、過去40年間に渡って、その両方を得意としてきたのは香港が誇る映画俳優/監督のジャッキー・チェン。近年、面白いシーンと格闘シーンを合わせたハリウッド映画が多くみられるようになりました。しかし、いい作品だとしても、コメディとアクションは全く異なる方向性とスタイルに感じられます。
だからこそ、ジャッキー・チェンは特別と言えるのです。彼の映画は「アクションはコメディ」というスタイルを取っており、面白いクセに強いというキャラクターを描くことに成功しています。
というわけで、ジャッキー・チェンのアクション・コメディの原則を紹介していきたいと思います。
■自分に不利な状況を与える

ギリギリな戦い
ジャッキーはどんな映画でも自分に不利な状況を作ります。靴が無い、手を縛られている、爆弾を咥えさせられている...といった具合です。そのような設定を作ることによって、ジャッキーは道を切り開くために奮闘しなくてはならなくなります。
彼の個々のアクションに対しては、論理的なリアクションが発せられます。観客はその論理的なやりとりを見て面白いと感じるのです。このような方法はサイレント映画の時代から存在し、チャーリー・チャップリンやハロルド・ロイド、バスター・キートンなんかが得意としていました。ジャッキーもこういったダイアログに従っていると考えられます。
■周囲の物を使う

武器は身近なモノ
ジャッキーはとても想像力が豊かです。周囲にある馴染みのものを使って、馴染みのない展開にするのです。彼の周りにあるものは何でも武器になります。椅子、ドレス、箸、キーボード、レゴ、冷蔵庫、そして脚立...。ジャッキーのそれらを使った戦いは自然で基せているだけでなく、誰にでも起こりうることをジョークにして見せているのです。
■画面の中で自分を見えやすくする

自分がよく見えるようにすることが大事
ジャッキーはオシャレさを追求するがあまり、画面全体を暗くしてファッションまでダークカラー中心のモノトーンにするといったことはしません。彼は、敵が黒を着用すれば、自分は白を着る。敵が白であれば、自分はカラフルにするといった「画面上の自分の見えやすさ」を意識しています。
また、アクションシーンのカメラワークにおいても、分かりやすさを追求しています。例えば、スタントマンが二階から落ちるシーンで、螺旋階段が映し出されますが、それは2秒後に螺旋階段を使ったアクションがあるからです。
それだけでなく、ジャッキーはカメラを手で持って振り回したり、ドリーを使うことも滅多にありません。
「アメリカの映画はカメラが頻繁に切り替わりますが、それは俳優がどうやって格闘するのかを知らないからです。」とジャッキーチェン。カメラが激しく振られるのは、アクションをより白熱しているように見せたいが為です。アクションができるジャッキーの場合はそんな小手先の技術に頼る必要はありません。

「僕はカメラを絶対に動かすことはしません。」
「いつだって広角で設置したままにしておきます。観客に僕がジャンプしたり落ちたりする様子を追えるようにしているのです」
■アクションとリアクションが同じフレームに収まっている

動きだけでなくカメラも。
カメラを動かさないことの利点は、ジャッキーの超人的な動きを観客が余すところなく楽しめるというだけではありません。アクションとリアクションを同じフレームに収めることができるのです。例えば、『ポリス・ストーリー2』(1998年)の壁に囲まれた通路でジャッキーがトラックに追われるシーンでは、一連の動きとその位置関係が全て見えるようになっています。
同様の撮り方のシーンが『ラッシュアワー3』にも登場しますが、カメラが切り替わってしまい全てを通して見ることはできません。また、この原則はアクションだけでなく、コメディにも適応されます。
サモ・ハン・キンポーが敵をパンチすると、後ろにいたジャッキーにも被害が及びます。同じようなことが『シャンハイ・ヌーン』でもありましたが、アクションとリアクションはバラバラに撮影されています。確かに面白いのですが、ひとつの画面で見れるほどではありません。
■必要あれば何度でも撮影しなおす

何度も何度も撮影をやり直します。
ジャッキーは完璧主義者でもあります。香港では、スタジオのサポートもありアクションの撮影に1ヶ月も時間を割くことができます。そのため、完璧なアクションが取れるまでに幾度となく撮影を繰り返すことが可能です。
「1番難しかったのは大きな扇子を飛ばして再び自分の所に戻って来させるというものです。これには120回以上もリテイクしました。こういったシーンを見たら、観客は『ジャッキーはすごい‼︎』となりますが、そうではなくて誰にでも出来るのです。ただ、本気で集中するかどうかの違いです。」
ジャッキーは非常に難しいように見えることを小技として入れてきます。本来ならばやらなくてもいい上に、すぐに成功しなければ無駄に予算を食うことでも、ジャッキーはあえてやるのです。
ジャッキーは「アメリカの映画では絶対に許可してもらえません。彼らは予算の管理に厳しいのです」と話しています。
■ 観客にリズムを感じさせる

リズミカルに
アメリカの映画が理解していないことのひとつに、「リズム」が挙げられます。動きにもショットにも、編集にさえもリズムが存在しているにも関わらず、それが無下にされているのです。
一方、ジャッキーは音楽的リズムを非常に大切にします。そして、それは熟練のマーシャルアーツ・パフォーマーにとっても容易ではありません。ジャッキーは初期の作品でもチャイニーズ・オペラのようなリズムを披露しているのがわかります。80年代中盤になるとお抱えのスタントチームと演じるようになり、その動きは独特なものになりました。
しかし、アメリカでは監督も編集者もこのリズムの大切さを理解していないのです。彼らはひとつひとつの攻撃に合わせてカットしてしまうので、観客はリズムまで楽しむことができません。香港の場合、観客がリズムを掴むまでカメラを固定したままなのです。
■編集で、「ふたつの良い絡み=ひとつの素晴らしい絡み」にする

はっきりと攻撃が見えるようにします。
「最も重要なのは編集です。しかし、ほとんどの監督はそれを知りません。スタントコーディネーターでさえ編集の仕方を理解していないのです」
ジャッキーやサモの撮り方にはある法則が見られます。それは、最初のショットで敵との絡みを見せ、次のショットではその攻撃がはっきり見えるまで近づくというもの。この2つめのショットは、1つめのショットの最後よりもフレームを巻き戻した所から始まります。その2つのショットを繋げることで攻撃の「強さ」を演出することが可能になるのです。
対照的に、現代のアメリカ映画では1つめの攻撃のギリギリの所で切り、肝心の攻撃の部分で次のショットをつなげるため攻撃が感じられないようになっています。これは、一般的に、PG13に対応させるための策だと考えられていますが、昨今ではRレーティングの映画でも同じようなことが見られるのです。そのため、一連の格闘シーンは「痛みを伴う戦い」ではなく、単に飛び回っているだけに見えてしまうのです。
■痛みは人間味を感じさせる
ジャッキーの映画には「痛み」が登場し、それが笑に繋がっています。彼は、例えどんなに鍛錬された役を演じようとも顔面に攻撃を食らうといったシーンを入れるのです。

春麗のコスプレ
また、ジャッキーの表情豊かな顔は素晴らしい道具でもあります。戦いの間じゅう鶏を抱いていた時も、春麗のコスプレの時も、彼の表情はユーモアに一役買っています。
■諦めないことで得られる「フィニッシュ」
ジャッキーの映画は、先の項目で触れたように、不利な立場から始まりますが、観客に胸がスッキリするような「フィニッシュ」を与えてくれます。それは、彼が「最強」だからではなく「諦めない」からなのです。だからこそ、フィナーレが感動的で面白いのです。
対照的なのがアメリカ映画です。フィナーレは「誰かが現れて射殺したから⁈」 開いた口が塞がりません...。
最後に、トニーさんは次のようにまとめています。
ジャッキーの映画から学べることは、アクションとコメディが全く方向性の違うジャンルではないということです。どのジャンルでも、視聴者は「最高の演技」を求めているのです。残念ながら、現代の多くのアクション映画監督がそのことを失念している、もしくは理解していないように感じます。これらの俳優は芸術家なのです。
それを理解していない監督が撮った映画をお金を払って映画館に見にいく必要があるのでしょうか? 観客が求めているのは「アクション」なのに。
「何をするにしても、ベストを尽くさなくてはいけません。映画は一生残るのですから。雨だったから、俳優に時間がなかったからなんてことをひとつひとつの映画館に行って観客に説明するのですか? そんなことできないでしょう。観客は良い映画を見に映画館に足を運ぶのです。ただそれだけのこと。」とジャッキーは力強く語ります。
まさしくその通りです。これらの作品は永遠にエンターテイメントとして愛され続けるでしょう。
[via Sploid]
(中川真知子)
関連記事
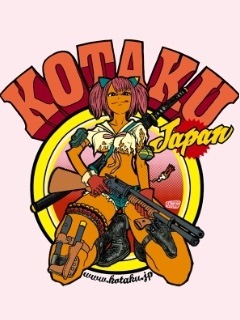



コメント
コメントを書く