
もしかしたら、22世紀には、動物や昆虫が国家の安全を担う重要な任務に就くかもしれません。今日は、サイエンスジャーナリストのエミリー・アンセス氏の新刊、 『Frankenstein's Cat』という本を紹介したいと思います。この本には、将来的に、動物達はハイテクを埋め込まれたエンジニアになるかもしれない、という興味深い内容が書かれているんです。
それでは、 『Frankenstein's Cat』から「Robo Revolution(ロボット革命)」の章を引用しましたので、以下からお楽しみ下さい。
【大きな画像や動画はこちら】
---------------------------------------
1960年代、CIAは特殊任務の為に、ある動物をリクルーティングをしました。それはネコ。局が用意した獣医が、1時間の手術でそのネコの外耳道にマイクロフォン、頭蓋骨に小さなラジオトランスミッター、そして細いワイヤー式アンテナを灰色と白い毛に紛れ込ませるように埋め込み、エリートスパイにしようと試みたのです。これは、トップシークレット扱いされていた「オペレーションアコースティックキティ」計画。ネコを「歩く監視マシン」にしようとしていたのです。このプロジェクトのリーダーは、訓練したネコを海外の官庁職員の側に座らせ、プライベートの会話を盗聴しようとしていました。
問題は、ネコは訓練に向いている動物では無いこと。彼らには、犬のように飼主に従いたいという気持ちがありません。そして、エージェンシーのロボキャットは残念なことに国家安全に興味が無かったのです。初の公式テストで、CIAの職員がアコ−スティックキティを公園に連れて行き、ベンチに座っているふたりの男性の会話を拾って来るように指示しました。しかし、ネコは道路へ迷い込み、タクシーにひかれてしまったのです。
結局、このプログラムの続行は断念せざるおえなくなりましえた。CIAは、その当時の様子を「私たちは、訓練したネコが我々の求めるニーズには向いていないという事が分かった」と言葉を選びながら書き残しています。
50年前にCIAが開発しようとしていたオペレーションアコースティックキティは、穴だらけの計画のように聞こえますが、実は先見の明があったのです。今日、アメリカ政府は再び国民と国を守るために動物とマシンのハイブリッドに興味を示しています。具体的に言うと、2006年に国防高等研究計画局(DARPA)は昆虫に狙いを定め、国の科学者達に「昆虫サイボーグを開発」するようにと言い渡しました。
まるで冗談のように聞こえますが、これは真面目な計画です。数年に渡り、米軍は危険な地域で監視を行うことが出来る極小の飛行ロボット「マイクロエアービークル」の開発を望んできました。このマシンの作成は容易ではありません。それは、飛行のダイナミクスを極小サイズで変化させること、そして飛行可能な軽量化を実現させること、そしてカメラやその他の機械を搭載させるだけの強度をクリアすることが必要だからです。最も難しいのは、マイクロエアービークルを長時間飛ばせるだけの電源をどうするか。試行錯誤の末、研究者達は羽を開いた状態で6.5インチ(約16.5センチ)、最長飛行時間は11分という「ザ・ナノ・ハミングバード」でした(ちなみに、DelFly Microは4インチ(約10センチ)以下で3分間空中に滞在することが出来ます)。
このザ・ナノ・ハミングバードを見たDARPAの職員は、他にも良い案があるに違いないと感じていました。「小規模飛行マシンの存在は、自然界に昆虫がいることでも証明されている。」とDARPAのプログラムマネージャーでありコーネルエンジニアのアミット・ラル氏が、未来を担う研究者達に向けて発行する小冊子の中に記しています。昆虫は生まれながらにして飛行するように出来ており、障害物も避けて飛ぶ事が出来ます。そして、なにより自力で動きます。ハエは何時間でも飛び続けることが可能です。
おそらく、DARPAの職員は、1から作る必要は無いということに気付いたのでしょう。もし、彼らが昆虫を使うのであれば、その時点で夢の飛行マシンの作成は折り返し地点まで来ているようなものです。彼らがやらなくてはならないことは、いかにして昆虫の体をハックし、動きをコントロールするかということです。科学者がそれを解決することが出来たなら、DARPAの小冊子に書かれた「昆虫を、我々が求めるデバイスにすることが出来たなら、危険区域や敵対領域への進入が必要なミッションに使えるようになるだろう」という言葉が現実になるかもしれません。
DARPAが出した課題は、世界中の科学者達を沸かせました。局は研究者達を集め、いかにして操縦可能な昆虫サイボーグを作るかを提案させました。そして、最も優秀なプロジェクトには資金を提供すると約束したのです。局が求めていたのは、5メートル離れた場所から遠隔操作できる昆虫で、最終的にはマイクロフォンやカメラ、もしくはガスセンサー、監視装置を搭載し、集めた情報を軍当局に持ち帰らせたいと考えていました。そうすることで、離れた場所にあるビルや洞窟から爆薬を検出したりすることが出来ます。それ以外にも、このサイボーグにビデオカメラを搭載すれば、建物に敵が潜んでいるかを偵察させる事も可能です。その上、会話を盗聴することが出来れば、対策を練る事も出来るでしょう。DARPAが求める操縦可能なロボット昆虫は、現代の科学技術を持ってすれば不可能ではないように思えます。あのアコースティックキティよりも現実的です。
DARPAの昆虫サイボーグの課題は、カリフォルニア大学バークレー校の電気技師、ミシェル・マハービッツ氏の興味を誘いました。彼は、生体の脳を電子ビット/バイトと融合させる飛行マシンの製作に強い関心を示したのです。「私がやりたいと考えていたことは、遠隔操作飛行機の製作でした。遠隔操作飛行機に最も近いもの、それが甲虫だったのです。」と、当時を思い返してマハービッツ氏は語りました。
マハービッツ氏は、小型電子機器のエキスパートでしたが、昆虫学に関しては全くの素人でした。そこで、彼は昆虫の研究を始めたのです。そして、多くの科学者達が、DARPAの課題にハエやガを採用していた中で、マハービッツ氏は甲虫こそが最適だという結論に至ったのです。ハエやガと比較しても、甲虫は硬い甲羅に包まれていて頑丈です。加え、多くの個体が貨物を運ぶに足りる大きさです。欠点は、科学者達はカブトムシの飛行に関与する特定の神経経路と脳の回路について、あまり知らなかったことです。
すなわち、第一の課題は昆虫の生態を解明することでした。マハービッツ氏と、彼のチームは何種類かの甲虫を調べ、最終的に、鋭い爪と額にサイのような角を持つ2インチ(約5センチ)程度のハナムグリという甲虫が最適だという結果に落ち着きました。試行錯誤の末、彼らはこの甲虫の視葉の元にある脳に、有望な領域を見つけました。これまでの研究で、この領域の神経活動は昆虫の羽の発振を保つのを助けることが分かっていました。しかし、マハービッツ氏のチームは、この脳の領域を正しく刺激すれば、甲虫の飛行を開始させたり停止させたりすることが出来るということを発見したのです。彼らが、その部分に急速な電気信号の系列を送ると、甲虫は羽をはばたき始め、離陸の準備をしました。また、同じエリアに単一の長いパルスを送ると、甲虫は羽の動きを停止させました。効果は抜群で、甲虫は飛行中でも羽の動きを止めるので地面に落下するほどでした。
これらのトリックを見つけた後、マハービッツ氏は飛行マシンの構築に取り掛かりました。ハナムグリのトランスフォーメーションは冷凍することから始まりました。冷たい空気の中にハナムグリを入れると、体温を下げる事が出来ます。そうして固定し、麻痺させるのです。それから、マハービッツ氏とそのチームは冷凍したハナムグリの外骨格に針を刺し、脳と視葉のベースに直接小さな穴をあけ、個々の穴に薄い鋼線をねじ込みました。
そして、ハナムグリの体の両側にある基翅節片筋(きしせっぺんきん/羽を推力を調節する役目を担う)にも穴をあけました。研究者達は、ワイヤで右の基翅節片筋を刺激し、右の羽をより力強く動かすように促しました。すると、ハナムグリは左側に向きを変えました。次に、別のワイヤーで左側の基翅節片筋を刺激し、右側に向きを変えさせました。穴から出ているワイヤーの端は、ハナムグリの背中に蜜蝋で固定された電子機器バックパックの中に差込まれています。この背中に固定された電子機器バックパックには、ハナムグリの中に埋め込まれたミニチュアラジオレシーバー、カスタム構築のサーキットボード、そしてバッテリーにワイヤレスで信号が送る装置が含まれます。
試験飛行の当日。マハービッツ氏のチーム研究員のひとりが、ラップトップで特別にデザインした「ビートルコマンダー」ソフトウェアで信号を送りました。ハナムグリの背中の機械から飛び出たアンテナが、メッセージを受信し、サーキットボードを介して視葉に信号を送りました。すると、ハナムグリは羽をはばたかせ、ブンブンと音をならしながら飛びたちました。ハナムグリは自力で飛んでいます。「飛ばせること」に関しては、人間は手を加える必要はありませんでした。そして、部屋を飛び回っている時に、研究者が基翅節片筋を刺激するとハナムグリは、まるで目に見えない迷路を通っているかのような動きを見せました。それは、航空ショーでパイロットが見せるスタントのようでもありました。視葉に別の信号を送ると、ハナムグリは空中で動きを止め、タイル張りの床に落ちてしまいました。
マハービッツ氏が彼の研究の成果を披露するやいなや、「サイボーグ昆虫軍設立に一歩前進」や「米軍の資金援助の研究のお陰で、スパイは実際の昆虫を使って貴方の会話を盗聴するようになるかもしれない」等というニュースが猛烈な勢いで発信されました。コラムニスト達は、致命的な細菌をばらまくビークルとして、この昆虫の大群が使用される可能性を予測。「ゾンビ化された甲虫」や、「差し迫るロボット対人間戦争」等も話題になりました。このような状態について、マハービッツ氏は、マスコミに「この作品に対する世間の非常に大きな関心は、予想の範疇だった」と述べました。
昆虫は人工的に変形させなくても複雑怪奇な形状をしており、まるでエイリアンのようです。マハービッツ氏は、「元々、昆虫はウサギには無いようなサイエンスフィクションの要素があります」と話しており、小型の電子機器を加える事によって、飛行装置や動物とマシンのハイブリッド、そして秘密軍事作戦に従事するという夢のような事柄も実現できるかもしれないと説明しています。と同時に、マハービッツ氏は、彼の甲虫は「政府の邪悪な陰謀に違いない」というメディアの報道に苛立ちを覚えていました。メディアは、米国政府がこの甲虫を殺人昆虫軍隊や自国民へのスパイ行為を行うために使おうと計画している可能性があると考えたのです。
「そんなの馬鹿げています。」とマハービッツ氏。彼の甲虫はフィールドに送り出される段階にも至っていません。そのような展開を迎える以前に、改良する必要があるのです。しかし、展開する時が来るとしたら、マハービッツ氏は海外での軍事作戦で使用されるだろうと予測しています。勿論、国民の為にも利用出来るでしょう。
例えば、大地震で多くの人達が瓦礫の下に閉じ込められてしまう等の被害にあったとします。そうなったら、甲虫に温度を感知するセンサーを装着して被災地に飛ばし、人間の体温に近い温度を感じ取ったら、その情報を救助隊に伝えるようにすれば良いのです。救助隊は、闇雲に探すのでは無く、ピンポイントで生存者のもとに駆け付けることが出来るでしょう。どんな分野での活躍にしろ、未来の昆虫コマンダー達は、単なる甲虫の域には留まらないのです。
今 マハービッツ氏は、彼が最も難しいと考える「遠隔操作のハエ」に着手しています。「ハエは非常に小さく、筋肉が集中しています。そして、何より全てのパーツが小さいのです。」とハマービッツ氏。電子装置を埋め込むだけでも至難の業でしょう。また、マハービッツ氏のハナムグリの他にも中国の研究チームは、ミツバチの飛行を開始および停止させることに成功し、DARPAのプログラムを率いるエンジニアのアミット・ラル氏は操縦可能なサイボーグのガを生み出しました。
それでも、ロボット昆虫は任務に付く段階ではありません。方向制御はまだかなり粗雑です。最終的には回転したり、35度左に傾けたり、または煙突やパイプといった複雑な三次元空間での移動等、左右に方向を向けさせる以上のことを可能にしたいと考えています。また、監視装置の問題も残されています。これまでの主な焦点は、昆虫を操作することにありました。しかし、有用なサイボーグにする為には様々なセンサーを搭載し、確実に周囲の情報を集め、運んで来る必要があるのです。そして、サイボーグ昆虫に搭載した監視機器を動かすエネルギーをどこから得るかということも課題となっています。
興味深い可能性のひとつとして、昆虫の羽を動力源とすることがあげられています。2011年、ミシガン大学の研究チームが、セラミックと真鍮から小型の発電機を構築することで、それを達成したと発表しました。それぞれの小さな発電機は平らなスパイラルで0.2インチ(約0.5センチ)程度。それを甲虫の胸部に装着して、昆虫の羽の振動を電力に変換させるというものです。研究者の話では、幾つかの改良を加えれば、これらのエネルギー収穫装置はサイボーグ昆虫に装着した機器に使用することが出来るそうです。
昆虫が、サイボーグ昆虫になれば、空を飛び回り、危険を示す兆候を調べることが出来るでしょう。しかし、地上の任務になれば、サイボーグ昆虫はその力を発揮することが難しくなります。そこで注目したいのが、ニューヨーク州立大学のラボで生み出された遠隔操作のラットです。
私たち人類は、長年にわたってラットの脳を研究してきました。神経科学者達は、しばしば、げっ歯類の頭蓋骨に直接電気信号を送り、特定の反応と行動を引き出そうとしてきました。通常この研究をする場合、ラットをケーブルで機械に繋げ、その動きを制御するのが一般的です。しかし、神経科学者のジョン・チャピン氏率いるニューヨーク州立大学のチームは、ワイヤレスで操作出来る装置を編み出したいと考えました。そのようなシステムがあれば、研究者とラットを面倒な実験装置から解放し、科学に新たな光をさす事が出来ると思ったわけです。
ワイヤレスシステムがあれば、科学者は自由に動き回るラットの動きと行動を操り、地上での特殊任務で活躍させることが出来るでしょう。ラットの嗅覚は非常に繊細のため、サイボーグラットに地雷の匂いを嗅ぎ分ける訓練を受けさせれば、フィールドに放って地雷探査に従事させることも可能です(ラットは体重が軽いので地雷を踏んでも爆発させる心配はありません)。
また、マハービッツ氏が考えるサイボーグ昆虫の仕事に類似していますが、サイボーグラットなら、人間が入る事の出来ない倒壊した建物の中に入り、瓦礫の下に閉じ込められた人間を探すことも不可能ではありません。「ブラッドハウンドドッグが這ってでも入る事の出来ないような狭いスペースにも行けるでしょう。」と、当時、ニューヨーク州立大学のチームに所属していた神経科学者のリンダ・ハーマー・ヴァッツクーツ氏は語っています。
しかし、それらを実現させる前に、ニューヨーク州立大学の科学者達は、どのようにしてロボットラットを作るのか? という方法を見つけ出さなくてはなりませんでした。まず、ラットの頭蓋骨を開き、脳に鋼線を埋め込みました。そのワイヤーは、脳から頭蓋骨に開けられた大きな穴を通り、ラットの体に装着されたバックパックの中に差込まれました(ハナムグリの時もそうでしたが、この「バックパック」は必要不可欠のようです)。このラットが背負うバックパックには、マイクロプロセッサーや、遠くの信号を拾うことが出来る受信機を含む電子機器が入ります。この電子機器は500ヤード(約450メートル)離れた所からでも信号を受信し、マイクロプロセッサーを介してラットの脳に指示を送ることが出来ました。
動物の行動を管理する為に、科学者は感覚を処理する場である体性感覚野に電極を移植。大脳皮質に電気ショックを与える事で、ラットは左側の顔を触られているような感覚を覚えます。大脳皮質の違う部分を刺激すると、右側の顔を触られているような感覚を覚えます。この最終的な目的は、ラットが触られたと感じた側とは反対の方向に回転させることでした(これは直感に反するように聞こえますが、ラットは本能で顔の右側を触られると、それを避けようと左側に逃げる習性があります)。
それと同時に、ニューヨーク州立大学の科学者達は型破りなシステムを導入しました。ラットが正しい方向に回転すると、研究者達は第3のワイヤーで内側前脳束(medial forebrain budle、MFB)に電気パルスを送るのです。人間や他の動物での研究では、内側前脳束を直接活性化させると気分が良くなるという事が明らかになっています(科学者が、ラットにレバーを押す事で自分の内側前脳束に刺激を送れるという実験をしたところ、20分で200回もレバーを押したという結果も出ています)。つまり、ラットの内側前脳束に刺激を送る事は、ラットが仮想の褒美を与えていることになるのです。
このセッションを10回行ったことで、ロボットラットは正しい行動をすれば、褒美が与えられるという事を学びました。科学者達はラットにハシゴを登らせたり、狭い板張りの坂を横断させたり、階段の下に身をよじらせたりと、挑戦的な障害物のコースを導く事に成功しました。最終のデモンストレーションでは、現実社会で与えられるであろう捜索救助作業をロボットラットでシミュレーションを実行。研究者は自分の腕をティッシュで擦り匂いをしみ込ませ、ネズミに嗅がせることで人間の匂いを覚えさせました。そして、分厚いおがくずを敷き詰めたプレキシグラスのアリーナの中に、人間の匂いがしみ込んだティッシュを隠したところ、ロボットラットをその中に放つと、1分以内にティッシュを見つけ出したのです。
また、科学者は内側前脳束に褒美を貰ったラットの方が、エサを褒美として与えられていたラットよりも、早くティッシュを見つけたことも発見したのです。ハーマー・ヴァツクイーツ氏はこのシミュレーションの結果を見て、「ロボットネズミは信じられないほどモチベーションが高く、また非常に正確でした」と語っています。
---------------------------------------
この続きが気になる方は、『Frankenstein's Cat: Cuddling Up to Biotech's Brave New Beasts』でどうぞ。
Excerpted from Frankenstein's Cat: Cuddling Up to Biotech's Brave New Beasts by Emily Anthes, published March 2013 by Scientific American / Farrar, Straus and Giroux, LLC. Copyright © 2013 by Emily Anthes. All rights reserved.
[via io9]
(中川真知子)
関連記事
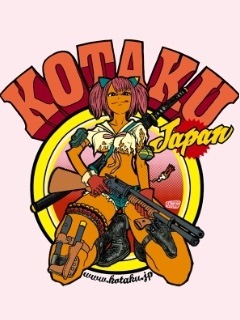




コメント
コメントを書く