徹さんの真実
裁判員裁判を終えた三十七歳の私に、香水をつけた便箋を送ってきた男性がいた。この小説を書くきっかけを与えてくれた出版社の二木さんからの手紙だった。新緑の美しい季節に、彼は本と共に、読書の感想のやりとりもできたらいいですね、という趣旨の文章を書いた手紙を添えて送ってくれたという。
残念ながら、私はこの贈り物を受け取ることができなかった。彼が送ってくれたものが届いた日に、私は拘置所の統括という役職の偉いおじさんに呼ばれて説明を受けた。香り付きの物は交付できない。紙片の匂いが本にも移っているので、宅下げか廃棄してほしいと言われてしまったのだ。手紙だけではなく、その時に同梱されていた物は全て、渡せないという。
この経緯と、高校時代交際していた彼が、いつも手紙に香水をつけて送ってくれたことや彼は香水のつけ方にもこだわっていたことを懐かしく思い出したという話を書いて、返信した。
すると二木さんはすぐに返事をくれた。
「僕の場合は慣れていないもので、便箋に文字を書いた後で香水を振りかけたら、見事に字が滲んでしまいました……」
と、書かれてあったので、どんな具合なのか気になった。
私は職員に、一目で良いから見せてほしいと相談すると一見後、手紙は領置、本は廃棄するという約束で願いが叶った。
統括殿がジッパー付きのビニール袋に個別に密封された便箋と本をテーブルに並べたその部屋は柑橘系の香りが充満していた。ジッパーを開けるまでもなく確認できる匂いの強さに、
「これは凄いですね」と、私が言うと、
「本人がそう感じてくれて良かった」と、統括殿は安堵なさった。
二木さんからの手紙は、ちょっと感心する程に、それはもうばっちり文字が滲みまくっていた。
彼が一番好きだというその香りを私に伝えようとする優しい心遣いと、文字を書いた便箋の全面に香水を振り掛けるという無謀なことをする若さと愚直な熱さに胸を打たれた。
この香水付き紙片を見た時には、まだ彼と会ったことがなかった。彼はそれまでにも何度か拘置所を訪れ、文房具の差入れをしてくれていた。
香水付きの手紙が届いた一ヶ月後に対面を果たし、内密に親密な交流を始めた半年後に、彼は脳出血で倒れ、入院した。リハビリ施設のある病院に移ったのは、2012年(平成二十四年年)の末だった。
寒に入ってから、手紙が届いた。そこに綴られていたのは間違いなく彼の言葉だったけれど、少年時代の彼が左手で書いたような弱々しい筆跡と誤字、脱字だらけの短い文章を見て、私は涙を抑えられなかった。
その手紙が届いた日に、映画監督の大島渚の訃報が流れた。彼は、ロンドン滞在中に脳出血で倒れ、右半身の麻痺と、歩行と言葉の自由も失い、十七年間介護生活を送っていたということを、二木さんの代わりを務めて下さっている早川さんが送ってくれた雑誌で知った。妻で女優の小山明子に付き添われ、リハビリしている大島渚の写真を見ては、二木さんもこんな風にリハビリをしているのかしらと想像して、切なくなった。
一月末には退院予定だった二木さんが、立春になっても入院している中で、私は徹さんのことを思い出している。
高校卒業後の進路について、父は、「東京の予備校に通ったらどうだ」と提案した。地縁・血縁の強い田舎では雑音がうるさくて受験勉強に集中できないだろうという。
「私は浪人はしたくない。五教科七科目の東大を目指してるわけじゃないのよ。三科目の成績さえ良ければ入学できる私大受験ために、浪人するなんて恥ずかしいわ」と、答えた。
正直言って、勉強する気力が残っていなかった。
大学や予備校に通うわけでもないのに上京するというのは、父としても示しがつかないだろうと思い、学校の進路指導室にある求人票のファイルから東京の企業を一つ見つけた。槇原敬之の『どんなときも。』をCFソングにしたことが印象に残っていた。
七十年にアメリカのファーストフードチェーン店企業と三菱商事の合弁で設立した会社だという。この会社が運営するフライドチキンチェーン店と宅配ピザチェーン店の店長候補を募集しているらしい。
入社試験の期日は過ぎていたのだが、大学の入試とは違うのだから一斉にする必要もないだろうと思い、直接人事課に連絡してみたら、学校推薦があれば、個別に入社試験を実施してくれるという。学校推薦は簡単に得ることが出来た。試験日が指定され、すぐに飛行機のチケットを予約した。
隣町の空港から東京への直通便に乗ると、羽田空港では人事担当の田代さんが出迎えてくれた。田代さんは紺色のツーピースを着た小柄な女性だった。ローズピンクの口紅を塗り、瞼は茶色のグラデーションできらきら光っている。セミロングの黒髪をバレッタでまとめた清潔感のある人だった。モノレールに乗っている間中、私は田代さんの化粧が気になりじっと見つめ、綺麗なお化粧ですね、と言うと田代さんは笑っていた。
天空橋や昭和島を過ぎると、大井競馬場前という駅を通り、浜松町で山手線に乗り換えた。大崎駅で下車し、ニューオータニイン東京というホテルに案内された。田代さんは私の荷物を持ち、部屋の使い方まで親切に教えてくれた。田舎の高校生はホテルに泊まり慣れていないと思っているようだった。レストランでディナーを食べると、接待を受けている気分になった。
翌日の筆記試験は小論文もあり、就職試験対策は全くしていなかったけれど、大学入試の過去問集を解くより容易だった。面接も警察の事情聴取に比べたら、友好的で楽なものだった。
自分が思っていることやしてきたことを大人に話すことには慣れていた。面接官たちは明らかに私を子供扱いした質問を投げかけてきたけれど、本気で答えるとその場の空気が変わった。ぱりっとしたスーツを着た紳士たちは、手元の資料を見ながら真剣に訊いてくる。そして、私が答えたことを紙に書き込んでいた。
これについて木山さんはどう思いますか? という質問の「これ」にセンスの良さを感じ、こんな面接なら何時間でも話していたいと思わされた。東京のビジネスマンは会話のテーマの選び方が違う、切り返しが巧みだといちいち感動した。面接官に、木山さんはいい質問をしますねと言われたことが印象に残っている。
入社試験は二日で終わったが、私は東京に住んでいる親戚に会うことになっていると田代さんに話し、二泊延泊した。
試験が終わった日の夕方、ホテルの部屋に会いに来てくれたのは雅也君だった。
彼は私が進学せず、就職を選んだことに納得していなかった。先月から起こった徹さんとの諸々の出来事は、雅也君に伝えていなかった。
私の身に降り懸かった災難を正直に伝えたら、きっと雅也君はすぐ様行動に移すだろうと思った。徹さんの自宅や職場に乗り込むだろう。殴ることもあるかもしれない。大勢で押し入って乱暴をするかもしれないと考えると、伝えられなかった。
そう考えている時点で、徹さんが私にひどい事をしたとわかっているのに、事実を受け入れられずにいた。
徹さんが私と連絡を取ることを拒否していると薄々感付いているのに、手紙を送り、電話をかけた。
警察官や郵便局員、河合先生や父から聞かされる徹さんの情報は、事実だと思えなかった。それを信じたら、徹さんと私の関係は終わってしまう。
徹さんがきっと、連絡を寄越すはずだという微かな希望に縋っていた。
その拠り所は、徹さんへの愛情と信頼と念書だった。父に見せられた念書には、宮部敬と署名してあったのだ。徹さんは、咄嗟に偽名を使ったのだろう。父に言質を取られ、念書まで作ることになり、私との関係を続けるために本名を書かなかったのだろうと私は解釈した。印鑑を押す都合上、名字は本名を伝えざるを得なかったに違いないと想像した。
それらが幻想だと教えてくれたのは、町の駐在さんだった。
「敬という名前に間違いはないんですか?」と、私は駐在さんに訊いた。
「運転免許証の記載事項だから間違いないよ」と言われ、念書に書かれた名前こそが本名だったのだとわかり、愕然とした。
「昭和二十三年生まれは三十八歳ですか」と、怖々訊いた。もう、「ですよね」と言う自信は持てなかった。
駐在さんは年齢早見表というカードを見て、
「ええと、昭和二十三年は1948年で十干は戊、十二支は子、鼠だな。今年四十四才歳になる。四月生まれだから、今はまだ四十三歳か」と言った。
父が昭和二十年生まれだということを思い出した。徹さんが父と三才しか違わない四十代の男性であると知っても、彼への思いは何の変わりもなかった。
彼は、出会った時に五歳鯖読んでいたと告白したことがあった。三十二歳って言ったけど、本当は三十七歳なんだと謝ったことがある。あの時点で彼は四十二歳だったのだ。なぜ、そんな嘘をつくのか不思議で仕方ない。
駐在さんは、
「しかし、花菜ちゃんみたいな賢い子が悪い男に引っ掛かったもんだなあ。一年半も付き合って気付かなかったのかい? 女子高生が四十を超えたおじさんと話が合うもんかねえ」
と、老眼鏡を外して私の顔を覗き込んだ。
「徹さんは、おじさんじゃありません」
私は、ぽろぽろ涙をこぼして言った。
「恋は盲目って言うけど、困ったもんだねえ。花菜ちゃんが恋してた男は宮部敬で、徹さんなんて人はいないんだよ。これは立派な詐欺だし、淫行にも当たるからね。まあ、法律のことは、花菜ちゃんのお父さんやお爺ちゃんの方が詳しいだろうさ。根室署の刑事さんと話したなら、お父さんはもう手を打ってくれてるんじゃないのかねえ。これ以上のことは、親御さんと一緒に来てもらわないとできないんだよ。ああ、お母さんはまだ入院中だったね。お父さんとよく相談してごらん。一人で決められることじゃないよ。被害届は出したのかな」
「被害届?」
私は首を傾げ思案した。
「お父さんが弁償した八百万近いお金は、本来、宮部が返すべきものだからね。花菜ちゃんは騙されたと被害届を出せるんだよ。そのことはお父さんと話していないのかい?」
「父は、彼とこれ以上関わりたくないと言ってました。あんな奴のことは一日も早く忘れろって言うんです」
話しながら、また涙が込み上げてくる。
「おじさんにも娘がいるから、花菜ちゃんのお父さんの気持ちはよくわかる。どんなに悔しい事か。憎んでも憎み足りないはずだ」
駐在さんは父に肩入れし、未成年の娘が成人の男に操を奪われたと知った父親の悲しみや怒りを、我が事のように訴えた。相手の男性が自分と年齢が近いことはショックを増幅させるらしい。何もかも気が滅入る話だった。
自宅に戻ると追い討ちをかけるように、父から彼のことを聞かされた。書斎に呼ばれると、調査報告書と記された大きな封筒を渡された。数枚の書類と多くの写真が入っていた。東京の探偵を雇ったと父は言った。
まず、探偵という職業が実在することに驚いた。レイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーロウやコナン・ドイルのシャーロックホームズといった小説や映画の世界の私立探偵しか思い浮かばない。封筒の表を見ると、全国に支社のあるリサーチ会社らしい。城南事務所と印刷されている。城南がどこかわからなかったが、東京都目黒の住所が書かれてあった。
書類を繰ると、彼のプロフィールが記されていた。写真は、私が見たことのない風景ばかりだった。ある建物の一室の出入りを数日かけて記録した写真らしい。その建物は紛れも無く彼が住んでいるマンションだった。
私は目を凝らして写真を見た。ご丁寧にマンション名が記されたエントランスの写真も撮ってある。宮部と書かれた名札が見える郵便受けや表札を掲げた戸口の写真もあった。
次の写真は、引越しのトラックに部屋の荷物を運び出しているものだった。彼の指示で、引越し会社の作業員が段ボール箱をトラックに積み込んでいる様子が写っていた。家具が毛布のようなものでくるまれている。ブラウン管の大型テレビは二人の男性が持っても重そうだ。鉢植えの観葉植物もいくつか見える。
最後に見覚えのある重厚なソファセットが運ばれてきた。このソファに座って寛ぐ彼の写真をもらったことがあった。とても気に入って長く愛用しているソファだと話していた。イタリアに張り替えを頼んだら往復の送料だけで数十万かかったという。
カッシーナのソファに、私も彼と座りたかった。ソファに座る彼にカメラのレンズを向けたのは誰だろうと、ふと思う。あの写真の彼は、とてもリラックスした表情でゆったりとソファにもたれていた。カメラを構えた人に心を許している関係が想像できた。素敵な笑顔の一葉だった。
引越業者はソファを慎重に梱包し、荷台に載せ、トラックの扉を閉め錠をかけ、立ち会った彼に鍵を渡している様子が写っていた。
次の写真には、シルバーのBMWに乗り込む彼の姿があった。キャップを被り、サングラスをかけているが、表情は明るい。唇の両端を緩やかに上げ、白い歯を見せている。助手席に向かって、笑顔で話しているようだ。
助手席には髪の長い痩身の女性が座っていた。東子さんだ。二十五歳だと思った。
私はどの写真より助手席の女性の顔をじっと見つめた。レストランの駐車場で、東子さんの肩を抱く彼の顔を、何て男前だろうと思いながら、涙を流した。
最後の写真は、名札が外された郵便受けと表札のない戸口だった。
父は何も言わずパイプから猛々しい勢いで煙を出している。白い煙が目の前を舞い上がる力強さに、問答無用の震えを覚えた。
父は、何の為に調査を依頼したのだろう。約束通り転居したか確認するためか。私の知っている場所に彼はもういないと、私にわからせるためだろうか。何日も尾行や隠し撮りを依頼するには、少なくない費用もかかったはずだ。
この調査報告書を見て以来、私は徹さんに連絡をとることを一切やめた。
入社試験を受けた会社が用意してくれたホテルが、彼の職場や住まいだった場所に近いのはわかっていたけれど、行ってみようとは思わなかった。両親が住んでいるという本籍地や勤めている会社を訪れることもしなかった。上京してからも、彼の行方を探すことはしなかった。
なぜしなかったかを考えたこともない。
私の中で徹さんを永遠のものにしたかったのかもしれない。


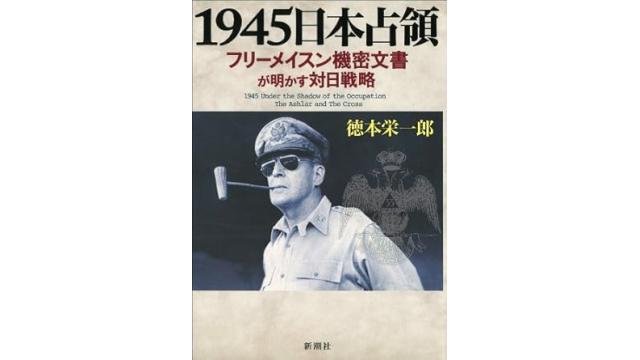

コメント
コメントを書く