勝賀城・城門前。
大堀川の橋を背に40人ほどの足軽が集まっていた。
鵜飼兵庫介率いる三番隊である。浪人衆、主に三郎左衛門の奇策により、一番隊、二番隊は壊滅。今や足軽隊側に残された兵力は彼ら三番隊だけとなっていた。
たかが浪人衆相手に一方的な攻勢を許してしまっているという事実は重く、三番隊の足軽たちの間にも焦りが広がっている。
特に気がかりなのは戦力比だ。浪人衆がほとんど無傷であれば、ゆうにこちらの倍はいると考えてよい。しかし指揮官の兵庫介は逆に部隊を分け、斥候に多くの人員を割いていた。
「のう、鵜飼兵庫介とかいうあの新参者、ほんとに大丈夫なんけ?」
「昨日の夜もどこぞにふらりと出かけておったぞ。よもや遊び女に入れ込んでおるのではあるまいな」
この試験において三番隊の活躍はほとんどないと思われていたこともあり、練度も士気もけして高くはない。加えて、着任して日の浅い兵庫介に対して懐疑的な目を向ける者も多い。
それは兵庫介本人も当然心得ていることではあるのだが、今彼の頭の中では別の思惑が渦巻いていた。
「伝令ーーっ! 浪人衆、前田の城下町を抜けて山道に入った模様! 数はおよそ四十!」
「ご苦労。して、どっちだ」
「青です!」
兵庫介はその報告を受けるや否や立ち上がり槍を担ぐと、部隊を移動させる準備に取り掛かる。足軽隊に更なる動揺が走った。
「わざわざこちらから出向くので? 放っておけば浪人どもはこの勝賀城に押し寄せてくるのにけ?」
足軽たちが戸惑うのも無理はない。浪人衆が目指しているのはこの勝賀城である。それが試験の目的である以上、彼らは迫り来る浪人衆を迎え討てばよいのであって、最終防衛線を担うべき三番隊が自ら討って出る必要はないのだ。
三番隊の立場からすれば、兵庫介の判断は地理の優位性を捨てる愚策に他ならないというわけである。
「一番隊、二番隊を退けたとて、相手は浪人でしょう? この橋に槍を並べておくだけじゃ事足りやせんかね」
「ならばおぬしの組が留守居を務めよ。他の組は某に続くがいい、おもしろいものを見せてやろう」
「うぇっ? ちょちょちょ、待っ」
10名ほどの守備隊を残し、勝賀城から鵜飼兵庫介率いる足軽隊、およそ30名が出撃した。
同じころ、勝賀の城下町には事の成り行きを見守ろうと多くの野次馬、もとい観客が集まっていた。
その中には当然、間接的な当事者である商人たちの姿もあった。
「これはこれは、本所のみなさまではありやせんか。いかがなすった、お店の番はよろしいので?」
「おや誰かと思えば、最近讃岐にいらした方でおますな。なにやら“商いごっこ”をされていらっしゃるとか。いやはや精が出ることで」
地元商人組合と新参商人たちの間にはバチバチと激しい火花が散っていた。赤組と青組に分かれて競う浪人衆。彼らの活躍如何に、彼ら商人の明日が賭かっているのである。
互いに自分たちの代理となる組に惜しげもなく金子をつぎ込んだ結果、今や浪人衆はちょっとした精鋭部隊に匹敵する戦力を有しているといっても過言ではない。それは足軽一番隊、二番隊を難なく破った手際からも見て取れる。
彼らは確信していた。よもや浪人衆が足軽隊、それも予備役に近しい三番隊に遅れを取ることはないだろう。
「なんとでも仰りなせえ。勝つのはわしら青組でさあ」
「ほほほ、どちらが“負けても”恨みっこなしですよ」
確信していたが故に、彼らが捻出したものは金だけではなかった。
知恵を搾るのもまた、商人なのである。
山林を抜ける狭い街道を駆ける一団があった。
青いはっぴを纏った浪人衆、つばめ率いる青組である。
青組には脚自慢の浪人たちが多く集められており、彼らは赤組に先行する形で部隊を進めていた。
「よおし、この勢いで城を落とすぞー!」
「「「おーっ!」」」
ここまで目立った損害もなく、赤青ともに4、50名ほどの兵力を残している。
青組だけで見ると数の上では三番隊と五分といったところだ。しかし二番隊を討ち破ったことで勢いづいた浪人たちの気合はじゅうぶんである。このまま両部隊が激突すれば、あるいは赤組の到着を待たずして兵庫介を討ち破ることもできるだろう。
「三郎左には悪いけど、こりゃ賞金は私たち青組がイタダキだな。むひょひょ……何食べようかな……ふへへ」
「よだれ垂らしてないでしっかりついてきてくだせえ、城はこの道を左に進んだ先ですぜ!」
地理不案内なつばめに代わり先頭を駆けるのは、地元の農家のせがれである。過去に何度もこの足軽試験に挑んではボコボコにされていた鬱憤を晴らすかのごとく、彼も鼻息を荒げて鹿のように狭く険しい山道を駆けていた。
「むおっ、すまんすまん。しかし道に詳しいヤツがいて助かったよ」
「へへっ、案内役なんてお安い御用ですぜ!」
分岐路を抜けた青組一行は、更に細く、深い山道へと分け入っていった。
自分たちがどの方角に向かって進んでいるかもわからぬほど木々は密集し、道はどんどん狭くなる。人ひとりがようやく通れるほどの狭い獣道が延々と続いていた。
山育ちのつばめはともかく、増していく傾斜に他の浪人たちは息も絶え絶えである。
部隊が縦に長く引き伸ばされ、無理な行軍速度に急勾配が加わったことでぼつぼつと脱落者も出始めていた。
「おい、おいい! ほんとにこの道で合ってるんだろうなあ!?」
「合ってます合ってますとも。この尾根を越えたらすぐそこでさあ! げへへ」
農家のせがれらしからぬ下卑た笑い声につばめが顔を上げると、山の端が目に入る。
ふと、その稜線で何かが揺れた。風で木々が揺れたにしては妙である。しかし獣の類ではない。
獣は武装したりはしない。
その男は山岳でも動きやすいよう最低限の具足をまとい、手には模擬戦用の弓矢を握りしめている。
むしろ獣であれば、追い散らすなり手は打てたかもしれない。しかしつばめたち青組の前に現れたのは、明確な敵意を持った人間。ようするに足軽であった。
「たっ、たたた、退却ーーーっ!!!」
つばめが状況を理解し叫ぶや否や、山の端に姿を隠していた足軽たちが次々と稜線を越えて姿を現す。それは鵜飼兵庫介が部隊の一部を割いてまで送り出した斥候隊であった。
木刀を片手に構えた足軽たちは斜面を滑るように駆け下り、手にした得物で青いはっぴの浪人たちに襲い掛かる。
「ひえーっ、来るなーっ!」
浪人衆の一人が槍を振り回す。しかし長柄の槍は密集する木々に阻まれ思うように振るうこともままならない。あっという間に一人が木刀の餌食となった。
「くそっ、槍を捨てろ! 刀で反撃するんだ! ってうおっ足が!」
商人たちから貢がれた高級で重厚な具足は、恐らく平時であれば心強い味方となってくれていたであろう。だが足場の悪い山道ではその重さと動きにくさが仇となる。
足軽隊の奇襲に浮き足立った浪人たちは、まるで地の底から這い出る亡者に絡みつかれたかの如く、足を滑らせ急な斜面を転がり落ちていった。
彼らが滑落した先には、後続する浪人たちが長蛇の列を成している。
具足を纏った重装歩兵は坂を転がる礫弾となり遅れていた浪人たちの頭上に降り注いだ。
「おい人が降ってくるぞ! 避けろーっ!」
「うぎゃーーーっ!!」
「いかん! 撤退だ! 来た道を戻れーーーっ!」
後続が異変に気づいた時には、既に部隊の半分近くが再起不能に陥っていた。
浪人たちは我先にと足をもつれさせながら急斜面を駆け下りていく。
背後では激しい剣戟が響き、青いはっぴを着た仲間が一人、また一人と打ちのめされていく。
彼らが体勢を立て直すには、赤組と合流するほかない。市街地など武装を十分に活かせる場所まで移動できればまだ勝機はあるかに思われた。
しかしその希望を打ち砕くかの如く、坂を下りきった先で悲鳴が上がった。
「よくぞ参られた。ゆるりと寛いでいかれよ」
坂道を封鎖するかのように並べられた模擬戦用の槍、槍、槍。
穂先を密集させた、槍衾と呼ばれるごく基本的な隊形である。それが山道の一角を占拠していた。そして隊を率いるのは勿論、三番隊指揮官・鵜飼兵庫介である。
「あいにく床の用意はできておらぬ故、雑魚寝で勘弁していただきたく候」
「わあーーーっ! 止まれ止まれ! 止まれないーーーっ!」
本来であれば射程内に入らず穂先を避ければ済む話なのだが、勢いよく転がるように駆け下っていた浪人たちは為す術もなくその槍衾へと吸い込まれていく。
流れの速い川では、一度流された小石はそう易々と止まることはできない。
その勢いの先を巨岩で塞がれたら、当たって砕けるしかないのだ。
青組壊滅。
対して数の上では拮抗していた足軽三番隊は一人の脱落者も出していない。
足軽たちはまだ信じられないといった様子だった。
「兵庫どんが言った通りだ……!」
「まさか、あんた……いや鵜兵様、いったい何をなさったので……?」
驚愕の目を向ける足軽たちに心底呆れるように、兵庫介は溜息をついた。
「たとえばの話だ。某がおぬしらに一粒ずつ朝顔の種を渡したとする。おぬしらの中で最も早く花を咲かせた者に金一両を取らせると言ったら、どうする?」
「そりゃあ手前の朝顔にゃ、我が子みてえに水やって育てまさあ」
「んだんだ、大事に育てるだよ。誰だってそうすらあな」
「某ならば、他の連中の朝顔に水をやって根を腐らせる」
「「「あっ!」」」
足軽たちは思わず互いの顔を見合わせた。
それは三郎左衛門が描いた壮大な作戦に、穿たれるべくして穿たれた穴であった。
商人同士の対立図式。そこに着眼するまではよかったものの彼らの対立は三郎左衛門の想像を越え、遥かに根深いものであった。
「今も昔も、人と人の諍いにおいて競い勝つ手は二つに一つしかない。己を高めるか、相手を貶めるかだ」
鵜飼兵庫介という男は、商人同士の対立を利用した三郎左衛門の作戦を伝え聞いたとき、既にこの絵を見据えていたのだ。
専売権の奪い合いは奉行所を通すべき案件であり、この試験を利用した賭けはあくまでも民間レベルでの取り決めである。故に細かいルールが設定されているわけでもない。するまでもないことであったのだ、本来であれば。
兵庫介はそこへ割り込み、足の引っ張り合いするよう、商人たちを唆したのだ。主催としてのお墨付きを与えたという次第である。
たとえば、青組の浪人に「赤組が勝つよう動いてくれれば本来受け取れる倍の賞金を支払う」と持ちかけたとしたら、いったい何人が首を縦に振るだろうか。
浪人衆は一見して、自分たちは順調に歩を進めていると思い込んでいたに違いない。
その腹に既に猛毒が仕込まれているとも知らずに。
もしこの男が敵に回だったらと思うと……。
足軽たちは新参の指揮官に、敬服を通り越し薄ら寒い畏怖を覚えていた。
「それではこれより残った赤い方を叩く。ものども、某に続けい!」
「「「おーっ!」」」
もはや兵庫介の指揮に異を唱えようという者はいなかった。
その頭角を現しつつある巨大な背を見送る、風景と同化した浪人が一人。
いち早く危機を察し、茂みの中で息を殺してなんとか足軽隊の奇襲を耐え忍ぶことができたのは、ひとえに山育ちであったが故のことだろう。
「はわわわわ、えらいこっちゃあ……!」
青組、残存兵力……1名! つばめ、ひとりだけ!
大堀川の橋を背に40人ほどの足軽が集まっていた。
鵜飼兵庫介率いる三番隊である。浪人衆、主に三郎左衛門の奇策により、一番隊、二番隊は壊滅。今や足軽隊側に残された兵力は彼ら三番隊だけとなっていた。
たかが浪人衆相手に一方的な攻勢を許してしまっているという事実は重く、三番隊の足軽たちの間にも焦りが広がっている。
特に気がかりなのは戦力比だ。浪人衆がほとんど無傷であれば、ゆうにこちらの倍はいると考えてよい。しかし指揮官の兵庫介は逆に部隊を分け、斥候に多くの人員を割いていた。
「のう、鵜飼兵庫介とかいうあの新参者、ほんとに大丈夫なんけ?」
「昨日の夜もどこぞにふらりと出かけておったぞ。よもや遊び女に入れ込んでおるのではあるまいな」
この試験において三番隊の活躍はほとんどないと思われていたこともあり、練度も士気もけして高くはない。加えて、着任して日の浅い兵庫介に対して懐疑的な目を向ける者も多い。
それは兵庫介本人も当然心得ていることではあるのだが、今彼の頭の中では別の思惑が渦巻いていた。
「伝令ーーっ! 浪人衆、前田の城下町を抜けて山道に入った模様! 数はおよそ四十!」
「ご苦労。して、どっちだ」
「青です!」
兵庫介はその報告を受けるや否や立ち上がり槍を担ぐと、部隊を移動させる準備に取り掛かる。足軽隊に更なる動揺が走った。
「わざわざこちらから出向くので? 放っておけば浪人どもはこの勝賀城に押し寄せてくるのにけ?」
足軽たちが戸惑うのも無理はない。浪人衆が目指しているのはこの勝賀城である。それが試験の目的である以上、彼らは迫り来る浪人衆を迎え討てばよいのであって、最終防衛線を担うべき三番隊が自ら討って出る必要はないのだ。
三番隊の立場からすれば、兵庫介の判断は地理の優位性を捨てる愚策に他ならないというわけである。
「一番隊、二番隊を退けたとて、相手は浪人でしょう? この橋に槍を並べておくだけじゃ事足りやせんかね」
「ならばおぬしの組が留守居を務めよ。他の組は某に続くがいい、おもしろいものを見せてやろう」
「うぇっ? ちょちょちょ、待っ」
10名ほどの守備隊を残し、勝賀城から鵜飼兵庫介率いる足軽隊、およそ30名が出撃した。
同じころ、勝賀の城下町には事の成り行きを見守ろうと多くの野次馬、もとい観客が集まっていた。
その中には当然、間接的な当事者である商人たちの姿もあった。
「これはこれは、本所のみなさまではありやせんか。いかがなすった、お店の番はよろしいので?」
「おや誰かと思えば、最近讃岐にいらした方でおますな。なにやら“商いごっこ”をされていらっしゃるとか。いやはや精が出ることで」
地元商人組合と新参商人たちの間にはバチバチと激しい火花が散っていた。赤組と青組に分かれて競う浪人衆。彼らの活躍如何に、彼ら商人の明日が賭かっているのである。
互いに自分たちの代理となる組に惜しげもなく金子をつぎ込んだ結果、今や浪人衆はちょっとした精鋭部隊に匹敵する戦力を有しているといっても過言ではない。それは足軽一番隊、二番隊を難なく破った手際からも見て取れる。
彼らは確信していた。よもや浪人衆が足軽隊、それも予備役に近しい三番隊に遅れを取ることはないだろう。
「なんとでも仰りなせえ。勝つのはわしら青組でさあ」
「ほほほ、どちらが“負けても”恨みっこなしですよ」
確信していたが故に、彼らが捻出したものは金だけではなかった。
知恵を搾るのもまた、商人なのである。
山林を抜ける狭い街道を駆ける一団があった。
青いはっぴを纏った浪人衆、つばめ率いる青組である。
青組には脚自慢の浪人たちが多く集められており、彼らは赤組に先行する形で部隊を進めていた。
「よおし、この勢いで城を落とすぞー!」
「「「おーっ!」」」
ここまで目立った損害もなく、赤青ともに4、50名ほどの兵力を残している。
青組だけで見ると数の上では三番隊と五分といったところだ。しかし二番隊を討ち破ったことで勢いづいた浪人たちの気合はじゅうぶんである。このまま両部隊が激突すれば、あるいは赤組の到着を待たずして兵庫介を討ち破ることもできるだろう。
「三郎左には悪いけど、こりゃ賞金は私たち青組がイタダキだな。むひょひょ……何食べようかな……ふへへ」
「よだれ垂らしてないでしっかりついてきてくだせえ、城はこの道を左に進んだ先ですぜ!」
地理不案内なつばめに代わり先頭を駆けるのは、地元の農家のせがれである。過去に何度もこの足軽試験に挑んではボコボコにされていた鬱憤を晴らすかのごとく、彼も鼻息を荒げて鹿のように狭く険しい山道を駆けていた。
「むおっ、すまんすまん。しかし道に詳しいヤツがいて助かったよ」
「へへっ、案内役なんてお安い御用ですぜ!」
分岐路を抜けた青組一行は、更に細く、深い山道へと分け入っていった。
自分たちがどの方角に向かって進んでいるかもわからぬほど木々は密集し、道はどんどん狭くなる。人ひとりがようやく通れるほどの狭い獣道が延々と続いていた。
山育ちのつばめはともかく、増していく傾斜に他の浪人たちは息も絶え絶えである。
部隊が縦に長く引き伸ばされ、無理な行軍速度に急勾配が加わったことでぼつぼつと脱落者も出始めていた。
「おい、おいい! ほんとにこの道で合ってるんだろうなあ!?」
「合ってます合ってますとも。この尾根を越えたらすぐそこでさあ! げへへ」
農家のせがれらしからぬ下卑た笑い声につばめが顔を上げると、山の端が目に入る。
ふと、その稜線で何かが揺れた。風で木々が揺れたにしては妙である。しかし獣の類ではない。
獣は武装したりはしない。
その男は山岳でも動きやすいよう最低限の具足をまとい、手には模擬戦用の弓矢を握りしめている。
むしろ獣であれば、追い散らすなり手は打てたかもしれない。しかしつばめたち青組の前に現れたのは、明確な敵意を持った人間。ようするに足軽であった。
「たっ、たたた、退却ーーーっ!!!」
つばめが状況を理解し叫ぶや否や、山の端に姿を隠していた足軽たちが次々と稜線を越えて姿を現す。それは鵜飼兵庫介が部隊の一部を割いてまで送り出した斥候隊であった。
木刀を片手に構えた足軽たちは斜面を滑るように駆け下り、手にした得物で青いはっぴの浪人たちに襲い掛かる。
「ひえーっ、来るなーっ!」
浪人衆の一人が槍を振り回す。しかし長柄の槍は密集する木々に阻まれ思うように振るうこともままならない。あっという間に一人が木刀の餌食となった。
「くそっ、槍を捨てろ! 刀で反撃するんだ! ってうおっ足が!」
商人たちから貢がれた高級で重厚な具足は、恐らく平時であれば心強い味方となってくれていたであろう。だが足場の悪い山道ではその重さと動きにくさが仇となる。
足軽隊の奇襲に浮き足立った浪人たちは、まるで地の底から這い出る亡者に絡みつかれたかの如く、足を滑らせ急な斜面を転がり落ちていった。
彼らが滑落した先には、後続する浪人たちが長蛇の列を成している。
具足を纏った重装歩兵は坂を転がる礫弾となり遅れていた浪人たちの頭上に降り注いだ。
「おい人が降ってくるぞ! 避けろーっ!」
「うぎゃーーーっ!!」
「いかん! 撤退だ! 来た道を戻れーーーっ!」
後続が異変に気づいた時には、既に部隊の半分近くが再起不能に陥っていた。
浪人たちは我先にと足をもつれさせながら急斜面を駆け下りていく。
背後では激しい剣戟が響き、青いはっぴを着た仲間が一人、また一人と打ちのめされていく。
彼らが体勢を立て直すには、赤組と合流するほかない。市街地など武装を十分に活かせる場所まで移動できればまだ勝機はあるかに思われた。
しかしその希望を打ち砕くかの如く、坂を下りきった先で悲鳴が上がった。
「よくぞ参られた。ゆるりと寛いでいかれよ」
坂道を封鎖するかのように並べられた模擬戦用の槍、槍、槍。
穂先を密集させた、槍衾と呼ばれるごく基本的な隊形である。それが山道の一角を占拠していた。そして隊を率いるのは勿論、三番隊指揮官・鵜飼兵庫介である。
「あいにく床の用意はできておらぬ故、雑魚寝で勘弁していただきたく候」
「わあーーーっ! 止まれ止まれ! 止まれないーーーっ!」
本来であれば射程内に入らず穂先を避ければ済む話なのだが、勢いよく転がるように駆け下っていた浪人たちは為す術もなくその槍衾へと吸い込まれていく。
流れの速い川では、一度流された小石はそう易々と止まることはできない。
その勢いの先を巨岩で塞がれたら、当たって砕けるしかないのだ。
青組壊滅。
対して数の上では拮抗していた足軽三番隊は一人の脱落者も出していない。
足軽たちはまだ信じられないといった様子だった。
「兵庫どんが言った通りだ……!」
「まさか、あんた……いや鵜兵様、いったい何をなさったので……?」
驚愕の目を向ける足軽たちに心底呆れるように、兵庫介は溜息をついた。
「たとえばの話だ。某がおぬしらに一粒ずつ朝顔の種を渡したとする。おぬしらの中で最も早く花を咲かせた者に金一両を取らせると言ったら、どうする?」
「そりゃあ手前の朝顔にゃ、我が子みてえに水やって育てまさあ」
「んだんだ、大事に育てるだよ。誰だってそうすらあな」
「某ならば、他の連中の朝顔に水をやって根を腐らせる」
「「「あっ!」」」
足軽たちは思わず互いの顔を見合わせた。
それは三郎左衛門が描いた壮大な作戦に、穿たれるべくして穿たれた穴であった。
商人同士の対立図式。そこに着眼するまではよかったものの彼らの対立は三郎左衛門の想像を越え、遥かに根深いものであった。
「今も昔も、人と人の諍いにおいて競い勝つ手は二つに一つしかない。己を高めるか、相手を貶めるかだ」
鵜飼兵庫介という男は、商人同士の対立を利用した三郎左衛門の作戦を伝え聞いたとき、既にこの絵を見据えていたのだ。
専売権の奪い合いは奉行所を通すべき案件であり、この試験を利用した賭けはあくまでも民間レベルでの取り決めである。故に細かいルールが設定されているわけでもない。するまでもないことであったのだ、本来であれば。
兵庫介はそこへ割り込み、足の引っ張り合いするよう、商人たちを唆したのだ。主催としてのお墨付きを与えたという次第である。
たとえば、青組の浪人に「赤組が勝つよう動いてくれれば本来受け取れる倍の賞金を支払う」と持ちかけたとしたら、いったい何人が首を縦に振るだろうか。
浪人衆は一見して、自分たちは順調に歩を進めていると思い込んでいたに違いない。
その腹に既に猛毒が仕込まれているとも知らずに。
もしこの男が敵に回だったらと思うと……。
足軽たちは新参の指揮官に、敬服を通り越し薄ら寒い畏怖を覚えていた。
「それではこれより残った赤い方を叩く。ものども、某に続けい!」
「「「おーっ!」」」
もはや兵庫介の指揮に異を唱えようという者はいなかった。
その頭角を現しつつある巨大な背を見送る、風景と同化した浪人が一人。
いち早く危機を察し、茂みの中で息を殺してなんとか足軽隊の奇襲を耐え忍ぶことができたのは、ひとえに山育ちであったが故のことだろう。
「はわわわわ、えらいこっちゃあ……!」
青組、残存兵力……1名! つばめ、ひとりだけ!


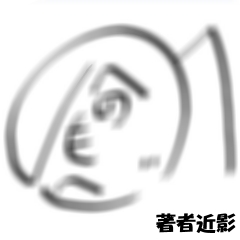


コメント
コメントを書く(ID:36387236)
毎回楽しみにしてます‼とても面白いです!動画の方も楽しみに待ってます‼(*^^*)