ひとくちに作家といっても、色々な人があることはもちろんだ。自作に対する評価ひとつ取っても、千差万別に違いない。自分こそ天才だと見做しているひともいれば、新作のたび、愚にもつかないものを書いてしまったと嘆くひともいることだろう。
 弱いなら弱いままで。
弱いなら弱いままで。
作家がいつもドヤ顔をしているべき理由。(1824文字)
ひとくちに作家といっても、色々な人があることはもちろんだ。自作に対する評価ひとつ取っても、千差万別に違いない。自分こそ天才だと見做しているひともいれば、新作のたび、愚にもつかないものを書いてしまったと嘆くひともいることだろう。
それじたいは何も問題ない。それぞれの作家にそれぞれの個性があって一向にかまわない。だれもが皆、自作につよい自負を持てるものでもないだろう。
また、作品の出来不出来をいちばんよく知っているのは作家自身だから、時には自信がない作品を世にだしてしまうことがあっても自然だ。じっさい、そうすばらしい作品ばかりでもないのだし。客観的にはそう思う。
しかし、一旦、読者の視点に立ってみれば、あまり自作の評価が低い作家に対してはいい気分がしない。少なくともぼくはそうだ。
あとがきなどで自作を「拙い出来」とか「まるで未熟な作品」と評している作家をみかけると、何となく自分の立場がない気分がなる。
というのも、ぼくはその作家が貶している自作を、大変な傑作だと思っていたりするからだ。その価値を作者自ら否定されてしまったら、何というか、立つ瀬がない。
もちろん、謙遜ということはある。自作を低く語る作家にしてみても、内心ではなかなかの出来だと考えているかもしれない。それはわからない。
だが、たとえそうだとしても、あまりそう謙遜されると困るのだ。その作品に覚えた感動が、単なる空回りになってしまうではないか。謙譲の美徳も時と場合に依る。可能なら作家には傲然と自作を誇ってもらいたいものである。
ドヤ顔、大いにけっこう。たとえ少々自信がない作品でも、ドヤ顔をしていてほしいと思う。その作品は、だれかが認め、おもしろいと思ったからこそ世にでるのだから、ともかく作者ひとりだけが評価しているとはいえないわけだ。
いつも思うのだが、作家の自己評価は案外あてにならない。作家にとって最高の自信作でも、大した出来とは思えないこともあるし、その反対もある。
先ほど、作品の出来不出来をいちばんよく知っているのは作家自身だと書いたけれど、最も作品を客観的にみれないのも作家自身である。あまりに距離が近すぎ、自作の価値を冷静に判定できないひとは少なくないだろう。
それが傲然たる自信という形で出たときは、まあいい。しかし、苦しげなため息という形をとったときは、少々問題がある。
カフカだったか、死の床で未発表の自作をすべて燃やしてほしいと頼んだ作家がいたと思うが、そういう低すぎる自己評価は読者にとって迷惑である。
この記事の続きを読む
ポイントで購入して読む
※ご購入後のキャンセルはできません。 支払い時期と提供時期はこちら
- ログインしてください
購入に関するご注意
- ニコニコの動作環境を満たした端末でご視聴ください。
- ニコニコチャンネル利用規約に同意の上ご購入ください。
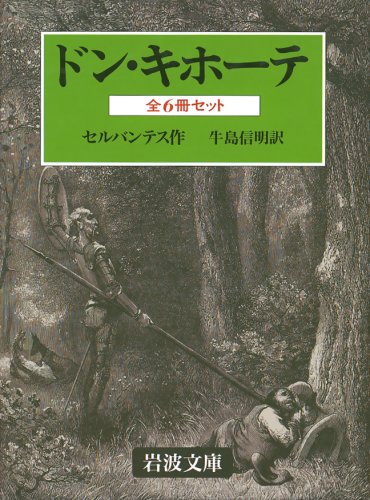




コメント
コメントを書く