続きです。
えっとね、何度でもいいますが、そのクールな認識を「あきらめ」とか「絶望」と受け止めてはいけません。そうではなく、「社会を変えることはかくもむずかしく、また、変えたからといって良くなるとは限らない」と知り、その事実を受け入れているのです。
「それを受け入れてはダメなのだ!」という人はいるでしょう。人間は必ず社会を良くしていけるという希望的な見方を保持するべきなのだ、と。ぼくはいうでしょう。「だったらおまえが社会を良くして見せろよ」と。
口先でいうだけならだれにでも何でもできます。むずかしいのは現実にやってのけることなのであって、単純な「正義」はむしろ有害であることは、マジメにアニメを見ている人ならだれでもわかっていることです。
そう、この種の「現実離れした理想論」を、「現実社会の不透明な複雑さ」を無視して、「唯一の正義」であるかのように押しつける独善性こそ、現在のリベラル勢力が省みなければならない決定的なポイントではないでしょうか?
「いま、そこにある現実」をひとまず現実として受け入れることとと、それを変更不可能なものとして容認することとはべつのことです。
「将来的には変えていかなければならないし、変えていくことができる」という意思と、「現実にはいまそこにあるし、変えることは困難である。また、どう変えていくのがベターなのかもわからない」という認識は両立するということ。
んー、わかりづらいでしょうか? そうですね、たとえば、ぼくたちがいま、ナチス政権の誕生の時代を生きているとしましょう。ナチスは、まあ、いってしまえば、かぎりなく「悪」の勢力ではある。
しかし、だからといって、時代の空気がナチスを歓迎していること、ナチスが大衆の人気を得て成立しようとしていることを「否認」しても始まらない、その現実は現実として受け入れなければならない、そのうえで時代の情勢に抵抗するべきだ、それと同じことです。
「ネオリベラル系」な一面を含む社会を嫌うからといって、それが現実に存在していること、しかも強固な構造を持っていることを否定してもどうしようもないということなのです。それこそ、単なる現実逃避に他ならないでしょう。
だからこそ、新海監督はあたかも「セカイ」のように変えがたい「社会」を描く。そのうえで、「大丈夫」だと、力強く宣言する。しかし、それは杉田氏にはこのように見えてしまうようです。
二つ目の疑念は、ラストの帆高の僕たちは「大丈夫」だ、というセリフが、どの視点から、誰が誰に向けて言ったものなのか、ということである。全てがじわじわ水没していく、この国も社会もどんどん狂っていく、けれども神様を信じたり恋愛したりして、日々を楽しく幸福に暮らすのは素晴らしいことだし、みんな大丈夫だよ――という論理によって若者たちを祝福するということ。
ええー。それはちゃうやろー。『天気の子』全編をまともに見て、そこに「けれども神様を信じたり恋愛したりして、日々を楽しく幸福に暮らすのは素晴らしいことだし、みんな大丈夫だよ――という論理」を見いだしてしまうことは、ちょっと信じられない。
あまりにも素朴な受け止め方すぎる。杉田氏は新海監督と現代の若者をよほどの愚か者だと思っているのでしょうか。
「大丈夫」という言葉を額面通りに「この世には何の問題もない。ハッピーハッピー」と受け取ってはならないのです。それは、「この世の中はままならないし、絶望的だし、あまりにも辛いことに満ちあふれているけれど、それでもなお、生きていくことはできるし、生きていきたいとも願う」という意味での「大丈夫」なのですから。
つまり、この「大丈夫」は「ちっとも大丈夫じゃないけれど、それでも大丈夫」という逆説的な(一周回った)意味の「大丈夫」だということ。
それを「大丈夫だといっているということは、大丈夫だと思っているのだろう」と受け止めてしまうことは、ぼくには致命的な誤読のように思えます。
続きを読んでみましょう。杉田氏の主張はこうです。
帆高は物語の中でいわば「セカイ系的な恋愛か、多数派の全員を不幸にするか」という二者択一の選択肢を強いられてしまう。しかしそうした問いを強いたのは誰か。若い世代を応援し希望を託しつつも、そのような社会を作ってきてしまった大人たちなのではないか。そのことが十分に問われないまま、大人たちは腐っているから仕方ない、あとは若者に希望を託そう、君たちは大丈夫だよ、という論理によって体よく責任を未来に先送りしてしまうこと。それを私は欺瞞的だ、と言いたいのである。社会や環境に対する無力感を強制しつつ、子どもたちの口から自己責任において「大丈夫」と言わせてしまうことが暴力的だ、と言いたいのだ。それはたとえば作中では天候はコントロール不可能なものとされているのに、話題になった「感情グラフ」(観客の感情を時間の流れの中でコントロールし、感情のピークへと誘導しようとするための仕組み)など、新海監督が観客の感情を積極的にコントロールしようとしている、若者の感情を「大丈夫」な方向へと調整し管理しようとしている、という矛盾とも無関係ではないように思える。
いや、それは「矛盾」ではないでしょう。『天気の子』はいままで縷々述べてきたように、天候を「コントロール不可能」なものとして描いているわけではありません。「コントロール困難」なものとして描写しているのです。
これは微妙でいて、決定的な違いです。杉田氏の用語を使うなら、『天気の子』のなかの天候は「(変更可能な)社会」としての側面と「(変更不可能な)セカイ」としての側面を併せもつ外部環境、そう、「セカイ」ならぬ、「社会」ならぬ、「世界」として描かれています。
杉田氏は『天気の子』が「社会や環境に対する無力感を強制」するといいますが、それではじっさいに「社会や環境」を変更することは容易なことなのでしょうか? そんなはずはないでしょう。
「不可能」ではないにしろ、けっして簡単なことではなく、またそれほど容易なことであってはいけないはずです。あるいは、杉田氏が提唱する「シャカイ系」はもっとあかるい、希望に満ちた作品なのかもしれませんが、それはいまの時代、あまりにリアルではない。
これは、おそらくいま、アニメを見ている人にはだれにでもわかってもらえる話だと思います。いい換えるなら、こういうことです。『天気の子』は「セカイ系」の行き着くところにして、いわば「世界系」――ぼくたち〈アズキアライアカデミア〉がいう「新世界系」の端緒に立つ作品なのだ、と。
それに対し、「あまりにも社会改革の困難さを強調し過ぎていて、若者の希望を萎えさせる」という批判はできるでしょう。ですが、いったい、「できるできる! かならず社会は改革できる!」とあおったところで、だれが説得されるというのでしょうか?
そのような作品で若者に希望と活力を与えられると考えることはいくらなんでも若者を甘く見すぎとしかいいようがありません。現実は、世界はきびしい。
それはたしかに人の手でコントロールしていくことができる「社会」でもあるが、それとともにどうしようもなく個々人の意思を押し流していく「セカイ」でもある。ぼくは、そういう卓抜な現状認識を『天気の子』に感じます。
有名なトロッコ問題のように、そのような「仕方ない」か「大丈夫」か、「最大多数の最大幸福」か「個人的な感情」か、という選択肢を若者たちに強いること自体が根本的に間違いであるかもしれないのに。二者択一を超える第三の意想外の選択肢を想像し創造していくこと。決して「大丈夫」とは言えないこの社会を見つめて、それを変えていくこと。しかも老若男女の協力によって。それが「共に生きる」ということなのではないだろうか。
なるほど、ご立派な意見です。非の打ちどころがないようにも見えます。ですが、これはいかにも当然のことだと思うのですが、「それなら、あなたが変えればいいじゃないですか」とぼくは考えます。
社会に対する無力感をもってはいけないのでしょう? 社会は変えられると信じつづけなければならず、なおかつ、それを否定するようなメッセージを発信してはならないのでしょう? それなら、ほかならぬあなたが変えてみせればいい。
そのうえで、「社会は変えられる」というのなら、説得力もあるし、論理的な一貫性、また正当性もありえることでしょう。で、杉田氏は社会を改善するために何をしてのけたのでしょう? そして、その努力によって社会はどう良い方向に変わったのでしょうか?
もし、何もしていないし、何もできていないなら、それにもかかわらずウエメセで「若者に無力感を強制してはならない」などというべきではありません。新海監督は少なくとも現代の若者がきわめて困難な状況に置かれていることを的確に認識している。
そして、そのうえで「それでもきみたちは大丈夫だよ」と鼓舞(祝福ではなく)している。その態度は、ぼくにはきわめて誠実なものに思えます。
もちろん、彼は「きみたちは社会を変えていける。それはほんとうはものすごく大変なことなんかじゃないんだ。ちょっとがんばればどうにかなることなんだよ」というような作品を作ることもできたでしょう。
ですが、そういった作品が若者の心を打つとはどうにも信じがたい。それはまさにイデオロギー先行のアジテーションであり、端的にいってしまえば「ウソ」です。
ぼくはフィクションにおいて「ウソ」をつくことが一概に悪いとは必ずしも考えない。むしろ、フィクションがその本質において絵空事である以上、たとえば「愛が奇跡を起こす」といったありえない「ウソ」を美しく描きだすことはその本質的な価値であると信じる。
しかし、そうはいっても「ウソ」は「ウソ」であるということもほんとうです。そして、それに対して「真実」、この場合は「世界(セカイではなく)はかぎりなく残酷で、それを変えていくことはとほうもなく困難である」という認識は、人の心を打ちます。
なぜなら、それは「ほんとうのこと」だから。そう、どれほど保守的に見えるとしても、左派から批判を受けるとしても、「世界は残酷な場所である」という「ほんとうのこと」はどうしたって揺らぎません。世界はそう簡単に理想的な場所に変わったりしないのです。
理想的、とぼくはいいました。この場合の「理想」とは何でしょう? それは、「人間の望み」です。「状況が人間が望んだ通りになること」をして、理想的というのです。
「世界のどうしようもない残酷さ」に直面したとき、人間はしばしば考えます。「こんな世界は間違えている! 自分の望むように変革しよう」と。そして、「世界」のなかに「社会」を持ち込み、より安全な、より快適な時空間を実現しようとする。
多くの場合、それは失敗するでしょう。何しろ、世界は残酷なのですから。ですが、それで着実に努力を続けるなら、少しずつ少しずつ「社会」を良くしていこうというその試みは前進するでしょう。そして、いま、ぼくたちが住んでいるこの現代社会ができたわけです。
異論もあるかもしれませんが、ごく自然に考えるなら、現代社会は過去の社会より「良い」状況にあるといっていいでしょう。一定の平和が実現し、病死者は激減し、貧困問題も、解決したとはとてもいえないにせよ、少なくとも江戸時代のように何万人という餓死者が出たりすることはほとんどありません。
地震とか津波というまさに「セカイ」のようにどうしようもないように思える自然災害に対してすら、一定の勝利を収めつつあります。その結果、「人々の心が貧しくなった」みたいな批判はありえるでしょうが、はっきりいってしまえば戯れ言に過ぎません。
人間は努力し、前進し、成長し、進歩しているのです。素晴らしい。ほんとうに素晴らしいことだと思います。
しかし、ここで勘違いしてはなりません。たしかに「社会」は改良されつづけ、前進しつづけていますが、だからといって「世界の法則」、ぼくやペトロニウスさんが「グランドルール」と呼ぶ、その「ほんとうのこと」を少しでもねじ曲げられたわけではないのです。
人間には「グランドルール」を曲げることはできません。たとえば時間の流れを止めることはできないし、過去起こったことを変更することもできない。タイムマシンとか、その種の物理法則に反する魔法めいた機械を生み出しでもしないかぎり。
つまり、「世界」のグランドルールは「セカイ」のように変更不可能だということです。これは、人間の敗北でしょうか? あくまでも「社会」を前進させつづけ、人間の望む理想にかぎりなく近い、ある種の「世界」を(それとも、それもまた「セカイ」と記した方が良いでしょうか?)実現することを目ざすべきでしょうか?
左派の理想主義とは、この問いに対して「イエス」と答えるものであるように思えます。左派イデオロギーの根底には「こんな世界は間違えている!」という怒りがある。ぼくは、その思想に心から共感し――そして、また、限界をも感じるものです。
なぜなら、どれほど「間違えて」いても、「狂って」いても、ぼくたちはそれを変えることはできないのだから。ただ、「受け入れる」ことしかできないのだから。
そして、もっというなら、そもそも「世界」を人間の理想通りに変えていくこと、「社会」を前進させていくことは無条件に正しいことなのでしょうか? ぼくにはそうは思えません。
これに「イエス」と答えるのが、たとえばアーサー・C・クラ―クやジェイムズ・P・ホーガン、そして山本弘といったSF作家たちでしょう。また、リチャード・ドーキンスなどのサイエンティストもそうかもしれません。
殊に山本弘氏などにはこの種の左派的な理想主義をつよく見いだせます。この狂った世界を、「科学」や「理性」を武器として、人間の望みにより近づけていこうという社会改良の意思がそこにはある。
例はいくらでも出せるのですが、今回の記事の趣旨とは異なるので(ただでさえもう長すぎる記事になっているし!)、やめておくことにします。
が、とにかく近代合理主義を礼賛する一部のSF作家や科学者は、「人間の思うままに世界を変更していくこと」を是とする傾向があります。それを、人間中心主義、ヒューマニズムと呼ぶこともできるでしょう。
グレッグ・イーガンがよく「不死の世界」を描くのは、「死」という「世界の法則=グランドルール」の限界を突破した状況を描こうとしているからだと思います。
山本氏がこのイーガンの作品を読んで、「そうだ。死なないほうがいいに決まっている!」といったことを書いていたことを記憶しています。ヒューマニズム的な理想主義からいえば、そういうことになるのでしょうね。
「世界」のどうしようもない(ように見える)残酷さをかぎりなく緩和し、いわば「世界」を「社会化」していくことこそが、左派の思想の究極的な到達点なのですから。
ですが、ぼくはこの種のヒューマニズムに強烈な違和感を覚えます。世界から残酷さを排除すること、痛みを、苦しみを、嘆きを、哀しみをなくしてしまうことは、ほんとうに端的に素晴らしいことだといえるのか?
その種のマイナスとも受け取れる感情をなくしてしまったら、プラスの想いもまた消え去ってしまうのではないか? なぜなら、プラスの感情とマイナスの感情とは、あるひとつの混沌とした情緒を人間に都合よく切り分けただけの概念に過ぎないのだから、と。
そう、「世界」はたしかに残酷です。その本質的な残酷さは、人間にはどうしようもない。だから、たとえばリベラリズムがいかに平等な社会を実現しようと努力を続けても、けっしてほんとうの意味では平等に等なるはずがない。
だけれども、「世界」には、その残酷さとうらはらの「美しさ」もある。この「残酷さ」と「美しさ」は一体のもので、切り離すことはできない。『進撃の巨人』序盤の、「世界は残酷だ。しかし、美しい」という意味のセリフは、このことを指しているわけです。
その意味で、ぼくは、人間の目には残酷とも、不条理とも、理不尽とも思える「世界の法則」は、「正しい」と思う。世界は、この世のすべてはかぎりなく残酷だけれど、「正しい」。そして、その残酷さ、人間の目には残酷と映る一面を曲げようとすることは「間違えている」。
ぼくとか、ペトロニウスさんが栗本薫の作品、『グイン・サーガ』などを愛好してやまないのは、それが「ほんとうのこと」にもとづく「世界系(新世界系)」だからです。
が、まあ、今回はそのことに深入りすると2019年のまとめという目的から逸れてしまうので、避けることにしましょう。ちなみに『グイン・サーガ』ではこの「世界の法則」のことを「大宇宙の黄金律」などと呼んだりします。かっこいい。
で――えっと、何だっけ(笑)。長すぎて、もう何を書いているのやらわからなくなってきた。いや、嘘。わかっている。つまりですね、『天気の子』は「セカイ系」の構造を突き抜けて「世界」を描く物語、「世界系(新世界系)」に到達しているということがいいたいのです。
で、「セカイ系」が、人間の意思がとどくナルシスティックな内面世界、つまり「セカイ」を描くものだとするなら、「新世界系」はまさに人間にはどうしようもない一面を持った現実の「世界」を描くものです。
その意味で、『天気の子』は「セカイ系のゴール」であるのと同時に「新世界系のスタート」の意味を持っています。そして、この「新世界系」こそが、ぼくら、アズキアライアカデミアにいわせれば、テン年代の「軸」を作ったものです。
杉田氏は、最後に『天気の子』を『もののけ姫』と比較したうえで、こう書きます。
『もののけ姫』の世界では、大人も若者も老人も、人間も神々も動物も、互いに争ったり、話し合ったり、和解したりしながら、全員が等しく滅びていきかねない「この社会」それ自体に対峙しようとしていた。自分たちを変え、社会を変え、世界を変えようとしていた。「大丈夫」ではないこの現実に向き合いつつ、それでも「大丈夫」と言える社会を、自分たちの能動的な責任と行動によって、何とか作っていこうとしていたのである。
なるほど。しかし、ぼくはその「それでも「大丈夫」と言える社会」を信じることができません。それは具体的にどのような社会なのでしょうか。社会福祉が充実した社会でしょうか。公平で、公正で、貧困も差別もない社会でしょうか。
ですが、仮にそのようなユートピア幻想的な社会が実現したとしても、「世界」の残酷さ、理不尽さが消えてなくなることはありませんし、仮に消えてなくなったとしたら、それはある種のディストピアでしょう。
オルダス・ハックスリーの『すばらしい新世界』を初めとして、それこそ栗本薫の『レダ』など、ディストピアSFが繰り返し繰り返し描いて来たことです。「完全に社会化された世界」、つまり楽園的なユートピアはそのじつ、地獄のディストピアなのだということ。
あるいは、ここで宮崎駿作品から『風の谷のナウシカ』を持ち出すこともできるでしょう。この物語において、主人公ナウシカは「墓所」の人間たちが提示するユートピアを否定し、かれらのこのままでは人類は滅亡するという強迫に対して、「それはこの星が決めること」といい放ちます。
この場合、「この星」という部分を「この世界」と変換することは許されるでしょう。つまり、ナウシカはこの世界の残酷な現実を受け入れるといっているのです。
さらにいうなら、ナウシカもまた、「わたしたちは大丈夫だ」といったのだ、と見ることもできるかと思います。衰えるかもしれない。滅びすらするかもしれない。それでも大丈夫だ、と。
あるいは『宮崎駿論』という著書もある杉田氏にこのような説明は釈迦に説法であるかもしれませんが、だからこそ、なぜ、杉田氏が『天気の子』に対し、このような一方的な批判を行うのか不思議に思えてなりません。
ぼくには、文中で「リベラル」や「フェミニズム」といった言葉が出てくることからもわかる通り、彼は作品理解にあたって、イデオロギーを先行させすぎているように思える。
イデオロギーとは、つまり、人間の「世界にこうあってほしい」という願い、理想を言葉にしたものです。しかし、人間が「こうあってほしい」と願うことと、現実に世界が「こうある」ということには、巨大な乖離が存在します。
人間は死にたくないと願い、苦しみたくないと望み、いつまでも幸せな時がつづけばよいと考える。そのために科学を発展させ、文明を形成し、堅牢な社会を実現する。
しかし、どれほど努力しても、死と滅びは避けられず、非情に時は過ぎる。それが世界の現実。「ほんとうのこと」。だからこそ、杉田氏のいう意味で「大丈夫」な状況は、ありえない。社会がどれほど前進したところで、人は理不尽に生き、不条理に死ぬのです。
その意味で、リベラリズムとは不可能な夢を追いつづける思想だということができるかもしれません。それに意味がないとは思わない。社会を少しずつ前進させていくことは、なるほど、必要なことではあるでしょう。
だけれど、それはどこまでいっても「死」と「滅び」を避けられない。一切の「衰退」のない社会、それはこの「世界」では、どこまでいっても不可能な夢なのです。
それでは、それでもなおかつ「大丈夫」といえるのはどのようなときなのでしょうか? それは、この世界の無常を受け入れ、残酷さを受け入れ、おのれ一身の力の限界を受け入れて、たとえ何が起こるとしても、いつかは死ぬとしてさえ、精いっぱいに生き抜くことができる、と確信したときなのではないでしょうか。
穂高が自分たちが大丈夫だというのは、けっして現実から目を逸らしているからではなく、社会改革をあきらめて絶望しているからでもなく、「世界の残酷さ」を甘受したうえで、「その美しさ」に目覚めたからです。
『天気の子』のラストシーン、水没しかけた東京の光景は、アニメーション的にかぎりなく美しい。それは、衰え、滅んでゆくかもしれないとしても、まさにそうだからこそ、生きることは素晴らしく美しいということを視覚的、聴覚的に感受させてくれます。
その意味で『ナウシカ』の「生きねば」という結論と、『天気の子』の「ぼくたちは大丈夫だ」という結論はつよく共振します。時代背景は異なりますが、両作品とも、少しずつ社会が衰退していく状況を背景としています。
そう、どうあがいても衰退や滅亡をまぬがれないという意味では、ぼくたちはけっして「大丈夫」ではないし、「大丈夫」になることはありえない。しかし、それでもなお、そのすべてを受容し、凛然と生きることができるという意味で、ぼくたちは「大丈夫」なのです。
社会の理不尽さを受容するなどとんでもない、と思われるでしょうか? そういうことではありません。ここで受け入れなければいけないというのは、「世界の理不尽な(理不尽に思える)残酷さ」であり、「社会が現在抱えている数々の問題」です。
「世界」はけっしてぼくたちの思う通りには動かないし、「社会」もほとんどどうしようもない。それでも、大丈夫。ぼくたちはこの滅びかけた世界で生きていくことができる。それが『天気の子』のテーマであり、メッセージだといっていいと思う。
それは、「この社会を良くしていこう!」という理想に燃える情熱的な人には、許すべからざる頽廃、あるいは諦念と見えるかもしれません。しかし、そういうことではないのです。
現実を受け入れることと、前進をあきらめることとは違う。「世の中はほぼどうしようもない」、「がんばってもどうにもならない」という「ほんとうのこと」をきびしく見つめるからこそ、「それでもなお、がんばって生きていこう」という意思が生まれる。それが人間の人間らしさではないでしょうか?
この世界の「残酷さ」と「美しさ」は切り離せない一体のもの。その「残酷で、なおかつ美しい(美しく、しかも残酷な)世界」をそのままに描くことこそ、「新世界系」の本質です。
というわけで、「その3」へ続きます。たぶんそれで終わり。読んでねー。




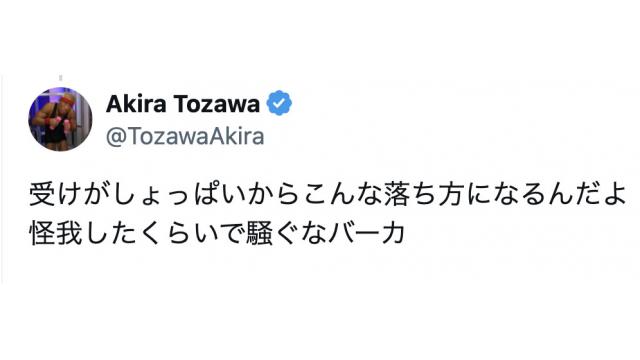
コメント
コメントを書く