1
ハムの連中の冷ややかな視線を背中に感じながら、宮澤武(みやざわたけし)は警察総合庁舎別館三階の廊下を早足で歩いた。
ハム――公安の連中に対する刑事警察の蔑称だ。公安の公の字を分解すればカタカナのハムになる。廊下をすれ違うハムの連中はだれもが没個性で、その辺を歩いているサラリーマンと見分けがつかない。十人十色、様々な個性がきら星のごとく寄り集まった捜査一課とはまるで毛色が違う。捜一では没個性は能無しと同じだと見なされる。
〈外事三課〉と書かれたプレートが貼ってあるドアをノックする。返事はなかった。宮澤はドアを開け、声を張り上げた。
「おはようございます」
だだっ広いフロアがロッカーで五つのスペースに区切られていた。人の気配はするのだが宮澤の挨拶に応じる者はいない。
舌打ちを押し殺し、宮澤はフロアを進んだ。五つに区切られたスペースを睥睨(へいげい)できるデスクに眠たそうな顔をした男が座っていた。年齢は三十半ば。外事三課の課長なら、階級は警視だろう。キャリアだ。
「滝山課長でしょうか?」
デスクの前で直立不動の姿勢をとる。男は宮澤に一瞥をくれようともしなかった。
「おまえが宮澤か?」
パソコンを睨みながら男は言った。
「はい。本日付で公安部外事三課に異動してきた宮澤武です」
「異動、か」男が笑った。「こっちは厄介者を押しつけられたとしか思えんのだがな。おれは課長の滝山だ」
宮澤は唇を噛んだ。辱めを受ける心構えはできていた。これぐらいの侮蔑はどうということもない。
「刑事から公安への異動は滅多にない。うちは刑事の連中をほしいとは思わんし、刑事も同じだろう。ひとくちに警察と言っても活動内容が根本的に異なる」
宮澤は無言で耳を傾けた。
「それが突然の辞令だ。調べさせてもらったよ」
「当然だと思います」
「とんだお荷物を押しつけられたと思っている。普通なら懲戒免職だ」
「告訴は取り下げられました」
滝山が鼻を鳴らした。
「おまえの経歴には瑕(きず)がついた。それに変わりはない。とにかく、面倒は起こすな。おまえがなにかしでかせば、おれの責任にされる」
「心得ております」
「どうだか、な」滝山は眉をひそめた。「ナベさん、いるか?」
「はい、課長」
五つに区切られたスペースの中央で野太い声が響いた。ごま塩頭の中年がこちらに向かってくる。
「渡辺管理官、こいつが例のあれだ」
滝山がごま塩頭に言った。
「捜一の厄介者か」
「捜一の厄介者か」
渡辺はごみくずを見るような目を宮澤に向けた。
「今日からお世話になります、管理官」
宮澤は渡辺の視線を受け流し、敬礼した。
「ナベさん、こいつをやつのところへ」
「了解しました」
滝山と渡辺は宮澤の敬礼を見事に無視した。
「ついてこい」
宮澤はフロアを出て行く渡辺の後を追った。
「おれはどんな部署に配属されるんですか?」
「焦らなくてもすぐにわかる」
渡辺は振り返りもしなかった。廊下を奥へ進み、突き当たりを右に曲がる。やがて、資料室と書かれたドアが見えてきた。渡辺はノックもせずそのドアを開けた。
「管理官、資料室って……」
渡辺は資料室に入っていく。ドアの前で戸惑っていると、ハムの捜査官が廊下を歩いてきた。捜査官は無遠慮な視線を宮澤と資料室に向け、あからさまな侮蔑の笑みを浮かべながら歩き去っていく。
宮澤は肩をすくめ資料室に入った。部屋は薄暗かった。部屋の右奥からかすかに光が差し込んできているだけだ。二十畳ほどの広さがあり、スティール製の書棚が整然と並んでいる。
「椿(つばき)さん、いるかい?」
渡辺が光の方へ声をかけている。すぐに人影が光を遮った。
「どなたでしょう?」
人影が近づいてくる。それにつれて、甘いパイプ煙草の匂いが漂ってきた。
「渡辺だ」
「これは管理官。こんなところになんの用ですか?」
椿と呼ばれた男が渡辺の前で足を止めた。巨漢だった。百九十はあるだろうか。背筋を伸ばし、穏やかな目で渡辺を見下ろしている。相手に威圧感を与えないよう絶えず気を配っているように見えた。
「新しい部下を連れてきた。宮澤巡査部長だ」
渡辺に肩を押され、宮澤は椿の正面に出て敬礼した。
「宮澤です。よろしくお願いします」
「君は公安の人間じゃないな?」
質問ではなかった。
「刑事から来たんだ」
渡辺が言った。
「なるほど。刑事から公安への異動は珍しい。ということは、君はよほど優秀なのに違いない」
「そんなことはありませんが――」
宮澤は頭を掻いた。
「それじゃ、椿さん、こいつをよろしく頼むよ。煮るなり焼くなり好きにしてくれ」
渡辺が踵を返した。
「あ、管理官――」
声をかけたが、渡辺は逃げるような速さで資料室を出て行った。
「宮君」
椿が口を開いた。
「はい? 今、なんと言いました?」
「宮君。君のことだよ。こちらへ」
椿は宮澤に背中を向けると光の方へ歩き出した。宮澤は舌打ちをこらえながら後に続いた。物心ついてからというもの、いろんなあだ名や呼び名をつけられたが『宮君』というのは初めてだった。皇族の尊称のようで尻のあたりがむず痒い。
光はブラインドの隙間から差し込んできていた。資料室に窓は一つしかなく、その窓に向き合うようにして、椿のものと思しいデスクが置かれていた。三メートルほど離れたところにもうひとつ、デスクがある。椿はそれを指さした。
「君の机だ。好きに使っていいよ」
宮澤はうなずいたが視線は椿のデスクから動かさなかった。形の違うパイプが三つ、デスクの上に無造作に転がっている。灰皿もあった。
「あの、椿さんはパイプを吸うんですか?」
「うん」
椿は椅子に腰を下ろした。安物の回転椅子が椿の体重を受けて悲鳴を上げるように軋んだ。
「ここで?」
「うん。特注のブレンド葉なんだ。まえにパリに行ったとき、有名なパイプ専門店でブレンドしてもらってね。それ以来、葉っぱが切れそうになるとインターネットで注文して送ってもらってる。いい香りだろう?」
椿はデスクの引き出しから分厚い財布のような革の容れ物を取りだした。中には細かく刻まれたパイプ用の煙草葉がぎっしりと詰まっていた。
「君も吸うかい?」
煙草葉をパイプに詰めながら椿が言った。宮澤は首を振った。
「ここ、禁煙じゃないんですか? というか、警視庁全体が禁煙になったの、だいぶ前じゃないですか」
「だれにも文句を言われたことはないよ」
椿は悪びれもせずスーツのポケットからデュポンのライターを出した。重い金属音を響かせ、火をつける。
「文句を言われたことはないって……ここは資料室で、燃えやすいものがたくさんあるし」
「聞かされてないのかい? ぼくは公安のアンタッチャブルなんだ」
宮澤は椿の横顔を凝視した。ふざけている様子はない。椿はうまそうに煙を吐き出し、目を細めている。
「あの、失礼ですが椿さんの階級は?」
「警視だけど、それがどうかした?」
宮澤は曖昧に首を振った。椿は不惑前後に見える。四十そこそこで警視ということは叩き上げではない。だが、キャリアにしても出世が遅すぎる。
いわゆるキャリアと呼ばれる連中は警察に入ると同時に警部補の階級を与えられる。日本全国、様々な部署をまわりながら三十歳頃には警視になる。警視の上の階級は警視正、警視長、警視監。その上は警視総監と警察庁長官しかない。
順調に出世街道を歩いているキャリアなら、椿の年代には警視正として重要なポストについているはずなのだ。だが、椿は警視で資料室の片隅のデスクでパイプをふかしている。部下の姿も見あたらない。
舌打ちをこらえた。出世街道を外れて閑職にまわされた落こぼれキャリアの世話を押しつけられたのだ。懲罰人事なのだから当然と言えば当然だが、公安での新しい仕事に漠然とした期待を抱いていた分だけ失望が大きい。
「椿警視の役職は?」
「警視庁公安部外事三課特別事項捜査係係長。長いんだよね、役職名」
「本庁の係長って、普通、警部がなるものじゃないんですか? 公安は違うんですか?」
「普通はね。でも言っただろう。ぼくは特別なんだ。アンタッチャブル」
皮肉をまぶした言葉をぶつけても、椿には暖簾(のれん)に腕押しだった。
「特別事項捜査係って、なにをする部署なんですか?」
「無任所班だよ。専門事項は持たないんだ。外事一課、二課、三課の枠にとらわれず広く捜査し、ときには他の係や課の手助けをする」
要するに窓際部署なのだ。宮澤は両手を腰に当て、天井を見上げた。
「なかなか捨てたもんじゃないよ、ここも。ぼくは公安に配属されてからずっと働きづめだったからね、ここは時間の自由も利いて快適なんだ」
「そんなものですか……」
「君はここに来る前はどの部署に?」
「捜一です」
「捜査一課」
椿は感極まったような声を上げた。
「なんですか、いきなり」
「捜査一課と言ったら、刑事の憧れの部署じゃないか。双六(すごろく)で言ったらあがりと同じだ」
「双六ですか?」
椿は忙(せわ)しなくパイプをふかしはじめた。
「若い頃、地方の県警に行ってたときは刑事で管理官をやったりもしたんだけれどね。それ以外はぼくは公安一筋で来たんだ。刑事のことはほとんどなにも知らない。特に捜査手法とかね。捜査一課か……これは、君にいろいろ教えてもらわないとならないな」
「捜査手法って、特別なことはありませんよ。地取り捜査が基本。足を使ってなんぼですから」
「そう勿体(もったい)ぶらなくてもいいよ。宮君、今夜は暇?」
「ええ。特に予定はありませんけど」
「じゃあ、歓迎会をやろう。いいね?」
「はあ……」
宮澤は俯(うつ)むいた。パイプの甘い煙に胸焼けがしはじめている。
宮澤は俯(うつ)むいた。パイプの甘い煙に胸焼けがしはじめている。
「店の選定とか、全部ぼくに任せてくれる?」
椿は遠足に出かける前の子供のように目を輝かせている。
「お好きにしてください」
宮澤は苦いものを吐き捨てるように言って、椿に背を向けた。
2
連れて行かれたのは六本木、芋洗坂を下った先の雑居ビルにあるバーだった。雑居ビル自体はこぢんまりとした造りだったが奥行きがあり、バーの中も予想よりは広々としていた。二十人ほどが座れそうなバーカウンターと、四人掛けのボックス席が五つ。客の入りは五分というところで、大半は外国人だった。それぞれが葉巻やパイプをふかしながら酒を酌み交わしている。また胸焼けがぶり返し、宮澤は唇を舐めた。
椿は自分の庭のような足取りで奥へ進み、カウンターの左端に腰を下ろした。椿の巨軀も、外国人だらけのこのバーではそれほど目立たなかった。
「宮君、なにをぼんやりしてるんだよ。こっちこっち」
ストゥールを左右に揺らしながら椿が手招きする。右手にはすでにパイプが握られていた。宮澤は客の品定めをしながらカウンターに向かった。白人が四割を占め、黒人とヒスパニック、それに黄色人種が残りの席を埋めている。みな、いいスーツを粋に着こなし、腕時計やアクセサリーも高級品が目についた。
「なんの店ですか、ここ?」
隣に腰を下ろしながら、椿の耳元で囁く。
「各国の外交官御用達(ごようたし)のバーっていうことになってる」
宮澤はうなずいた。
「なるほど、外交官か」
「表向きはね」
椿が思わせぶりに微笑んだ。
「表向き?」
「まず、酒と食べ物を頼もうよ。ぼくが公安捜査のイロハを宮君に教えるから、宮君は捜一のことをよろしくね」
そう言うと、椿は宮澤の意見も聞かず、次から次へと食べるものを注文しはじめた。ミックス・ピザにソーセージの盛り合わせ、スペアリブ、フィッシュ・アンド・チップス。聞いているだけで胸焼けが酷くなっていく。その身体が示すとおり、椿は大食漢なのだろう。
「あ、それから、ターキーサンドももらおうかな。宮君、ここのターキーサンド、絶品なんだよ」
「そうなんですか」
宮澤はメニューに視線を走らせた。印刷されている写真を見る限り、食べ物の量も外国人サイズのようだった。日本人なら二皿も食べれば満腹になるだろう。
「飲み物はぼくはジン・フィズを。宮君は?」
「生ビールをお願いします」
宮澤は背後に視線を向けた。店内では数種類の言語が飛び交っている。英語にフランス語、中国語と朝鮮語は意味はわからなくても判別はついたが、初めて耳にするたぐいの言語もかなりあった。
「さっきの話ですけど」
「なに、さっきの話って?」
椿はまだメニューを睨んでいた。
「ほら。外交官御用達は表向きだっていう話ですよ」
宮澤は声を潜めた。
※冒頭部分を抜粋。続きは以下書籍にてご覧ください。
【受賞作決定の瞬間を生放送】

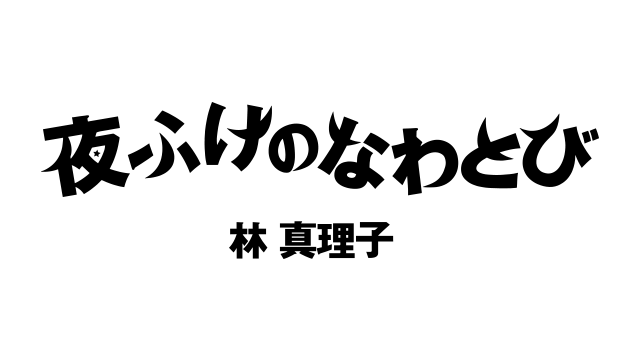
コメント
コメントを書く