南アフリカ共和国南西部、スヴァルト准尉はいつも通りの通勤ルートを車で走らせ、やってきた。朝五時、ケープタウンから北東に五十キロ離れたパールの町はまだ目覚めた直後、昇り始めた陽が草むらを白い息で照らし出したころあいで、運転席から見えるドラケンスバーグ(竜の山々)山脈の峰々も、眠ったまま微動だにしない竜の背中に見える。道が空いているのはいつも通り、駐車場のいつもと同じ場所、刑務所職員用エリアの隅に車を止めた。
これもいつも通りに通用口へ進むと、前に見慣れぬ二人組が歩いていた。今日のために召集された応援部隊だろうかとスヴァルト准尉は見当をつけたが、しばらくするとそのうちの一人が、もう一人を殴った。拳を火打石みたいな鋭さで顎に打ちつけたため、スヴァルト准尉は何が起きたのかすぐには見えなかった。効果音も歓声もなく、ただ静かに、紙の人形が倒れるかのように男が横たわった。
口論があったのか。予兆も何もない突然のことで、スヴァルト准尉は状況が理解できない。
殴った男は自分でやったにもかかわらず、男が倒れていることに取り乱した。巣を荒らされた動物のようで、やがてその場を立ち去る。
スヴァルト准尉はとるものもとりあえず警備室に顔を出し、外に倒れている男を病院に連れて行ったほうがいいと伝えた。
逃げていく男が響かせる靴音が、遠くで駆ける馬の蹄のように鳴る。
蹄の音は秒針のかわりとなり、時間を進める。
馬喰町(ばくろちょう)はもともと、馬の町だ。徳川家康が厩舎を作らせ、管理や売買を馬工郎(ばくろう)たちに任せていたが今は問屋街で、オフィスの入ったビルもいくつかあるが、馬はすでに一頭もおらず、そのかわりと言っては何だが、社員が馬の如く扱き使われている会社ならあった。
顔面の右頬に大きな黒子(ほくろ)を備えた女性は、唐突に内村のいる会社にやってきた。葦毛色の長いコートを着て、足取りは重い。表情はほとんどなく、受付カウンターにいる社員の前に立つと、
――ここで働かれている方に、イニシャルがUの方いますか。
と訴えた。
受付の社員はその大きな黒子に目が行きそうになるのをこらえながら話を交わすが、やり取りはどうにも噛み合わず、警察を呼ぶことまで視野に入れたが、
――わたし、ここで働いていたハヤミさんと交際をしていたのですが。
と女性が言うものだから、慌てて、社員が仕事をしているフロアにやってきて課長に説明をした。課長が、
――何、ハヤミの恋人? 難癖つけてきたのか?
と応じる。耳には瞼がないため、聞きたくなくとも、テーブルに向かう社員たちは当然それを耳にし、キーボードを叩いていた社員たちは手を一瞬止めた。
仲間が敵にやられたと報告を受けた不良少年が発するような、迫力ある物言いをする課長は、実際に十代の頃には、敵対するチームに仲間がやられれば、副腎からアドレナリンを放出させ、興奮状態で喧嘩に飛び込んでいた人物だった。アドレナリンとはホルモンもしくは神経伝達物質の一つ、人間の体をコントロールする真の支配者で、この物語においても重要なもの、真犯人と言ってもよいものなのだが、とにかく課長の柄の悪さと、嗜虐趣味は大したもので、職場の雰囲気がどんよりしているのも、社員たちが日々の睡眠不足で頭痛に悩まされているのも、自主退職に追い込まれる者が多いのも、郵便ポストの色はさておき、みんな課長が悪いのよと言えた。
とはいえ課長が諸悪の根源ではない。
実年齢は三十代半ば、精神年齢は不良時代で止ったままの男を管理職に据えている会社の人事こそが間違っているのだが、それはあくまでも「社員や世間からすれば間違っている」だけだ。
――できる限り安い労働力をできるだけ長く働かせ、用済みになれば、なるべく速やかに辞めてもらいたい。
という会社側の本音からすれば、当然の采配、適材適所の名人事と言える。
ハヤミの自殺が会社側の責任となるのかどうか、過労死認定されるのかどうかはまだはっきりせず、遺族がどう考えているのか、そもそも遺族がいるのかどうかも同僚たちにははっきりしなかったのだが、ただ会社からははっきりと、
――ハヤミの件は誰かに聞かれても答えるな。
と指示が出ていた。チクッた奴はただじゃおかねえぞ、という不良のやり口は、職場でも機能した。
――おい、内村。
下を向き、仕事に専念しているふりをしていた内村は呼ばれた。同じ三十代であるにもかかわらず、高圧的な物言いをされると、内村は小学生の頃に被害者として経験した、恐喝による金品巻き上げ(かつあげ)のことを思い出さずにはいられない。ドラクエⅣ買えたんだろ? と中学生三人が取り囲んできた時をだ。
課長の声にびくっとしたこともあり、勢いよく立ち上がるとキャスター付きの椅子が、後ろへ滑るように移動する。内村は課長の席へ近づき、媚び諂う御用聞きといった風情で、中腰になった。
――内村、おまえ、ハヤミと仲が良かったのか。
――仲が良いかどうかは。ただ、良くしてもらいました。
――日記に出てくるくらいにか。
理解できない内村を、受付社員は連れていく。受付カウンターのところには、葦毛色コートの女性が待っており、弱々しい顔つきをしていた。
内村の視線が真っ先に引き寄せられたのは、彼女の顔面の、向かって左頬にある大きな黒子だった。火傷痕とも湿疹とも異なる黒の円形は、こちらを覗き込む第三の瞳に感じられた。美しい円を描いているにもかかわらず、黒子は美しくは見えない。内村は黒子に目を向けた後、咄嗟に、目を逸らした。目を逸らしたことはつまり、彼女の黒子を意識していることになるのだから、それは外見の美醜、体質についての差別心ではないかと内村は急に気になり、視線を逸らした事実から心を逸らしたくなるが、かと言ってもう一度凝視するわけにもいかない。
――わたし、ハヤミさんと交際していた者なのですが。
――はあ。
――日記に、Uさんという方のことがちらほら載っていまして。
――ハヤミさんの日記にですか。
――彼がああなってしまって、わたし、まだそれを受け入れられないので。
――そりゃそうでしょうとも。
――彼の部屋を掃除していたら、日記が出てきて。そんなものを書いているなんてまったく知らなかったんですけど。悪いと思いつつ、読んでしまって。
勝手に死を選んだハヤミさんがいけないのだから日記を読むくらい後ろめたく思う必要もない、と内村の心が発言するが、口には出せず、
――はあ。
としか言えなかった。
――Uというイニシャルがたびたび登場してきていて。
――確かに、職場で、イニシャルがUなのは僕だけかもしれません。それにハヤミさんの隣の席ですから。日記に出ていることを教えるためにわざわざ来てくれたんですか。
――一応、お伝えしたほうがいいかと思って。
彼女が日記のコピーめいたものを差し出してきた。有名人の日記に登場しているのならばまだしも、会社の同僚の日記に名前が出ていたところで、しかもビルの屋上から飛び降りたという先輩社員なのだから、光栄だと感じるよりも不吉さを覚える。とはいえ紙を拒むこともできず内村はそれを受け取り、目を落とす。一ページに三日分の日記を書けるレイアウトで、ハヤミさんの手書き文字が埋まっていた。小さい文字ではあったが、読みやすい。
ぱっと目に飛び込んできた文章があった。
――昼休み、Uが子供の頃、かつあげをされた話を聞いた。途中から、驚きを隠すのに必死だった。Uには打ち明けられなかった。Uよ、俺がその男だったんだ!
※冒頭部分を抜粋。続きは以下書籍にてご覧ください。
【受賞作決定の瞬間を生放送】
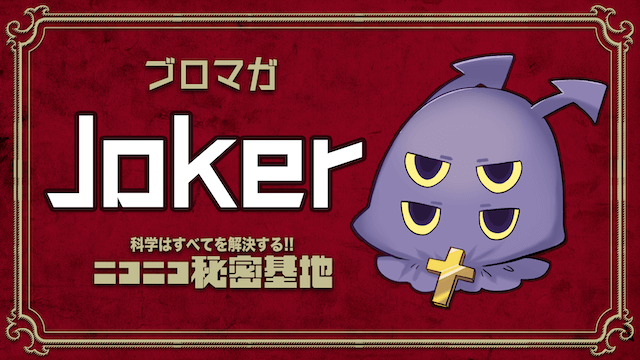

コメント
コメントを書く