 荻上チキの αシノドス
荻上チキの αシノドス
“α-Synodos” vol.294(2021/12/15)
- 登録タグはありません
━━━━━━━━━
“α-Synodos”
vol.294(2021/12/15)
━━━━━━━━━
〇はじめに
いつもお読みいただきありがとうございます。シノドスの芹沢一也です。最新号のラインナップを紹介いいたします。
01.小崎哲哉×志田陽子「現代アートは「美術」ではない――現代アートをめぐる文化戦争」
広げること/広がることの可能性を無限にもったアートの中でも、現代アートは「文化戦争」と呼ばれる政治社会の波に翻弄されてきました。とくにアメリカと日本では、この傾向が極端な形で起こりやすいため、境界に立って境界を問う《アートの呼びかけ》が封じられやすく、それがもたらす「豊かさ」が一般社会になかなか届かないのが現状です。小崎哲哉さんは、この問題に深い考察と洞察を示してきたアートプロデューサーでありジャーナリストです。小崎さんの近著『現代アートを殺さないために ソフトな恐怖政治と表現の自由』を取り上げ、現代アートの「不自由」問題を読み解いていきます。
02.穂鷹知美「専門家の役割と政治との関係――コロナ危機下のドイツで問われたもの」
昨年12月、ドイツが全国的なロックダウンをする際に、メルケル首相がその必要性を訴える演説を行いました。この演説は大きな感動を呼び、日本でも大きく報道されましたが、メルケルの演説の背後には、学術機関レオポルディーナによる声明がありました。その4カ月後、『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』に、この声明への批判的な論考が掲載されます。そこで、レオポルディーナによる声明は、専門家の役割を逸脱していた、つまり過渡に政治的に振舞っていたと批判されます。科学者としての基本線は、あくまで政治に科学的な助言をすることであって、政治的な決定はそれとは独立して、さまざまなファクターを比較考量してなされるべきですが、しかし、このコロナ禍にあって、科学の中立という規範を逸脱した専門家の言動が目立つのは、日本でもみなさんが目の当たりにしている通りです。日本でも今後、この点は批判的に検証されるべきでしょう。穂鷹知美さんのこのレポートで、ぜひ基本的な論点を抑えていただければと思います。
03.加藤一晃「クラブ活動への全員参加はなぜ求められたのか――学校の「非人間性」と「人間化」からの考察」
最近、部活動について批判的に言及されることが増えてきました。そこでは、部活動の指導にあたる教師の過酷な労働環境や、また中学生や高校生が部活動に入れ込むことの問題性が指摘されています。そうしたなか、2015年には、教員や生徒に部活動への関与を強制しないよう求める署名活動が展開され、2018年にはスポーツ庁から、運動部活動の活動頻度や時間の抑制を求めたガイドラインが発表されました。しかし、そもそもどのような経緯で、部活動は日本の学校教育に組み込まれたのでしょうか。加藤一晃さんが歴史的に明らかにするのは、高度成長期に学校が受験競争に巻き込まれ、非人間的なものとなっていくなかで、「人間らしさ」を取り戻すためにクラブ活動が要請されたという事実です。そして、そのようなロジックが部活動にも及んでいるのですが、つまり、学校を人間的な空間にするための部活動が、現在、教師と生徒を苦しめているということになります。この皮肉を理解するためには、学校とはそもそもどういう場であるのか、という根本的なところから考える必要があるはずです。
04.浅野幸治「J.ロールズの国際援助論の批判的検討(3・完)」
現実の地球社会がきわめて不正な社会であることは自明です。したがって、ロールズの『正義論』の考えを地球社会に適用すれば、先進国に援助義務が生ずるはずなのですが、しかし、ロールズの『万民の法』における国際正義論では、そうした義務は否定されているようにみえます。今回の記事では、ロールズの国際援助論を擁護する2人の論者、R.マーティンとS.フリーマンの議論が取り上げられます。彼らはロールズを国際援助論者に仕立て上げていますが、しかしそれははたして妥当な議論なのでしょうか? 浅野幸治さんの結論は、ロールズの国際援助論は、最低限の消極的な援助論であり、国際関係に大きな不正義を認めるものでも、世界の極貧層の人たちが置かれた状況の改善を先進国およびその市民たちに要求するものでもない、というものとなります。
05.芹沢一也「今月の1冊――『ジョブ型雇用社会とは何か』濱口桂一郎』
今月取り上げるのは濱口桂一郎さんの『ジョブ型雇用社会とは何か』です。本書は、日本の「働き方」であるメンバーシップ型の特徴を、ジョブ型と対照させながら分析しつつ、そのような「働き方」に規定された日本社会がどのような性格をもつ社会なのかも明らかにする素晴らしい本です。
次号は1月15日配信です。お楽しみに!
この記事の続きを読む
ポイントで購入して読む
※ご購入後のキャンセルはできません。 支払い時期と提供時期はこちら
- ログインしてください
購入に関するご注意
- ニコニコの動作環境を満たした端末でご視聴ください。
- ニコニコチャンネル利用規約に同意の上ご購入ください。




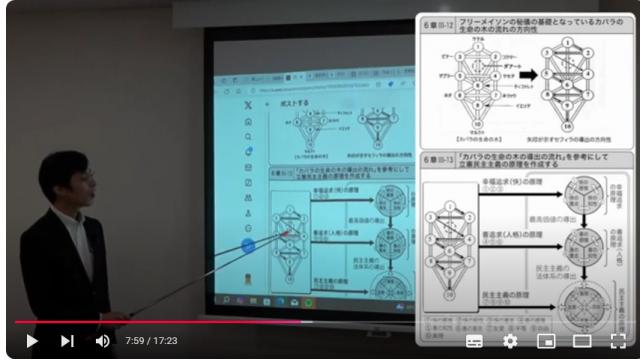
コメント
コメントを書く