アメリカに来た時にまず不安に思ったこと。
それは「飯(メシ)」。
僕は死ぬほど和食が好き。それに加え、”東京イタリアン”と言われる、和の要素を取り入れた繊細な味付けのイタリア料理が好きである。
果たしてハンバーガーなどの肉食を中心とする濃い味付けの国で、「食」に関してストレスを感じないで生きていけるのであろうか。
食べるということは根源的なことであり、そこに不安があるとつらい。

大学に入学してまず気づいたのが、みんな授業中に物を食べること。
「食べてはいけない」と一応要項には書かれてあって、先生も注意はする。
しかし、あくまでアメリカは「自己選択」の国。
気がつくと後ろの席で足を組んでサンドウィッチを頬張りながら堂々と先生に、
「マリア・シュナイダーってどの曲も同じに聴こえるのですけれど何が素晴らしいのですか?」
とか、
「ジョン・レジェンドって大したことないと思います」
なんて、自信たっぷりにもぐもぐ言われちゃった日には、そのあまりの大胆不敵な行為に驚き、拒絶感を覚え、心の奥底で少しだけその大味なストレートさに憧れたりもした。
食べたら食べっぱなし。教室の机に置きっ放し。掃除をする人を授業料でやとっているわけだから、「彼らの仕事を奪っちゃいけない」という考え方もあるわけだが、でも、それってどうなの? って思う。
教室で、ロビーで、廊下で、トイレで、非常階段で、カフェで、あちこちに散乱した「若気の傲慢」の屑を見やりながら、「ここで僕はやっていけるのだろうか」とため息をついた。

不思議なもので、そこらへんのビヘイバー(行い)に対し、細かなニュアンスを分かち合える生徒同士が国籍や肌の色に関係なく仲良くなる。
僕の場合、最初に通じ合えたのはイスラエル人のロータム。彼は物静かな青年で、学校の近くにあるベーグル屋で毎日挟む具の相談をしながら笑い、足を組み、カフェの外の席でわずかな時間を分け合った。
♪ ♪ ♪ ♪ ♪
ビル・エバンスのことを深く掘り下げる1時間のクラス。金曜日の昼過ぎ、小さな教室に男子が15人ほどぎゅうぎゅう詰めで受講する。
イタリアのシシリーから来た自信満々なピアニスト、サミュエルは入学時に既にピアニストとして出来上がっていたし、マスカリン(マッチョ)な思想の持ち主で、ビルの音楽性をやたらひとつの解釈で論じ込めようとする。多分に他の生徒への威嚇もあるのだろうけれど、
「音楽性は大したことはない。作曲家としてはいまいちだし、ジャズ度が低い」
などと一刀両断の勢いで語り出す。
「大好きなビル・エバンスの音楽を語り合い、分け合う」クラスで「前へ前へ自分の理論を強引に押し出す」サミュエルのやり方には内心閉口した。まるで味付けの濃い茹ですぎたパスタを出されたような気分になった。ビルについて語る僕の番が来た。
「ラベルを感じます。クラシック音楽の整合性と美しさ、それに地に足をつけた彼なりのビバップに根ざしたスケールやモードなどが適材適所に加わると、彼の世界観に大きな広がりを感じるのです」
と言うと、先生のリアン(ビルに傾倒している素晴らしいピアニスト)が「もっと詳しく教えて」と促す。
「僕はジャズがまだよくできません。学校近くのユニオンスクエアに出るのに、どの道が北側なのか南側なのか、簡単に迷ってしまう。僕にとってジャズとはまだそういうもの。ニューヨークの街のストリート(横の通り)とアベニュー(縦の通り)をしっかり覚えて目をつむっていても迷わなくなる。それが課題なのです。ビル・エバンスの音楽は明快でそんな僕に勇気をくれるのです」
授業が終わってエレベーターを待っている僕にロータムが、「よ!」と声をかけにきた。
「さっきの話、俺は好きだったな。よかったら一緒に学校の近くの安いバル(スペインのバー)で飲まない?」
僕たちはその日、月が頭のてっぺんになって街路樹の隙間から時折笑い出しそうになる時刻までスペインのビールとハモンイベリコで話し続けた。
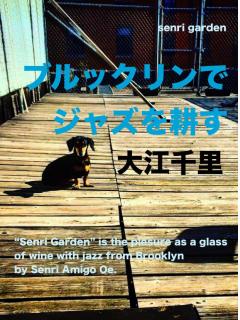

コメント
コメントを書く