太陽のピラミッドとはよく言ったもので、頂上の「天に近い場所」で両手を広げると「宇宙」にちょっぴり近くなったような気持ちになる。
それは言うならば「無」の境地。
「自然」と一体になったような不思議な感覚。周りで記念撮影する人たちの賑わいが消えて「風の音」だけが自分の耳に聞こえる。さっきまでここで27年前の僕が「写ルンです!」で撮影していた気がする。
同じようなピラミッドの縁で同じように足を震わせ同じように地上を覗き込み、緑と青と茶の色のメキシコの自然を目に写し込んだ。もう少しここに居ようと、太陽が少し傾いて午前中より暑くなった天辺で、空をもう一度仰ぐ。
「繋がった!」
1994年NYを諦め日本での活動に集中しようと、アパートの荷物を引き払った時、クィーンズボロブリッジから一回だけマンハッタン島を振り返った。「さよなら、NY!でも人生何があるかわからない。次にもし万が一ここに来ることがあったら、その時は……永住だな」とありもしないような幻想をつぶやく。日本に帰ってからは無我夢中で、その「一瞬のつぶやき」などすっかり忘れていた。友達の結婚式で再びNYを訪れ帰りの空港に向かう途中、ふと同じ橋の真ん中でまた同じようにマンハッタン島を振り返ってしまった。その時、僕は過去と未来を橋の上で「繋げた」のだ。数ヶ月後にジャズ大学であるニュースクールを受験、いきなり想像もつかない速さでNYに戻ってくることになる。
頂上から地上に降りる時の方が足元に気をつけないと危ない。鎖に掴まりながら慎重に一歩一歩下ってゆく。傾斜があまりに急で、登頂の余韻をゆっくり味わう余裕がないまま、とにかく必死に降りる。汗が滲む。息が上がる。不恰好だが両手でガシッと握り締め、ブラ下がるように降りることにする。もうすぐだ。最後の一歩は「ふわっ」とパラグライダーで地上に降りるように地上へ戻る。
1秒前まで「別世界の宇宙」にいた。あれは「瞑想」とも言って良い。振り返って手を伸ばすとピラミッドの一部に触れることが出来そうなのに、そこは「今いる世界」とは隔絶された別のステージだった。
太陽のピラミッドが聳え立つ。手を伸ばし手のひらにそれを載せてみるとマッチ箱の大きさの小さな三角形。豆粒のような人たちが空との境目である壁面を上へ下へ。風に乗って時折の嬌声も聞こえる。
「面白い経験だったな」と僕。
「汗びっしょりですね」とJ氏。
「みんなどこだろう」とO氏。
僕たちはK氏や美樹ちゃんを探してテクテク歩き始めた。
「みなさん、いかがでした? 今このメキシコ人のおじちゃんと話してたんですけど、黒曜石を格安で売ってるんですよ」
ガイドのFさんが日焼け止め用のスカーフをぐるぐる巻きにして、眩しそうな目でそう叫ぶ。
外見は黒く(茶色、また半透明の場合にも見えるが)、ガラスとよく似た性質を持ち、割ると非常に鋭い破断面(貝殻状断口)を示すことから、先史時代より世界各地でナイフや鏃(やじり)、槍の穂先などの石器として長く使用された黒曜石。見事だ。
神秘的な色と光と丸みの中にある一抹の「頑なさ、強さ」と「脆さ」、時に身を守り時に凶器に使われる「諸刃」の石。K氏はすっかり魅了されたらしく、しばらく石売りの親父さんと対面で話し込んでいた。
「で、買ったんですか?」
「うん。引き込まれちゃってね」
この日最高の燃えるような太陽が僕たち一行の背中を刺す。駐車場に戻る途中、朝閉まっていた土産物屋が開いているのでふらっと立ち寄ってみる。どの店も同じような「やる気があるのかないのかわからない」のんびりしたノリでやっている。K氏はまたもやある店をターゲットに何やら売り子と話し込んでいる。
インディオの人たちがパレードを始めるらしく、民族衣装に身を包み集まり出した。金網越しのサボテンと枯れた大地のコントラストを携帯で「カシャ!」。「あの日も同じような場所で」似たようなことをしたなと思い出す。小さな出来事が過去の自分と現在を引き合わせてくれているようで、なんだか「お帰りなさい」をメキシコに言われている気分になる。現在のメキシコに着陸成功! その大地を踏みしめているんだな、と嬉しくなる。コンサートはきっとうまくいく、そんな予感に溢れてくる。
「何買ったんですか?」
「いやね。このガラスの置物なんだけど、値切ったよ。NYオフィスのテーブルの上にちょこんと置こうと思って(笑)。けっこう精巧にできてていいでしょう?」
「とかなんとか言って、実はメイドインジャパンだったりしたら笑えるよね」
「そんなわけ、あ、メイドインジャパンだ!」
K氏と僕のそんな同い年軽妙トークに周りは大爆笑。
# # #
日墨会館があるエリアは高級住宅街で、大きな敷地に堂々と建てられた家々が並ぶ。その中にひっそりと位置するこの施設は60周年に於ける日墨協会の象徴であり、メキシコ人と日本人をつなぐ場所、メキシコに根ざす日系人たちの誇りの場所でもある。
日墨協会はメキシコにある日系の組織では最も歴史も古く、日系社会の中心として今日までその役割を果たしてきた。長い歴史の中で試行錯誤しながら先人たちは知恵を絞り、汗を流し、資金を捻出しながらの舵取りであった事だろう。
駐車場に車を停めてテニスコートを横目に会館の中へ足を踏み入れる。「感謝を報恩に」「逆境を誇りに」「課題を使命に」「停滞を前進に」「夢を現実に」「一瞬を永遠に」ーー次世代日系の後継者につなぐ「橋渡し的意識」の標語が掲示板に並ぶ。
立派な兜や日本画が飾ってある和洋折衷の建物の中をキョロキョロ見学し、恐る恐る2階へと進む。プエルタ・カンデーラ3がリハをやっている音が上から漏れてくる。
大きなパーテイー会場。その先に3人がいる。
「初めましてルイス。Senriです」
「はい、マエストロSenri。やっと会えた。ようこそメキシコへ 」
お互いにスペイン語と日本語を補い余るくらい激しく抱き合い喜びを表現する2人のピアニスト。ルイスは音楽や踊りが非常に盛んなべラクルス出身、プエルタ・カンデーラ3のリーダー。ダンソン(キューバで20世紀初頭よく踊られていたリズム)やソンという即興で歌詞を作っていく伝統音楽の地で育つ。ソンハローチョ (son jarocho) はメキシコ民族音楽とキューバのソンから生まれたベラクルスの伝統音楽。「ラ・バンバ」はソンハローチョの曲が原曲だ。ルイスのお父さんもピアニストだそう。
顔をほころばせながらもちょっぴりシャイにお辞儀をするボーカルのビオレッタ。
「はい、ビオレッタ。やっと会えました」
「ありがとう。マエストロSenri。ようこそ」
ビオレッタはおばあさんがベラクルス出身で、ルイス同様、お客さんの盛り上がり次第のソンを得意とする。
僕たちの様子を若い女性がカメラで撮影している。もう1人のメンバー、アレハンドラだった。アメリカにいたことがある彼女は英語が喋れるので、僕たちはダムが決壊したように情報を伝え合う。要するに彼女も音楽家で、ジャズアーティストを撮影する有名なカメラウーマンでもあり、プエルタ・カンデーラ3を盛り立てるパーカッショニストだ。
協賛のメキシコYAMAHAが貸してくれている立派なグランドピアノがステージ中央に。もう一台YAMAHAのアップライトピアノが向かって左側に。音響のクルー達が丁度楽器の周りでどこに置くべきか相談していたので、僕とルイスがすかさず位置を一緒に決める。指差しで、
「ここに僕。だったら君は僕が見える」
「君が見える。だから僕はあそこ。2人ノリノリ」
「シーシー」
「グラシャスグラシャス」
そんな剽軽な会話にその場が湧く。早速一同で「よっこいしょどっこいしょ!」ピアノを移動させる。
ルイスのグループの3人は、この日、立ち位置の確認、音響のチェックをしていたのだが、「予期せぬ来客」にテンションが上がりまくっている。
ポロポロとピアノの響きを鍵盤で確かめる僕に、伺うように明日セッションする曲「ブルーボッサ」とメキシコの20世紀を代表する作曲家ルーベン・フエンテスの代表曲、メキシコ人なら誰でも知っている「La Bikina」を弾き始めるルイス。それに反応して載っかる僕。ニヤッとルイス。更に挑発する僕。しばらく挨拶がてらのセッションが続き、どちらからともなくエンディング。美樹ちゃん、K氏、O氏、J氏、YAMAHAの人たち、皆、頬が紅潮して割れんばかりの拍手をくれた。照れる2人。
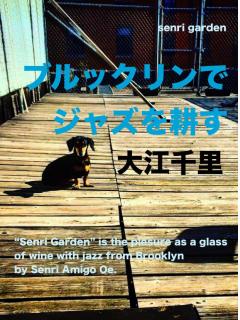
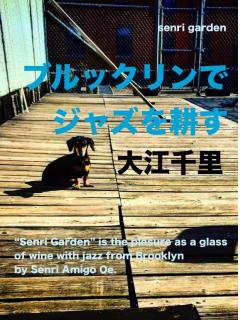




コメント
コメントを書く