作品を作り上げる時間はタイトロープだ。不安とワクワクが表と裏に。
風が吹くと橋の途中で吹き飛ばされそうになるが、なんとか耐えて先へ進む。一歩一歩。揺れながら。

作品はすでにそれぞれが築いてきたものを持ち寄って、集合体としての更なる完成形へと近づけることから始まる。時間は限られているからその中でやりきらねばならない。もし初日の幕が上がらなかったらどうしよう、と考えた時点で負ける。必ず出来上がる。必ず成功する。それしか頭にイメージしないようにする。細かいどうでもいいようなことからどんどん落として「大事なこと」だけを炙り出し、入念に積み上げる。舞踊の現場も音楽と変わらないようだ。そこには関わるお互いの信頼、感謝、率直さが大きなパワーとして作品を左右する。自分の領分をしっかりこなしつつ、他人が困っていると無条件に助け合う。誰がどの役など関係なく、皆一つの出し物の同じ「担ぎ手」なのだ。
僕が今回やらねばいけないのはチリの詩人であり音楽家のPedro Humbertoの「Broken Memory」を僕流に再現することと、もう1曲自分の曲である「Just a little wine」を素敵に演奏すること。この2曲が美樹ちゃんとのパートである。キャノピーの公演の今回のテーマは、マーサグラハムという世界観であり、マーサの伝道師である美樹ちゃんがキャノピーのダンサーたちにその型を伝えてゆくのと同時に、自分の現在の踊りでそれを魅せてゆく。
演目は他にもマーティンという舞踊家、振付家による作品。マーティン自身が踊る実験的な踊り。彼も美樹ちゃんやリサと古い友達で、踊りの根底にはマーサグラハムの哲学がある。
リサの旦那のロバートは、80年代前衛的だった振付師。その頃振り付けてすでにウィスコンシンの舞踊界では古典になりつつある彼の作品を、今回はキャノピーのダンサーに踊らせる。男と女の狂おしいほど可笑しくて残酷なやりとりのダンスだ。
そして何よりも大きな核は「Heretic」というマーサグラハムの伝説の作品。1929年に完成して以後、マーサグラハム舞踊団はもとより世界各地で繰り返されている名作の再演である。これにはグラハムの作品をちゃんと上演、伝播する確かさが求められるので、グラハムのプリンシパルを長く勤めた美樹ちゃんがその「語り部」と「伝授役」を務めているわけだ。アメリカの無形文化でもあるマーサの作品を日本人の美樹ちゃんがアメリカ人に伝えていく。そこには人種を超えた実力至上主義のアメリカ社会のリベラルな構図が見え隠れする。
初日の朝9時から、美樹ちゃんはキャノピーのダンサーにマーサテクニークを教えるクラスを受け持つ。そのあと12時から1時間半きっかり、僕とのパフォーマンスのリハが、実際の舞台上で照明、音響、舞台監督などと共に行われる。そしてしばらく僕たちは時間が空き、その間他のアーテイストたちのリハをやる。6時に全員が舞台に再集合し、最終テクニカルリハを行い、そのあとすぐ8時から初日の本番の幕が開く。なんというめまぐるしさ。
僕はここ数ヶ月旅が多かったので、万年時差ボケ状態。時間が空くと倒れ込むように眠ってしまう。やらねばならぬことが目の前にあると夢中でやれるのだが、一旦時間が空くと泥のようにベッドにばたんきゅう。ぴも心配そうにそんなダッドに添い寝する。
「Senri , 大丈夫? 全然音がしないから心配になっちゃったよ。何か必要なことがあったら教えてね」
昼の美樹ちゃんとのリハを終えて一旦宿泊先に帰った僕は、そのままベッドに沈み込む。家の主で宿泊所を提供してくれているコリンさん(サイエンテイスト、70歳を超える大柄イギリス人)が僕のいる地下の部屋をそろりと覗き、優しく声をかけた。
「大丈夫です。ただ眠くて。もうちょっと寝かせてください。4時半には起きますから」
と声を振り絞るように答える僕。
「それはよかった。帰って来るなり、降りていったきり階下から全く音もしないし一体どうしちゃったのかと心配になったので」
ぴがそわそわコリンさんに反応してベッドの上をごそごそ歩き回る。
本当にあと数時間後に初日が開くとは思えないほど、僕は眠りの沼に誘い込まれていた。頭は起きても体が起き上がれない。仕方ないのでとにかく寝る。あと2時間は寝れる。
「ああ、わかる。私もそう。でも朝からクラス教えなきゃいけないから無理矢理起きて頑張ってるけど」
そう言いながらも空き時間、近所のジムで軽く汗を流してきた美樹ちゃん。僕がなんとか目覚ましどおりに起床し劇場に戻った時、美樹ちゃんはいつもの「身体が冷えないような」完全防備姿でストレッチ中だった。舞台では気になる作品をリサが真剣にダメ出しをしている。残りのダンサーたちはリラックスムードで、思い思いにナッツを囓ったり床で身体を伸ばしたり。

僕はロバートが劇場のマネージャーに話してくれたおかげで、ロビーにあるピアノで少しだけ指慣らしができた。一緒に劇場に来ていたぴがそばでじっとそれを聞いている。いつものことだ。時々うろうろロビーを歩き回ってはダデイの足元に戻る。大きい方のホールでは明日シンフォニーのコンサートがあるので、クラシックのミュージシャンたちが本番と同じタキシードやドレス姿で撮影を行なっていて騒がしい。あらかじめビデオに挿入するカットを撮るためらしいが、モーツアルトの交響曲が劇場へのドアが開くたびに漏れて来る。その音と僕の弾く「Just a little wine」が混ざり合う。刻々と本番が近づく気配が高まっていく。

会場して間もなく舞台に椅子が並べられ、リサ、ロバート、美樹、マーチンによるMCの人を交えたトークショーが始まった。モダンダンスとは? 音楽との関係は? マーサの素顔? などなどのお題目でそれは始まり、時おり笑いが起こりつつ和やかな雰囲気で過ぎていった。会場は立錐(りっすい)の余地もないほど初日を観ようと集まった観客で満杯だ。NYでもダンスやオペラなどを見るたびに思うのだが、エンタに満遍なく老若男女が観に来ている。80歳を超えて杖をついたり車椅子に乗っていらしているご年配の方もいれば10歳くらいのボーイズ、ガールズもいる。きっとどの世代をも繋ぐのがモダンダンスだったり舞踏だったりするんだなと美樹ちゃんたちのトークショーで起こる和やかな客席の反応を見ながら思う。

「さあ、それではこのあといよいよ開幕です。REVOLUTION ~black and white~!心ゆくまでお楽しみください」というような気の利いたフリもなく、トークショーはダラダラ普段のテンションのままFOで終わり、照明がゆっくり落ちる。ロバートの軽妙な挨拶が始まり、間もなくリサの作品「カサンドラの叫び」が始まった。なんでも先に予言してしまうカサンドラの悲劇を描いたこの作品は、体の動き以前に気持ちが大事な作品だ。初日の配役の3人は臆することなく演じきった。割れんばかりの拍手とブラボーコールが起こる。

初日前 特有の高揚感。波に乗るとそのままいける。観客もサポート体制にあるし余計なことを考えずにやればいい。僕と美樹ちゃんはStage Flight (幕間)でしっかり握手をして日本人らしく暗闇の中でお辞儀をし合いながら、
「よろしくお願いしますね」
「こちらこそ。平常心でいきましょう」
「そうだわね。出(舞台に出る入り口)はこっちよ」
平常心をと言って起きながら、幕を一つ後ろから登場しようとして美樹ちゃんに諭される。もう一つ前の幕だった。そこならピアノに最短距離で到達できる。ロバートと舞台監督のレイチェルがグランドピアノのセットアップを完了して、僕たちがいるStage Flighに帰って来る。すれ違い間際の二人が緊張しているのが伝わって来る。僕もPedroの書いた譜面を右手に持つか左手に持つかなど小さな験担ぎをしてしまう自分に今さらながら笑った。この男、緊張している。
暗闇の中、僕はゆっくりピアノの前へ出向き座る。譜面を広げ、深呼吸。そしてフリーズ。
大きなスクリーンにヘルズキッチンのアパートの屋上で撮影された「Broken Memory」が流される。曲の間、僕は身じろぎもしない。シャドーの一部としてただそこにいる。フィルムの中にいる美樹ちゃんの動きとPedroのメロデイを注意深く観察しながら時を待つ僕。
静かに踊りが終わり、最後の曲のフレーズが減衰するとテロップが流れる。無音の中、左右から幕がスクリーンを隠す。それと同時に美樹ちゃんが素足でセンターに出て来る音が聞こえる。
一瞬の間。
暗闇の天井から月光のような一筋の光が落ち、やがて舞台全体に柔らかく広がっていく。僕の目の前のPedroの曲の音符が俄かに浮かび上がる。僕はおもむろに最初の音を鍵盤に載せる。どうぞうまくいきますように。美樹ちゃんが踊り出す気配をそばで感じながら、夢中で鍵盤に指を滑らせる。奇しくも時はスーパームーン。月の光に引っ張られていたのかもしれないが、迷う暇もなく二人は2曲をやり終えた。
暗転。
美樹ちゃんが再び舞台に現れ二人でセンターへ挨拶をしに。バウ(お辞儀)。あちこちからブラボーの声が上がり、辺りは大きな拍手に包まれた。初日の興奮は僕たちを守ってくれた。
暗転。
心からホッとしてまたStage Flighへと消えると、暗闇の中で「お疲れ様」とねぎらいあう。
次の出し物、マーサの1929年の「Heretic」が始まる。モダンダンスの歩みの源流にある、雪解けのようなマーサグラハムの機知に富んだ世界が広がる。直前までダメ出しを繰り返されながら無我夢中で舞台に上がったハンナ、ジェシカ、サラ、などのダンサーたち。自分のパートを終わった僕は、Stage Flighからお客さんにバレないように彼女たちの踊りをじっくり見守ることにする。それはまるで隣のホールやっているモーツアルトの曲のように「キャッチー」で「喜怒哀楽」に満ち満ちて、どこか飄々としているように僕には思えた。僕たちが生まれるずっとずっと前の作品に、観客は水を打ったように見入り、やがては大きな拍手が起こる。
そのあと10分の休憩ののち、マーテインの作品が3つ続く。どれもが濃密なこってりした内容のものだった。そして次第に地鳴りのような盛大な拍手の後に、全てのショーのカーテンコールの意味で、美樹ちゃん、リサ、ロバート、マーティン、僕が手を繋ぎ、バウを行うために再び舞台に登場する。
舞台の神様はキャノピーダンスに微笑んでくれた。この日はサポーターの人たちを招いてロビーでパーテイが行われた。移動したピアノで僕は静かにピアノを弾いた。初日の夢のような時間を思い返しながら、まだ半分夢の途中にいるような気持ちのまま。
2日目に事件が起こった。
最初に流すBroken Memoryのフィルムの途中で音がよれ映像がスクラッチし始めたのだ。そして全てが突然止まった。影としてその場にいた僕はスッとStage Flighに引っ込み、舞台監督のレイチェルと美樹ちゃんと短い会話を交わす。
「フィルムはなしでやりましょう」
「うん、わかった」
何事もなかったかのように再びピアノの前に戻った僕を、観客は固唾をのんで見守った。そして再び静かに照明が落ちて漆黒の闇が訪れる。素早い風が僕のそばを駆け抜けたかと思うと、センターに移動した美樹ちゃんが細い光の中にゆっくり浮かび上がる。
2日目の恐怖。抗っても勝てないこのジンクス。
ポップスのツアーでもそうだったのだが、ツアーの初日に大成功すると必ず2日目には事件が起こり思うような結果を出せないことが多い。
何故なのか。
Stage Flightに魔が差す。舞台に違和感が炙り出される。この日もフィルムの事故の後、何事もなかったかのように美樹ちゃんと僕はミスもなく終えた。できることは精一杯やったと思う。
しかしstage flightに戻った時、舞台の上に何かやり残したような不思議な違和感が残った。フィルムが止まってしまったことじゃない。事件はナマモノの舞台をやっていれば起こるべくして起こることはわかっている。違和感の元は、そのあとに生の舞台を素敵なハプニングに陽転させることができなかったという後悔だった。日本とアメリカという全く別の場所で30年近く舞台に立ち続けてきた美樹ちゃんと僕だけれど、「アクシデントをプラスに変える」難しさを痛いほど感じた瞬間だった。
舞台の恐ろしさ。再びの暗転。
バックステージに戻った美樹ちゃんは初日よりも汗をかいていたし、僕は指を鍵盤にチョップしすぎて痛さを感じていた。こういう時はダンサーたちのまばらな拍手で迎えられる瞬間さえもが辛い。しかも笑顔で、
「グッジョブ!」
「ありがとう」
と交わし合う。舞台では次の演目がすでに始まっているのだ。2日目のジンクスはすでに過去の藻屑だ。舞台は「タッパ(高さ)前っつら(幅)奥行き」でできた3次元の世界だ。ここで有機的に作る世界は現実のようであって現実ではもはやない。全てが研ぎ澄まされたフェイクの塊であり、限りなく現実に近い精巧で訓練された虚構で固められたリアリテイショーだ。その禍々しい世界を、人はどこか自分の目で透かし咀嚼して見ているところがある。そしてその先の落とし所をいつもどこにするかを密かに準備している。うまい嘘にとことん「騙されたい」気持ち。だから騙すならばとことんやってほしい。
この日の拍手は大きかったし反響もあった。でも僕の中ではアクシデントをプラスに変えることができなかった残念さが、心の中で鉛のように重くのしかかった。お客さんに夢中でいられない隙を与えてしまった悔しさ。この日は二回公演だったので、そのあとの公演では再び夢中でパフォームし、こちらは大成功に終わる。が、さっきのトラウマは心に残った。
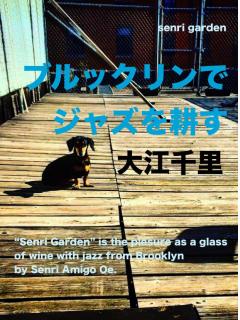
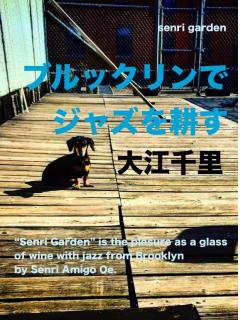


コメント
コメントを書く