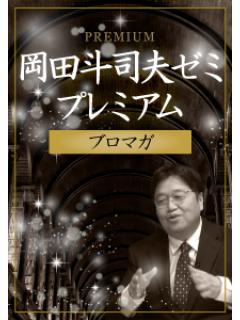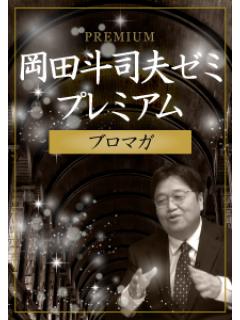岡田斗司夫プレミアムブロマガ 2019/03/06
おはよう! 岡田斗司夫です。
今回は、2019/02/17配信「『ファースト・マン』は後々評価されるが、今は当たらない理由」の内容をご紹介します。
岡田斗司夫アーカイブチャンネルの会員は、限定放送を含むニコ生ゼミの動画およびテキスト、Webコラムやインタビュー記事、過去のイベント動画などのコンテンツをアーカイブサイトで自由にご覧いただけます。
サイトにアクセスするためのパスワードは、メール末尾に記載しています(2018年12月1日より新サイトに移行しURLが変更されました。これに伴い、ログイン画面も変更されています。詳しくはメール末尾の注意事項をご覧ください)。
(※ご注意:アーカイブサイトにアクセスするためには、この「メルマガ専用 岡田斗司夫アーカイブ」、「岡田斗司夫 独演・講義チャンネル」、DMMオンラインサロン「岡田斗司夫ゼミ室」のいずれかの会員である必要があります。チャンネルに入会せずに過去のメルマガを単品購入されてもアーカイブサイトはご利用いただけませんのでご注意ください)
2019/02/17の内容一覧
- 興行成績の悪い『ファースト・マン』
- X-15 死と隣合わせの日常
- 2歳の娘・カレンの死
- 「ニュー・ナイン」への選出
- 親友・エリオットの死 前編
- 月軌道ランデブーを実験するためのジェミニ計画
- 親友・エリオットの死 後編
- ジェミニ8号 宇宙へ
- アポロ1号の事故は、なぜ起こったのか
- 操縦が超絶難しかった月着陸研究機
- 月着陸、死を飛び越えて鷹は舞い降りた
- 歴史に残る月面の第一歩
- ニールの私物ポケットに入っていたもの
X-15 死と隣合わせの日常
今日は、さっきも言った通り『ファースト・マン』で描かれた事件を、映画とは違う方向で語ってみる、「ファースト・マン番外編」です。
まず、映画の冒頭から「X-15」という飛行機が出てきます。こいつですね。
(模型を見せる)
これ、実は1962年の事件なんですね。
ニールとX-15の話は前回話しましたから置いときますけど、この時期のアメリカがどんな状況だったかというと。
第2次大戦が終わった時に、危うくアメリカ軍は縮小されるところだったんですよ。
「もう戦争は終わったから、軍隊なんかなくていいや」と、予算を食うから縮小されようとしてたんですね。
海軍は、巨大な空母や戦艦の建造を何十隻もキャンセルされました。
陸軍航空隊は爆撃機をキャンセルされ、慌てた飛行機メーカーは、その材料で家庭用のジュラルミンの流し台を売ったりして、なんとか生き延びようとしたんですけども、いっぱい倒産しました。プレハブの家を作って売ったりしたんですけど、倒産が相次いだと。
そんな陸軍航空隊も、戦後「アメリカ空軍」という形で独立します。そして、海軍に次ぐ大きい存在になってしまいます。
ところが、ソ連との冷戦が始まって「核ミサイル」という兵器が生まれました。
そのおかげで、空軍はどんどん巨大化しました。実はアメリカから発射する戦略核ミサイル……地面に掘ってある穴の蓋がガーッと開いてロケットがドーンと飛び出すあれのことですね。あれは、陸軍じゃなく、アメリカ空軍の管轄なんです。
陸軍というのは、あくまで陸上兵器。だから、例えば敵の戦闘機とか爆撃機がやって来た時に迎撃する「地対空ミサイル」、つまり、地面から空を攻撃するミサイルまでは持っていいんです。
だけど、直接、相手の土地まで行って攻撃する爆撃機は空軍だし、相手のところまで届くミサイルも空軍。なんか、そういう仕分けになっていたんです。
というわけで、この時点で陸軍の弱体化が予想されたんですね。
海軍は、どんどん巨大化する空軍に対抗して、例えばこういう、アンドリュー・ジャクソンという名前の「核ミサイル原子力潜水艦」というのを作ったわけですね。
(アンドリュー・ジャクソンのプラモデルの箱を見せる)
空軍の管轄する、アメリカ本土から発射する大陸弾道ミサイルというのは、開発が大変なんですよ。おまけに、ミサイル基地って、場所もバレてるから、敵に最初に狙われやすい。
なので、潜水艦にミサイルを縦にぎっしり積んで、これを海中で運んでしまおうというアイデアだったんですね。動力も原子力にしてしまえば半年くらい水の中に潜りっぱなしにできる。
「これでこっそりソ連に近づいて行けば、射程の短いこういうミサイルでも、モスクワに届くんじゃないのか?」と。こういうアイデアですね。
それに対して、アメリカ陸軍はというと。空軍は大陸間ミサイルも爆撃機も持っている。その上、海軍まで、こういう原子力潜水艦の中にミサイルを縦に積んで運用しようとしている。
それに対して、陸軍の方は、もう本当に手の出しようがなかったんですね。なので、仕方なくこういうものを考えました。
(巨大なプラモデルの箱を見せる)
これ、僕はニューメキシコのホワイトサンズという場所で見てきたんですけど「アトミックキャノン」と呼ばれる兵器ですね。当時、最新兵器だった原爆を発射できる大砲です。
これくらいしか、陸軍の力を伸ばす方法が思いつかなかったんですね。
もともと、ドイツと日本を降伏させたのは陸軍の力なんですよ。
「空軍が力を削いだ」と言っても、あくまで陸軍が敵と戦って占領したから、戦争に勝てた。
ドイツを占領した後でも、陸軍は、捕まえたウェルナー・フォン・ブラウンのチームを、わざわざアラバマ州ハンツビルというところに迎えて、ミサイルの研究までさせてたんですよ。
しかし、さっきも言ったように、陸軍に許可されたのは、あくまで迎撃用の地対空ミサイルまで。空軍が開発しているソ連まで届くような巨大ミサイルの開発許可は、陸軍には下りませんでした。
もう、なかなか思うようにいかないわけですね。
ソ連が1957年にスプートニクを飛ばすまで、この不毛な争いで、ウェルナー・フォン・ブラウンたちのロケットチームの開発はまったく進みませんでした。
そんな合間に、空軍が勝手に宇宙へと縄張りを延ばそうとして作ったのが、このX-15実験機です。
ニール・アームストロングは、この飛行機のテスト飛行中に、自動操縦装置が故障して、機首が上がったままの状態……つまり、水平からそれ以下の状態で大気圏に入らなきゃいけないのに、機首が上がったままの状態で大気圏に入ってしまいました。
これ、「ニール以外のパイロットだったら、たぶん死んでる」と言われています。
ニールが、ギリギリでX-15を着陸させたのは、デコボコした地面が地平線までずっと続いている「エドワーズ鹹湖(かんこ)」という場所です。大昔、紀元前遥かの世界には塩の湖があったんですけど、それが乾いてしまって、平坦な地面が地平線まで続く、エドワーズ鹹湖の底に着陸しました。
このエドワーズ鹹湖のデコボコの地面というのは、ラストシーンの月と映像的な韻を踏んでいるんですね。ラストで「月という死の世界で生き延びたニール・アームストロング」というのを見せる時に。
このエドワーズ鹹湖というのは、エドワーズ空軍基地の着陸場と言われているんですけど、本当に何もないデコボコした地面が延々と続いているような場所なんです。
そこが真っ昼間の光に照らされているところが、映像的な韻を踏んでいる。
まあ、要するに「死を免れたと思ったら、エドワーズ鹹湖のような、乾いた湖の底という死の世界が広がっていた」と。
『ファースト・マン』では、このように、常に死と隣り合わせのニールの8年間を扱っています。
(続きはアーカイブサイトでご覧ください)
アーカイブサイトへのアクセス方法
限定放送を含むニコ生ゼミの動画およびテキスト、Webコラムやインタビュー記事、過去のイベント動画など、岡田斗司夫のコンテンツを下記のアーカイブサイトからご覧いただけます。