ネコが、喋っていた。
二本足で歩き、蝶ネクタイを付け、杖まで持ったネコが、僕に向かって、流暢な日本語を話していた。そんな夢を見た。
彼は、僕が納得するまで「信じて」と言い続けた。そして翌朝、目が覚めると、僕の手の上には指輪がひとつ置いてあった。
――そんなことがあったとする。この世界に、ひとつだけ恋を手助けする未来のテクノロジーが存在したとする。それを貴方が手にしたら、どんな恋をするだろう。
この連載では、ライター・カツセマサヒコが、ひたすらありもしない「もしも」を考えていく。
Chapter 1 「指輪、落ちてなかった?」「あ、ごめん、起きてる?」
「うん。いま、起きたとこ」
夢の記憶が飛ばないうちに、そして指輪が手の上にあるうちに、僕は彼女に連絡をした。
もしかすると、彼女の手のひらにも同じように、この指輪が置いてあるのではないかと思ったからだ。
東京と愛知は、新幹線に乗れば2時間で着く。でも、その2時間が、僕らにとっては地球の裏側のように遠く感じられた。
泣いて喜ぶほどうれしいことがあったとき、死にたくなるほど悲しいことがあったとき、一番に抱き合って想いを分け合いたい相手は、いつだって遥か遠くにいたのだった。
「あのさ、ちょっと頭おかしくなってる前提で聞いて?」
「うん? なぁに?」
まだ寝起きらしい、甘く小さな声に笑い声が加わって、気持ちが少し柔らかくなる。
「起きたら、指輪を握りしめてたり、しなかった?」
僕は、できるだけ真面目なトーンで彼女に聞いた。
結論、彼女の手のひらに、それらしいものは落ちていなかった。
僕は夢で見たネコの話と、いま目の前にある指輪の話をして、「お前も、持ってるんじゃないかと思って」と正直に伝えたが、それでもやっぱり見当たらないと言われた。
そして「その夢見て、わたしに連絡くれたんだ? それ、うれしいなあ」と、茶化すわけでもなくヘラヘラ笑う声を聞いた。
期待はしていたものの、現実的ではないと思っていたから、大して落胆もせずに「ごめん」と言って電話を切った。
彼女との遠距離生活は、まだまだ解消されそうになかった。
Chapter 2 「何も起きなかったらどうする?」「今朝の電話の件なんだけど」
連絡があったのは、苦手な得意先との接待を終えて、ようやく酔いが冷めてきたタクシーのなかだった。
24時をとっくに越えているのに環状7号線は混雑していて、家まであと少しというところで、立ち往生していた。
「手のひらにはなかったんだけど、ベッドの下に、落ちてたみたい」
彼女から届くLINEの文字列には、どこか実感が沸かないニュアンスが込められていた。酔いがまた回り始め、鼓動が早くなるのを感じる。
「なんで、ベッドの下?」
理由をたずねると、意外と単純な答えが返ってくる。
「たぶん、寝相悪くて、落としちゃってた...(笑)」
家に帰ってきたら、母親が見つけてくれていたらしい。「なるほどね(笑)」と相槌を打ってから、一度画面から目を離す。
本当にあった。僕は鞄にしまっていた指輪を取りだし、リング越しに信号機を眺める。青色のランプが光ると、タクシーはゆっくりと走り出した。
「どうなるかわかんないから、部屋にこもって、ベッドの上でやろう」
半信半疑ではあるものの、僕らはそれなりの準備をして、未知なる体験に挑もうとしていた。
日当たりが悪く冷え切った部屋に戻ってくると、すぐにコンタクトレンズを外し、顔を洗って、部屋着に着替えてベッドに着いた。
準備ができた旨を伝えると、彼女は「ごめん、一応、眉毛だけ書かせて」と言って、しばらく音信不通になった。僕も、接待で餃子を食べたことを思い出し、歯だけ磨くことにした。
彼女から再び電話が来る。スマートフォンを耳に当てると、少し緊張した面持ちの声が聞こえた。
「いいよ」
「うん、おれも」
「何も起きなかったらどうする?」
「あのネコにラーメンでもおごってもらう」
「それ、いいなあ」
ふたつ、みっつやりとりをしたあとで、電話を切る。
事前に取り決めたとおり、胸の前あたりで、薬指に指輪を通した。
Chapter 3 「ラーメンどころじゃない、フルコースでもおごってもらおう」目には、見えなかった。
書きなおしたであろう眉毛も、わからなかった。
ただ、指にリングを通した瞬間から、気配を感じた。
目の前に、いるのがわかった。
「いる...?」
僕は尋ねる。でも、言葉は部屋の壁まで飛んでいき、返ってこなかった。
見えない。言葉も届かない。でも、そこにいることだけがわかった。
僕はそっと手を伸ばして、彼女の手に触れた。
少し硬直する感覚が伝わるが、それもすぐにほどけ、ぴたりと手のひらが重なった。
不思議な感覚だった。誰もいない空間で、存在だけがたしかにあった。
僕は見えない恋人の肩を抱き、頭を撫でた。
涙のようなものが、首筋に落ちた感覚があったが、それが水分かも確認できなかった。
しばらく時間が経ち、体を離すと、LINEが届いた。
「これはさすがに、せつなすぎるよ」
まだ気配が感じられる部屋で、僕も文字を打つ。
「ごめん。ラーメンどころじゃない、フルコースでもおごってもらおう」
指輪を外して、ベランダに出た。
着信履歴から彼女の名前を探して、通話ボタンをタップした。
「次の土日、そっちに行ってもいい?」
今度は、きちんと声が届いた。
――遠距離恋愛というものを経験したことがないんですけど、きっと「会いたいときに会えない」というのは、想像以上のストレスを生むと思っていて。
同じ東京に住んでいたって、なんらかの事情で会えない日が続くとあんなにイライラしたり、不安になっていたりしたのに、ましてや片道2時間3時間かかるなんて、もう自分の住んでいる世界に、恋人はいないような錯覚すら起こりそうで。
心の距離はどうしようもないけれど、実距離を超えるテクノロジーはいつか誕生する。
電話はもう声を届けてくれるようになったし、スマートフォンは映像をくれた。でも、そのあとに届くものは、何だろう? そんなことを想像しながら書きました。
結局は、ちゃんと会いに行くのが一番だという結論。
聞いて、見て、嗅いで、感じるのが一番だと思いました。
写真/PIXTA、Visual Hunt 文/カツセマサヒコ
【参照サイト・画像・動画へのアクセスはこちら】



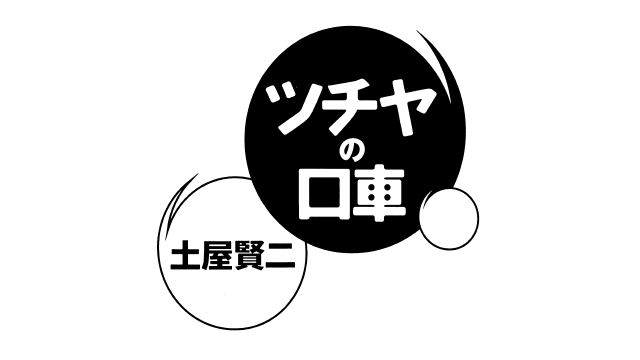


コメント
コメントを書く